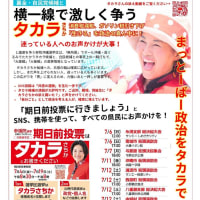今日(9月13日・火)、沖縄平和市民連絡会と島ぐるみ宗教者会議の呼びかけに応じた県民61名が、安倍元首相の国葬に知事・県議会議長が参列するための公金支出の差し止めを求める住民監査請求書を提出した(末尾に全文を掲載する)。
27日の国葬が迫っているので、監査請求と同時に、地方自治法242条第4項に基づき「国葬派遣費用支出の暫定的な停止勧告の申立て」も併せて行った。
知事は、昨日、国葬への不参加を表明したが、報道によると赤嶺県議会議長は出席するという。今日の差止め請求が間に合わない場合、議長が出席すれば、その費用の損害賠償を求める監査請求を行いたい。
なお、記者会見の後、教育委員会に行き、国葬当日、学校での弔旗の掲揚や黙祷を実施しないよう申し入れた。担当者は、「今のところその予定はない」と説明したが、来週、改めて教育長との面談の場を持つよう求めた。
国葬当日には、県庁前広場で抗議集会を開催したい。

(監査請求書の提出)

(県庁記者クラブでの会見)

(今日、夕刻のOTVニュースより)
********************************
以下、監査請求書の全文を掲載する。
沖縄県監査委員 様 2022年 9月13日
沖縄県職員措置請求書
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
第1 請求の要旨
1 概要
政府は本年7月22日、故安倍晋三元首相の国葬儀(以下「本件国葬」)を9月27日に挙行することを閣議決定しました(資料1)。
すでに、三権の長や国会議員(元議員を含む)、地方自治体・各界の代表者、海外の要人等、約6000人に案内状が出されており(資料2)、沖縄県知事(以下、「知事」)及び沖縄県議会議長(以下、「議長」)らも公費で出席・参列する可能性があります。
しかし、本件国葬は以下に述べるとおり、違憲・違法なものであり、本件国葬に関連して支出される公費もまた違憲・違法な支出です。
私たちは、地方自治法第242条第1項の規定に基づき、沖縄県監査委員に対して、本件国葬に知事及び議長が参列するための公金支出を差し止める措置をとられるよう求めます。
2 対象となる知事及び議長の行為及びそれに関する公金の支出
2022年9月27日に挙行される「故安倍晋三国葬儀」への知事及び議会議長の参列・出席に関連する公金の支出行為一切(知事・議長の代理者、また、随行職員に関する支出等も含む。)。
3 本件国葬の違憲性・違法性
⑴ 「国葬」が持つ歴史的政治的意味
そもそも「国葬」とはいかなる性質をもつものなのでしょうか。
日本最初の国葬は、1883年に行われた、岩倉具視の葬儀ですが、その原型は、さらに5年前の大久保利通の葬儀だったと言われています。大久保家の葬儀でしたが、天皇が弔意の品を贈り、勅使を派遣しています。その費用には国費が支出され、政府職員も要員として派遣され、国葬に準じたものとして行われています。これは、暗殺された大久保の葬儀を盛大に営むことで、「政府に逆らうことは天皇の意思に背くことだ」ということを、内外にアピールすることで、いまだ不安定な明治政府の基盤を強めようとしたものでした。
そのことは、国葬について定めていた「国葬令」からも読み取れます。国葬令では、天皇・皇太后・皇后の葬儀である大喪儀と、皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃及び摂政在任中の親王・内親王・王・女王の喪儀を国葬とするとしたうえで(同令1条、2条)、皇族以外の「國家ニ偉功アル者薨去又ハ死亡シタルトキハ特旨ニ依リ國葬ヲ賜フコトアルヘシ」とされていました(同令3条)。「特旨」とは、すなわち天皇の「思召」を意味します。「國葬ヲ賜フ」との「特旨」は、勅書の形式をもって公にされ、内閣総理大臣はこれを公告し、葬儀の式次第は総理が案を作成して勅裁を経たうえで決定されることになっていました。つまり、「國家ニ偉功アル者」の葬儀は、天皇の「思召」をもって、天皇の命令により、内閣の主導で実施される形がとられていました。
また、国葬令4条は、「皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ葬儀ヲ行フ當日廢朝シ國民喪ヲ服ス」として、臣下の国葬当日、「国民」が喪に服すことを義務付けていました。これは、「国民」の立場に立てば、国葬の対象となる人物に対して、生前の「偉功」を讃える場が、国民の望むと望まないとにかかわらず、政府によって用意されることになるのです。こうして行われる国葬には、莫大な国費が投じられ、新聞各紙もこれを大きく報じています。ほとんどの国葬は東京で行われたようですが、東京から離れた各地の行政機関・学校・宗教施設などでは、葬儀の前後に遥祭が営まれるようになり、その葬儀の場にいなかった人たちも間接的に「國家ニ偉功アル者」の死に接することとなり、全国を巻き込んだ一大イベントになっていたのです。
平民出身者で初めて国葬の対象となったのは、日本海軍連合艦隊司令長官であった山本五十六海軍大将です。これは、国民の戦意高揚をもたらしました。山本は、1943年4月18日にブーゲンビル島上空で乗機が撃墜され戦死しましたが、その死はしばらくの間公表されることはありませんでした。しかし、5月21日に大本営からその死が発表されるとともに、国葬とすることが決められました。当時の新聞報道は次のようなものです。
情報局発表(昭和一八年五月二十一日午後五時)
天皇陛下に於かせられては聯合艦隊司令長官海軍大将山本五十六の多年の偉功を嘉せられ、大勲位功一級に叙せられ、元帥府に列せられ特に元帥の称号を賜ひ、正三位に叙らせれ、薨去に付特に国葬を賜ふ旨仰出さる
同年六月五日に行われた国葬に際しては、東条英機首相は「元帥の闘志を継げ」と国民を激励しました。
また、全国民が喪に服することとされ、午前10時15分を「国民遙拝の時刻」と定め、遙拝式を行うことなどが通達されていました。
このように、「国葬」は、国家が特定の「功臣」の死に政治的な狙いをもって、積極的に介入しているのです。特に明治憲法下における天皇の介在はその点を強調する意味合いがあったと考えられます。
国葬令は、1947年に「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)第1条の規定により、失効しています。その理由は、日本国憲法の基本原理と両立しないからです。そのため、現在の日本において、国を挙げて行なう公葬を規定する法は存在しません。
地方公共団体においても、1946年11月1日内務文部次官通達で「地方官衙及び都道府県市町村等の地方公共団体は、公葬その他の宗教的儀式及び行事(慰霊祭、追弔会等)は、その対象の如何を問わず、今後挙行しないこと」と地方長官に命令が出され、行政が主導して宗教性を伴う慰霊行為を行うことは政教分離の観点から全面的に禁止されています。
日本国憲法の下では、皇室に関するものとして、1951年の貞明皇后に対する「事実上の国葬」と、1989年の昭和天皇に対する大喪の礼(皇室典範に基づくもの)の2回があり、皇室以外では、1967年に吉田茂元首相に対する「国葬」が行われています。もっとも、首相経験者については、その後も国葬が検討されたようですが、根拠法令がないとのことで実行されず、ノ-ベル平和賞を受賞した佐藤栄作元首相を含め、近年まで「内閣・自由民主党合同葬」が慣例的に行われています。
⑵ 本件国葬の挙行に至る経緯
本件国葬が挙行されるに至った経過は、次の通りです。
2022年7月8日午前、同月10日に執行される第26回参議院議員通常選挙の選挙応援のため奈良県内を遊説していた安倍晋三衆議院議員(元内閣総理大臣、元自由民主党総裁)が、街頭演説中に銃撃を受け、同日午後に亡くなりました。
岸田文雄内閣総理大臣(以下「岸田首相」といいます。)は、2022年7月22日、亡安倍晋三氏について本件国葬を行うこととし、その名称を故安倍晋三国葬儀とすることなどを閣議決定しました(資料1)。岸田首相によると、安倍氏について国葬を行うことについて、「①憲政史上最長になる8年8か月にわたり内閣総理大臣の重責を担ったこと、②東日本大震災からの復興、日本経済の再生や日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を残したこと、③外国首脳を含む関係社会からの高い評価があること、④選挙中の蛮行による急逝であること」等と説明しています(資料3)。
⑶ 本件国葬の違憲性
ア 日本国憲法の根底にある個人主義(individualism)
私たちが、今回の監査請求をするにあたり、もっとも重要だと考えていることは、私たちの住む日本社会において、私たち一人ひとりが、等しく尊重される社会であるということです。
憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定しています。これは、私たちの社会を考えるうえで、極めて重要な前提を示している部分です。なぜ、私たちは社会を作るのかという根本的な問いに立ち返る部分でもあるからです。私たちを取り巻く社会的関係を一つずつ取り除き、最後に残った「私自身」「あなた自身」という独立した存在を「個人」といい、その個人一人ひとりは自由で平等であるという前提が共有されていなければなりません。その「個人」が持つ自由や権利を維持・発展させるために私たちは社会を作り、その社会を運営する際に、運営者たる権力者にたいし、構成員の侵してはならない自由や権利を「基本的人権」という形で注意喚起をしているのです。
このように、私たちの社会は、何よりもまず、私たち一人ひとりが等しく尊重される存在であるということを大前提として成り立っており、これを個人主義と呼んでいます。この反対概念は全体主義ということになります。
イ 憲法14条(個人の平等)違反
このように述べたところで、現実社会をみると、それぞれの個人は決して自由で平等であるとはいいがたい状況にあることはわかります。男女の性差であったり、障害の有無や資産の有無などいたるところに物理的な格差があるからです。
しかし、私たちが、心のうちで何を考えようと、いかなる神を信じようと、あるいは仏を信じまいと、誰かを愛おしいと感じようと、あるいは殺してしまいたいほどに憎しみを感じようと自由です。他者とのかかわりの中で、他人の自由や最低限の秩序を侵害しなければ、基本的に何をしようと自由です。これは、人間として生まれたという一点において、私もあなたも等しく同じ存在だからです。個人はそれぞれ自由かつ平等です。より正確に言うならば、個人はその自由性において平等だということです。このことを宣言したのが、憲法14条です。
この憲法14条の唯一の例外が、日本国の象徴たる天皇です。裏を返せば、天皇以外は日本国との関係で当然に特別扱いされることはありません。むしろ、してはならないのです。特別な対応をしようとするならば、その根拠となる法律がなければなりません。
今回の安倍氏に対する国葬儀は、日本国として安倍氏を特別扱いして国費において葬儀をするということです。当然のことながら、私やあなたも、将来亡くなったときに国が葬儀をしてくれることなどないでしょう。どうして安倍氏が国葬の対象になるのか、納得のいく説明はありません。憲政史上最長の首相在任期間は理由にはなりません。加えて、その長期政権の中で政治の私物化を追及されるなど、安倍氏の政権運営には否定的評価も多くありました。首相の座こそ降りましたが現職の国会議員でしたし、この評価は今なお定まるところではありません。そのような中で国家として葬儀を行うとするのは、あまりに安倍氏の特別扱いが過ぎ、個人の平等という基本的な大原則に正面から反するものです。
ウ 憲法19条(思想及び良心の自由)違反
先に述べたように、日本国憲法が施行されてから、「国葬」は皇族を除けば吉田茂元首相の例しかありません。首相経験者について、これまでの慣例をあえて破って半世紀以上上行われてこなかった「国葬」という形式を取るということは、そのこと自体に意味を見出していると言わざるを得ません。
岸田首相は、7月14日の記者会見で、本件国葬によって、安倍氏を追悼するとともに、暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示す、活力にあふれた日本を受け継ぎ、未来を切り拓いていくという気持ちを示す、としています(資料3)。また、8月10日の記者会見では、「国葬」について、「故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式」と説明しています(資料4)。
すなわち、「国葬」という形式を取ることの意味は、国を挙げて故人を追悼し、一定の決意や気持ちを示す、ということにほかなりません。そのために、本件国葬当日は弔旗の掲揚や黙祷の「要請」が官民問わず行われ、またマスコミも本件国葬一色の報道になることが予想されます(吉田茂氏の国葬に際してはまさにそのようなことが行われましたし、安倍晋三氏についても、7月12日の葬儀に際して多くの公共団体が弔旗の掲揚を行いました。)。
しかし、故人に対して追悼の念を抱くか否かは本来きわめて個人的な営為であり、とりわけ、首相経験者である故人に対するそれは、個人の歴史観や世界観、政治信条に深く根ざした行為です。そして、「国葬」は、個人の歴史観や世界観に基づいた営為であるはずの追悼を、故人に対する敬意や弔意を持ち合わせていない人も含めて、国中の人々に強いるという意味で、思想良心の自由を保障した憲法19条に反するものです。
エ 憲法20条(信教の自由)違反
安倍氏国葬は憲法20条や89条の政教分離規定に違反し、市民の信教の自由を侵害する可能性があります。
憲法20条1項前段は信教の自由は何人に対しても保障するとし、2項は何人も宗教上の行為を強制されないとしています。しかし、明治憲法のもとでは国が宗教、とりわけ神道と結びつくことによって市民の信教の自由が保障されていたとはいえませんでした。そこで日本国憲法20条1項後段、3項や89条は、政教分離原則に基づき国と宗教が結びつくことを禁止する政教分離規定を定めました。それによって、信教の自由の保障を制度的に確保しようとしたのです。
安倍氏国葬は、故安倍晋三元内閣総理大臣に対し、哀悼や追悼の意を表するために行われるものです。岸田文雄首相は、2022年7月14日夜の記者会見において、「国の内外から幅広く哀悼や追悼の意が寄せられていること」などを「勘案し、この秋に『国葬儀』の形式」で本件国葬を行うと表明しました(資料3)。
本件国葬は、「国」として故安倍晋三元内閣総理大臣を追悼し、故安倍氏に弔意を示す儀式です。追悼とは故人の生前を思い返してその死を悲しむことであり、弔意とは故人が亡くなったことによる自分の悲しみ・弔いの気持ちを意味します。いずれにせよ、国民一人ひとりの内心に深く関わり、人それぞれであり、宗教的側面と切り離すことができません。
本件国葬を決めた同年7月22日の閣議後の記者会見で、松野博一官房長官は、「無宗教形式で行うこととし、厳粛かつ心のこもった国葬儀となるよう関係者と密接に連携をとりながら速やかに準備を進めていく。」と述べました。しかし、形式が無宗教であったとしても、既存の宗教団体の方式を踏襲しないというだけで、「国葬儀」が宗教的な意味合いをもった行為であることに変わりはありません。
日本国憲法20条3項は国及びその機関が「宗教的活動」を行うことを禁止しています。したがって、国が主催して本件国葬を執行し、地方公共団体の知事等がこれに参列し、公金を支出することは、憲法20条3項に反するものであり、許されないことです。
オ 憲法21条(表現の自由)違反
故人に対して追悼の念を抱くことはもちろん、さらに追悼の念を表明する、しないということも、思想良心に基づく表現行為としてきわめて個人的な営為です。
儀式の価値は、外形にあらわれた荘厳な形式によって発揮されると言われることがあります。前述のように、「国葬」当日は弔旗の掲揚や黙祷の「要請」が官民問わず行われることが強く予想されます。「国葬」が「故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式」であるならば、本件国葬の会場である日本武道館にとどまらず、国全体に弔意の表明が行き渡っている必要があります。「要請」であると言いながらも、本件国葬が儀式として完成するためには、安倍氏に対する「敬意と弔意」を表明することの有形無形の圧力が生じるものと考えられます。しかし、追悼の念を表明するということは一種の表現活動であり、弔旗の掲揚や黙祷はその具体的な表明行為です。
「国葬」を実施することは、そのような弔意表明の「要請」が官民問わず行われ、有形無形の圧力がかけられることにつながり、憲法21条が保障する表現の自由が侵害されることになります。
⑷ 本件国葬の違法性
ア 行政活動は法律に基づいて行われなければならない
ところで、今回の国葬は内閣府に実行委員会を置く方式で運営されることと閣議決定がなされました。内閣総理大臣が実行委員長であり、その実務機関を内閣府に置くのですから、今回の国葬儀は国の行政活動の一つというべきでしょう。
大日本帝国憲法の下においては、国家権力のすべてを統帥する天皇がいましたから、行政権はア・プリオリに法に先立つものと考えられていました。しかしながら、日本国憲法の下においては、憲法によって行政権が創設され、国会の制定した法律によって組織され、個別の法律によって一定の権限を与えられることになりました。つまり、行政という営みの本質は、「法律を誠実に執行する」こと(憲法73条1号)にあるというべきです。そのため、行政権を発動するためには、法律を執行するための機関を作る根拠となる「行政組織法」と、具体的に行政活動を営む際の手続や要件、活動の内容や効果に関する「行政作用法」が必要になります。行政組織法がハードウェアで、行政作用法がソフトウェアといえばわかりやすいでしょう。
行政活動は、あくまでも個別具体的な行政作用法の存在を前提とし、その法律に拘束されるのであって、行政権は法律による授権なしに私人の権利義務に影響を与える決定をしてはなりません。
このような行政法の執行過程を貫く基本原理を「法律に基づく行政の原理」といいます。
イ 内閣府設置法を根拠にするという詭弁
本件国葬の実施に際して、国葬を行う具体的な法律根拠がないという厳しい指摘がなされていました。先の述べた通り、戦前の日本で実施されていた国葬は「国葬令」に基づいて行われていましたが、日本国憲法の制定によってこの国葬令が廃止されています。そこで、政府が打ち出した法律が内閣府設置法です。内閣府設置法には内閣府の所掌事務として「国の儀式」が挙げられていると言うのです。
たしかに、内閣府設置法第4条第3項第33号をみると、「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。」とあります。
しかしながら、この説明は詭弁にすぎません。内閣府設置法は、「内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定める」(同法第1条前段)とあることから明確なとおり、「行政組織法」の一つだからです。先に確認した通り、行政活動は、あくまでも個別具体的な行政作用法の存在を前提とするものです。内閣府設置法はハードウェアであって、国葬を実施するためのソフトウェアにはなりえません。
この内閣府設置法にいう「国の儀式」は、天皇が行う国事行為として定められている「儀式」(日本国憲法第7条第10号)が念頭に置かれています。この「儀式」の行政作用法の1つとして、皇室典範が挙げられます。天皇の即位に伴う「即位の礼」は同法第24条に、天皇の崩御に伴う「大喪の礼」は同法第25条に規定されています。今回の閣議決定が皇室典範の規定と同等の位置づけにあると言い難いことは明らかです。
結局のところ、今回の国葬儀は、何らの法的根拠のないものというほかなく、違法な行政行為と言わざるを得ないものです[2]。
4 本件国葬に関して地方公共団体が公費を支出することの違法性
本件国葬に地方公共団体の知事等が出席したり、公金を支出したりすることは、地方自治法に反します。
地方自治法2条2項は、普通地方公共団体は、「地域における事務及びその他の事務」で「法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの」を処理するとしています。これは、住民自治と団体自治を地方自治の本旨とする憲法92条に基づく規定です。
そこで、問題は地方公共団体の知事らが本件国葬に出席したり、そのための出張費用等に公金を支出したりすることが、地方公共団体の「事務」といえるかです。これについて、関係省庁が検討したり、地方公共団体が検討したりしている形跡はありません。
この点を検討すると、地方公共団体が行う「事務」はまず「法律」により処理することとされているこことが必要とされますが、本件国葬に知事らが出席したり、公金を支出することを根拠づける「法律」は存在しません。
また、「法律に基づく政令により処理することとされている」場合は、それも地方公共団体の「事務」といえますが、本件国葬に知事らが出席したり、公金支出することを根拠づける「政令」も存在しません。
仮に、本件国葬に関する法律や政令がなくても、地方公共団体が社会的実体を有し、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」されていること(地方自治法1条の2第1項)から、法律や政令に基づく「事務」に直接該当しなくても、なお独自に地方公共団体の「事務」にあたるといえる場合があるという議論もありえます。
しかし、国葬への出席は「住民の福祉の増進」を図るものとは言えず、やはり、地方公共団体の「事務」には該当しないというべきです。
このように検討してくると、本件国葬に知事らが参加したり、公金を支出したりすることが、地方自治の本旨を具体化した地方自治法2条2項に反する違法な行為であることは明らかです。
5 本件国葬に関して地方公共団体が公費を支出することの不当性
⑴ はじめに
唐突に「国葬」なる言葉が飛び出しました。法律に規定もなく、誰も考えてもいなかった言葉が岸田首相の口から飛び出しました。漫画であれば、皆が口をあんぐりと開けて驚きあきれている姿です。規程も何もないから基準もない。しかし、言葉の意味からは、「立派なことをした人」というイメージが浮かびますが、この安倍元首相に関しては想像もできないミスキャストであると、多くの国民が思っています。そのこと自体が、国を挙げて追悼すべきことか(不当性)という問い掛けにほかなりません。
⑵ 国民生活の困窮-賃金は全く上昇せず
本件国葬を実施する理由として挙げられたのが「憲政史上最長の8年8ヶ月」です。そうであれば、単に長い期間、首相の座に座っていただけではなく、最長期間その場にいた者の国民に対する責任が問われなければなりません。
実は、日本は20数年にわたり、労働者の実質賃金は全く上がっていません。OECD諸国は概ね1.5倍以上になっているのに、ひとり日本だけ下がっているのです。大企業はアベノミクスの恩恵を受け、史上最高益を稼ぎ出してきた一方で、労働者は「国際競争力強化」を口実に低賃金を強いられ、労働市場の非正規化が急速に進んだのです。この最大の責任者が安倍元首相です。
安倍元首相がしたことは、国民の貴重な年金財源を取り崩し、これを大企業の株価安定のために投資し続けたことです。従来違法であった年金財源を法改正して投資にあてました。このようなやり方で日本経済が再生するはずはなく、実質経済はガタガタです。多くの国民にとって生活水準は低下する一方です。安倍元首相に「経済の功績」など認めることはできません。
⑶ 権力の私物化-「モリ」「カケ」「サクラ」
安倍元首相に国葬と聞いて、第一に思い浮かぶのは、「モリ」「カケ」「サクラ」です。いずれも「ミミッチイ」話です。権勢を傘に、違法行為に蓋をして強行突破しようとして、芝居がかった「大見得」を切りました。「私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということをはっきり申し上げておきたい」と安倍元首相は国会質疑の中で高らかに宣言しました。これを聞いて泡を食った財務省は公文書の改ざんを行い、事実を消してしまいました。そのために最もまじめで貴重な一人の国家公務員の命が失われました。
「国葬」になる様な人は、このような違法はもちろん、人格的倫理性に傷がつく事実があれば、初めから候補にならないはずです。死亡した銃撃事件で明らかになった旧統一協会との関係も然りです。
岸田首相はこの「安倍元首相」の追悼で何を遺すつもりなのでしょうか。
⑷ 「民主主義」と「憲法秩序」の破壊
ア 教育基本法の改悪
2006年第一次安倍内閣が真っ先に取り上げた課題は「教育基本法」の改悪でした。もともと、旧教育基本法は、準憲法的性格をもつと言われた法律です。戦前の天皇制絶対主義国家において狂信的軍国主義を発生させた反省から、新憲法の平和主義・基本的人権尊重主義の実現は「教育の力による」として、この基本法が作られました。
ところが第一次安倍内閣は、この基本法から、教育行政の根本たる「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」という規定を削除しました。その結果、今では、行政当局の意のままに行われる上意下達教育と愛国心教育に子どもたちが晒される事態を作り上げ、教育の危機を招いています。
安倍元首相は、ここで、教育に関する「憲法改悪」を断行したのです。
その結果、ユニセフ「レポートカード16」(2020年)によれば、日本の子供の精神的幸福度は先進国38か国中37位という状況になっています。
イ 安保法制・集団的自衛権行使の違憲行為
安倍元首相の最大の「罪」は、集団的自衛権行使を可能とする「安保法制」を強制採決したことです。これによって、日本国民全体は、いつ何時でも、アメリカの行う戦争にその片棒を担がされることになり、戦争国家による被害を受ける危険が発生しています。もし、台湾有事でも発生すれば、沖縄の米軍基地ならびに今さかんに南西諸島に自衛隊が配備している軍事施設から戦争がはじまることになりかねません。安倍元首相は、ここで、「専守防衛」の憲法9条の政府解釈を変える「実質改憲」を断行したのです。
この責任をとらずに安倍元首相は死亡しました。
思い起こせば、集団的自衛権行使を認める閣議決定を行なった2014年4月、安倍元首相はワシントンに行き、オバマ大統領の前で、「越えられぬ山はない」という恋歌を引用して、「私はいつでもあなたのおそばに参ります」と言いました。民族主義者でなくとも日本国民の名誉と誇りに傷つけ、戦争国家への道筋をつけた総理でもありました。
岸田首相は、これも実績として「追悼」するのでしょうか。
⑸ 「民主主義」から最もかけ離れた安倍政権の沖縄政策
岸田首相は、安倍元首相が死亡して1週間も経たないうちに、「民主主義を守りぬく決意を示すため」に国葬を実施すると閣議決定しました。しかし以下、述べるように、8年8ケ月の安倍政権による沖縄政策は、民主主義からは最もかけ離れたものでした。
ア 沖縄戦史実の改ざんと沖縄戦後史の徹底した無視
第1次安倍政権下の2007年、沖縄戦における「集団自決」(強制集団死)の軍命に関する記述が高校歴史教科書から削除されました。沖縄では、県議会と全市町村議会が意見書を採択、11万人が参加する県民大会も開かれました。2014年には、八重山地区の中学公民教科書採択に介入し、地域の独自性を認めない教科書無償措置法の改定を行ったのです。
さらに2013年4月28日には、沖縄にとって「屈辱の日」であるにもかかわらず、サンフランシスコ講和条約発効による「主権回復」を祝う「記念式典」まで行い、県民の怒りを集めました。
イ 辺野古・高江への基地建設の強行・暴力的弾圧
2016年、高江のヘリパッド建設では、反対する市民の排除に全国から500名もの機動隊を動員し、凄まじい弾圧のもとに工事を強行しました。その工事では、自衛隊ヘリまで民間工事車両の空輸に投入しています。また、市民排除の際、大阪府警機動隊員の発した沖縄県民に対する「土人」発言に対しては、「(差別用語に該当するかは)一義的に述べることは困難」とする閣議決定まで行いました。
辺野古でも、自衛隊掃海母艦「ぶんご」が2007年と2014年、ボーリング調査を支援するとして辺野古沖に派遣されました。キャンプ・シュワブのゲート前や安和・塩川そして海上での抗議活動に対しては、機動隊・海上保安庁・民間ガードマンが一体となった弾圧が常態化しています。
また、大幅な設計変更を強いられることになった辺野古大浦湾側の「軟弱地盤」について、政府は2015年にはその存在を把握していました。真実をひた隠しにして、護岸工事(2017年4月)・土砂投入(2018年12月)を強行してきた安倍政権のどこに「民主主義」があるといえるのでしょうか?
ウ 米軍再編交付金、沖縄関係予算による基地と振興の露骨なリンク
歴代の自民党政権による沖縄政策は、日米安保と在沖米軍基地の維持をすべての前提に進められてきましたが、それを一層露骨に進めたのが安倍政権です。
米軍再編に伴い基地を受け入れる市町村に国が直接交付金を支給する米軍再編交付金は、2007年第1次安倍政権により制度化されたものです。以後、辺野古新基地への賛否が公的資金の配分を左右する、地方自治破壊と地域分断を常態化させたのです。2015年には、辺野古反対の名護市を介さず、久辺3区に直接補助金を交付する制度まで新設しています。
2013年の年末には、沖縄関係予算3千億円台確保を約束することで、仲井眞知事から辺野古埋立承認を引き出しました。その後の辺野古反対を掲げた翁長知事、玉城知事のもとで同予算は減額され差別的扱いが続いています。さらに2019年には、県を通さず国が市町村に交付する沖縄振興特別事業推進費を創設しています。いうまでもなく、沖縄関係予算は県民のためのものであり、このような政治介入は許されません。
エ 徹底した沖縄県民の民意無視と自治権侵害
2012年に始まるオスプレイの普天間基地配備は、10万人余が参加した県民大会の開催、県議会・県内41全市町村と議会等が賛同した「建白書」による上京要請行動など、考えうる民意のすべてが示される中で強行されました。
普天間基地の辺野古移設問題をめぐっても、何度もの知事選挙・国政選挙で、県民の反対の意思が示され続けてきました。特に2019年の県民投票では、投票率が5割を上回り、「反対」が7割を超えました。しかし、これらの民意を受けても、安倍政権は工事を中断する気配さえ見せませんでした。
それだけではなく、安倍首相は、翁長新知事との面会を4ヶ月間拒否し続け、県民投票結果を受けた岩屋防衛大臣は、「沖縄には沖縄の民主主義があり、国には国の民主主義がある」とうそぶいたのです。
沖縄県による埋立承認の「取り消し」「撤回」、設計変更申請「不承認」に対しては、本来の地方自治法による解決の道筋を無視し、手っ取り早く工事を再開するために行政不服審査制度を利用できるとする理屈までつくり出しました。いわゆる「国の私人成り済まし」です。この問題をめぐっては、今後も沖縄県と国による法廷闘争が続くことになります。
オ 小括
このように、安倍政権による沖縄政策は、まだそれまでの保守政権にはいくらか意識されていた、「償いの心」「過去(沖縄戦と米占領)の清算」という責務を投げ捨て、辺野古新基地建設、南西諸島への自衛隊配備をはじめ、新たな軍事化を平然と強要してきました。沖縄にとって安倍政権は、民主主義や法治国家の対極に位置するもので、まさに悪夢のような8年8ケ月だったのです。
6 結論
以上、述べたとおり、本件国葬は違憲・違法なものであり、国葬に関連して支出される工費もまた違憲・違法な支出です。
よって、私たち請求人は、地方自治法第242条第1項の規定に基づき、本件国葬に知事及び議長が出席・参列するための公金を支出することの差止めの措置を求めて、住民監査請求をします。
第2 請求人
別紙のとおり。
第3 事実証明書
別紙のとおり。