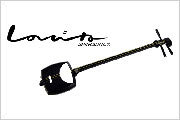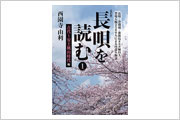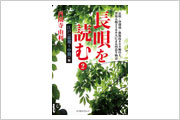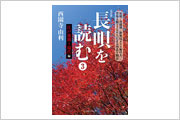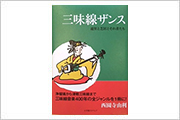122ー「水仙丹前」※その2(1755・宝暦5年・市村座)
丹前といえば今では「どてら」をイメージしてしまうが、
そもそもは湯女として一世を風靡した、勝山が着ていた衣装が原点。
勝山の勤める湯女風呂は、神田雉子町の松平丹後守の屋敷前にあった。
ゆえにこの辺りの湯女風呂は、丹前風呂と呼ばれていた。
そこのスターが勝山だ。
顔もいいけど気風もいい。それに唄、三味線が巧いときている。
着物のセンスも独特で、外出時の出で立ちは、
袴に木刀の大小を差し、編み笠をきりりと被る。
まさに武家風の男装の麗人。
旗本奴、侠客がほっておくわけがない。
ちなみに今日京都で、祇園祭の時だけ舞妓が結う髪形は”勝山”といい、
彼女の創案によるもの。
勝山の元に通う彼らが、その衣装を真似て伊達を競うようになり、
いつしか「丹前奴」「丹前風」という称が生まれた。
奴といっても下僕の奴ではない。伊達男の意味だ。
つまるところ、丹前とは、
袖口の広い勝山好みの、おしゃれな綿入れ羽織といったところ。
『恋は様々あるが中にもさ
分けて恋路は
逢う恋 待つ恋 忍ぶ恋
我が恋は必ず今宵は合点か
合点合点 そなたも合点
我等も合点
合図の手管飲み込んだ
えいえいえいえい
やっと手を打ち
勇み勇んで廓大寄せ』
これは若衆姿の中村粂三郎が、引き抜きで丹前奴になっての槍踊り。
リズミカルな恋づくしだ。
特に意訳の必要はないだろう。
勇み勇んで廓大寄せ、とは、大勢が勇んで廓に遊びに来るの意。
※その1は2010年6/9にあり。
〓 〓 〓
tea breaku・海中百景
photo by 和尚

丹前といえば今では「どてら」をイメージしてしまうが、
そもそもは湯女として一世を風靡した、勝山が着ていた衣装が原点。
勝山の勤める湯女風呂は、神田雉子町の松平丹後守の屋敷前にあった。
ゆえにこの辺りの湯女風呂は、丹前風呂と呼ばれていた。
そこのスターが勝山だ。
顔もいいけど気風もいい。それに唄、三味線が巧いときている。
着物のセンスも独特で、外出時の出で立ちは、
袴に木刀の大小を差し、編み笠をきりりと被る。
まさに武家風の男装の麗人。
旗本奴、侠客がほっておくわけがない。
ちなみに今日京都で、祇園祭の時だけ舞妓が結う髪形は”勝山”といい、
彼女の創案によるもの。
勝山の元に通う彼らが、その衣装を真似て伊達を競うようになり、
いつしか「丹前奴」「丹前風」という称が生まれた。
奴といっても下僕の奴ではない。伊達男の意味だ。
つまるところ、丹前とは、
袖口の広い勝山好みの、おしゃれな綿入れ羽織といったところ。
『恋は様々あるが中にもさ
分けて恋路は
逢う恋 待つ恋 忍ぶ恋
我が恋は必ず今宵は合点か
合点合点 そなたも合点
我等も合点
合図の手管飲み込んだ
えいえいえいえい
やっと手を打ち
勇み勇んで廓大寄せ』
これは若衆姿の中村粂三郎が、引き抜きで丹前奴になっての槍踊り。
リズミカルな恋づくしだ。
特に意訳の必要はないだろう。
勇み勇んで廓大寄せ、とは、大勢が勇んで廓に遊びに来るの意。
※その1は2010年6/9にあり。
〓 〓 〓
tea breaku・海中百景
photo by 和尚