
5月27日Ⓜaitabiツアーで両神山へ行ってきた。
前回は2007年10月、日向大谷からピストンした。
下山時ヘッドランプ装着で降りてきた記憶がある。
今回は白井差登山口から、4~5時間の行程だ。

10:20 

 曇り空、入山料
曇り空、入山料


 円を払って
円を払って 



曇り予報、 新
新 緑がいい
緑がいい

 信仰の山だが、メインコースではないので祠は少ない
信仰の山だが、メインコースではないので祠は少ない

(フイリ)フモトスミレ

エイザンスミレ、花が終わると葉が成長し養分を 蓄え来年に備えます
蓄え来年に備えます

10:30  昇竜の滝(気付かない人も)
昇竜の滝(気付かない人も) 帰りに滝壺へ寄ります
帰りに滝壺へ寄ります

ヒメレンゲ(コマンネングサ):ベンケイソウ科

個人の山、管理もオーナー山中さんの仕事。桟橋も 手作り感あり
手作り感あり

途中で合流し”付かず、離れず”山頂まで同行した。杖と地下足袋のおじさん

 クワガタソウ:ゴマノハグサ科
クワガタソウ:ゴマノハグサ科

オオトリ河原





ブナ林を上ります、ストックを持った K野TD(二週続けての付き合いです)
K野TD(二週続けての付き合いです)

 アミガサダケ(食用:欧米では
アミガサダケ(食用:欧米では 高級品だそうです)
高級品だそうです)

11:45・12:00 ブナ平・昼食 


木に挟んであるのは管理人の「 置き傘」殺虫剤スプレーも各所にあった。
置き傘」殺虫剤スプレーも各所にあった。

クワガタソウ(鍬形草)

コバイケイソウの群落

 ハシリドコロの実:「猛毒アルカロイド、ヘロインの合成物質」含有
ハシリドコロの実:「猛毒アルカロイド、ヘロインの合成物質」含有

空に 突き上げる岩の峰
突き上げる岩の峰

ヤマ ネコノメソウ
ネコノメソウ

ハルリンドウ

稜線手前でザックをデポ、 空身で山頂へ
空身で山頂へ

13:00 梵天尾根(ほぼ平行している登山道)と 合
合 流
流

山頂までミツバツツジが

13:05 日向大谷(メインルート) 登山道
登山道 合流
合流

13:10 両神山:1724m 

秩父の北端に位置し、鋸歯状の山容を誇る。
シロヤシオ、アカヤシオ、紅葉の時期がいい。
日本武尊に関する伝説がある。
山名の由来には、①東征の折に八日間見続けて歩いたので「八日見説」
②イザナギ、イザナミの「両神説」等ある。
 :@父不見山秋
:@父不見山秋
深田久弥さんの「日本百名山
 両神山」を紹介すると
両神山」を紹介すると
~中略 大よその山は、三角形であったり屋根形であったりしても、
左右に稜線を引いて山の体裁を作っているものだが、両神山は異風である。
それがギザギザした頂稜の一線を引いているが、左右はブッ切れている。
あたかも巨大四角い岩のブロックが空中に突き立っているような、
一種怪奇なさまを呈している。古くから名山として尊崇されているのも
この威圧的な山容からであろう。 【深田久弥著: 日本百名山】より
日本百名山】より
 :日本百名山標柱
:日本百名山標柱 
岩峰なので山頂はせまい。

眺望は360°

 でこの通り(雲取山~奥多摩方面)
でこの通り(雲取山~奥多摩方面)
 『山頂写真はピンボケで不記載』
『山頂写真はピンボケで不記載』 トットト降りました
トットト降りました

保護網を被ったササバギンラン@ブナ平

🍄 


膨らんだコバイケイソウの蕾 



15:00 昇竜の滝 




ヒメレンゲ

15:20 登山口、チチブサラサドウダン @山中宅

”登山バッジ”の バッグがありました、キャッシュのほうが
バッグがありました、キャッシュのほうが

16:10 道の駅「薬師の 湯」小鹿野町🚐ターミナル
湯」小鹿野町🚐ターミナル
*
行程:標高差863m/6km/5時間
10:10 白井差登山口 ⇒10:30 昇竜の滝 ⇒11:10 大又
⇒11:40・12:00 ブナ平・昼食 ⇒13:00 梵天尾根合流
⇒13:05 日向大谷合流 ⇒13:10 両神山 ⇒14:00 ブナ平
⇒15:00 昇竜の滝 ⇒15:20 登山口 =19:30 新宿駅
**

 連れが『
連れが『 喜寿
喜寿 』に
』に 






「横浜市敬老特別乗車証」を購入、市内 、地下鉄、モノレール無料で乗れます
、地下鉄、モノレール無料で乗れます

元町で昼食をご馳走しました












 降ってます。
降ってます。













 陽ざしも出てきました
陽ざしも出てきました
 男体山へ、エイザンスミレ
男体山へ、エイザンスミレ











 カタクリ
カタクリ









 出船
出船 入船
入船





 スタンバイ)
スタンバイ)
 蛇弁財天
蛇弁財天

 筑波山神社
筑波山神社
 快晴でした
快晴でした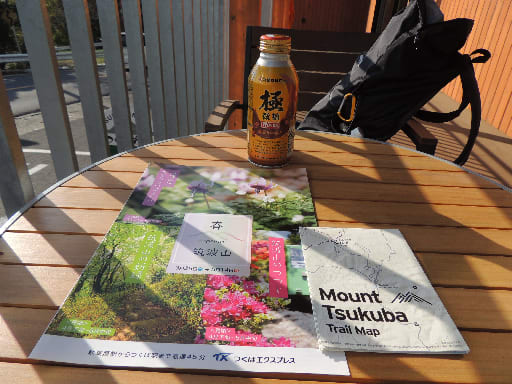
 貴重だし、
貴重だし、 役に立つ・・・・・。
役に立つ・・・・・。
 ~塔ノ岳
~塔ノ岳
 下りは大倉尾根で
下りは大倉尾根で




 尾関廣』氏の銅像です
尾関廣』氏の銅像です

 渉
渉 



 ウドン類+Etcを小屋まで
ウドン類+Etcを小屋まで



 protrek(casio)
protrek(casio)


 ・・・鍋焼うどんが待ってる
・・・鍋焼うどんが待ってる




 もらいました)
もらいました)
 花粉で霞んでます
花粉で霞んでます







 大丸の下り、足元は
大丸の下り、足元は 泥濘・
泥濘・ ぬかるみ・
ぬかるみ・ グチャグチャです
グチャグチャです







 お汁粉よりも
お汁粉よりも ソフトクリームかな?
ソフトクリームかな? 

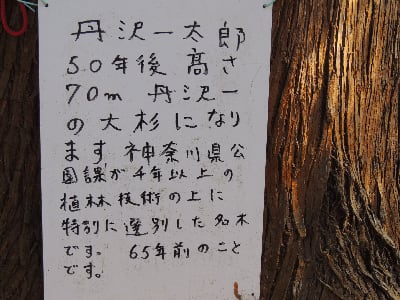
 キャンプ
キャンプ サイト経由で
サイト経由で


 「丹沢の門」足元はフッキソウ
「丹沢の門」足元はフッキソウ




 フリープラン:現地で約
フリープラン:現地で約






 紅葉
紅葉













 2228m
2228m

 不良に
不良に


























 何かに見えませんか?)
何かに見えませんか?)








 ピンぼけ(視力はよくなったはず
ピンぼけ(視力はよくなったはず だけど)
だけど)



 苔坊主
苔坊主





 下ります。
下ります。







 未想定)
未想定)

 撤収・・・・。
撤収・・・・。






 大弛峠着、15:00発のバスで塩山駅へ
大弛峠着、15:00発のバスで塩山駅へ 戻りました。
戻りました。