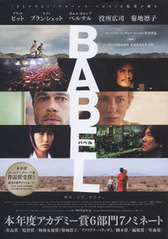モロッコで少年が遊び半分で銃の引き金を引いた。
銃弾は1台のバスをめがけて放たれ、
バスに乗っていたスーザン(ケイト・ブランシェット)に命中した。
スーザンはアメリカ人で、夫のリチャード(ブラッド・ピット)と旅行中だった。
3人目の子供を亡くしてから、冷え込んだ夫婦の溝を埋めようとしていた旅だった。
モロッコの山道で、突然の不幸に見舞われた二人は、医者を求めて近くの村へ向かった。
一方、リチャード夫婦の留守を預かるアメリア(アドリアナ・バラーザ)は苛立っていた。
息子の結婚式が迫っているのに、リチャード夫婦が帰ってこないことには、結婚式に出かけることができないのだ。
アメリアは、リチャードの二人の子供マイクとデビーを連れて、メキシコに向かうことにする。
甥のサンチャゴ(ガエル・ガルシア・ベルナル)の車に乗り込んだ3人は、国境に向かう。
そのころ、東京ではヤスジロー(役所広司)を探す刑事の姿があった。
世界のあちこちでバラバラに起きた出来事は、実は関係のあるものだったのだ。
物事が順調に進んでいるとき
私たちは、つい傲慢な気持ちを持ってしまう。
誰の力も借りずに、自分ひとりの力で生きてきたようなつもりになる。
でも、いったん物事が悪いほうへ転がりだすと
ボタンを掛け違えたように
次々と悪いことが連鎖して起こって
傲慢な気持ちは、もろく崩れ去る。
誰かに責任を押し付けたくなる。
逃げたくなる。
叫びたい。
誰か助けて。
大声で助けを呼びたくなる。
でも、それがもし、言葉の繋がらない場所だったら?
大昔、世界中の人々は、ひとつの同じ言語を話していたという
しかし、神の怒りに触れ、神は言語をばらばらにし
人々の心もバラバラになったのだという。
モロッコ、アメリカ、メキシコ
東京のクラブの天井にまで空が映し出される。
そうなんだ。
まだ、全てがバラバラになったわけではないんだ。
少なくとも、まだ繋がっているものがある。
同じ言語を持っていても、繋がらない想いもある。
誰もが、人と人との距離の取り方に悩んでいる。
伝えきれない想いを抱えた時、人は人のぬくもりを求めるのかもしれない。
言葉を持たないチエコ(菊池凛子)は、吐き出せない想いを胸に抱えていた。
母に自殺されてしまった悲しみを、父のヤスジローにも誰にも吐き出せないでいる。
チエコが望んでいるのは、なぐさめの言葉でもない。
ただ誰かにそっと抱きしめてもらいたいのだ。
その願いを伝えるためにとったチエコの行動は、あまりにも突飛で痛々しくて
観ているこちらの心まで、ヒリヒリと痛くなってくる。
湧き上がるような感動を期待してはいけない映画だと思う。
どこか痛さを感じて
それでも暗い夜道にポツンを灯った明かりを見つけて
映画館を出てこれたら、それでいいのだと思う。
どうやって想いを伝えよう。
人と人との距離を、どうとったらいいのだろう。
誰もが悩むことだけど、
答えなんかないし、出せっこないのだ。
きっと、ずっとずっと生きている限り、それぞれが探し続けていくものなんだと思う。