
本作は、2003年、第129回直木三十五賞候補作。2006年に文庫化にあたった改稿されているそうです。私にとっては「死神の精度」(5/5付け記事「人生が調査される時に示される、『死神の精度』(伊坂幸太郎著/文春文庫)」)に続く、伊坂作品の二作目。映画では「最後にわかるタイトルの意味、『アヒルと鴨のコインロッカー』(2007年)」(5/6付け記事)を観ています。明らかに伊坂ワールドにはまりつつあります。
ストーリーの中に繰り出されるキーワードが、作品を読み進む中で時折、柳の葉が顔を掠めるように、目の前にひらひらとなびいてくる、そんなしかけが心憎いばかりです。「山椒魚」と「走れメロス」、ネアンデルタール人とクロマニオン人との対比も見事です。本作の内容については、北上次郎さんが解説で、「放火と落書きと遺伝子の物語」と端的に表現しています。
タイトルの「重力ピエロ」という風変わりなネーミングは、次の一節で説明されています。
「『本当に深刻なことは、陽気に伝えるべきなんだよ』 まさに今がそうだ。ピエロは、重力を忘れさせるために、メイクをし、玉に乗り、空中ブランコで優雅に空を飛び、時には不恰好に転ぶ。何かを忘れさせるために、だ。私が常識や法律を持ち出すまでもなく、重力は放っておいても働いてくる。それならば、唯一の兄弟である私は、その重力に逆らってみせるべきではないか」。
ちなみに、ピエロは、道化師とも呼ばれ、その滑稽な格好、行動、言動などから、サーカスのなかでも低く見られがちですが、サーカス団の中では代表者が演じるのが基本のようです。もう少し、詳しくチェックしてみると、次のように解説されます。
「サーカスのクラウン (Clown) や中世ヨーロッパの宮廷道化師 (Jester) がそれにあたる。派手な衣装と化粧をし、サーカスなどで玉乗りや司会を行う人のことをピエロとよぶのは日本だけであり、正しくは「クラウン」とよばれる。こうしたもののステレオタイプ的な例は、マクドナルドの イメージキャラクターや、バットマンのジョーカーなどにみることができる。本来のピエロは、コメディア・デラルテに登場する、顔は真っ白で哀愁を漂わせ、好きな人を殺してしまうことでしか愛情表現できないキャラクターが起源とされる」。
「古代エジプトまで遡ることができる。中世のヨーロッパなどでは、特権階級にある人物が城内に道化としての従者を雇っていたことが確認されており『宮廷道化師』と呼ばれている。宮廷道化師の仕事はその名の通りの主人または周囲の人物達を楽しませる役割の他、王のスパイとして主に城内の(反逆の恐れのある人物などの)様子を探る諜報活動も行っていた」。
「また、宮廷道化師達は小人症などの肉体的障害を持っているものが多く、笑い物としての対象にされていた。しかし、君主に向かって無礼なことでも自由にものを言うことができる唯一の存在でもあった。尚、宮廷道化師達の肖像は犬と一緒に描かれることが多く、彼らが犬と同様に王の持ち物とされていたことを裏付けている。シェイクスピアの戯曲などにもしばしば登場し、重要な役を担う。日本では明治時代に始めて曲芸を行った」。(ウィキペディア)
本書で印象的だった箴言は次の一節でした。
「世の中の悲劇は、一般人の勘違いと政治家の自信から起きるんだ」(泉水)
ストーリーの中に繰り出されるキーワードが、作品を読み進む中で時折、柳の葉が顔を掠めるように、目の前にひらひらとなびいてくる、そんなしかけが心憎いばかりです。「山椒魚」と「走れメロス」、ネアンデルタール人とクロマニオン人との対比も見事です。本作の内容については、北上次郎さんが解説で、「放火と落書きと遺伝子の物語」と端的に表現しています。
タイトルの「重力ピエロ」という風変わりなネーミングは、次の一節で説明されています。
「『本当に深刻なことは、陽気に伝えるべきなんだよ』 まさに今がそうだ。ピエロは、重力を忘れさせるために、メイクをし、玉に乗り、空中ブランコで優雅に空を飛び、時には不恰好に転ぶ。何かを忘れさせるために、だ。私が常識や法律を持ち出すまでもなく、重力は放っておいても働いてくる。それならば、唯一の兄弟である私は、その重力に逆らってみせるべきではないか」。
ちなみに、ピエロは、道化師とも呼ばれ、その滑稽な格好、行動、言動などから、サーカスのなかでも低く見られがちですが、サーカス団の中では代表者が演じるのが基本のようです。もう少し、詳しくチェックしてみると、次のように解説されます。
「サーカスのクラウン (Clown) や中世ヨーロッパの宮廷道化師 (Jester) がそれにあたる。派手な衣装と化粧をし、サーカスなどで玉乗りや司会を行う人のことをピエロとよぶのは日本だけであり、正しくは「クラウン」とよばれる。こうしたもののステレオタイプ的な例は、マクドナルドの イメージキャラクターや、バットマンのジョーカーなどにみることができる。本来のピエロは、コメディア・デラルテに登場する、顔は真っ白で哀愁を漂わせ、好きな人を殺してしまうことでしか愛情表現できないキャラクターが起源とされる」。
「古代エジプトまで遡ることができる。中世のヨーロッパなどでは、特権階級にある人物が城内に道化としての従者を雇っていたことが確認されており『宮廷道化師』と呼ばれている。宮廷道化師の仕事はその名の通りの主人または周囲の人物達を楽しませる役割の他、王のスパイとして主に城内の(反逆の恐れのある人物などの)様子を探る諜報活動も行っていた」。
「また、宮廷道化師達は小人症などの肉体的障害を持っているものが多く、笑い物としての対象にされていた。しかし、君主に向かって無礼なことでも自由にものを言うことができる唯一の存在でもあった。尚、宮廷道化師達の肖像は犬と一緒に描かれることが多く、彼らが犬と同様に王の持ち物とされていたことを裏付けている。シェイクスピアの戯曲などにもしばしば登場し、重要な役を担う。日本では明治時代に始めて曲芸を行った」。(ウィキペディア)
本書で印象的だった箴言は次の一節でした。
「世の中の悲劇は、一般人の勘違いと政治家の自信から起きるんだ」(泉水)










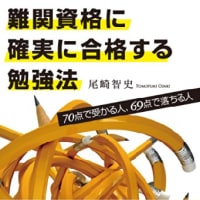
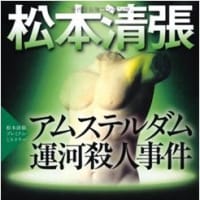
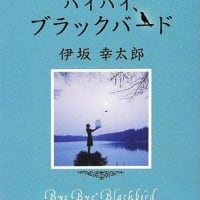

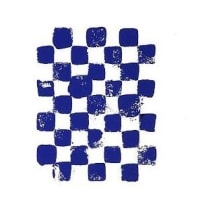
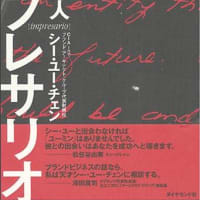



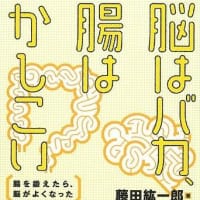
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます