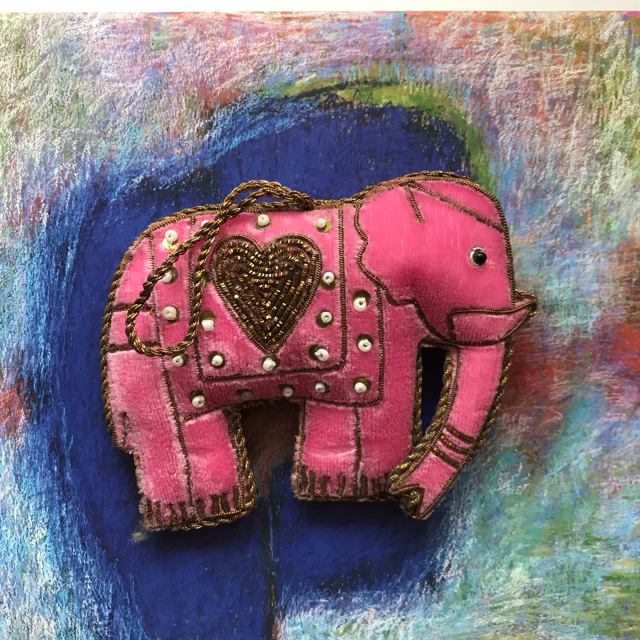アップルの元CEO、スティーブ・ジョブズ氏が5日死去されました。
私は全然アップル・ユーザーではないので、その製品の魅力を実感しているわけではないのですが、
熱烈なアップル・ファンが魅かれるところを聞くと、理解できる気がします。
そこには、「アート」があるのではないか?と思うわけです。
今回のニュース等で、「現代のダ・ヴィンチ」とたとえる表現がありましたが、
なるほど、その通りだな、と思いました。まさにイノベーターと呼べる人。こんな人はちょっと思い当たりません。なので、よく知っている人ではないのですが、死去の知らせを聞いた時、本当に「惜しい人が亡くなってしまった…」と心から残念に、残念に思いました。
それで、テレビなどで一部は目にしていた、2005年の有名なスタンフォード大学での演説をネットで初めて見てみました。
ものすごーく感動していまいました。彼が語る3つのストーリーは、どれも体験に裏打ちされた強いメッセージが込められています。
特に3つ目の「死」についてのストーリーは、彼が亡くなってしまった後に聞くと、この数年間のアップルの革新と躍進は、そのような壮絶な思いものもとでなされたものであったのだ、と思い知らされます。
そして、テレビなどで取り上げられていなかった1つめのストーリーが、わたしの心を最も惹きつけました。
彼が退学することになったリード大学は、国内で最高のカリグラフィ教育が提供されていて、そこで学問として学んだ美しいフォントの作り方が後にマックを開発するときに活かされたというのです。
長い歴史における文字の変遷、その中で生み出された美しい書体を学ぶこと、美しい文章に見せるために文字と文字のスペースを微妙に調整していく技術、そのような科学では把握できないフォントの美というものに魅せられたジョブズ氏。
「ああ、やっぱりそうだったんだ…!」と思いました。美しいフォントを持つ世界初のコンピュータの誕生という直接的なつながりもさることながら、彼のイノベーションにアートがある理由がわかった気がしたのです。
「Stay hungry. Stay foolish.」
この演説のひとつひとつのストーリーに、「君は今、どうなんだ?」と突きつけられている気がします。
改めてジョブズ氏の偉大さに敬服し、ご冥福をお祈りします。

私は全然アップル・ユーザーではないので、その製品の魅力を実感しているわけではないのですが、
熱烈なアップル・ファンが魅かれるところを聞くと、理解できる気がします。
そこには、「アート」があるのではないか?と思うわけです。
今回のニュース等で、「現代のダ・ヴィンチ」とたとえる表現がありましたが、
なるほど、その通りだな、と思いました。まさにイノベーターと呼べる人。こんな人はちょっと思い当たりません。なので、よく知っている人ではないのですが、死去の知らせを聞いた時、本当に「惜しい人が亡くなってしまった…」と心から残念に、残念に思いました。
それで、テレビなどで一部は目にしていた、2005年の有名なスタンフォード大学での演説をネットで初めて見てみました。
ものすごーく感動していまいました。彼が語る3つのストーリーは、どれも体験に裏打ちされた強いメッセージが込められています。
特に3つ目の「死」についてのストーリーは、彼が亡くなってしまった後に聞くと、この数年間のアップルの革新と躍進は、そのような壮絶な思いものもとでなされたものであったのだ、と思い知らされます。
そして、テレビなどで取り上げられていなかった1つめのストーリーが、わたしの心を最も惹きつけました。
彼が退学することになったリード大学は、国内で最高のカリグラフィ教育が提供されていて、そこで学問として学んだ美しいフォントの作り方が後にマックを開発するときに活かされたというのです。
長い歴史における文字の変遷、その中で生み出された美しい書体を学ぶこと、美しい文章に見せるために文字と文字のスペースを微妙に調整していく技術、そのような科学では把握できないフォントの美というものに魅せられたジョブズ氏。
「ああ、やっぱりそうだったんだ…!」と思いました。美しいフォントを持つ世界初のコンピュータの誕生という直接的なつながりもさることながら、彼のイノベーションにアートがある理由がわかった気がしたのです。
「Stay hungry. Stay foolish.」
この演説のひとつひとつのストーリーに、「君は今、どうなんだ?」と突きつけられている気がします。
改めてジョブズ氏の偉大さに敬服し、ご冥福をお祈りします。