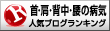4月なのに夏日になったりと、今年の夏も酷暑となりそうな予感がします。
いきなり暑くなると、とても疲れますよね。
まだ暑さに体が慣れていない証拠です。
直射日光による紫外線を避け
水分補給も意識的にしましょうね。
外出時には、帽子やサングラス
目に入る紫外線をカットするだけでも
疲れが違いますよ。
そしてこれから気を付けないといけないのが、熱中症や夏バテ。
以前は梅雨明けからというイメージでしたが
ここ数年はゴールデンウイーク明けから
どっと増えているのです。

本格的に暑くなる前の対策がとても大切になります。
その対策が「暑熱順化」です。
特に気を付けてほしいのが
・体温が低い人
・汗をかきづらい冷え性の人
・日頃から水分不足の人
・運動不足の人
・高齢者
上記に当てはまる方は是非対策をしてください。
1,暑熱順化とは
暑熱順化とは「体が暑さに慣れること」です
最初はちょっとした暑さも堪えますよね。
体がだるくなったり、すぐ疲れたりします。
暑い日がしばらく続くと、
体は次第に暑さに慣れて(暑熱順化)、暑さに強くなります。

本格的な暑さが来る前に
ある程度、暑さに慣れる事で
スムーズに夏を迎えられるようになります。
2,暑熱順化のポイントは発汗
熱中症・夏バテの予防となる「暑熱順化」
ポイントは発汗です。
特に気を付けてほしいのが最初に書きました
・体温が低い人
・汗をかきづらい冷え性の人
・日頃から水分不足の人
・運動不足の人
・高齢者
に当てはまる人です。
年齢が上がるにつれて発汗機能も衰えがちです。
そもそも、汗をかくとなぜ暑さに順応しやすいのでしょうか?
人は運動や仕事などで体を動かすと、
体内で熱が作られて体温が上昇します。
体温が上がった時は、
汗をかくこと(発汗)による気化熱や、
心拍数の上昇や皮膚血管拡張によって
体の表面から空気中に熱を逃がす熱放散で、
体温を調節しています。
この体温の調節がうまくできなくなると・・・
体の中に熱がたまって体温が上昇し、熱中症が引き起こされます。
暑熱順化がすすむと、発汗量や皮膚血流量が増加し、
発汗による気化熱や体の表面から熱を逃がす熱放散がしやすくなります。
ですので
発汗や血流量を増やすことが一番の対策になります。

3,暑熱順化をするには?
日常生活でできる暑熱順化に効果的な行動として
・ウォーキングやジョギング、サイクリング など、
汗をかく程度の運動を週に2~3回
・筋トレやストレッチ、ラジオ体操など、
体が暖まる程度の運動を週に4~5日
・サウナや入浴(湯船につかる) できれば毎日

運動はもちろんですが、お風呂で湯船につかるのも暑熱順化に繋がります。
シャワーだけで済ませず、湯船にお湯をはって入りましょう。
お湯の温度が高めの場合には時間は短め、温度が低めの場合は少し長めの入浴することがおすすめです。
4,暑熱順化にはどの位かかる?
暑熱順化には個人差もありますが、
数日から2週間程度かかります。
また、個人差もありますが
1週間以上開けてしまうと効果がリセットされてしまいます。
暑くなる前から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始め、暑さに備えましょう。