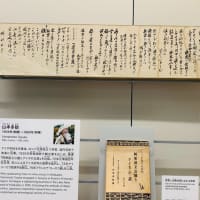レーニンの始めた共産主義経済運営は第二次大戦後のアメリカとの軍拡・宇宙覇権争いの高コストを支えきれず、綻びをきたした。 それが直接的なソヴィエト型社会主義統治失敗の物的原因とするのは
恐らく正しい。 かたや、1985年以降のソ連が自ら壊れゆく過程で人々が指導原理を探しながら疑い・問い続けた概念は『ソヴィエト』であり『連邦』の2語であった。
それは、此の国家が抱えてきた構造的課題を”レーニン主義の誤謬”云々に押し付けるだけでは済まない深さを示していた、と私は思う。 昨日用いた表現に戻るなら・・・
≪ロシア正教の説く(人と神)&(救済観)を新しい国家統治イデオロギーに取り込む試み≫は、ロシア的大衆概念<ボリシェヴィキ>を拠り所とする『ソヴィエト』に依存し、其の裏打ちにロシア正教の力を利用するものである。1993年のエリツィン対ソ連最高会議派+教会勢力との対決は『ソヴィエト』概念による連邦形態の維持を巡る争いでもあった。
他方≪ロシア正教の取り込みを迂回した社会民主主義的統治への模索≫とは、共産主義イデオロギーの代替物として既存宗教を利用せず、実務的で効率の良い国家統治形態のみを求めた。
此の考え方は(多数ではない少数派)を意味する<メンシェヴィキ>が多様な存在を前提に置くので、連邦は解体し民族・言語単位で独立国家運営に任せる。もう『連邦』概念は必須とみなされないのだ。
事実、バルト3国の独立をゴルバチョフが認めたばかりか、91年12月の独立国家共同体の創設とソ連崩壊は、ロシア中心に寄り添う小国とウクライナ・ベラルーシ・カザフスタンなどの広大で資源に
恵まれた大国の併存を招いた。この結果は一見、レーニンの戦略と真逆な<メンシェヴィキ>派の勝利に映る。だが混迷の90年代でも消えなかったのが、軍人及びKGB勢力の国家イデオロギーだった。
国防を職業意識だけでなく国民としてのアイデンティティーと思いながら生きてきた軍人及びKGB勢力にとり、85年以降続く国力衰退、経済の疲弊、ソ連解体に向けられた欧米の嘲笑は看過できなかっただろう。もはや、イデオロギーも宗教も彼らには本義ではない。
91年の”対ゴルバチョフクーデター”失敗後、訴追の危機にあったアルクスニスという名の高級軍人と同年8月24日接触した著者は、次のような言葉を引用している・・。(P481)
【非常事態国家委員会の連中はソ連体制を守っただけで、ソ連憲法に違反する事は何もしていない。次々と大統領令を繰りだしてソ連国家を破壊しているエリツィンのやり方こそがクーデターだ。
ソ連に共産主義は要らない。必要なのは国家だけだ。】・・此の言葉こそ、マルクス・レーニン主義を捨てたロシア人の本音であり、現在のプーチン政権が受け継いだものだ。
ソ連崩壊よりも10年早く共産主義を捨てた鄧小平の<改革開放>が奏功し始めたのは、奇しくも80年代後半から90年代にかけて。エリツィン以降のプーチンに至る権力者は恐らく中国の変身ぶりを
横目で見ながら学んだに違いない。学んだのは資本主義型自由市場経済の果実を国家が吸い上げつつ(多数ではない少数派)を意味する<メンシェヴィキ>支配ではなく、<ボリシェヴィキ>概念で
く疑似代議制をまとう少数者による独裁統治体制>の維持だ。これは毛沢東の『人民独裁』と呼応する。中国との違いは、ロシアが宗教(=ロシア正教)の影響力を統治力学に活用している点しかない。
此の方法で、一度崩れたソ連帝国はロシア共和国という名の帝国に生まれ変わった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ソ連自壊の精神的側面とプロセスをここまで整理すると、ここ数週間騒がしくなってきた”ロシアのウクライナ侵攻懸念”と、自壊の教訓がどの様に繋がっているのかも朧気ながら見えてくる。
旧ソ連最高会議派と軍部は独立国家共同体の創設時、ソ連を構成していた全諸国の分離独立に反対し<ロシア・ウクライナ・ベラルーシ・カザフスタン>だけは独立国家共同体に残そうと主張したが、
エリツィン大統領の指導力に陰りが見えた末期、国務長官であったブルブリスは完全分解を進言、結果は進言通りになった。この解体が現在のロシア外交を方向づけた、と思われる。
混乱の15年を経て世紀が変わるまでの間に東欧諸国の多くがNATOに加盟。ロシアから観れば欧米勢力圏の東進であり、盟主ロシアにとり無視できない脅威ゆえ、強権統治で対応するほかないと映る。
中でも、ウクライナがNATOに加盟するなら喉元に欧米の軍事基地が置かれるので、失う訳にはいかない。其の先駆けが2014年のクリミア半島併合だ。危ないトランプから大人しいバイデンに変わり、プーチンは足元を見て出方を窺ってるのだろう。
現下の国際情勢とソ連自壊後の繋がりはここまでにしておき、次は著者が「あとがき」の最後で述べている重要なポイントについて紹介したい。 < つづく >
恐らく正しい。 かたや、1985年以降のソ連が自ら壊れゆく過程で人々が指導原理を探しながら疑い・問い続けた概念は『ソヴィエト』であり『連邦』の2語であった。
それは、此の国家が抱えてきた構造的課題を”レーニン主義の誤謬”云々に押し付けるだけでは済まない深さを示していた、と私は思う。 昨日用いた表現に戻るなら・・・
≪ロシア正教の説く(人と神)&(救済観)を新しい国家統治イデオロギーに取り込む試み≫は、ロシア的大衆概念<ボリシェヴィキ>を拠り所とする『ソヴィエト』に依存し、其の裏打ちにロシア正教の力を利用するものである。1993年のエリツィン対ソ連最高会議派+教会勢力との対決は『ソヴィエト』概念による連邦形態の維持を巡る争いでもあった。
他方≪ロシア正教の取り込みを迂回した社会民主主義的統治への模索≫とは、共産主義イデオロギーの代替物として既存宗教を利用せず、実務的で効率の良い国家統治形態のみを求めた。
此の考え方は(多数ではない少数派)を意味する<メンシェヴィキ>が多様な存在を前提に置くので、連邦は解体し民族・言語単位で独立国家運営に任せる。もう『連邦』概念は必須とみなされないのだ。
事実、バルト3国の独立をゴルバチョフが認めたばかりか、91年12月の独立国家共同体の創設とソ連崩壊は、ロシア中心に寄り添う小国とウクライナ・ベラルーシ・カザフスタンなどの広大で資源に
恵まれた大国の併存を招いた。この結果は一見、レーニンの戦略と真逆な<メンシェヴィキ>派の勝利に映る。だが混迷の90年代でも消えなかったのが、軍人及びKGB勢力の国家イデオロギーだった。
国防を職業意識だけでなく国民としてのアイデンティティーと思いながら生きてきた軍人及びKGB勢力にとり、85年以降続く国力衰退、経済の疲弊、ソ連解体に向けられた欧米の嘲笑は看過できなかっただろう。もはや、イデオロギーも宗教も彼らには本義ではない。
91年の”対ゴルバチョフクーデター”失敗後、訴追の危機にあったアルクスニスという名の高級軍人と同年8月24日接触した著者は、次のような言葉を引用している・・。(P481)
【非常事態国家委員会の連中はソ連体制を守っただけで、ソ連憲法に違反する事は何もしていない。次々と大統領令を繰りだしてソ連国家を破壊しているエリツィンのやり方こそがクーデターだ。
ソ連に共産主義は要らない。必要なのは国家だけだ。】・・此の言葉こそ、マルクス・レーニン主義を捨てたロシア人の本音であり、現在のプーチン政権が受け継いだものだ。
ソ連崩壊よりも10年早く共産主義を捨てた鄧小平の<改革開放>が奏功し始めたのは、奇しくも80年代後半から90年代にかけて。エリツィン以降のプーチンに至る権力者は恐らく中国の変身ぶりを
横目で見ながら学んだに違いない。学んだのは資本主義型自由市場経済の果実を国家が吸い上げつつ(多数ではない少数派)を意味する<メンシェヴィキ>支配ではなく、<ボリシェヴィキ>概念で
く疑似代議制をまとう少数者による独裁統治体制>の維持だ。これは毛沢東の『人民独裁』と呼応する。中国との違いは、ロシアが宗教(=ロシア正教)の影響力を統治力学に活用している点しかない。
此の方法で、一度崩れたソ連帝国はロシア共和国という名の帝国に生まれ変わった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ソ連自壊の精神的側面とプロセスをここまで整理すると、ここ数週間騒がしくなってきた”ロシアのウクライナ侵攻懸念”と、自壊の教訓がどの様に繋がっているのかも朧気ながら見えてくる。
旧ソ連最高会議派と軍部は独立国家共同体の創設時、ソ連を構成していた全諸国の分離独立に反対し<ロシア・ウクライナ・ベラルーシ・カザフスタン>だけは独立国家共同体に残そうと主張したが、
エリツィン大統領の指導力に陰りが見えた末期、国務長官であったブルブリスは完全分解を進言、結果は進言通りになった。この解体が現在のロシア外交を方向づけた、と思われる。
混乱の15年を経て世紀が変わるまでの間に東欧諸国の多くがNATOに加盟。ロシアから観れば欧米勢力圏の東進であり、盟主ロシアにとり無視できない脅威ゆえ、強権統治で対応するほかないと映る。
中でも、ウクライナがNATOに加盟するなら喉元に欧米の軍事基地が置かれるので、失う訳にはいかない。其の先駆けが2014年のクリミア半島併合だ。危ないトランプから大人しいバイデンに変わり、プーチンは足元を見て出方を窺ってるのだろう。
現下の国際情勢とソ連自壊後の繋がりはここまでにしておき、次は著者が「あとがき」の最後で述べている重要なポイントについて紹介したい。 < つづく >