8時半、起床。
今日も晴れて暖かい。でも、明日からはしばらく曇り日が続くそうだ。

胡桃パン、目玉焼き、豚汁、牛乳、珈琲の朝食。日曜は妻が寝坊するので、サラダを作ってもらえない。もちろん自分で作ることはできるが、「サラダは妻が用意してくれる」という頭があるので、手が動かないのである。

昨日のブログを書いてアップする。初訪問した近所のインド料理店の話や、『いちばんすきな花』の「美鳥」の役割について考察していたら、長いものになった。
昼食は昨日臨時休業だった「吉岡家」で食べる。

天ざる(1250円)を注文する。

キンドルで志賀直哉の「好人物の夫婦」を読みながら、食事をする。食事中は、行儀の問題以前に、両手を使っていることが多いので、本は扱いにくいのだが、キンドルだと立てて読むことができるので(ページをめくるときだけ指先でちょっと画面をタッチすればよい)食事の邪魔にならない。

食後のお茶は「きりん珈琲」で。

「いらっしゃいませ」

「好人物の夫婦」の続きを読む。ずいぶんと久しぶりで読んで、どんな話だったか忘れていたが、夫の浮気を心配する妻を夫の視点から描いた作品だった。この文庫に収められている11篇は作者の自選だそうだが、なるほど、完成度の高い作品ばかりだ。もっとも私が好きなのはこういう物語仕立ての作品よりも、筋らしい筋のない作品(たとえば「豊年中」とか)の方で、その方が志賀直哉の文体の魅力がいっそう際立つ。高校時代、私はそういう作品を繰り返し読み、なんとか志賀直哉の文体を吸収できないかと思ったものである。

苺あんと削りホワイトチョコのレアチーズケーキ。珈琲はグァテマラ。

星新一『ノックの音が』(新潮文庫)の冒頭の一篇「なぞの女」を読む。本書には15のショート・ショートが収められているが、いずれも「ノックの音がした」で始まっている。そこから多様な物語が展開するわけで、中学生の私は、その発想の豊かさに舌を巻いたのはもちろんだが、いまにして思うと、星新一のモダンな文体にも大いに惹かれていたのだと思う。ちなみに私の息子も中学生の頃に星新一にはまり、彼の書棚には文庫化された星新一の全作品がそろっている。新井素子編『ほしのはじまりー決定版星新一ショート・ショート』が電子書籍化されていないのは残念である。
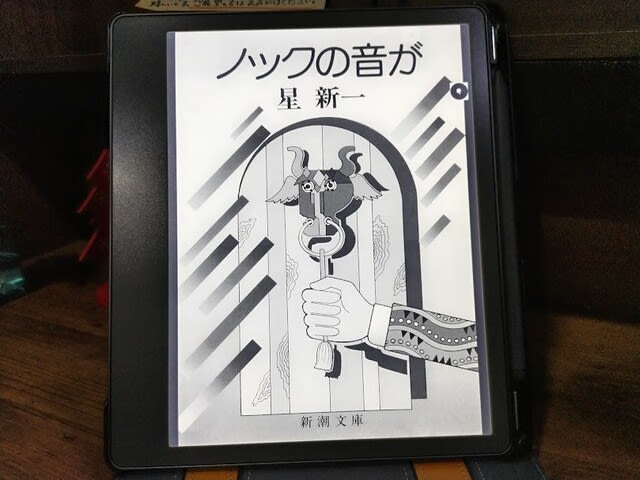
東海林さだお『大盛り!さだおの丸かじり』(文春文庫)。『週刊朝日』に長期にわたって連載されたエッセー「あれも食いたいこれも食べたい」は雑誌の休刊(終刊)よって惜しまれつつ終わってしまったが、「丸かじり」シリーズとして単行本化されており、来年1月に出る予定の『カレーライスの丸かじり』で47巻目になる。もちろん全巻所有している。本書はその傑作選。

冒頭の一篇「午後の定食屋」を読む。私が自宅にいる日も昼食は外に食べに出るのは東海林さだおの影響もある(かもしれない)。ただし、彼はカフェごはんというのあまりしないように見受けられる。食堂中心である。彼のフィールドワークのまなざしは社会学者(とくにゴフマン)のようであり、学生には社会学の入門書としても薦めている。

挿入されるスケッチには漫画家としての才が十分に発揮されている。

珈琲豆が焙煎されるのを待つ間、もう一冊。米長邦雄『人間における勝負の研究』(祥伝社黄金文庫)を読む。私はいまはもっぱらNHKの将棋講座やネットTVで藤井聡太のタイトル戦を観るだけだが、若いころは、将棋道場でよく将棋を指していた。将棋道場で他人と将棋を指すのは周囲に(互角以上に戦える)相手がいなかったからである。将棋の戦法について解説した本はたくさん買ったが、読み物としての面白さは米長邦雄と彼の弟子の先崎学が抜きんでていた。本書は彼の勝負哲学について書かれたもの。「自分にとっては消化試合のような対局であっても、相手にとってタイトル挑戦や昇段のかかった大切な一番こそ、全力で戦うべし」という教えはいまの若い棋士たちにも伝わっているようである。
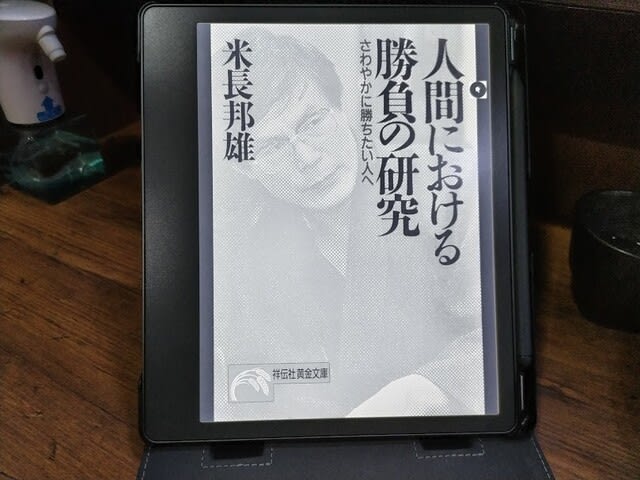
店に入ったときに注文しておいた「きりん珈琲ブレンド」が出来上がった。

帰り道、JRの跨線橋を渡ったら、何かのロケが行われていた。たくさんのスタッフがいて、韓国語と日本語はまじりあっていた。

妻がホームセンターから木材を買ってきて自分で本棚を作っていた。チャイがさっそく興味をしめしている。

夕食は「マーボ屋」でテイクアウトした。

昨日、昼食で食べたかった(満席で入れなかった)牡蠣の甘辛炒めと海老のサクサクフリッター、春雨サラダ、ワカメと卵のスープ、ごはん。

食事をしながら『どうする家康』が始まるまで『ザ・マンザイ2023』を観る。たまたま観た中では「銀シャリ」が上手いなと思った。選抜された若手ががむしゃらに頑張っているのに比べて、余裕がある。笑いに余裕があることは大切。くつろいで観ていられる。

『どうする家康』はいよいよ来週が最終回。大阪夏の陣、そして家康の死までが描かれるようである。

少し横になってから、レビューシートのチェック。いつも週末は少ないのだが、それでも今週は二科目分あるので(「ライフストーリーの社会学」と「現代人間論系総合講座1」)、それなりの量である。
風呂から出て、『桑田佳祐のやさしい夜遊び』をタイムフリーで聴きながら、今日の日記を付ける。

1時半、就寝。















