「さらば、わが愛/覇王別姫」 1993年 香港

監督 チェン・カイコー
出演 レスリー・チャン
チャン・フォンイー
コン・リー
グォ・ヨウ
ストーリー
1925年、北京。娼婦の母親に連れられ、孤児や貧民の子供たちが集まる京劇の養成所に入った9歳の少年・小豆子は他の子供たちからいじめられたが、彼を弟のようにかばったのは小石頭だけだった。
2人は成長し、女性的な小豆子は女役に、男性的な小石頭は男役に決められる。
彼らは演技に磨きをかけ、小豆子は程蝶衣、小石頭は段小と芸名を改め、京劇のコンビとして人気を博す。
段小はある日、しつこい客に絡まれていた娼婦の菊仙を助けたことをきっかけに、彼女と結婚する。
少年時代より段小にほのかな恋情を覚えていた程蝶衣は2度と共演はしないと捨てゼリフを吐いて去る。
その日北京は日本軍に占領された。
ある日小は楽屋で騒動を起こし連行されてしまう。
菊仙は日本側に取り入ってもらえるのだったら小と別れてもいいと蝶衣に告げるが、彼の協力で釈放された小は日本のイヌと蝶衣を罵り菊仙を連れて去り、深く傷ついた蝶衣はアヘンに溺れる。
そんなことがありながらも2人は和解へと進む。
日本軍の敗退で抗日戦争は終わり、1949年に共産党政権が樹立された。
蝶衣と小は再び舞台に立つが、京劇は新しい革命思想に沿うよう変革を求められていた。
変革に懐疑的な蝶衣は小四に批判され、そればかりか彼に『覇王別姫』の虞姫役を奪われてしまう。
ショックを受けた蝶衣は芝居をやめてしまい、1966年に文化大革命が起きた。
寸評
時代に翻弄される京劇役者の段小や程蝶衣の目を通して近代中国の50年が描かれているが、単なる歴史絵巻ではなく菊仙を交えた段小や程蝶衣の愛憎劇が異国文化の中で演じられていく。
冒頭で四人組のことが語られ回想形式で物語が始まるが、四人組は僕の世代には記憶に残っているはずだ。
四人組とは、中華人民共和国の文化大革命を主導し、革命を隠れ蓑にした極端な政策で反対派を徹底的に弾圧し、迫害して殺害したが、中国共産党中央委員会主席毛沢東の死後に失脚し、特別法廷で死刑や終身刑などの判決を受けた、江青、張春橋、姚文元、王洪文の四名を指す。
従って、歴史の変遷が中心的に描かれたり、政治的メッセージがあるのかと思ったのだが、そうではなかった。
背景として描かれているのは盧溝橋事件から始まる日中戦争、蒋介石総統率いる中国国民党政府の台湾亡命、文化大革命などの世相的混乱だが、感じるのは歴史の中で翻弄されながらも生きながらえていくために、時の権力者に取り入らざるを得ない人間の弱さである。
どんな相手であろうとも自分の最高の芸を演じ続けるという芸人のプライドよりも、僕は人の弱さを感じた。
それに絶望した菊仙の最後も悲しいものがある。
同時に描かれ、大きなウェイトを占めるのが程蝶衣の段小に寄せる思いだ。
女役をやっていることもあって、蝶衣はホモセクシャルな存在で、秘かな思いを段小に寄せているが、男色の権力者にもてあそばれるし、またそれを利用したりする微妙な立ち位置である。
この二人に菊仙が加わり、段小を巡る男と女の確執が生じるという何とも艶めかしい話だ。
しかしその艶めかしさが前面に出ている訳ではなく、後半で同じような内容が繰り返されるのはくどいように思う。
興味を引くのは京劇の裏事情であった。
僕は香港旅行をした際に、路地に設けられた舞台で京劇の練習が行われている場面に遭遇したことがある。
京劇の内容は分からなかったが、印象に残るのはケバイ飾りつけと独特の音楽、人々を圧倒するメイクと付け髭などだった。
京劇の「覇王別姫」は四面楚歌で有名な項羽と虞美人を描いた作品で、劉邦軍により垓下に追い詰められ、四面楚歌の状態になって自らの破滅を悟った項羽は彼女に「虞や虞や若を如何せん」と歌を贈り垓下から脱出、足手まといにならぬよう虞は自殺したとする内容のようである。
前もって劇の内容が語られているので、ラストシーンにおける程蝶衣の行為が想像できる。
このラストシーンは決まっていた。
この作品は1993年第46回カンヌ国際映画祭で作品賞に当たるパルム・ドールを受賞するなど評価が高い。
異文化に触れたという思いはあったが、僕はそれほどの感動を得たわけではなく少し不満が残る。
中国の近代史を描いているとは言え、歴史を変えていくうねりのようなものは感じ取れなかったし、程蝶衣が段小に寄せる同性愛的な感情も強いものを感じなかった。
程蝶衣と菊仙の確執もよく似た話が繰り返されていて、心の内に入り込む前に飽きが生じてしまっていた。
京劇という馴染みの薄い世界を描いていたので、興味と共に作品内容の雰囲気だけは感じ取れたのだが・・・。

監督 チェン・カイコー
出演 レスリー・チャン
チャン・フォンイー
コン・リー
グォ・ヨウ
ストーリー
1925年、北京。娼婦の母親に連れられ、孤児や貧民の子供たちが集まる京劇の養成所に入った9歳の少年・小豆子は他の子供たちからいじめられたが、彼を弟のようにかばったのは小石頭だけだった。
2人は成長し、女性的な小豆子は女役に、男性的な小石頭は男役に決められる。
彼らは演技に磨きをかけ、小豆子は程蝶衣、小石頭は段小と芸名を改め、京劇のコンビとして人気を博す。
段小はある日、しつこい客に絡まれていた娼婦の菊仙を助けたことをきっかけに、彼女と結婚する。
少年時代より段小にほのかな恋情を覚えていた程蝶衣は2度と共演はしないと捨てゼリフを吐いて去る。
その日北京は日本軍に占領された。
ある日小は楽屋で騒動を起こし連行されてしまう。
菊仙は日本側に取り入ってもらえるのだったら小と別れてもいいと蝶衣に告げるが、彼の協力で釈放された小は日本のイヌと蝶衣を罵り菊仙を連れて去り、深く傷ついた蝶衣はアヘンに溺れる。
そんなことがありながらも2人は和解へと進む。
日本軍の敗退で抗日戦争は終わり、1949年に共産党政権が樹立された。
蝶衣と小は再び舞台に立つが、京劇は新しい革命思想に沿うよう変革を求められていた。
変革に懐疑的な蝶衣は小四に批判され、そればかりか彼に『覇王別姫』の虞姫役を奪われてしまう。
ショックを受けた蝶衣は芝居をやめてしまい、1966年に文化大革命が起きた。
寸評
時代に翻弄される京劇役者の段小や程蝶衣の目を通して近代中国の50年が描かれているが、単なる歴史絵巻ではなく菊仙を交えた段小や程蝶衣の愛憎劇が異国文化の中で演じられていく。
冒頭で四人組のことが語られ回想形式で物語が始まるが、四人組は僕の世代には記憶に残っているはずだ。
四人組とは、中華人民共和国の文化大革命を主導し、革命を隠れ蓑にした極端な政策で反対派を徹底的に弾圧し、迫害して殺害したが、中国共産党中央委員会主席毛沢東の死後に失脚し、特別法廷で死刑や終身刑などの判決を受けた、江青、張春橋、姚文元、王洪文の四名を指す。
従って、歴史の変遷が中心的に描かれたり、政治的メッセージがあるのかと思ったのだが、そうではなかった。
背景として描かれているのは盧溝橋事件から始まる日中戦争、蒋介石総統率いる中国国民党政府の台湾亡命、文化大革命などの世相的混乱だが、感じるのは歴史の中で翻弄されながらも生きながらえていくために、時の権力者に取り入らざるを得ない人間の弱さである。
どんな相手であろうとも自分の最高の芸を演じ続けるという芸人のプライドよりも、僕は人の弱さを感じた。
それに絶望した菊仙の最後も悲しいものがある。
同時に描かれ、大きなウェイトを占めるのが程蝶衣の段小に寄せる思いだ。
女役をやっていることもあって、蝶衣はホモセクシャルな存在で、秘かな思いを段小に寄せているが、男色の権力者にもてあそばれるし、またそれを利用したりする微妙な立ち位置である。
この二人に菊仙が加わり、段小を巡る男と女の確執が生じるという何とも艶めかしい話だ。
しかしその艶めかしさが前面に出ている訳ではなく、後半で同じような内容が繰り返されるのはくどいように思う。
興味を引くのは京劇の裏事情であった。
僕は香港旅行をした際に、路地に設けられた舞台で京劇の練習が行われている場面に遭遇したことがある。
京劇の内容は分からなかったが、印象に残るのはケバイ飾りつけと独特の音楽、人々を圧倒するメイクと付け髭などだった。
京劇の「覇王別姫」は四面楚歌で有名な項羽と虞美人を描いた作品で、劉邦軍により垓下に追い詰められ、四面楚歌の状態になって自らの破滅を悟った項羽は彼女に「虞や虞や若を如何せん」と歌を贈り垓下から脱出、足手まといにならぬよう虞は自殺したとする内容のようである。
前もって劇の内容が語られているので、ラストシーンにおける程蝶衣の行為が想像できる。
このラストシーンは決まっていた。
この作品は1993年第46回カンヌ国際映画祭で作品賞に当たるパルム・ドールを受賞するなど評価が高い。
異文化に触れたという思いはあったが、僕はそれほどの感動を得たわけではなく少し不満が残る。
中国の近代史を描いているとは言え、歴史を変えていくうねりのようなものは感じ取れなかったし、程蝶衣が段小に寄せる同性愛的な感情も強いものを感じなかった。
程蝶衣と菊仙の確執もよく似た話が繰り返されていて、心の内に入り込む前に飽きが生じてしまっていた。
京劇という馴染みの薄い世界を描いていたので、興味と共に作品内容の雰囲気だけは感じ取れたのだが・・・。










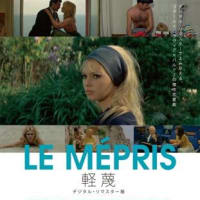
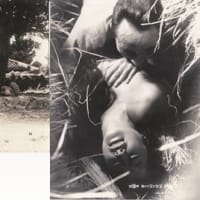

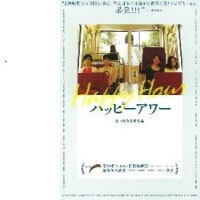
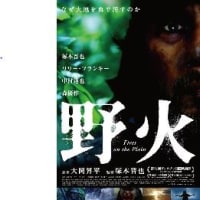
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます