「ブラス!」 1996年 イギリス

監督 マーク・ハーマン
出演 ピート・ポスルスウェイト
ユアン・マクレガー
タラ・フィッツジェラルド
スティーヴン・トンプキンソン
ジム・カーター
メラニー・ヒル
ストーリー
1990年中盤、イギリス・ヨークシャーの炭坑町グリムリー。
仕事のために宿を借りたグロリアは、宿屋の夫人に炭坑夫達で作る歴史あるバンド「グリムリー・コリアリー・バンド」の練習場で練習することを薦められる。
バンドマン達は炭坑の閉鎖騒ぎで気が気ではなく、全英ブラスバンド選手権に備えた練習もおぼつかなかった。
そこへ入ってきたグロリアに、指揮者ダニーは「よそ者は入れない決まりだ」と断るが、グロリアはここの町の生まれだと主張する。
ファミリーネームから、グロリアの祖父がダニーの親友で勇敢な炭坑夫でバンドマンだったと分かる。
バンドマンの一人アンディは、グロリアの幼なじみだった。
グロリアは「アランフェス協奏曲」のソロパートで見事な演奏を見せ、拍手が巻き起こる。
こうして新たなメンバーを得たグリムリー・コリアリー・バンドだったが、実は彼女の仕事は、炭坑についての報告書を作成することだった。
経営側は組合と折衝の結果、炭坑存続か、閉鎖の代わりに高額の退職金を支払うかのどちらかを、炭坑夫に投票させることになる。
バンドは準決勝を勝ち取ったものの、町に帰ってきた彼らを待っていたのは、閉鎖決定という結果であった。
ダニーは長年の炭坑夫生活で、肺をやられていて路上で倒れた。
その後偶然に、バンドマン達はグロリアが経営会社の建物から出てくるのを目撃してしまう。
特にグロリアと恋仲に落ちていたアンディは、少なからずショックを受けるのだった。
アンディは賭けビリヤードでテナーホーンを取られてしまう。
他のメンバー達の心も揺れ動き、生活が逼迫していることや、グロリアに裏切られたという思いもあり、バンドを辞めることを決意する。
寸評
マーガレット・サッチャーは1979年から1990年まで英国首相を務め鉄の女と称された。
サッチャーは電話・ガス・空港・航空・自動車・水道などの国有企業の民営化や規制緩和、金融システム改革を掲げ、改革の障害になっていた労働組合の影響力を削いで、サッチャリズムと呼ばれる新自由主義的・新保守主義的な政策を強いリーダーシップで推し進めた。
本国ではイギリス経済を立て直した救世主と言われる反面、失業者を増大させて地方経済を不振に追いやったとの評価もあるとのこと。
僕は1982年に起こったフォークランド紛争時における毅然とした態度によってサッチャー首相のイメージが植え付けられた。
映画は正にサッチャー政権時の炭鉱を舞台にしている。
フィルが「サッチャーがピンピンしているのに父親のダニーが死にかかっている」と叫んでいるように、作品はサッチャリズムを否定している。
炭鉱閉鎖によって人々の生活は困窮し、家庭は崩壊状態だし、彼らのコミュニティも壊れかけている。
10年前にも長期のストがあり、その時の借金を未だに抱えている家庭もある。
フィルの家庭は差し押さえにあい家財道具を全部持っていかれ、奥さんは子供を連れて出て行ってしまう。
奥さんが夜の仕事についているのか、すれ違いの生活を強いられている者もいる。
それでも彼らは音楽活動を続けていて、それが彼らの生き甲斐の様でもある。
描かれている内容は辛いものだが、ユーモアを織り交ぜながら描いているので楽しめる。
そして誰もが音楽によって癒されるものがあるので、音楽映画は自然と楽しめる部分を有していると思う。
この映画においても演奏シーンはどれもが感動的である。
僕は最初の演奏曲であるホアキン・ロドリーゴの「アランフエス協奏曲」でうっとりしてしまった。
病室のダニーを励ますために、病院の庭で「ダニー・ボーイ」を演奏するシーンも良かったけれど、ロイヤル・アルバート・ホールでメンバーが「ウィリアム・テル序曲」を演奏するシーンでは涙腺が緩んでしまった。
グリムリー・コリアリー・バンドは優勝するがダニーは優勝トロフィーを拒絶し、炭鉱とそこで働く人々とその家族の窮状を訴える演説を行うが、それはきわめて政治的なシーンであった。
ただしダニーが拒否したトロフィを貰っていく者が居て、審査員が「返上するのでは?」と問いかけるが、「ダニーが言ったのは言葉のあやだ」とチャッカリ持ち去る。
前半でメンバーが相乗りの車の中で「女の立ちション」だの「へのつっぱり」などの言葉のあやについて言いあっていたことが伏線となっている愉快なシーンである。
最後までそのようなユーモアを忘れることはなかった。
帰りのバスの中でロンドンの街を走りながらエドワード・エルガーの「威風堂々」を演奏することに彼らのプライドを垣間見た気がする。
世の中、皆が満足することなどは少なくて割を食う人が出てくるのはやむを得ないことだと思うが、日本人の僕は英国の炭鉱労働者が味わっていた過酷な状況を身をもって知るすべはなかったのだなと思った。
他人事と思われることにも注視しないといけないのだろう。
でも彼らの音楽を愛する気持ちと情熱を信じたいし応援したい気持ちが湧いたのは紛れもない。

監督 マーク・ハーマン
出演 ピート・ポスルスウェイト
ユアン・マクレガー
タラ・フィッツジェラルド
スティーヴン・トンプキンソン
ジム・カーター
メラニー・ヒル
ストーリー
1990年中盤、イギリス・ヨークシャーの炭坑町グリムリー。
仕事のために宿を借りたグロリアは、宿屋の夫人に炭坑夫達で作る歴史あるバンド「グリムリー・コリアリー・バンド」の練習場で練習することを薦められる。
バンドマン達は炭坑の閉鎖騒ぎで気が気ではなく、全英ブラスバンド選手権に備えた練習もおぼつかなかった。
そこへ入ってきたグロリアに、指揮者ダニーは「よそ者は入れない決まりだ」と断るが、グロリアはここの町の生まれだと主張する。
ファミリーネームから、グロリアの祖父がダニーの親友で勇敢な炭坑夫でバンドマンだったと分かる。
バンドマンの一人アンディは、グロリアの幼なじみだった。
グロリアは「アランフェス協奏曲」のソロパートで見事な演奏を見せ、拍手が巻き起こる。
こうして新たなメンバーを得たグリムリー・コリアリー・バンドだったが、実は彼女の仕事は、炭坑についての報告書を作成することだった。
経営側は組合と折衝の結果、炭坑存続か、閉鎖の代わりに高額の退職金を支払うかのどちらかを、炭坑夫に投票させることになる。
バンドは準決勝を勝ち取ったものの、町に帰ってきた彼らを待っていたのは、閉鎖決定という結果であった。
ダニーは長年の炭坑夫生活で、肺をやられていて路上で倒れた。
その後偶然に、バンドマン達はグロリアが経営会社の建物から出てくるのを目撃してしまう。
特にグロリアと恋仲に落ちていたアンディは、少なからずショックを受けるのだった。
アンディは賭けビリヤードでテナーホーンを取られてしまう。
他のメンバー達の心も揺れ動き、生活が逼迫していることや、グロリアに裏切られたという思いもあり、バンドを辞めることを決意する。
寸評
マーガレット・サッチャーは1979年から1990年まで英国首相を務め鉄の女と称された。
サッチャーは電話・ガス・空港・航空・自動車・水道などの国有企業の民営化や規制緩和、金融システム改革を掲げ、改革の障害になっていた労働組合の影響力を削いで、サッチャリズムと呼ばれる新自由主義的・新保守主義的な政策を強いリーダーシップで推し進めた。
本国ではイギリス経済を立て直した救世主と言われる反面、失業者を増大させて地方経済を不振に追いやったとの評価もあるとのこと。
僕は1982年に起こったフォークランド紛争時における毅然とした態度によってサッチャー首相のイメージが植え付けられた。
映画は正にサッチャー政権時の炭鉱を舞台にしている。
フィルが「サッチャーがピンピンしているのに父親のダニーが死にかかっている」と叫んでいるように、作品はサッチャリズムを否定している。
炭鉱閉鎖によって人々の生活は困窮し、家庭は崩壊状態だし、彼らのコミュニティも壊れかけている。
10年前にも長期のストがあり、その時の借金を未だに抱えている家庭もある。
フィルの家庭は差し押さえにあい家財道具を全部持っていかれ、奥さんは子供を連れて出て行ってしまう。
奥さんが夜の仕事についているのか、すれ違いの生活を強いられている者もいる。
それでも彼らは音楽活動を続けていて、それが彼らの生き甲斐の様でもある。
描かれている内容は辛いものだが、ユーモアを織り交ぜながら描いているので楽しめる。
そして誰もが音楽によって癒されるものがあるので、音楽映画は自然と楽しめる部分を有していると思う。
この映画においても演奏シーンはどれもが感動的である。
僕は最初の演奏曲であるホアキン・ロドリーゴの「アランフエス協奏曲」でうっとりしてしまった。
病室のダニーを励ますために、病院の庭で「ダニー・ボーイ」を演奏するシーンも良かったけれど、ロイヤル・アルバート・ホールでメンバーが「ウィリアム・テル序曲」を演奏するシーンでは涙腺が緩んでしまった。
グリムリー・コリアリー・バンドは優勝するがダニーは優勝トロフィーを拒絶し、炭鉱とそこで働く人々とその家族の窮状を訴える演説を行うが、それはきわめて政治的なシーンであった。
ただしダニーが拒否したトロフィを貰っていく者が居て、審査員が「返上するのでは?」と問いかけるが、「ダニーが言ったのは言葉のあやだ」とチャッカリ持ち去る。
前半でメンバーが相乗りの車の中で「女の立ちション」だの「へのつっぱり」などの言葉のあやについて言いあっていたことが伏線となっている愉快なシーンである。
最後までそのようなユーモアを忘れることはなかった。
帰りのバスの中でロンドンの街を走りながらエドワード・エルガーの「威風堂々」を演奏することに彼らのプライドを垣間見た気がする。
世の中、皆が満足することなどは少なくて割を食う人が出てくるのはやむを得ないことだと思うが、日本人の僕は英国の炭鉱労働者が味わっていた過酷な状況を身をもって知るすべはなかったのだなと思った。
他人事と思われることにも注視しないといけないのだろう。
でも彼らの音楽を愛する気持ちと情熱を信じたいし応援したい気持ちが湧いたのは紛れもない。










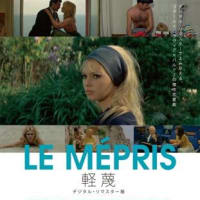
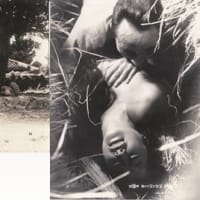

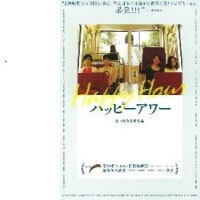
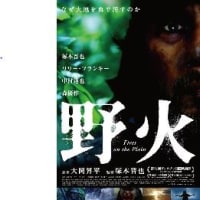
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます