「お葬式」 1984年 日本

監督 伊丹十三
出演 山崎努 宮本信子 菅井きん 大滝秀治
奥村公延 財津一郎 江戸家猫八
友里千賀子 尾藤イサオ 岸部一徳
津川雅彦 横山道代 小林薫 池内万平
西川ひかる 海老名美どり 津村隆
高瀬春奈 香川良介 藤原釜足 田中春男
佐野浅夫 左右田一平 井上陽水 笠智衆
ストーリー
井上佗助(山崎努)、雨宮千鶴子(宮本信子)は俳優の夫婦だ。
二人がCFの撮影中に、千鶴子の父が亡くなったと連絡が入った。
千鶴子の父、真吉(奥村公延)と母、きく江(菅井きん)は佗助の別荘に住んでいる。
その夜、夫婦は二人の子供、マネージャーの里見(財津一郎)と別荘に向かった。
一行は病院に安置されている亡き父と対面する。
佗助にとって、お葬式は初めてのこと、全てが分らない。
お坊さん(笠智衆)への心づけも、相場というのが分らず、葬儀屋の海老原(江戸家猫八)に教えてもらった。
別荘では、真吉の兄で、一族の出世頭の正吉(大滝秀治)が待っており、佗助の進行に口をはさむ。
そんな中で、正吉を心よく思わない茂(尾藤イサオ)が、千鶴子をなぐさめる。
そこへ、佗助の愛人の良子(高瀬春奈)が手伝いに来たと現れる。
良子がゴタゴタの中で佗助を外の林に連れ出し、抱いてくれなければ二人の関係をみんなにバラすと脅したので、しかたなく佗助は木にもたれる良子を後ろから抱いた。
そして、良子はそのドサクサにクシを落としてしまい、佗助はそれを探して泥だらけになってしまう。
良子は満足気に東京に帰り、家に戻った佗助の姿にみんなは驚くが、葬儀の準備でそれどころではない。
告別式が済むと、佗助と血縁者は火葬場に向かった。
煙突から出る白いけむりをながめる佗助たち。
全てが終り、手をつなぎ、集まった人々を見送る佗助と千鶴子だった・・・。
寸評
お葬式という暗い題材をここまで明るくまとめあげた手腕はスゴイ。
義父の葬儀の体験を映画化したらしいのだが、ラスト近くに出てくる森の中に突き出た煙突から出る煙を見上げるシーンは現実にもあって、まるで小津映画に出ているみたいだと感じたのがきっかけになっていると聞いている。
実際、ここからラストに至るシーンはいい。
予算の都合でセットではなくご自身の別荘を使用して撮影しているとのことであるが、それが幸いしたのか限られたアングルから撮られた映像に臨場感がある。
部屋のどこかに据えられたカメラで収めたシーンに趣があり、自宅から出棺する雰囲気がよく出ていた。
亡くなった真吉の兄で口うるさい正吉が北枕を気にして、家族を背景に棺の前で一人芝居をするシーン、棺と遺影が安置された前に母親と娘の千鶴子が布団をサッと敷くシーンなどは映画を感じさせる。
会館での葬儀や家族葬が増えてきて、ご近所の夫婦が手伝っての葬式は少なくなってきたが、小規模ながらもご近所付き合いの中で出す葬式の雰囲気はよく出ていた。
通夜の様子やお手伝いの様子なども見事に活写されている。
途中で侘助の付き人らしい青木が手伝いで加わり、カメラを回して記録映画を撮り始める。
その映像がモノトーンで記録映画のように挿入されるのだが、これがまた何とも言えない雰囲気を生み出していて、とてもいいアクセントとなっている。
若い人や子供のお葬式は沈んだものであるが、老人のお葬式は順番だからとのあきらめもあり、「やれやれ」という気持ちもあり、悲しいはずの葬式で笑い声があったりするものである。
ここに集まった人々の笑顔は正にそのような笑顔で、親族の葬儀に参列したものなら経験があるものだ。
どこかに喜劇的なものがあって楽しませるのだが、その最たるものが高瀬春奈の良子の登場である。
彼女は侘助の愛人なのだが、まるで千鶴子に当てつけるように葬儀に現れ侘助にせまる。
本妻と愛人の修羅場は起きなかったが、もしかすると千鶴子は愛人の存在を感じていたのかもしれない。
宮本信子がブランコで揺れるシーンは印象に残る。
死体役といってもいいぐらいの真吉さんを演じた奥村公延さんは、本当に死んでいるみたいで隠れた功労者だ。
宮本信子さんは久しぶりの出演で、役者にカムバックどころか完全にトップ女優の仲間入りである。
葬儀屋の海老原を演じた江戸家猫八も飄々とした演技を見せて大いに存在感を示し、侘助を陰から支えるマネージャーの里見を演じた財津一郎もいい。
総じて脇役が充実している作品だ。
多分に喜劇的要素も含まれていたが、最後に喪主であるばあちゃんの挨拶でしんみりさせるのもいい構成だ。
伊丹十三さんはあらゆる分野で才能を発揮した方だが、この作品は映画監督としての才能が最初に発揮された作品だ(第1回作品だから当然だ)。
映画の中で、「俺が死ぬのは春にしよう。皆が待っている時に花吹雪だ」と言わせているのだが、寒い時の時の葬儀も暑い時の葬儀も、雨の日の葬儀も大変なので、僕の葬儀はそんな日でありたい。
できれば賑やかに見送ってほしいものだ。

監督 伊丹十三
出演 山崎努 宮本信子 菅井きん 大滝秀治
奥村公延 財津一郎 江戸家猫八
友里千賀子 尾藤イサオ 岸部一徳
津川雅彦 横山道代 小林薫 池内万平
西川ひかる 海老名美どり 津村隆
高瀬春奈 香川良介 藤原釜足 田中春男
佐野浅夫 左右田一平 井上陽水 笠智衆
ストーリー
井上佗助(山崎努)、雨宮千鶴子(宮本信子)は俳優の夫婦だ。
二人がCFの撮影中に、千鶴子の父が亡くなったと連絡が入った。
千鶴子の父、真吉(奥村公延)と母、きく江(菅井きん)は佗助の別荘に住んでいる。
その夜、夫婦は二人の子供、マネージャーの里見(財津一郎)と別荘に向かった。
一行は病院に安置されている亡き父と対面する。
佗助にとって、お葬式は初めてのこと、全てが分らない。
お坊さん(笠智衆)への心づけも、相場というのが分らず、葬儀屋の海老原(江戸家猫八)に教えてもらった。
別荘では、真吉の兄で、一族の出世頭の正吉(大滝秀治)が待っており、佗助の進行に口をはさむ。
そんな中で、正吉を心よく思わない茂(尾藤イサオ)が、千鶴子をなぐさめる。
そこへ、佗助の愛人の良子(高瀬春奈)が手伝いに来たと現れる。
良子がゴタゴタの中で佗助を外の林に連れ出し、抱いてくれなければ二人の関係をみんなにバラすと脅したので、しかたなく佗助は木にもたれる良子を後ろから抱いた。
そして、良子はそのドサクサにクシを落としてしまい、佗助はそれを探して泥だらけになってしまう。
良子は満足気に東京に帰り、家に戻った佗助の姿にみんなは驚くが、葬儀の準備でそれどころではない。
告別式が済むと、佗助と血縁者は火葬場に向かった。
煙突から出る白いけむりをながめる佗助たち。
全てが終り、手をつなぎ、集まった人々を見送る佗助と千鶴子だった・・・。
寸評
お葬式という暗い題材をここまで明るくまとめあげた手腕はスゴイ。
義父の葬儀の体験を映画化したらしいのだが、ラスト近くに出てくる森の中に突き出た煙突から出る煙を見上げるシーンは現実にもあって、まるで小津映画に出ているみたいだと感じたのがきっかけになっていると聞いている。
実際、ここからラストに至るシーンはいい。
予算の都合でセットではなくご自身の別荘を使用して撮影しているとのことであるが、それが幸いしたのか限られたアングルから撮られた映像に臨場感がある。
部屋のどこかに据えられたカメラで収めたシーンに趣があり、自宅から出棺する雰囲気がよく出ていた。
亡くなった真吉の兄で口うるさい正吉が北枕を気にして、家族を背景に棺の前で一人芝居をするシーン、棺と遺影が安置された前に母親と娘の千鶴子が布団をサッと敷くシーンなどは映画を感じさせる。
会館での葬儀や家族葬が増えてきて、ご近所の夫婦が手伝っての葬式は少なくなってきたが、小規模ながらもご近所付き合いの中で出す葬式の雰囲気はよく出ていた。
通夜の様子やお手伝いの様子なども見事に活写されている。
途中で侘助の付き人らしい青木が手伝いで加わり、カメラを回して記録映画を撮り始める。
その映像がモノトーンで記録映画のように挿入されるのだが、これがまた何とも言えない雰囲気を生み出していて、とてもいいアクセントとなっている。
若い人や子供のお葬式は沈んだものであるが、老人のお葬式は順番だからとのあきらめもあり、「やれやれ」という気持ちもあり、悲しいはずの葬式で笑い声があったりするものである。
ここに集まった人々の笑顔は正にそのような笑顔で、親族の葬儀に参列したものなら経験があるものだ。
どこかに喜劇的なものがあって楽しませるのだが、その最たるものが高瀬春奈の良子の登場である。
彼女は侘助の愛人なのだが、まるで千鶴子に当てつけるように葬儀に現れ侘助にせまる。
本妻と愛人の修羅場は起きなかったが、もしかすると千鶴子は愛人の存在を感じていたのかもしれない。
宮本信子がブランコで揺れるシーンは印象に残る。
死体役といってもいいぐらいの真吉さんを演じた奥村公延さんは、本当に死んでいるみたいで隠れた功労者だ。
宮本信子さんは久しぶりの出演で、役者にカムバックどころか完全にトップ女優の仲間入りである。
葬儀屋の海老原を演じた江戸家猫八も飄々とした演技を見せて大いに存在感を示し、侘助を陰から支えるマネージャーの里見を演じた財津一郎もいい。
総じて脇役が充実している作品だ。
多分に喜劇的要素も含まれていたが、最後に喪主であるばあちゃんの挨拶でしんみりさせるのもいい構成だ。
伊丹十三さんはあらゆる分野で才能を発揮した方だが、この作品は映画監督としての才能が最初に発揮された作品だ(第1回作品だから当然だ)。
映画の中で、「俺が死ぬのは春にしよう。皆が待っている時に花吹雪だ」と言わせているのだが、寒い時の時の葬儀も暑い時の葬儀も、雨の日の葬儀も大変なので、僕の葬儀はそんな日でありたい。
できれば賑やかに見送ってほしいものだ。










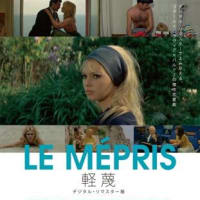
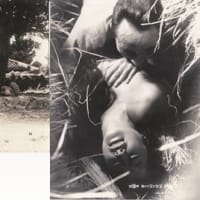

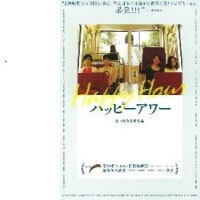
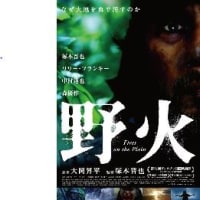
その彼の作品の中で、最も素晴らしいと思うのは、やはり「お葬式」だと思います。
この映画「お葬式」は、日本という無宗教社会でのお葬式という儀式を通して、儀式の意味を問いかけ、人々の心の空虚さを、涙と笑いのうちに描いた伊丹十三監督の傑作だと思います。
この映画「お葬式」は、当時、個性派の俳優であり、優れたエッセイ等を数多く書き、多彩な才能に恵まれた伊丹十三の第一回監督作品ですね。
この映画を撮る前年に、彼の夫人の女優・宮本信子の父親が亡くなった際の葬儀を主宰して、彼は「これはまるで映画だ」と感じたと後に語っていましたが、この葬儀の間中、彼は冷たいカメラの目で、この映画の構想を練っていたのかも知れません。
しかし、彼ほどではなくても、葬儀に参列する人それぞれの心の中ほどわからないものはないような気がします。
「冠婚葬祭」のうち、「葬」という人間最後のお葬式だけをテーマに据えた映画は、外国映画を含めて恐らく今までなく、前代未聞ではないかと思います。
この「お葬式」は、誰もが参列者として一度は経験した事のある、そして、人間は必ず死ぬ事によってその対象となる、「お葬式」という日本独特の儀式の意味を問いかけている映画だと思います。
人生最後の最も厳粛であるべき死を司る「お葬式」が、誰が観ても面白く、思わず笑いがこみ上げてくるばかりか、お色気や淫猥さまで感じさせられるのは何故なのか? とこの映画を観終わって、ふと不気味な気持ちに襲われました。
世界各国それぞれに宗教は異るし、その集約された儀式である葬送を映画のテーマにする事自体、見方によっては不謹慎な問題なのです。
そのような映画が、当時の日本国内で面白く観られて評判が高かったのは、我が国での仏教というものが形骸化してしまっている事への、監督・伊丹十三の痛烈な風刺があったからだと思います。
もし、外国でこの映画が受け入れられるとすれば、その国での宗教が、我が国と同様に単なる儀礼に堕している事への批判になるのかも知れません。
しかし、考えてみると、我が国の仏教による「お葬式」ほど、本当の宗教心からかけ離れた儀式は、世界的にみても稀なような気がします。
この映画が喜劇的であり、面白いという事は、日本という無宗教社会での人々の心の空虚さを反映しているのだと思うし、にもかかわらず、この映画が変に説教臭くなく、色事のハプニングはあっても、スケジュール通りに進められる3日間の日常性を描いているところに、かえって無宗教な心の自由というものを感じさせてくれます。
しかし、重苦しい戒律で拘束された西欧社会では、このような、ある意味、不埒な自由は到底考えられないと思います。
日本映画と洋画との本質的な差異は、宗教的な社会が背景としてあるのかどうかであり、それが人間の個性に深く関係しているのではないかと日頃から思っています。
日本映画は無宗教なのに、"没個性的"、これに対して洋画は宗教的にして、"個性的"という気がしてなりません。
才人でもある伊丹十三監督は、きっとこのような宗教と自由の問題を心の奥底に秘めているのかも知れません。
そして、それを深刻に描かないところが素晴らしいと思います。
伊丹十三監督は、この映画の製作意図として、「この作品では、葬式というふるさとの儀式の中に突然投げ込まれた社会人たちの滑稽にして悲惨な混乱ぶりを、涙と笑いのうちに描きたい。私の目的はただ一つ。映画らしい映画を作りたい。ただそれだけです」と語っていて、ある意味、伊丹十三という非職業監督の映画的な成功は、彼の人間を見る目の奥深さからきているのだと思います。
また、「キャスティングは演出の仕事の半分」という彼の信条は、実父の伊丹万作監督の「百の演技指導も、一つの打ってつけの配役にはかなわない」という有名な言葉通り、この映画の一人一人の人物像が、我々のごく身近にいる人間のように生き生きと輝いているのは、まさに配役の妙以外の何物でもありません。
彼は「出演者の一人一人が主役だ」と語っているだけに、山崎努、大滝秀治、江戸屋猫八、財津一郎、高瀬春奈、友里千賀子とそれぞれに個性的でいい味を出しているし、特に、宮本信子、菅井きん、笠智衆、藤原釜足の演技が光っていて、強く印象に残りましたね。
伊丹十三監督作品としても、やはりこれが一番でしょう。