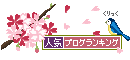さーて、少しばかり深く考えてみようと思います。
そもそも…
ジャズとクラシック…
これって、定義が恐ろしく難しいです。果てしなくジャズっぽいクラシックの曲もあるし、古いラグタイムなんかはクラシックですよ、と言われたら、あ~そうですか…と言ってしまいそうです。
それでも自分の中で、ジャズっぽいだのクラシックだの言ってるところをみると、漠然とした区別みたいなものはやっぱりありそうです…
でも、それはそれとして、今回はrhythmosっていうテーマなので、そこを中心に考えよう…と思います。
この「rhythmos!」ってのは、今回、大学の学生が企画しているコンサートのタイトル。
現在使われるrhythmの元になった、古代ギリシャ語。
で、ここで余計な道に逸れてみよう…
rhythmosはギリシャ語で書くと ρυθμος となるらしい。んで、ギリシャ語辞典が手元にないので、お手軽に翻訳ソフトなんか使ったりしてみると、日本語では「ペース」、なので英語でも「pace」、んで、ドイツ語やロシア語だとTEMPOとなる。フランス語などではようやくrythmeで、まあリズムだね…となる。
10月11日追記
やっぱりよくわからないので、もう一度検索しました。するってーと、rhythmosをギリシャ語に表記した時点で間違って表示されたようで、ρυθμός が正解のようです。ほとんど一緒じゃん?って感じだけど、点がoみたいな字の上にあるかないかが違うだけで、だいぶ違うことになりました。
この ρυθμός にして調べたら、日本語訳もGoogleでは「リズム」となり、他言語に直しても、およそ「リズム」に近い言葉になりました。普通の翻訳ではペース、歩調、速度となるようで、するってーと最初の点がないものとおんなじ感じになったりして…ちなみに私レベルではこの2つの発音の違いは聞き分けられない感じ。ギリシャ語の規則がよくわからないので、なんとも言えませんが、こうやって調べていくととっても面白い!
というわけで、訂正というか、追記というかを付け加えておきたいと思います。(藤井)
今言う「リズム」はギリシャ語の「流れ」から来る、という説があったり、いやいやもっと古い起源ですよという話だったりしているようだ。
で、音楽用語的「リズム」も定義しだすと、まあいわゆる西洋音楽では
(1)拍節的リズム…いわゆる何拍子みたいに言える感じ。
(2)定量リズム…ストラヴィンスキーの春の祭典なんかに見られるような、不規則的アクセントによる感じで、結果的に激しい変拍子みたいになる。
(3)自由リズム…たぶんグレゴリオ聖歌みたいな感じなのかな?
…というふうに辞書的にはなるようだ。
で、今回のテーマである、rhythmosはきっとこの中では、(1)的な意味で、本当に普通に音楽の3要素なんかを語るときのメロディーと和声と「リズム」ってやつに違いない。
ようやく話が戻ってきたところで…
これを「ジャズとクラシック」、そして「ロシア」の楽曲というところで結んで行こう、というなかなか意欲的な企画である。
使う楽曲は…ロシア民謡「コロブチカ」(途中からジャズチーム)、カバレフスキー『道化師』より「ギャロップ」、ストラヴィンスキー『ペトルーシュカ』より「ロシアの踊り」、♪ボロディンの「ダッタン人の踊り」をジャズで「ストレンジャー・イン・パラダイス」、♪「オーバー・ザ・レインボー」、リムスキー=コルサコフ「熊蜂の飛行」、チャイコフスキー『眠れる森の美女』より「ワルツ」、♪「ス・ワンダフル」、♪「シング・シング・シング」。
♪がついているのは、ジャズチームによる演奏。
「コロブチカ」は、パズルゲームの元祖「テトリス」のBGMとして聞いた方も多いのではと思う。また余談だけど、このテトリス、元々はソ連の科学者らが開発した教育用ソフトだった。ソ連の科学者が考えたゲームだったから、ロシア民謡がBGMになったんだろうか???はてさて…??(^_^;)
私もテトリスにハマったタイプなので、あー!あれかぁ~って感じ。でもあらためて元々の民謡を聴いてみると、あ~いかにもロシアの歌だなぁ…という感じで、メロディーラインもちょいちょい違うのね。行商人の荷物ってな意味で、ちょっとした若い男女の恋の物語みたいだ。
はてさて、また逸れたついでに…
なーんとなく、ロシアの曲ってスローテンポからスタートして、徐々にテンポアップする~みたいなイメージがある。ロシアではないが、チャルダッシュなんかも、スローから始まってカッ飛びテンポで盛り上がって終わる。考えてみると、ドイツのビアソングなんかは、想像よりはなんとものんきなテンポでずーっと最後までずーっとずーっと飽くことなく行くって感じがする。
演奏する私としては、ポルカバンドでも、ずーっとずーっとおんなじく行くってのが次第に耐えられなくなり、ついついテンポアップしたくなったりしてしまう。という当たりで、どうやら日本人である私は、ドイツ人の感覚よりやっぱりロシア人に近いんじゃないか???なんて勝手に思うのであった。
チャイコフスキーとか日本人の叙情的な感覚にめっちゃ合うもんね。
ワーグナーとかブラームスもかなり好きではあるけれど、ずーっとずーっと聞いているうちにどこかで一瞬気絶して盛り上がったころに、あ!!イケナイ!!!気を失ってた…と思う当たり…あ、これはきっと私だけかもしれない…。単にロシアの音楽が好きだっていうだけです。。。
ところで、「コロブチカ」は本来はテンポは変わらない曲らしい。でもやっぱり徐々に早くしている演奏もいっぱいあるし、まあそうやって演奏しても良い感じではある。
この同じ曲をクラシックとジャズで演奏する。どんな違いが出るか?これはひょっとするとひとえにジャズの方々がどんなスタイルで演奏するかにかかってる気がする。
ところで…こういう曲を「クラシックで」演奏する、という話になると、クラシックというのは「演奏スタイル」なのであろうか?
それとも、作曲された時点で「曲のスタイル」として決まるのだろうか?
その一方で、ジャズの場合は原曲が何であろうとジャズの「スタイル」で演奏すれば、ジャズであるって気がする。
では、ジャズの曲を「クラシック」スタイルで演奏すれば、「クラシック」たりえるのだろうか????
正直、ちょっと分かりません。。。
そもそもコロブチカはクラシックなのだろうか???
「民謡」というのは、どういうくくりになるのだろう???
「○○の主題による○○」というクラシックは結構ある。民謡を元にしたクラシック音楽もいっぱいある。
では、原曲の民謡は???
変に深く考えようとすると、むしろ本筋から激しく逸れるということが分かった…(^_^;)
全体テーマが「リズム」なので、それを中心に考えると、コロブチカを「クラシック」としてどんな風に演奏するのがいいのか。
クラシックとジャズを2つ並べようとすると、いかに違うか、ということを上げたくなるけれど、まあこの曲では単に2バージョン聞いて頂いて、クラシックとジャズを両方聞いて頂きますよ~という単に紹介に留め、判断はお客さまにお任せするのがいいのかな。。。
と、ここまで書いてちょっと長くなってきたので、続きはあらためて!
そもそも…
ジャズとクラシック…
これって、定義が恐ろしく難しいです。果てしなくジャズっぽいクラシックの曲もあるし、古いラグタイムなんかはクラシックですよ、と言われたら、あ~そうですか…と言ってしまいそうです。
それでも自分の中で、ジャズっぽいだのクラシックだの言ってるところをみると、漠然とした区別みたいなものはやっぱりありそうです…
でも、それはそれとして、今回はrhythmosっていうテーマなので、そこを中心に考えよう…と思います。
この「rhythmos!」ってのは、今回、大学の学生が企画しているコンサートのタイトル。
現在使われるrhythmの元になった、古代ギリシャ語。
で、ここで余計な道に逸れてみよう…
rhythmosはギリシャ語で書くと ρυθμος となるらしい。んで、ギリシャ語辞典が手元にないので、お手軽に翻訳ソフトなんか使ったりしてみると、日本語では「ペース」、なので英語でも「pace」、んで、ドイツ語やロシア語だとTEMPOとなる。フランス語などではようやくrythmeで、まあリズムだね…となる。
10月11日追記
やっぱりよくわからないので、もう一度検索しました。するってーと、rhythmosをギリシャ語に表記した時点で間違って表示されたようで、ρυθμός が正解のようです。ほとんど一緒じゃん?って感じだけど、点がoみたいな字の上にあるかないかが違うだけで、だいぶ違うことになりました。
この ρυθμός にして調べたら、日本語訳もGoogleでは「リズム」となり、他言語に直しても、およそ「リズム」に近い言葉になりました。普通の翻訳ではペース、歩調、速度となるようで、するってーと最初の点がないものとおんなじ感じになったりして…ちなみに私レベルではこの2つの発音の違いは聞き分けられない感じ。ギリシャ語の規則がよくわからないので、なんとも言えませんが、こうやって調べていくととっても面白い!
というわけで、訂正というか、追記というかを付け加えておきたいと思います。(藤井)
今言う「リズム」はギリシャ語の「流れ」から来る、という説があったり、いやいやもっと古い起源ですよという話だったりしているようだ。
で、音楽用語的「リズム」も定義しだすと、まあいわゆる西洋音楽では
(1)拍節的リズム…いわゆる何拍子みたいに言える感じ。
(2)定量リズム…ストラヴィンスキーの春の祭典なんかに見られるような、不規則的アクセントによる感じで、結果的に激しい変拍子みたいになる。
(3)自由リズム…たぶんグレゴリオ聖歌みたいな感じなのかな?
…というふうに辞書的にはなるようだ。
で、今回のテーマである、rhythmosはきっとこの中では、(1)的な意味で、本当に普通に音楽の3要素なんかを語るときのメロディーと和声と「リズム」ってやつに違いない。
ようやく話が戻ってきたところで…
これを「ジャズとクラシック」、そして「ロシア」の楽曲というところで結んで行こう、というなかなか意欲的な企画である。
使う楽曲は…ロシア民謡「コロブチカ」(途中からジャズチーム)、カバレフスキー『道化師』より「ギャロップ」、ストラヴィンスキー『ペトルーシュカ』より「ロシアの踊り」、♪ボロディンの「ダッタン人の踊り」をジャズで「ストレンジャー・イン・パラダイス」、♪「オーバー・ザ・レインボー」、リムスキー=コルサコフ「熊蜂の飛行」、チャイコフスキー『眠れる森の美女』より「ワルツ」、♪「ス・ワンダフル」、♪「シング・シング・シング」。
♪がついているのは、ジャズチームによる演奏。
「コロブチカ」は、パズルゲームの元祖「テトリス」のBGMとして聞いた方も多いのではと思う。また余談だけど、このテトリス、元々はソ連の科学者らが開発した教育用ソフトだった。ソ連の科学者が考えたゲームだったから、ロシア民謡がBGMになったんだろうか???はてさて…??(^_^;)
私もテトリスにハマったタイプなので、あー!あれかぁ~って感じ。でもあらためて元々の民謡を聴いてみると、あ~いかにもロシアの歌だなぁ…という感じで、メロディーラインもちょいちょい違うのね。行商人の荷物ってな意味で、ちょっとした若い男女の恋の物語みたいだ。
はてさて、また逸れたついでに…
なーんとなく、ロシアの曲ってスローテンポからスタートして、徐々にテンポアップする~みたいなイメージがある。ロシアではないが、チャルダッシュなんかも、スローから始まってカッ飛びテンポで盛り上がって終わる。考えてみると、ドイツのビアソングなんかは、想像よりはなんとものんきなテンポでずーっと最後までずーっとずーっと飽くことなく行くって感じがする。
演奏する私としては、ポルカバンドでも、ずーっとずーっとおんなじく行くってのが次第に耐えられなくなり、ついついテンポアップしたくなったりしてしまう。という当たりで、どうやら日本人である私は、ドイツ人の感覚よりやっぱりロシア人に近いんじゃないか???なんて勝手に思うのであった。
チャイコフスキーとか日本人の叙情的な感覚にめっちゃ合うもんね。
ワーグナーとかブラームスもかなり好きではあるけれど、ずーっとずーっと聞いているうちにどこかで一瞬気絶して盛り上がったころに、あ!!イケナイ!!!気を失ってた…と思う当たり…あ、これはきっと私だけかもしれない…。単にロシアの音楽が好きだっていうだけです。。。
ところで、「コロブチカ」は本来はテンポは変わらない曲らしい。でもやっぱり徐々に早くしている演奏もいっぱいあるし、まあそうやって演奏しても良い感じではある。
この同じ曲をクラシックとジャズで演奏する。どんな違いが出るか?これはひょっとするとひとえにジャズの方々がどんなスタイルで演奏するかにかかってる気がする。
ところで…こういう曲を「クラシックで」演奏する、という話になると、クラシックというのは「演奏スタイル」なのであろうか?
それとも、作曲された時点で「曲のスタイル」として決まるのだろうか?
その一方で、ジャズの場合は原曲が何であろうとジャズの「スタイル」で演奏すれば、ジャズであるって気がする。
では、ジャズの曲を「クラシック」スタイルで演奏すれば、「クラシック」たりえるのだろうか????
正直、ちょっと分かりません。。。
そもそもコロブチカはクラシックなのだろうか???
「民謡」というのは、どういうくくりになるのだろう???
「○○の主題による○○」というクラシックは結構ある。民謡を元にしたクラシック音楽もいっぱいある。
では、原曲の民謡は???
変に深く考えようとすると、むしろ本筋から激しく逸れるということが分かった…(^_^;)
全体テーマが「リズム」なので、それを中心に考えると、コロブチカを「クラシック」としてどんな風に演奏するのがいいのか。
クラシックとジャズを2つ並べようとすると、いかに違うか、ということを上げたくなるけれど、まあこの曲では単に2バージョン聞いて頂いて、クラシックとジャズを両方聞いて頂きますよ~という単に紹介に留め、判断はお客さまにお任せするのがいいのかな。。。
と、ここまで書いてちょっと長くなってきたので、続きはあらためて!










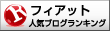

 藤井裕子 @YukoTrumpeter
藤井裕子 @YukoTrumpeter