こんばんはー!
ご飯を食べてから、Facebookで見つけたフリードリヒとハーデンベルガーとマルサリスという素晴らしいプレイヤーのZOOM対談を見ながら(もちろん英語!!)、おそらく脳がショートしたのか寝てしまい、気がつけば1時半…やたらと寝たようです。
なので、すっかり復活してシャワーして、エヴェリン・グレニーのこれまた素晴らしい本「リズムは心に響く」を読んで、さてそろそろとブログに取りかかったところでございます(笑)
今日のテーマ、蝶形骨とアンブシュアですけど、
本当は「アンブシュア」とは言いたくないんだけど、じゃあなんていうのさ?が思い浮かばなかったんで、、、えへへ。
ここのところ、
「音を出すために身に付いてしまった動き」を手離して、
「やりたいことをやってる(であろう)動き」を「楽器を持っても実際にやれる」ように練習する
ということに注力してるわけですけど、
今日見ていたFacebookのZOOM対談でウイントンの質問に対してハーデンベルガーが、
毎朝、(筋肉の)緊張のない状態で音のセンターを探すことが自分には必要だ
首とか喉、胸、上唇下唇の振動のバランスを取る
自分には分からないけれど、体(首、後頭部、肩あたり)の後ろが大切だという人もいる。ドクシツェルとかもそうだ
(以上、藤井的意訳)
的なことを言ってて、
前にハーデンベルガーの若い頃のウチでのウォーミングアップからコンサートや対談を撮った動画を見ていたので、その大まかな雰囲気は想像出来て、
上下の唇、振動、バランスかー、、、
ん?
あら??
音を出す時に、ここ数年で身に付けてしまった、息が来る前に唇が前に突き出ていく(開こうとする)動き、、、
ほんのりと、でも明らか良くないと気が付いてはいたものの、それよりもっと気になることに隠れて、見逃してた、、
でも、この先に開けるっていう癖はおそらくとてもよくないし、
それに絶好調の時には音が生まれるのを「見つめる」感覚があるんだけど、自分で唇を開くと、時間的な感覚がズルッと滑って体感できない感じになる、、それでは曲の深い感じが全くコントロールできないから表現不能〜!!
そこで、音が出る前には唇が知らんぷりしていられるように…
でも、なーんかマウスピースの当たり加減が気持ち悪くて、どうしても先に唇動くヤンケー!!
そこで、さらに子供の頃を思い出し、マウスピースのリムに上唇の上端をちゃんとひっかけて(収めて?止めて??言い方がわからん!)、そのあとは唇の存在は単に第三者的に内側から観察するだけにして、
つまり唇のことはマウスピースに任せて、単にマウスピースの中の上下の唇が綺麗でリラクシーな状態でセッティングされてるかだけ気にして、
その上で蝶形骨辺りも動けるようなイメージでいると、口の中を「広くしよう」と筋肉を「使わなくて」も、口の中に適度な空間が勝手にできる余地ができ、
そうすると、唇へ向かってくる息の流れの通り道も良くなり、唇を抜けた先の音のイメージに繋がりやすくなる。
で、これと同時に、「歌いたさ」「出したい音のアタック、響き、明るさ・暗さ、柔らかさ・強さ、音量…」などが「できてるときにやっているはずの動き」を楽器があってもできる、
ということをできるだけ100発100中にする
という練習!!
これなら、「よくないけどやれちゃう別なやり方」という、ありがたくない癖を練習するのではない、「やりたいことができる」ための練習になるから、手取り早いしクリエイティブ!!
いろんなメンタルやフィジカルのことを調べていくと、
どんどん細分化していくパターンと、
実は「もうヤーメた!!」と思って、しばらく離れたあと、気負いなくやりたいようにやったら、あら?前より上手くなってる、
というパターンの2分化していく気がする。
細かく細かく入っていくと、大抵どんどん吹けなくなって、、、あーもーぉ!!!となり、、
そこで辞めると、下手のまま終わるか、吹けなくなった、、、あまり書きたくない言葉だけど、潰れた、みたいになる。
おそらく、細かく細かく入っていって成功している人たちは、
その時点で「上手くいっている人」だと思う。
調子の悪い人、上手くいってない人、初心者は細かく細かくから初めてはいけない。
そういう人はまずは、「ま、いっか!」というメンタルになること。
メンタルとフィジカルは直結している
だから、ここで「わわわわ!!!」「どうしよう!!」「頑張らなきゃ」「努力が足りない」と焦れば焦るほど、体に余計な力が入り、冷静さも次第に失われ、アンブシュア界隈が固まってしまえば、蝶形骨周りも動けなくなり、そうするとここは横隔膜などの呼吸系に直結しているから、管楽器の生命線である「息」がショボくなって、もはや何やってもダメだぁ…ってなり、もっと細かく必死に…のループに入ることになる。
細かなことまで感じる「センサー」は必要だと思うが、楽器を「吹く」ために使う項目が多くなれば多くなるほど、その処理に時間とエネルギーを取られて、トランペットを吹くのに大切なスピードや瞬発的なエネルギーが分散して、思い通りからかけ離れてしまう。
だから、めっちゃ上手くいってる人以外は、
出したい音、やりたい音楽をいかに自然に楽に吹いてるところを想像できるか、その時のフィジカル(と言っても、細かな筋肉の動きではなくて、「エアギター」くらいのイメージでいい)はもちろん、メンタルも含め、どうなってるか、を想像すること
がまず勝負。
その想像したものを、楽器があってもどこまでやれるか
それに尽きる。
と、今は思って来ました。
脱力が分からないと全力も出せないからね。そこだ。
はーい、そんなカンナで、なんか電車の音がしたぞ??始発はまだのはずだけど(笑)
さー、ついに6月ですね!張り切っていきましょー!
と言った瞬間に…
おやすみなさーい!また明日ー(*´∀`*)ノ″



























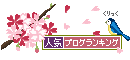

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます