 絵=入澤光世・水仙。もうじき花が咲きますよ。
絵=入澤光世・水仙。もうじき花が咲きますよ。
京都府下の笠置町で、昨年の出生児がゼロだったことが報告されている(京都新聞1月14日)。この町に限らず、地方の小さな自治体では、同じようなことが起こっているように思う。出産年齢の男女が都市に移住してしまっているのだから、致し方ないことである。そうしたところでは、若者の雇用を確保できる地域産業を起こす画策を色々工夫しているが、成果が出るまでには至っていない。僕の田舎でもそうである。
老人だからというわけではないが、僕だったら若者対策とか産業誘致といった施策ではなく、残された老人をどうするか、という対策を地方活性の要に据えたい。若者は都会に出て仕事を見つけることができるが、老人はそうはいかない。地域にとどまるほかない老人達をどうするのか、という問題である。
で現在、老人問題の解決を若者に依存にするのが、主な考えや制度の中心となっているが、これは状況を顧みない時代錯誤だと思う。社会保障制度など、現役世代で先行世代をカバーしようとする制度は、今日のような少子社会では、若者世代に負担を押しつけるばかりである。
そういう視角ではなく、老人が老人自身をまかなう、老老社会を構想したい。
ひとつの具体的な考えだが、限界集落に近い自治体では給食センターをつくるべきだ。都会だと和民(居酒屋チェーン)などがすでに単身老人所帯に食事を配達する取り組みを行っている。これは本来、交通の不便な地方ですべき事業である。廃校になった施設などを利用して給食センターをつくり、地域の老人達に食事を配る。その献立や食事づくりには地域の老婦人達が担当する。管理栄養士などいらない。かつて冠婚葬祭の時にはそのように隣近所の夫人達が協力して、食事づくりをしてきたのである。配達には運転のできる老人たちで分担すればいい。こうした場合の労力には当然ながら僅かであっても対価を払うべきで、そこに雇用が生まれる。昔とちがって、老人自身が活動できる体力は、今日の長寿社会では十分可能なのである。
そのほか、地域に銭湯をつくることなど、自治体が多少の援助をすればできることはたくさんある。ぜひ、実験的にでも取り組んでもらいたいことである。
老人をまったく受け身の存在と位置づけるのではなく、活動の主体とすることによって、地域の動きがでてくる。そうした動きに民間の事業者が近づいてくるのだ。企業誘致ではなく、まず地域の老老社会の動きを始めるべきだ。【彬】











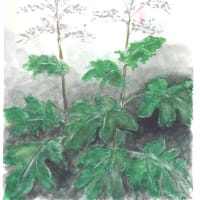













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます