
ガクアジサイ
5月25日、第75回の植樹祭が埼玉県の秩父市で開催された。天皇、衆議院議長、埼玉県知事、農水相らの列席による恒例の行事である。もう75回を数える。
植樹祭が開催さrた当初は、戦禍で荒廃した山野の回復を目指す行事で、大きな注目を浴びたものである。スギ、ヒノキ等の針葉樹は成長も早く、真っ直ぐに伸びるので、街の再興のは欠かせない建築材として、各地で植樹された。コウヤスギ、アキタスギなど、名木として今でもその名残を残している。林野の作業も機械化され、運搬のための森林鉄道が各地で敷設された。日本の戦後復興の主要な事業であった。
しかし1980年代ごろからカナダやインドネシアからの輸入材が大量に出回るようになって林野事業は衰退するばかり。植樹されたスギ、ヒノキは放置され、その結果、花粉症という疾病を産むことになった。
そして植林というのは、建築資材という経済的な需要から、自然や環境を守るという視座へと変わってきた。その結果、スギでは小花粉という花粉症を予防する品種改良も施されるようになった。
スギ、ヒノキについては、台風などの自然災害の観点からも見直しが進んだ。根が浅く、大雨や地震などに弱いため、背の低い広葉樹にすべきとして、多くの里山で伐採、植え替えが行われた。
針葉樹というのは北海道などの低温地帯の植物で、縄文期などは広葉樹に覆われていたはずという「照葉樹林文化」(佐々木高明)なども注目を集めたこともある。
一方、日本の木材建築の伝統から、高野山のヒノキ、コウヤマキなどを保護する行政があり、江戸期には木曽五木と言って幕府が伐採を制限した樹木もあった。いずれもスギ、ヒノキの仲間である。
以上のように、日本の植林については長い伝統があって、上記したものはその一端である。
植樹祭に話を戻そう。
樹木を育て、自然豊かな山地を涵養するという目的のこの行事は、少なくとも上記のような経緯を踏まえる必要があると思う。
その上で今回天皇が植樹した樹種は
ケヤキ スギ(少花粉) トチノキ
であり、種まきしたのは、
ヒノキ(少花粉) アカシデ
である。
体調のせいで欠席した皇后の植樹は
ヒノキ(少花粉) コナラ ヤマザクラ
が予定だった。
いくら少花粉とはいえ、ヒノキ、スギが選ばれたのはなぜのだろうか。私には疑問である。樹種には様々な言い伝えや歴史が隠されている。それが日本の文化とつながっている。それを踏まえた上で、なぜこの樹種が選ばれたのか、それを知りたい。
林野庁に問い合わせをすれば、植樹祭の全ての樹木が分かろうが、ネット上では明らかではない。祭りにとらわれることなく、植樹祭に選ばれた地域と樹木を一覧できることが、私たちの樹木についての理解を深めることに役立つはずである。【彬】











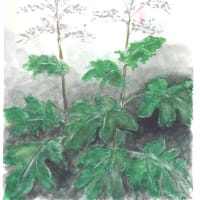













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます