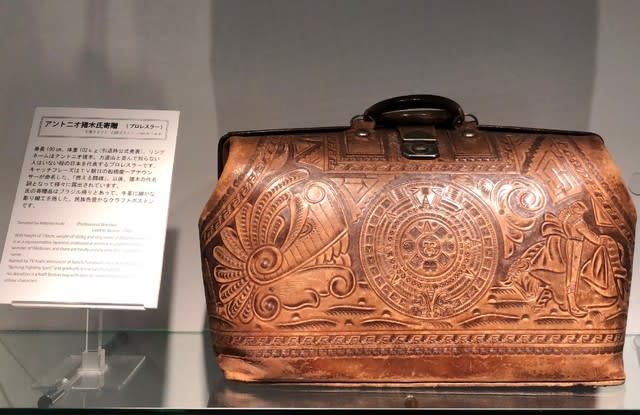2020/10/22
JR山手線・田端駅そばに田端文士村記念館があります。
「文士たちのアオハル ―芥川龍之介と田端の雑誌ー」という企画を展示中ということで、見に行ってきました。

大正時代の田端は、若い文士たちが多く住んでいた文士村と呼ばれる地域がありました。
芥川龍之介、菊池寛、室生犀星、萩原朔太郎、堀辰雄。若い人たちが希望に燃えて雑誌を編集・発行していた時期でした。雑誌『新思潮』、『感情』、『赤い鳥』、『金の星』、『文藝春秋』『驢馬』など。『文藝春秋』はこの頃からの長い歴史があるんですね。
雑誌の初版本、原稿、色紙、絵画などの展示があり、当時の雰囲気が感じられました。この当時は、メールでもするように、よく手紙やはがきを書いて連絡を取り合っていたんですね。
展示の中心は芥川龍之介です。芥川の田端の家の精巧な復元模型があり、この模型がよくできてました。家をもとに動画が作られていて、貴重な記録映像もはめ込まれています。
芥川が家の庭の木にのぼっていたという逸話を聞いたことがありましたが、実際に庭の木にのぼっている映像を見ることができました。着物の前をはだけながらスルスルとのぼっていきます。これは珍しかったですね。
展示概要 ↓
https://kitabunka.or.jp/tabata/exhibition/
芥川は1927年、35歳で自死しています。亡くなるまで田端の家で暮らしていたということです。「将来に対するぼんやりした不安」という言葉を残していますが、世話好きで社交的な一面があったそうです。
人気ゲーム「文豪とアルケミスト」と田端文士村記念館がタイアップしており、イラストやイメージキャラクターのパネルも展示されていましたよ。
田端駅周辺の切通しの道。 明治時代に台地を削って道を通したのですね。
高い建物は田端アスカタワー

東台橋で行き来する

このあたりの住宅地に芥川の旧居があったのかなあと思いながら歩いてみたのですが、きちんと調べてないので、よくわからなかったです。
歴史のある地区ですから、ちゃんと調べて、またゆっくり散歩してみたいと思います。