

などと感じました。
必然的に手紙を書かざるを
得ないのでしょうが
それでも筆まめな人だったのでしょう。




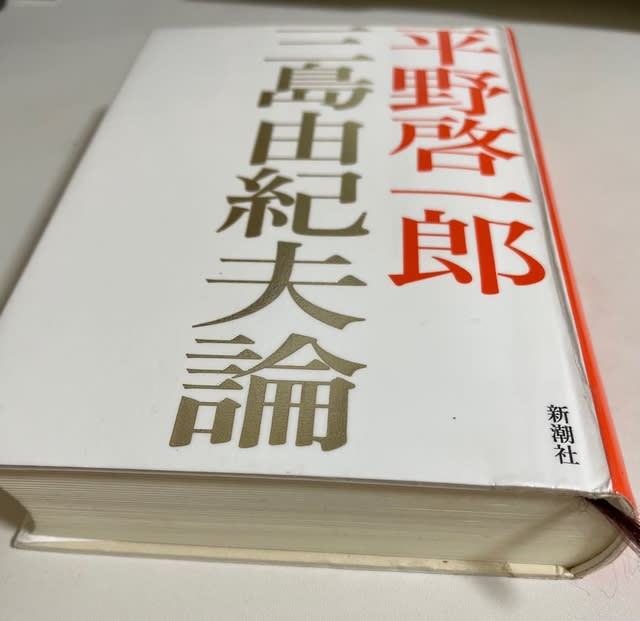

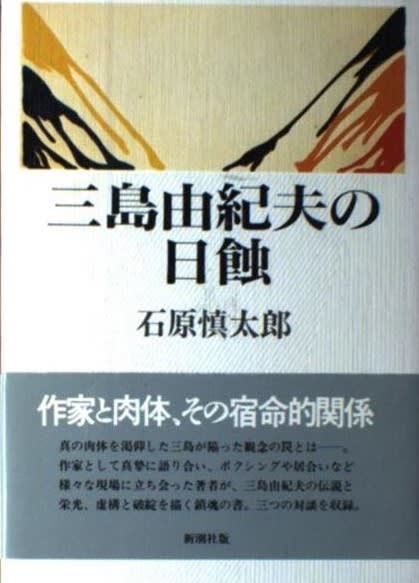
2021/11/24
1年前の今日は三島由紀夫の「ヒタメン」(岩下尚史著)のことを書いていた。
昨年は三島の死後50年で、ずいぶんメディアに三島が取りあげられたが、今はもう三島の名前も見ることが少ない。
私は昨年三島関係の本をたくさん読んでいて、読書ノートをつけていたが、そのノートを先ほど読みかえしてみたら、野坂昭如氏が書いた『赫奕たる逆光』がとても面白くて、熱心に読んだことを思い出した。
本書の bookデータベースより
「焼跡で読んだ短篇に衝撃を受けて以来、深く三島を意識し、三島の激賞によって文壇にデビュー、突然の自裁まで、さまざまな形で一方的な「恩恵」を受けつづけた著者が、父祖の地、幼時体験をはじめとする三島と自分との数奇な共通項をたどりながら、十七回忌にあえて描く、三島由紀夫の禁忌!」
野坂氏は三島をかなり意識しており、自分と三島の生い立ちの共通項を見つけることに興味を持っていたと書かれています。
2021/02/26
久しぶりの三島由紀夫の書きつけ。
昨年は没後50年だったので、メディアの三島特集が多かったが、年が明けてしまうと、もう過ぎてしまったことなのか、名前が見られなくなった。
ここに読んだ本のことを書きたいと思いながら、なかなかエネルギーのいることで、先送りしているうちに日が過ぎて、そのうち記憶の彼方に消えていってしまうのだろうなと思ったりしている。
感想を書きたいと思っている本、実は昨年から下書き状態のまま。
・『ペルソナ』猪瀬直樹
・『暴流のごとく』平岡倭文重
・『金閣を焼かなければならぬ』内海健
そして今、書こうとしている『女のいない死の楽園 供犠の身体・三島由紀夫』(発行=パンドラ 発売=現代書館)は、1997年10月発行で、私は2003年に読み、数多くの三島本の中でも最も感銘を受けた本である。
この本の感想を書いてしまえば、きっと私の三島に対する書きつけも終わってしまうだろうと思われる。そのくらい、この本に書かれていることは私の腑に落ちた。死の謎が氷解したような気がしたのだ。その後多くの三島本を読んでも、その思いは変わっていない。
著者の渡辺みえこ氏は、2003年に私が通信制大学の夏季スクーリングで教わった先生なのである。
たぶん女性学(そういう科目名であったかさえ記憶にないが)だったと思う。たった1週間の講義で、私はその他大勢の学生の一人にすぎなかったし、先生と個人的な会話を交わしたこともない。先生は私という学生がいたことすら認識されていないと思う。
しかし私には、最も印象に残る先生だった。それは先生の講義に対する熱心さ、フェミニズムついての認識を新たにしてくれたからでもあるし、先生が三島研究者でもあったからだ。
ここで紹介する『女のいない死の楽園』は、三島の同性愛をテーマに置き、その同性愛こそが三島の違和感・苦悩の中心であり、死に至る原因であったと書いている。
蛇足ながら書いておくと、三島が同性愛(ゲイ)であったかどうかの判断は、書く人によって異なっている。
私の読んだ限りでは、三島の両親・梓と倭文重、友人の村松剛、『ペルソナ』の猪瀬直樹、『ヒタメン』の岩下尚史は同性愛ではないと書いている。認めていないという言い方をしたほうがいいかもしれない。
いっぽう、友人の湯浅あつ子、福島次郎、野坂昭如、ジョン・ネイスンは、エピソードを示しながら同性愛であると書いている。
石原慎太郎、徳岡孝夫はわかっていたけれど、特に触れてはいないというような感じを受ける。
ここからは本書から引用しながら、いきたいと思う。
三島の作品の「最上の読者」であり、最大の理解者であるはずの母が、彼の人生については「世間並み」に当てはめる母のエゴイズムを押し通した。しかしこのような母、「恋人」が求める「人生のルール」という期待に沿おうとした三島の「可憐な」(「椅子」)心は、『仮面の告白』の時点の「私」をクローゼットの奥に押しやり、彼の頭部と肉体を二つに引き裂く道へと向かわせていくこととなった。(p.18)
祖母に気に入られるために、あらゆる努力をし続けた少年時代から、常に周囲の思惑を気にする性格があったことは、さまざまな方面から指摘されている。その後昭和という疑似益荒男文化の規範〈男らしさ〉〈正常〉を内面化し、〈雄々しい筋肉〉、〈武〉を身につけていった。(P.19)
アメリカ精神医学会が精神疾病リストから同性愛を削除したのは、1973年であり、日本では22年後の1995年であった。
女性化願望も同性愛も容認されている社会なら、「死と血潮と固い肉体へ」(『仮面の告白』)の願望は別の方向へとずらされていったであろう。そして、女々しさと倒錯を堅持し続けたなら、力や制服やナショナリズムではなく、それらを超え、突き崩す方向に向かい、他者も老いも受け止める活路は見いだせたかもしれない。「私」の人生の始まりが異性愛者としての「私」にしかない、規定したところに、1940年代末期の同性愛者の絶望的悲劇があった。(p.20)
岸田秀は「三島由紀夫の精神ははじめから死んでいた。(中略)一生を通じてついに生き返れなかった」という。 自我意識のまとまりがなく、精神病的人格構造を持っていながら発狂しなかったのは書いたからだが、すべてに実在感がないので「外的、観念的尺度に頼らざるを得ない。ボディビルによって隆々たる筋肉を人工栽培(三島自身の用語)する気になりえたこともこれと無縁のことではない」と述べる。(p.21)
三島の自刃と前後して、アメリカでは公民権運動と共に同性愛の解放運動(ゲイリベレイシオン)が生まれ、それは日本でも女性解放運動と共に起こった。もし彼がその時代までも生き抜いたなら、多くの同性愛者たちのように性指向の公言(カムアウト)をし、自分のなかの女性性を開放し、〈自分自身〉という〈人間〉として生き直す、五十代、六十代の三島由紀夫を私たちは見ることができたかもしれない。(p.23)
この最後の文章は「ほぅ」という感じでした。
三島は、兵隊になる強い男が必要とされる戦前の軍国主義の中では、自分の性指向はとても口に出せるものではなかった。
1度死んだつもりで書いた『仮面の告白』は、正真正銘の自分のことだっただろう。
「この本を書くことは私にとって裏返しの自殺だ。(中略)この本を書くことによって私が試みたのは、生の回復術である。」
三島の『仮面の告白』はカムアウトだったが、世の中はまだゲイを認めていなかった。世間の受け取り方は分かれ、作家の創作であると読み取るものも多くいた。
ゲイであることを世の中に真正面から告白できるようになったのは、日本では2,000年になってからのことではないだろうか。
2020/12/30
三島由紀夫のことを少しでも知っている人は、彼の死の原因、そして「なぜあのような死に方をしたのか」ということを考えると思う。
ここでは前回12月8日の続きで『ヒタメン』(岩下尚史著 文春文庫)で湯浅あつ子が語っている三島の死の理由から、引用してみようと思う。
9章「最後の証言者」より(湯浅あつ子の言)
歌舞伎座で『椿説弓張月』の興行のとき(昭和44年11月)に偶然、三島と会った。その時「萬之助のために芝居を書いて欲しい」と頼むと、「残念だが、もう時間がないんだ。今ちょうど一生作(ライフワーク)に打ち込んでいるところで、これを書き上げたら、あっちゃん、僕は、此の世から居なくなるからね」と言いましたのよ。
あの人は、「20台(原文ママ)の頃から45歳になったら死ぬんだ、男が人間として見ていられるのは、45まで。」と公言して居りましたからね。
「あっちゃん、後を頼むよ。ずいぶん会わなかったのに、ここで遇ったのも、やっぱり縁があるんだね」というんです。後を頼むとは、子どもだけは守ってほしいと云うメッセージだったんです。つまりマスコミ対策を頼んだつもりだったのでしょう。(p.325)
先程から申し上げているように、20台の頃から45になったら死ぬと公言しておりましたから、彼の計画通りと言えば、言えないこともありませんね。(P.326)
それと・・案外、お金の苦労もあったんじゃないでしょうか?
”楯の会”を作った頃だと思いますが、「みんなの制服代だってバカにならないんだぞ、ぼくの貯金だって、多いときからみると10分の1になっちゃたんだ」なんて、こぼしていましたもの。
もちろん、そのことだけが、ああした死に結びつくとは考えられませんけれども、40を過ぎた頃から金銭的なことで、だんだん心細くなっていったことは事実です。
もうその頃になると、公ちゃんの書く小説だって、彼が30前後のときのようには、売れなくなっていたではありませんか?
・・・・・・・・・・
湯浅あつ子が話した「楯の会」費用については、『ペルソナ 三島由紀夫伝』で猪瀬直樹も書いているので引用します。
「楯の会は100名近くに膨らんでいた。運営費は三島のポケットマネーから捻出された。西武百貨店社長・堤清二の好意で派手なデザインの制服が提供されたが、貰ったわけではない。イージーオーダーで1着1万円が支払われたが実費は2万円強である。夏服、冬服で101着分202着が発注された。(中略)喫茶店代や合宿代、自衛隊体験入隊費用、制服支給費など、三島が2年間(昭和43~45年)で支払った総額は1500万円になるという。
『新潮』に連載した「春の雪から「天人五衰」までの「豊饒の海」シリーズの原稿料は、4百字詰め原稿用紙1枚につき1500円だった。全部で3千枚だから、原稿料収入は450万円に過ぎない。(単行本は別途)。当時、湯浅あつ子に「支出がばかにならない」とぼやいている。」(p.364~365)
・・・・・・・・・・
湯浅あつ子の証言の続き
ノーベル賞のことは大きいですね。あれは三島由紀夫にとって、大きな打衝(ショック)だったと思いますから。
だって、自分では当然受けるつもりで、授賞式用の礼服まで誂えちゃって、傍目にも可笑しいほど浮き浮きしていたんですから・・・。
それが、恩師として立てていた人に横から取られちゃった形で、私たちの前では、ずいぶん、口惜しがっていましたし、恨んでもいました。
ほんとうに、公ちゃんの人生は、色んなことが思うようにならず、可哀想でした。(p.327)
・・・・・・・・・・
ノーベル賞が取れなかったこと、川端康成に横取りされたと感じた恨みについては、他の人も語っている。
テレビのBS1スペシャル「三島由紀夫X川端康成 運命の物語」では、そのことを取り上げていた。
三島と親しかった女優・村松英子によれば、三島は川端の鎌倉の住まいに呼ばれ、ノーベル賞は辞退してほしいこと、そして川端の推薦文を書いてほしいと頼まれたと話したという。
そして瀬戸内寂聴は、「平岡家はみんな川端を憎んでいた、と弟の千之から聞いた」と語っている。
母・倭文重も「ノーベル賞を取っていたら死ななかったと思う」と書いている。
川端の受賞を知り、お祝いに駆けつけた三島

1963年度(昭和38年)から1965年度(昭和40年)の有力候補の中に川端康成、谷崎潤一郎、西脇順三郎と共に三島が入っていた。そして1961年(昭和36年)5月には川端が三島にノーベル賞推薦文を依頼し、彼が川端の推薦文を書いていたとされる。
世界の文豪を特集したドイツのラジオ新聞(昭和38年12月)上から2段目、右2人目が三島

三島が推薦文を書いたのは36歳の時だったから、まだ三島は若かった。年功序列的な日本文壇では、断り切れなかったのであろう。
候補として名前が出たのは38歳。川端がノーベル賞をもらったとき、三島は43歳だから、10年待てば、また日本人にまわってくるのでは、という気もするが、三島はそこまで生きるつもりはなかった。昭和43年の日本人のノーベル文学賞が、三島にとって最初で最後のノーベル賞チャンスだったのである。
たくさんの三島関係の書物を読んで感じるのは、三島ほど、称賛や名誉を欲しがった人はいないということ。どんな場合も、小説だけでなく、ボディビルでも映画でも、注目されること、称賛されることを強く願った。
ジョン・ネイスンの『三島由紀夫・ある評伝』には、こう書いてある。
三島はノーベル賞を飢渇しつづけた。
昭和40年2月の初めのこと、三島は私にはっきりとノーベル賞が欲しいと語り、私に助力も依頼した。
三島と銀座「浜作」で待ち合わせ、次の小説を翻訳するだけでなく自分の正式な翻訳者になってノーベル賞を取る手助けをするという約束をしてくれないかと申し出たのであった。私は夢見心地でそれを承諾し、二人は握手を交わした。
『絹と明察』(昭和39年)は(中略)錯雑を極めた。それを英語に移すことはたいへんな労苦になるだろう。私は翻訳の仕事を続けるのに必要な熱意を持つことができまいと悟った。
このことを三島に伝えると彼は穏やかに了承したが、その後連絡を取ることはなかった。
私には三島のきっぱりした絶縁の背後に何があったのか、今もって完全には理解できない。当時それを理解するにはあまりに手痛い打撃だったのだが、今になって分かった1つだけ確実なことは、私は深く三島を傷つけてしまったことである。
私たちが最後に会ってから程ない頃、三島は一群の作家たちに私のことを「左翼に誘惑された与太者」であるといった。(P.246~247)
先日、これと同じようなことを私は、ドナルド・キーン研究会のブックトークでも聞いた。
三島はノーベル賞を取ることに執心した時期があって、ドナルド・キーンに『愛の渇き』の翻訳を頼んできたが、その当時は忙しかった。後になって『愛の渇き』は忘れて、安倍公房を翻訳してしまった。それがノーベル賞受賞と関係があるかどうかわからないが、自分の心残りになっている、というものだ。
翻訳を断ることは作品の否定ではない。翻訳者の事情もある。だが、三島は作品を否定されたように感じたのかもしれない。後の三島の死を知った2人の翻訳者は、悔恨の情を抱かざるを得なかった。
三島が「楯の会」を立ち上げたのは、昭和43年10月のこと。川端康成のノーベル賞が決まったのも43年10月であったことを思うと単なる偶然とも思えない。文壇の道ははっきりと諦めて、武の道へ向かったのが、この川端のノーベル賞受賞がきっかけだったかもしれない。
三島の死の理由は、ノーベル賞をもらえなかったことだけではない。ノーベル賞のことは大きなきっかけではあったと思うが、私が考えることは他にもある。
それはまた次回にします。
2020/12/13
北区中央図書館で「ドナルド・キーンを読む会」の主催で、「わが親愛なる三島由紀夫~キーン先生の著作から」というブックトークが行われたので、参加しました。
先日、初めて図書館を訪れて、このような催しがあることを知りました。
6名の会員の方が、キーン氏の著作の中から三島について書かれた部分を取り上げて、トークをしてくださいました。
メモ用紙を持っていかなかったので、小さな資料の端っこにメモを取ったのですが、後から見ると判別不明でした(笑)。自分の覚えのため、思い出すまま書き留めておきます。不正確な部分があるかもしれません。
・・・・・
三島とはいつも敬語で話した。三島から、敬語はやめてざっくばらんに話そうと言われたが、自分にとっては敬語が心地よかったので、それで通した。しかし、あのとき、敬語をやめて話すようになっていたら、もっと深い話ができたかもしれない。
三島はノーベル賞を取ることに執心した時期があって、『愛の渇き』の翻訳を頼んできたが、その当時は忙しかった。後になって『愛の渇き』は忘れて、安倍公房を翻訳してしまった。それがノーベル賞受賞と関係があるかどうかわからないが、心残りになっている。
三島は自分と似ている人を好まなかった。かけ離れている人を好んだ。
ロンドンで2015年当時(年代不正確かも)最も多く上演されている劇は、1位 シェイクスピア、2位 チェーホフ、3位 三島由紀夫である。三島のサド侯爵夫人は海外でも人気の作品である。
三島の自決について、日本と海外では反応が違う。三島はバカな死に方ではなかった。日本では長い間疎んじられたが、海外では最初のうちこそ衝撃があったが、それはすぐにおさまり、彼の文学の評価はずっと高い。あの死によって彼は古今東西、最も高名な作家になった。
作家の辻井喬が、三島の自決1か月前に、三島から急用があると銀座の店に呼び出された。2時間話をしたが、肝心の急用が何であるかは最後まで言わなかった。
三島は筆まめで、よく手紙をくれた。何か頼むと必ず忘れずにすぐに送ってくれた。
・・・・・
西武デパートで楯の会の制服を作ったことや、伊豆で高級な伊勢海老を三島が、3名なのに7人前注文した逸話は私も知っている話でしたね。
キーン氏は三島への親愛の情というか哀惜の情や小さな後悔を、彼の死後もずっと持ち続けていたのですね。
6冊の本の紹介がありました。三島の本は今でさえ読みたい本が山積みですが、時間が取れたら、ぜひ読みたい本です。
2020/12/09
北区の中央図書館で「ドナルド・キーンと三島由紀夫 ~三島没後50年によせて~」という展示を開催中だというので、行ってきました。
北区中央図書館は初めて入りました。
近代的な図書館の建物のそばに、煉瓦の古い建物(赤レンガ倉庫)がありました。旧陸上自衛隊十条駐屯地275号棟を移築・改装したものだそうです。

レストランになっていました。いい感じですね。

ドナルド・キーン氏は北区西ヶ原に居を構え、45年の間執筆活動を続けて来たそうです。
2012年に日本国籍を取得し、北区アンバサダー、北区名誉市民として活動されていました。昨年2月24日、96歳でお亡くなりになっています。
展示はドナルド・キーンコレクションコーナーにあり、それほど大きななものではありませんでしたが、三島がキーン氏に送った最後の手紙(複製)や二人の写真など貴重なものもありました。
昭和28~31年頃、キーン氏が京大大学院に留学していた頃に出逢っています。この時期は三島にとっても一番幸せな時代でしたね。
キーン氏は三島の『近代能楽集』、『サド公爵夫人』、『宴のあと」などを翻訳しています。
11月23日には、キーン氏の養子、誠己氏の講演「父ドナルド・キーンと”親友”三島由紀夫 ~父から聞いた知られざるエピソード~」が開催されていたそうです。徳岡孝夫氏も電話出演されたそうで、これを知っていたら、絶対行っていたのにと残念でした。
ドナルド・キーンコーナー、三島由紀夫コーナーと各々の蔵書のコーナーがあり、三島については珍しい本もありました。
三島の本については、家に読むべき本が積んである状態なので借りてきませんでしたが、一応、北区の図書貸し出しカードを作ってきました。他区でもカードが作れるのですね。
2020/12/08
岩下尚史著『ヒタメン 三島由紀夫 若き日の恋』①、②の続きです。
徳岡孝夫著『五衰の人』には三島の結婚について、「愛を前提としない結婚をした」と書かれています。

前にも書きましたが、『五衰の人』から瑤子夫人について書かれた部分を抜き書きします。
・・・・・・・・・・・・
〈瑤子夫人に会った時も、故人のことは何も聞かなかった。瑤子夫人が決意をもって亡き夫の私事を守る人であるのを承知していた。
周知のように、三島さんは愛を前提としない結婚をした人だった。
「結婚適齢期で、文学なんかにはちっとも興味をもたず、家事が好きで、両親を大切に思ってくれる素直な女らしいやさしい人、ハイヒールをはいても僕より背が低く、僕の好みの丸顔で可愛らしいお嬢さん。僕の仕事に決して立ち入ることなしに、家庭をキチンとして、そのことで間接に僕を支えてくれる人」(『私の見合い結婚』) という条件を出し、日本画家・杉山寧氏の長女と結婚した。〉(p.279)
〈瑤子夫人の言葉によると、「主人のこと、彼との生活のことについては、いままで1度も書いたことはありません。書く手法も知らないし、主人との昔からの約束もあります。こういう夫でございましたと妻が書いても、それはたかだか興味の対象になるくらいでしょう。私自身、そういうものを読むのが好きではないし、妻が書くことによって亡くなった人の姿を変えるすべもありません。書く意志もなければ書くこともできません。」『諸君!』昭和60年1月号〉(P304)
瑤子夫人は語らないことを貫いたのでした。
岩下尚史著『ヒタメン 三島由紀夫 若き日の恋』(文春文庫)には、三島の結婚について、友人・湯浅あつ子の証言が載っています。湯浅さんは『鏡子の家』の鏡子のモデルになった女性です。小説に描かれたように、自宅のサロンには多くの人が集まってきました。
画家・杉山寧の娘瑤子との縁談は、三島の両親から見合い相手を探してくれるように頼まれて、湯浅さんが持っていった話でした。
湯浅さんは、かなりざっくばらんな人だとお見受けしました。ここまで言っていいのかと思った箇所もあります。しかし湯浅さんが語らなければ、語られないまま消えていくエピソードだったでしょう。
三島の両親や瑤子夫人が亡くなった後のインタビューだからこそ言えたことでしょう。三島に興味を持つ人や研究者には貴重な情報です。インタビュー時期は2010年とあります。
〈湯浅あつ子の知人の姪御にあたる杉山瑤子とのお見合いを設定した。(p.305)杉山瑤子と見合いをした帰りの車の中で、公威(三島)は「縁談を断ってくれ」といった。
「彼女はまだ学生なのに、親に言い含められて嫁に行かされようとしているかもしれないけれど、ぼくとしてはこの場でお断りするからね。すまないが、あっちゃん(湯浅あつ子)、明日から円満な手続きを頼むよ」(p.306)
断ると、瑤子ちゃんが私の家に駆け込んできて「三島由紀夫ではなく、平岡公威というひとを好きになっちゃったんだから、絶対にお嫁に行かせてください、お願いします」って、それこそ泣いて訴えるじゃありませんか。
断りをお伝えしましたら、こんどは杉山夫妻が私や小松さんを通り越して、平岡の家と直接、この縁談の交渉をするようになったんです。(P.308)
杉山家が経済上の攻勢をかけたんです。奥さんの御実家が御内福だという話もありましたから。決して裕福ではなかった平岡家が倒れたわけですよ。
しかし、結婚してからは杉山家からの応援も期待したほどではなくて、平岡の両親からは、あとになって種々の愚痴を聞かされましたけれども・・・。
結婚して新築した馬込の家の、家具調度の類はほとんど、瑤子ちゃんの実家から出たお金で買ったものだと聞いたことはあります。(P.309)
ですから、後になって、おばさま(倭文重)がね、とんでもない家との縁談を世話してくれたと云うような苦情をおっしゃるたびに、私は一度はお断りしたのよ、って言いたくなりましたよ(笑)
2人が新婚旅行から帰ってきて、半月ほど経ってからでしょうかしら、「この結婚はやっぱり失敗だった。あっちゃん、別れたいんだけど」って言うんですよ。(P.311)
しかし、まもなく瑤子ちゃんが妊娠しているらしいということになったんですね。ですから、そのときの別れ話はしぜんと立ち消えになりましたのよ。(p.312)
・・・・・・・・・
文学座や大映の女優さんと写っている写真などは、全て瑤子ちゃんの手で破棄されたそうです。そうした嫉妬の的になったのは女ばかりでなく、男の友だちにまで及びましたから。
結婚以前の三島由紀夫の交友関係を一掃しようとしたんですもの。それも自分が表に出るのではなく、わざと公ちゃんに喧嘩させる形で、どなたとも縁を切らせましたからね。(P.313)
そんなことで、唯一の親友だった黛敏郎さんも絶交することになったンです。
それと同じ頃に、瑤子ちゃんは私のことも公ちゃんから遠ざけました。
・・・・・・・・・・
瑤子ちゃんだって、女として、妻として、可哀想でしたよ。
だこさん(貞子)と結婚していたならば名作が書けるでしょ、ええ、書くことができましたね。華やかで豊かな暮らしと云うものが、彼らしい名作を生むには、何より必要だったのだと思います。
その証拠に、あれは確か、「楯の会」を作ったときですよ。「あっちゃん、もう、以前のように書けないんだよ。僕、小説書けなくなっちゃった」などと、泣き言をいうのを聞きましたもの・・・作家がね、そんなことを言うようになったら、もう、了りなんじゃありませんか。
だけどね、夫婦はおたがいさまですからね、公ちゃんばかりでなく、お嫁さんも気の毒でしたよ、女ですもの。
だって、表向きはともかく、良人から敬遠されてばかりでは、妻としての立場がありませんよ。
その上に、別棟とは言いながら、隠居所を隔てた塀の向こうからは、息子を溺愛する姑の目がいつもいつも光って居りましたしね。(p.320)
三島の未亡人ということよりも、ふたりの子供の母親としての瑤子ちゃんが、世間の好奇の目から、幼い子どもたちを守るために、それこそ必死で闘いましたからね。その覇気たるや、子を持つ母親として、実に偉いものでした。(p.326) 〉
これは湯浅あつ子から見た平岡家(三島)の様子である。別の人が見れば、また別の感じ方があったかもしれない。しかし、ぎくしゃくした結婚生活であったことは、平岡家を知っている他の何人かが語っているところである。
次回は、湯浅あつ子が語る三島の死の理由を書いてみたいと思います。
2020/11/25
今日は三島由紀夫が亡くなって50年の祥月命日。
前回の岩下尚史著『ヒタメン 三島由紀夫 若き日の恋』続きです。

ヒタメンとは「直面」と書きます。
「能のシテが仮面をつけずに舞台にあらわれると、それは役者の素顔ではなく『直面』というもうひとつの仮面である。」
素顔のようでいて、やはり演技しているということですね。
第9章「おそらく最後の証言者」。
湯浅あつ子さんの聞き書きです。湯浅あつ子さんは、三島の妹・美津子の同級生の姉にあたり、三島とも親しく、三島の両親にも可愛がられて平岡家(三島家)に出入りしていた女性。夫はロイ・ジェームス。
「まるで弟のように・・・・・と申しましても同い年ですけれども。まあ、私は三島由紀夫にとって、親友と姉と恋人を兼ねたような存在でしたからね、たとえ、血はつながらなくても、おたがいに1ばん近い身内でした。」(P.287)
あつ子さんの聞き書きには驚くべきことが語られ、まるで週刊誌的興味で私は読んでしまったのです。
抜き書きして引用させていただきます。
【引用】
その頃の公ちゃんは、(中村)歌右衛門にぞっこんでございましたから。平岡のおばさまが嫉妬なさるくらい。当時の公ちゃんには、『仮面の告白』に書いたような傾きが、実際、見受けられましたからね。
歌右衛門とは、まさか、深い仲ではなかったとは思うんですけど、実際にあったかどうかはともかく、それに近いような思い入れは、確かにありましたもの。
湯浅さんによれば、三島は歌右衛門にぞっこん惚れ込んでおり、お顔も様子も似ていた貞子さんに歌右衛門を重ねていた部分がある。(p.270~272)
・・・・・
前夜の逢瀬のあれこれを、翌日、そのまま話に来るんですもの。私にだけは、女の恋人ができたことを自慢したかったのかもしれません。
ずっと後になって、彼女(貞子さん)に会ったときに、「あの頃、熱海や京都にも泊り掛けで行ってたって、公ちゃんからよく聞かされていたけど、あなたのご両親は御存知だったの?」と聴きましたら、「その頃はお店が忙しかったし、何しろ使用人も何十人もいて、取り紛れていたんでしょう」なんておっしゃっていましたが・・・・・赤坂でしたっけ?花柳界と云うのは、私たちから見ると、不思議な世界ですね。(P.273)
毎日のように会っていても、3年のあいだ、だこさん(貞子さん)が同じ衣装を着ているのを見たことがないと、公さんは感心していましたよ。それこそ帯から何から、お金のかかった凝ったものばかり・・・・・それを、たった今、しつけの糸を取ったばかりといった様子で、あらわれたそうですよ。
どこへ行くにも、だこさんの好きそうな場所を一生懸命選んでは連れて行くわけです。それこそ超一流なんですね。ですから、いつもお金が足りない。文士の稿料なんて知れてますわねえ。
当時は平岡のおじさまは年金生活者ですから、長男である公ちゃんが両親や弟を助けなければなりませんもの。
そこで、私がお立て替えをしていました。公ちゃんは必ず返しに来ましたからね。借りに来るのは週に1度で、いつも七萬円と決まっているんです。
(昭和29年当時の7万円を現在の価値に換算すると、当時の国会議員の月額歳費が七萬八千円、現在のそれは130万円である)
19歳のだこさんの財布には、いつも10万円の新札が入っていたそうである。
公ちゃんは結婚するまで親と同居しておりまして、緑ヶ丘の借家住まいでしたが、2階が6畳と3畳でしたか、そこを公ちゃんが占領して、自分の書斎にしていましたの。そこへ寝るんでしたからね。可哀想なくらい薄い煎餅布団のシーツが、いつ見てもヨレておりましてね、布団の真ん中がつぶれて両側だけかぶさって、ちょっと太鼓みたいな形になっているんですよ。
ーーそれで家督の惣領である三島由紀夫が、親兄弟を養わなければならなかったわけですね。
そうです、お金を稼ぐためには、公ちゃんは作家として、何としても有名になる必要がありました。
ーーなるほど、私などが想像していたよりもつつましい暮らしのようですね。
・・・・・・
以下は、後書きでの岩下氏の感想である。
「まるで生まれながらの貴公子のような言動を繰り返しながらも、ありようは、緑ヶ丘の借家なる屋根裏のような中2階にささやかな机を据え、古浴衣の紐を巻き付けた木綿布団にくるまりながら、夜の目も寝ずに筆を執り、年金暮らしの両親と弟妹を養う、若き日の三島由紀夫の健気さー」
「絢爛、豪華、荘厳、華麗等々・・・お決まりの誉め言葉で形容されるのが型となった当代文壇の驍将の、つつましい楽屋を覗いた思いがする。」(p.349)
・・・・・
再び第9章より【引用】
公ちゃんに対するおばさまの偏愛ぶり、これにはおじさまも匙を投げていらしたくらいです。
それも度を越しておりました。おばさまが「公威さん、足を虫に刺されてイタイイタイだから、ちょっと舐めて頂戴よ」なんて仰言ると、「はいはい、どこどこ」って、むき出しの肌をぺろぺろ舐めてましたもの。
ですから、世間には、近親相姦じゃないか、なんてうわさする人たちもあったほどですよ。(P.289)
ーーそんなふうでは、貞子さんと付き合っていることなど、三島由紀夫から母親にはいいにくかったでしょうね。
そうかもしれません。でも、平岡の両親は知っておりました。だって、一緒に住んでいますから、ああ毎晩のように帰りが遅いんじゃ、どこの親だって、たいてい察しがつきますよ。
貞子さんのことは興味津々といったところです。ちょっと、変わった親たちですから・・・・・。
それにいくら何でも、料亭の娘さんと結婚するところまで、この交際が進展することはないだろうと云うような暗黙の了解が、平岡の親子にはあったと思います。
あちらのお母さまも、長男のところへは、ぜったいお嫁に行ってはならないとおっしゃったそうです。それと後ろ盾のない家の息子はダメだとも・・・・ね。(P.292)
貞子さんは、旧財閥の次男と結婚したそうです。
だこさんという人は、男たちに人気がありましたもの、言い寄ったのは、公ちゃんばかりではありませんでしたよ。ですから、ほかの男に誘われて、彼女がそっちへなびかないように、毎晩会うことで、自分に縛りつけておこうとしたわけです。
・・・・・
そして次には、瑤子夫人との結婚のいきさつになるわけですが、単純に幸せな結婚、とはいえない、ここから苦しみが始まったのかと思われる結婚の様子が語られます。
それは次回にしましょう。