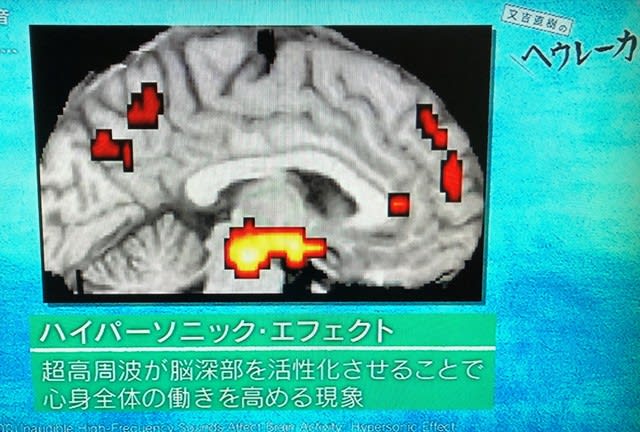2021/03/05
高い壁を見あげる女性の写真を見たのは、2月のこと。
衝撃を受けました。海岸線がこんなふうになっているのかと・・・
私が2016年に復興応援バスで訪れたことのある宮城県石巻市雄勝の海岸の写真です。

3㎞にわたって作られた防潮堤

私のパソコンの画面撮りなので不鮮明な写真ですが、おおよそはわかると思います。(お写真お借りします)
引用元のAERA ↓
https://dot.asahi.com/aera/2021020900050.html?page=1
AERAより抜き書きで引用します。
〈灰色の巨大な壁が現れた。高さ9.7メートル、長さ3キロにおよぶ防潮堤だ。城壁のように延びる防潮堤のすぐ裏にある海は見えず、その気配すら感じない。
震災前、この海沿いには住宅や商店が立ち並び、350世帯が暮らす街があった。だがいま、地区に残るのはわずか30世帯ほど。海際の低地は災害危険区域に指定されて住むことはできず、高台の集団移転地に暮らしている。
「雄勝は、防潮堤に殺された」
高橋頼雄さん(53)は絞り出すように言う。雄勝の名産でもある硯(すずり)職人の3代目。震災後の地域復興を引っ張るリーダーだった。だが、高橋さんは19年春に雄勝を離れ、いまは福島県いわき市で暮らす。
高橋さんら地元住民の多くは、巨大防潮堤の建設に反対してきた。市役所支所が事務局を担い、高橋さんが副会長に就いた雄勝地区震災復興まちづくり協議会では11年7月、石巻市長に11項目の要望書を提出した。要望の一つ目は住宅再建のための高台造成。二つ目に、高い堤防を築かないよう求めた。
震災前と同じ4.1メートルに留めるよう求め続けた。しかし、16年、工事は始まった。
高さ9.7メートルもの防潮堤をつくっても、東日本大震災規模の津波が来れば、たやすく越水する。それどころか防潮堤で海が見えず、避難が遅れるとの指摘も多い。
防潮堤をつくらず、海際には大事なものを置かない。そして、あの日のことを語り継いでいくのが本当の防災ではないかと高橋さんは言う。
工事が進んだある日、高橋さんは趣味の釣りのために沖へ出て愕然とした。
「青い海の先に山が連なり、幾筋もの沢が輝く。そんな海から見た雄勝が私の原風景です。でもその日は、高い壁で囲まれたグロテスクな景色でした」
この日、雄勝に住み続けることを完全に諦めたという。
東日本大震災で破壊された海岸堤防等の復旧・復興事業は被災6県(青森、茨城、千葉を含む)の621カ所(延長432キロ、原子力被災12市町村除く)で進められ、昨年9月末現在で75%が完成、今年度末を目途に工事終了を目指す。昨年度までに1.4兆円が投じられ、東北各地に10メートルを超える防潮堤が出現した。
政府の中央防災会議の方針を基本に防潮堤を計画。村井嘉浩知事は「やめたらもう先には、どんな理由があってもやれない」と、全額国費で賄える復興期間の5年間(のちに延長)での完成を目指したのだ。〉
私がこの記事に目を留めたのは、先にも書いたように、2016年に訪れたことのある場所だったからです。
仙台駅からJRの復興応援バスに乗り、石巻市の「大川小学校」を左に見ながら、右折して雄勝湾に向かって行くと、雄勝店こや街(おがつたなこやがい)がありました。

そこで昼食をいただいたのです。

この海鮮丼のおいしさは今でも忘れられません。ここはおいしい海産物が採れるところなのだと知りました。
ガイドさんが雄勝は風光明媚な場所で「日本一美しい漁村」だと言っていたのが印象的でした。
雨で暗かったので、海の写真はあまり撮りませんでしたが、店こやの裏側にあった雄勝港です。

(おがつ店こや街は令和2年3月をもって閉店したそうです)
地元の方たちが、防潮堤を「これで安心だ、よいものができた」と喜んでいるなら、それでいいのです。地元民でない私がとやかく言うことではありません。
でも地元の方が悲しんでいるというなら話は別。住民の意見を無視した復興は、本当の復興なのでしょうか。
私は静岡県の浜名湖西岸の海の近くで育ちました。海まで歩いて行けました。浜は美しい砂浜でした。だから、そういう場所にこのような防潮堤ができたらと想像すると、気持ちがわかります。
住民はいつも海を見て、海からの恩恵を受けて暮らしていたのでしょう。何十年、何百年に1度の津波のために、毎日の生活の恩恵を奪われてしまうのは悲しいことです。そこに住んでいる住民の意見を聞かないのも悲しいことです。
この防潮堤は今後ずっと、何十年もあり続けるのでしょうね。