グループホーム居住痴呆性高齢者の地域生活の構造に関する研究
—グループホーム入居者の外出行動による事例的考察—
絹川麻里、外山義、三浦研
日本建築学会計画系論文集第564号157−164、2003年2月
1.研究目的
医学分野では、虚弱期・要介護期にある高齢者の生活範囲の過ごし方、生活の中での社会的接点の有無の重要性は高齢者のQOLや日常生活動作(以下ADL)の維持という視点から多く説かれている。この考えのもと、本研究ではグループホーム(以下GH)入居者の地域性格の構造を明らかにすることを目的とする。
2.調査方法
入居者の施設外活動を総体的にみるため過去1年間(2000.11~2001.10)の生活日誌から入居者の外出行動に関するデータを抽出した。また、開設直後から2年間にわたり週1回施設内外の活動に参加し、参与観察を行い、外出先やルートの確認などを行い分析、他にも地域住民に対するアンケート調査結果の分析。
3.入居者の外出行動の分析
・入居者の地域生活は地域でもGHを基点に限定された範囲に集中した外出行動によって支えられている。
・ADLが高く痴呆レベルが軽~中等度の入居者の外出行動は地域内で分散され拡大されること、痴呆が重度化しまたADLも低下した入居者の外出はより狭い範囲で行われることが明らかになった。
4.生活のコンテクストにみる入居者の外出行動
・自発的外出は生活の流れをくんだ自発的行為の連続として発生した行為であった。
また自発的外出は新たな自発的行為を生み出させる。
・自発的外出は入居者を生活の中で行為の主体として位置づけるものとして機能している。
5.地域の中での入居者の地域生活の存在
日々の生活の場の重なりが多い方がGH入居者を深く認知し、積極的交流を育む機会を生むことが予想できる。地域住民の意識からみて、入居者と地域住民の生活の場の重なるGH周辺の領域の確保やそこでの住民との交流の創出は入居者の生活の質を大きく左右するものであると考える。
6.まとめ
痴呆症ケアの重要な項目として挙げられる過去という時間とのつながりや家庭的な生活環境との接点をGHで実践していくため、なによりもGHにすまわれる痴呆性高齢者が個人として主体的に暮らしていくことを可能とするためには、入居者と地域とのつながりは非常に重要な要件である。質の高いGHを計画するにはGH内と同様にGH周辺の環境の重要性を認識することが大切であると考える。玄関を出れば果てしなく1つの領域(public)が広がるのではなく、入居者の個別性、主体性を尊重した外出行動を支えることのできる周辺環境を1つの差別化された空間構成と認識し整備することは入居者のQOLの向上につながると考えられる。
7.感想
入居者の外出先を周辺図にまとめてあり、外出先や外出内容、外出理由の関係も図でまとまっており見やすかった。
痴呆ケアにとって自発的行動がとても重要だと感じた。
(上石康平)











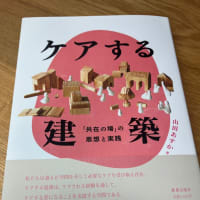


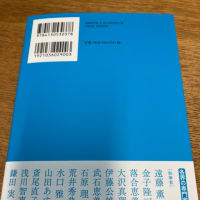
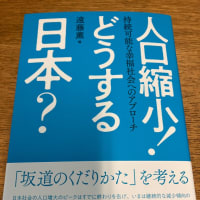






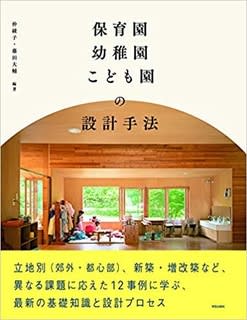
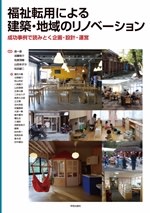



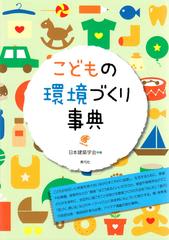



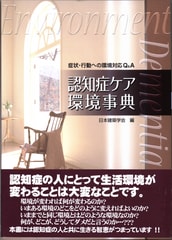

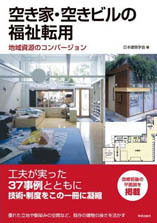





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます