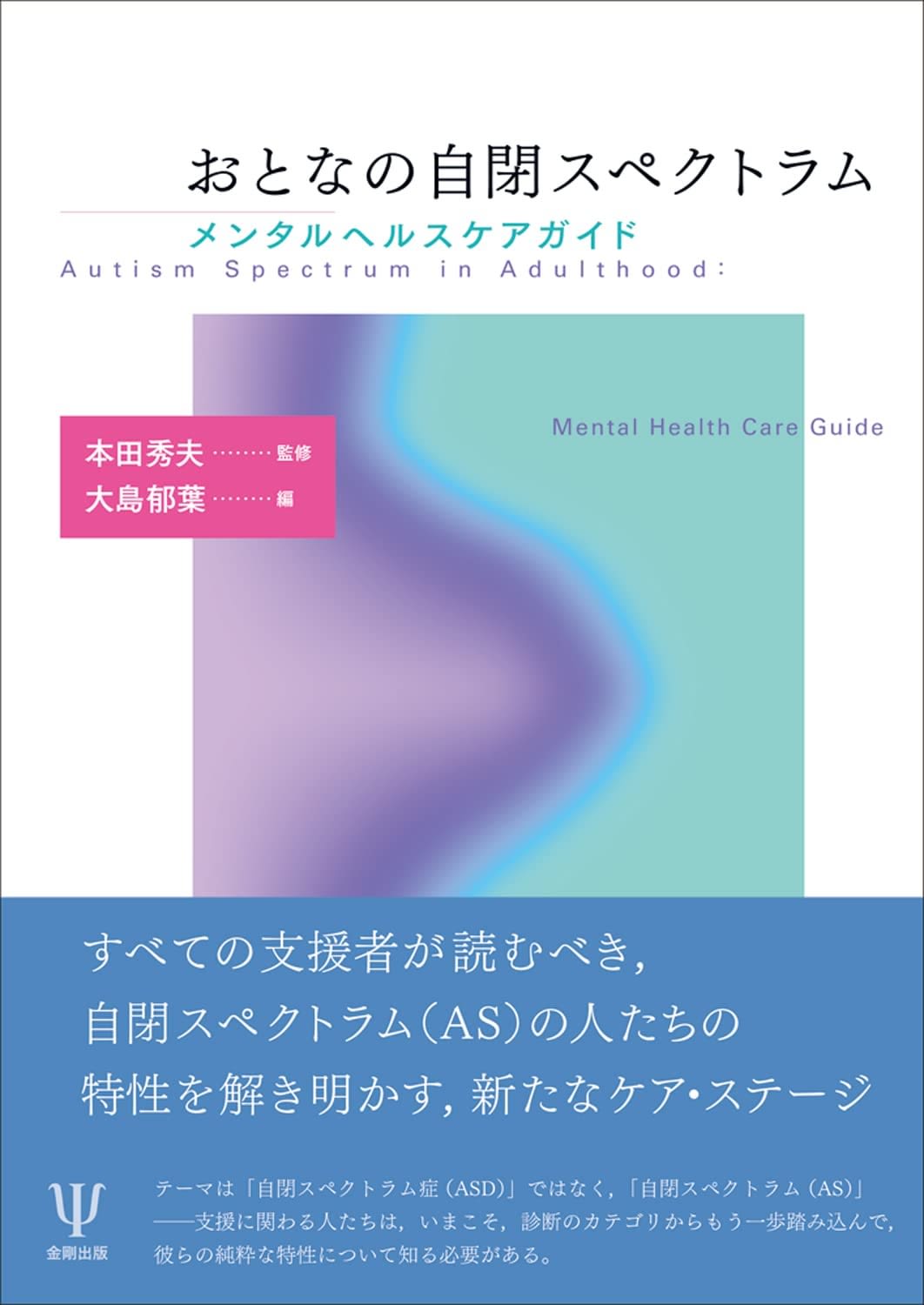
個人的に、認知行動療法についてと自閉スペクトラム症について、それぞれ別個に学んできたのだが、認知行動療法は自閉スペクトラム症に効果はあるのだろうかという興味は以前からあった。これまでそういったテーマの本は見当たらなかったのだが、本書ではそうした題材についてもそれなりの解説がなされているようなので、得るものがあるに違いないという思いで読んでみた。本書はそれに限らず、自閉スペクトラムのケアについて、多くの分担著者による8ページ程度の各論がたくさん集められている。その多くは、支援者だけでなく、自閉スペクトラム(症)者自身にとっても役に立つことが多いと思う。私なりに気になったポイントを下記にピックアップした。
[はじめに]本田秀夫
・本書は、自閉スペクトラム症(ASD)ではなく、自閉スペクトラム(AS)がキーワードとなっている。つまり、医学的な疾患概念ではなく、人の認知や思考のあり方としてのASを念頭において書かれている。ニューロダイバーシティ(神経多様性)という言葉はよく聞くようになったが、ここでは、ニューロトライブ(神経種族?)というキーワードも出てくる。
[特異な選好(preference)をもつ種族(tribe)としての自閉スペクトラム]本田秀夫
・成人期にASであることを自覚して対人・コミュニケーションに苦手意識をもつ当事者が、対人関係に自信がもてず、自ら回避しがちであることを発信することが、今や当たり前になっている。かつての自閉症概念で括られた人たちでは考えられなかったことであり、いかにASの概念が拡大してきたかがわかる。
・中学校では、いわゆる「スクールカースト」が形成され、主に社交性の高低によって目に見えない対人関係の序列ができる。スモールトークを好む人たちが序列の上位になることが多く、AS特性をもつ人たちが上位になることは少ない。多くのASの人たちにとって、この時期は人生における最大の関門と言ってもよい。
・能力の有無よりも、好きなことがあるかどうか、好きなことを余暇活動として楽しめているかどうかの方が、二次障害の保護因子としては重要であると筆者は考えている。
[知ることからはじめるーASDの診断から自己理解とアイデンティティの再構築へ]大島郁葉
・スティグマとは、個人の持つある属性によって、いわれのない差別や偏見の対象となることを指す。スティグマの諸側面を表す代表的な概念として、パブリック・スティグマやセルフ・スティグマがある。パブリック・スティグマは、社会全体が持つスティグマである。例えば「障害者は能力がない」といった社会風潮を指す。一方、セルフ・スティグマは、パブリック・スティグマを内在化し、「障害のある自分には能力がない」とする個人的な信念を指す。「ASDであること」は次のような告知を受けるようなものかもしれない。「あなたには常識がなく人を不快にさせる病気があります」
[自閉スペクトラムのパーソナリティ]青木省三
・ASの人は目の前の対象に引き付けられて、考えが頭から離れない、ということが起こりやすい。頭にこびりついた考えや心配を切り替えるには、そこに向かっている注意を他のものに向けることが大切になる。好きな音楽を大きな音にしてイヤホンで聞く。好きな食べ物をしっかり味わって食べる。ジョギングをする。自転車に乗る・・・その人にあった切り替え手段を2つ3つもつことである。
・筆者は「仕事は飯の種。こつこつと働こう。趣味を大切にして趣味人として生きよう」とか、「自分の仕事にこだわって、職人っぽく生きていこう」などと話すことがある。職人、趣味人のすすめである。
[ASの人たちの感覚]青木悠太
・ASDの中核症状は社会性の障害と興味の限局であり、感覚症状は周辺症状と考えられてきた。しかし、最近は、感覚症状は実は周辺症状ではなく中核症状の根底症状ともいうべき存在であるという知見が蓄積している。感覚症状に対する治療として薬物療法は確立されていないが、例えば、視覚にはサングラスや紙を使って一部の情報を隠すような工夫、聴覚にも耳栓やイヤホンなどで入力段階から対応することが病態生理の少なくとも一部に対して効果的であると想定される。
[AS/ASDを診断する]内山登紀夫
・ASDと診断されることは自己をみるための新たなレンズを得ることでもある。現在と過去の経験や苦難は自閉症のレンズで見直されて、新たな意味を付与される。自己の行動や感じ方、生きづらさに対して説明がつき、自分自身を理解することについての新たな視点が生じる。医学的な理解は諦めや妥協をもたらすのではなく、本来の豊かな自己に純化される契機になる。
[ASとアタッチメントー症状論・支援論]田中究
・自閉スペクトラム症をもつ人では、好きなこと、やりたいことができること、これが制約されることは定型発達の人よりも顕著に影響を及ぼし、精神機能の失調につながりやすい。精神機能の安定のためには、こうした選好する対象と過ごし、それを通して人とのつながりを保持する(同好の集まり)ことが欠かせない。
[ASとトラウマー症状論・支援論]桑原斉
・ASD(に併存する症状)において薬物治療が行われる場合もある。攻撃的行動・易刺激性の改善が行動分析などによっても不十分な場合、抗精神病薬の投与で易刺激性を治療する。リスペリドンとアリピプラゾールの効果は確立しており、保険適用(ASDの易刺激性)も得ている。
[ASと不安ー症状論・支援論]村上伸治
・AS者は、他人の気持ちや意図が読めずに苦労しているので、「他人の気持ちや意図」を解説することも重要である。さらに「自分の気持ち」も解説する必要がある。AS者は自分の気持ちに気づきにくいので、自分で説明のつかないイライラ、怒り、悲しみ、衝動などが頻発しやすい。自分の気持ちについて話し合いながら、推察でも良いので、自分の気持ちを察することを支援していくことは、不安の対処としても重要である。
[CBT/ACAT]大島郁葉
・日本においても徐々にニューロダイバーシティという運動がASの人たちの間で起こりつつあるが、海外においてはより明白に、アカデミズムにおいても社会運動としても活発である。研究論文においても、ひと昔前は、ASD者に定型発達者の適応を身につけさせることをコンセプトに置いた論文をよく見かけたが、現在においては、本人の変容よりも、社会がASの人を容認すべきであるという論調に変わってきているように思う。
・第三世代のCBT(認知行動療法)は、個人の性格や素因そのものに問題の起因をあえて置かず。環境と個人の反応(誤った連合学習)の環境の機能をメタ的にとらえ、それが非機能的であれば、機能的文脈に再学習していくというプロセスをたどることから、認知療法というより行動療法よりのCBTに近い心理学的介入法であろう。このように現在の第三世代のCBTは社会モデルに準拠していると考えられ、薬理学的治療といった医学モデルでの介入法と併用して行うことに、筆者は一定の意義があると考えている。
・近年、ASDの自己理解や受容を目的とした親子の心理教育プログラムが施行されており、その効果も実証されている。一方、これまでも国内ではそのようなプログラムは存在しなかったため、筆者らはCBTのフレームワークに欧米諸国で活用されている心理教育を加え、「ASDに気づいてケアするプログラム」(Aware and Care of my AS Traits : ACAT)を開発した。(参照:大島郁葉、桑原斉(2020)ASDに気づいてケアするCBTーーACAT実践ガイド.金剛出版.)
[マインドフルネス/ACT]杉山風輝子、熊野宏昭
・マインドフルネスやACTを用いた治療の効果研究は、年々、その対象や範囲を拡大し増加傾向にはあるが、ASD者を対象とした実証的研究は今のところ多いとは言えない。特に、子どもから思春期のASD者やASD者の両親を対象とした研究の方が多く、成人のASD者を対象とした研究は、未だ検討されている最中である。これまでのところ、マインドフルネスやACTを用いた治療を行うことで、ASD者特有の思考過程や感情体験などは変化しないが、特に反芻思考を減らすことは可能であり、それによりASD者が二次障害として経験しやすい抑うつや不安に対して、一定の効果が期待できることが先行研究により示されている。
・ASD者にマインドフルネスやACTを適用する場合に、注意が必要なことが2点ある。1点目に、ASD者の中には、特定の身体感覚が過敏すぎたり鈍感すぎたりすることで、アクセプタンスに重要な感情や身体感覚をそのまま感じることが難しい場合がある。このような場合、「不安な時」や「やる気が出ない時」など、対象となる感情や場面を限定し、そのような時に体験している身体感覚のうち、何か1つ、本人にとって分かりやすく目印となるような特徴を見つけることが役に立つ可能性がある。2点目に、脱フュージョンにおいて、思考と距離をとるプロセスが重要であるが、ASD者には、言語の重要な機能のひとつである認知対象との心理的な距離を作るという機能が働かない(字義通りに捉えてしまう)認知特徴がある。そのため、思考と距離を取ることが実現しなかったり、時間がかかったりすることがある。それでも、自分が思考しはじめたことに気づき、それ以上考え続けるのをやめることは、反復的に練習すれば、時間がかかっても、ある程度できるようになることが多い。
[PEERSー友だち作りのSSTの可能性]山田智子
・ASDの若者の社会適応を支援するうえで、ソーシャルスキルトレーニング(SST)へのニーズは高い。ソーシャルスキルとは、対人関係の構築や円滑な集団活動への参加に必要なスキルであり、PEERSプログラムは、なかでも”友だち作り”に焦点をあてたカリキュラムとなっている。PEERSでは、まずは”見る・聞く”(グループの様子を見て、楽しそうに話しているか、話題は何かを聞く)、次に”待つ”(会話の間を待って、流れを止めないようなタイミングを捉える)、それからいよいよ”加わる”(今、話されている話題に沿った一言を言って、会話に加わる)という3ステップを提示している。
[行動活性化/シェイピング]温泉美雪
・行動活性化では、対象者の行動を変容させるために、行動に対して報酬が得られる機会を増やしたり、嫌悪的に感じる社会的活動からの回避を減らすよう導いていく。
・家族により、ひきこもり状態にある本人の行動活性化が行える。つまり、家族がひきこもり状態にある本人の家庭での快活な行動を見つけて、細やかに好子を与える。好子を与える行動は日常のささやかなもので十分である。例えば、本人がリビングでテレビを見ているとしたら、そのテレビ番組の内容を話題にして肯定的な注目を与え、リビングに滞在する行動や家族との会話を増やすように試みるのである。このように、行動が活性化されていない人のわずかな行動に対して好子を与え、段階的に他の行動にも好子を与えるようにし、行動レパートリーを増やすことを「シェイピング」という。
・幼児期の療育では、「子どもに失敗させないように」という方針を掲げることがあるが、学童期の頃には、子どもは自らの行動の行動分析を経験的にある程度できるようになっているため、幼児期に比べると、失敗しても「次はこうしよう」と考えることができるくらいタフになっているということだ。あえて失敗させる必要はないが、ASDの自立を応援する人は、本人が達成感を感じる経験を重ねていることを前提として、過保護になることなく、本人ができることを見守り、時にうまくいかなくても援助要請するのを待つ姿勢が求められる。
[大人の自閉スペクトラムにおける産業メンタルヘルス]横山太範
・自閉的な傾向は障害特性に由来するものに加えて、本人の社会適応の方策として感情に蓋をすることにより一層自閉的となっていくという負のスパイラルが強化されていくことになる。
[学生相談]石垣琢磨、川瀬英理
・大学院の学生に対して、教授自身が忙しすぎて、学生にあまり手をかけて指導できないという場合もあり、「自分でやれるところまで研究を進めて、成果だけ見せてくれればよい」という態度になることもある。こうした上昇志向的、あるいは成果主義的な態度は営利目的の組織のリーダーであれば当然のことかもしれないし、就職すれば当たり前に要求されることでもある。自閉スペクトラム症の学生のなかには、それに適応できず、研究環境との間に軋轢が生じ、場合によっては被害的になって、教授や大学とのトラブルに発展するケースもある。
[自助グループ]片岡聡
・ASD当事者の筆者は、統合失調症と誤診された発達障害の人たちによる自助活動を始めた。著者がASD診断を受けた2010年当時は、現在のように成人のASD者が多く存在するという認識が広く精神科医の間に共有されていたとは言い難い。本来なら健康維持の支援こそが必要なASDの人たちが、統合失調症の治療ガイドラインに沿った不必要かつ有害な抗精神病薬の投与を受け続ける現状をなんとか変えたいと思った。
・高機能成人ASDの自助活動につかれた筆者を救ってくれたのが、知的障害のあるASDの人たちとの即時的・非言語的なコミュニケ―ションだった。筆者は特に言葉がなくてもまったくコミュニケーションに困らないことが多い。また、筆者が急に健常者にとっては意味不明な奇声を発し、また共同感覚遊びを始めるのでよく驚かれた。
[ピアサポート]綿貫愛子
・ASD当事者の筆者は、ASDであることを知ってから、ASDについて学んでいった。この作業は、周囲からはつらいのではないかと心配されたが、個人的には長年の謎が解明されていくような面白さとある種の爽快感があり、始終前向きに進められたように思われる。
・ある気づきは、当事者の手記や当事者会のなかでも、自分と合う人と合わない人がいるということである。面白いことに、この適合性には、年齢や性別はあまり関係がない。自分との類似性や興味関心、趣味嗜好、価値観、ライフスタイルなど、心が通じ合えるかどうかが筆者には重要であった。
[AS特性をめぐるクロストーク]青木省三、大島郁葉、桑原斉、日戸由刈、本田秀夫
・AS特性への理解が深く、また自らAS特性を有していると思われる執筆者たちが集められ、自分の特性の臨床における活用などが語られた。
・横浜には各区に1つずつ地域生活支援センターというものがあり、それぞれ別の法人が運営しているのでカラーがある。筆者がよく関わっているある地域生活支援センターは、希望があれば特に問題がなくても月1回定期的に会ってくれる。行って近況報告して帰るだけなのだが、それがよく機能している。そうすると本当に何かあったときにアクセスしやすくなる。(本田秀夫)
・胸を張って自分らしくASらしく生きていくことは大事なことだ。自分なりのこだわりは大切に、楽しみつつ生きていく。些細なこだわりをいっぱい作りながら、大きな問題を回避するとか。こだわりは生きる戦略としてすごく役に立つ。(青木省三)













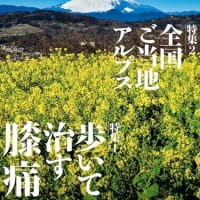






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます