
 | 長岡鉄男のスーパーAV―ホームシアターをつくる |
| 長岡鉄男 | |
| 共同通信社 |
「長岡鉄男のスーパーAV―ホームシアターをつくる」という本があり、これを読んでプロジェクターの導入を考えた。長岡氏は大画面ホームシアターによるインパクトを「麻薬以上の何か」と評した。AVフロントという雑誌に長岡鉄男氏が連載を持っており、3管型のプロジェクター調整の記事を掲載していた。調整に恐ろしく面倒な手順を踏んでおり、メーカーの調整師まで呼んだと書いていた。
とにかく大画面が夢だった。船舶振興会の「船の万博」で、500畳相当の映像を見たことがある。正方形のスクリーンなのだが、客席がすり鉢状になっており、中央の付近に視野がある。蒸気機関車が真っ直ぐに迫ってくる映像では、圧倒的なリアリティがあり、逃げ出そうかと思ったぐらいである。この時の経験で、後に床面上ぎりぎりから投射して、視野角中央に視点が来る方がリアリティが出るということを学んだ。
1985年のつくば万博「国際科学技術博覧会 」には3回行った。大画面映像のパビリオンを幾つか見てしびれた。
1990年代は地元に映画館が無く、隣町の川越に行って映画を見るしか無かった。川越ホームラン劇場はBoseの直管共鳴管を導入しており、スコーンと伸びる低音を堪能した。
私見では実物以上に人物や物体が投影されると、俄然本物感が出て来る。人物の全身が写った場合、一般的な人は160cm前後なので、立寸法がその程度以上あると、映像が視聴者を支配する。テレビの場合はどんなに近づいても、映像に支配されてしまうことはない。部屋の照明の有無の差もあるのだが、大画面は人を圧倒し、魅了して束縛して離さないのである。
当時、液晶プロジェクターも登場しており、DLP型という設置の自由度が高いタイプがあった。軽量(といっても10kg超え)で上部も置ける。当時のオーディオ部屋は6帖しかなく、先入観で液晶型一択だと考えていた。しかし、長岡氏も指摘していたが、当時の液晶は表示品位が低かった。画面上に格子が見えるし、輝度も低く、映像ダイナミックレンジも低かった。私自個人は大枚はたいてシャープの液晶プロジェクターを3台乗り継いだ。当時プロジェクターは内部にホコリを吸い込みやすく、ホコリとの戦いでもあった。2台目を買ったときには、ホコリだらけになったプロジェクターを中古販売店に売ったが、内部清掃をどうやったのか気にはなった。
当時6畳間でSonyのブラウン管式3管型ビデオプロジェクターVPH-100QJを床置で使っている猛者がいた。当時の3管vs液晶の映像性能差を考えればそのほうが正解だった。私は床面直上から映像を投射するという考えに至らなかった。6畳間にプロジェクターがど真ん中に居座れば、当然正面に座ることができない。それでも、今考えれば90年代当時はブラウン管式3管型を選択するのが正解だった。木工工作するか床下の高い別途を購入して、プロジェクターの上の高い位置に自分が座るという逆転的発想もあり得た。
その次は20帖の仕事場で映像を見ていた。輝度優先で安いCanonのデータプロジェクターを3台乗り継いだ。当時4:3の映像ソースがまだまだ多かった時代である。16:9のプロジェクターでは横が余ってしまう。そういう事もあって、4:3画面サイズの廉価な中古データプロジェクターで妥協した。
やがて念願のホームシアター専用スペースを入手したので、さすがに専用の映像プロジェクター購入を考えた。AE86中山さんの家でパナソニックの液晶プロジェクターを見た。既に性能は3管PJ程度か、それ以上に進化していた。
いろいろ調べるとソニーのVPL-HW15が手頃だったので、導入した。見てぶったまげたデータプロジェクターと比較して、ダイナミックコントラスト値が圧倒的に違う。黒が真っ黒になる。当たり前のことなのだが、データプロジェクターは輝度優先なので、ダイナミックコントラストを犠牲にしている。
その次はVPL-HW50に乗り換えた。Sonyはある意味正直者で型番の数値が性能進化をそのまま反映している。15→50ということで、輝度が上がり、電源ONから映像投射までの時間が大幅に短縮された。VPL-HW50は「データベース型超解像処理LSI(リアリティークリエーション)」を搭載した。平たく言えうと映像がシャッキっとする。オブジェクトを認識して輪郭などを強調する。VPL-HW15よりも人工的な絵作りだが、見やすい方が良いので、リアリティークリエーションはONにして見ていた。
しばらくして、VPL-HW60が登場した。 VPL-HW15もVPL-HW50もヤフオクで比較的廉価に入手した。VPL-HW60は定価が上昇している。実売価格が落ち着くのに半年ぐらいかかる。実際、実売価格は下がったのだが、それでも結構な値段だった。ヤフオクで出物を狙ったが、全く出てこない。どうやら、ビデオプロジェクター自体があまり売れないという情報がちらほら出ていた。欲しい人は買ってしまったし、横解像度2Kプロジェクター自体には劇的な性能向上は起きていないということもあって市場は縮小気味のようだ。ということで、AVAC本店と交渉して新品で購入した。
VPL-HW60はリアリティークリエーションの強化と、モーションエンハンサーとフィルムプロジェクションの2つの機能を持つ「モーションフロー」の実装である。 リアリティークリエーションは強くすると輪郭にジャギーが出るので「最弱」にしている。
アニメの場合はおおよそリミテッドアニメなので、1秒の動画枚数が少ない。動画枚数が少なくても少しぎこちない程度で動画として破綻しない。「モーションフロー」はフレーム補間を行い、人工的にフレームレートを引き上げる。するとヌルヌルした動画になる。モーションフローには欠点があって、字幕が出ると、字の輪郭にリンギング(ノイズ)がでる。「強」ではリンギングも強くでるので、モーションフローは「弱」の設定にしてある。
○4Kプロジェクターは必要か?
AVAC主催のサンシャインシティ展示会に行き、ブロジェクターコーナーに行くと、5社のプロジェクターが並んで投影されていたが、殆どの人がソニーのところに居た。これはまたメーカーにとっては可哀想な状態だが、ユーザーは正直である。厳密に性能を比較して、値段なども考慮すると、ひょっとしたら、ソニーに拮抗する機種もあったのかもしれない。当時は2K時代で競合各社が性能を競い合っていたが、3管時代に培ったソニー神話もあって、ソニー人気は他社を圧倒していた。
その内、プロジェクターも4K時代になりソニーvsJVCとなった。ソニーとて万能ではなく、4Kプロジェクターの出始めの頃は不具合があったようである。しかし、もう一方の、JVCの不良品率をメーカーの人から直接聞いてぶったまげた。
画素で言うと、32mmフィルムで1000万画素。2Kで200万画素、4Kで800万画素、8Kで3200万画素となる。8Kは明らかにオーバースペックである。フィルムの画素から考えると4Kの存在意義があるように思える。展示会で実際のネイティブ4KをMKVファイルにエンコードして、それをパソコンから再生し、150インチ超えのサイズで見たが、背景の抜けが凄い。本当に存在感がある。もう一方で、Master in 4Kという4Kでマスターを作り、2KにダウンエンコードしてBlu-rayに収め、これをリアリティクリエーション技術を使って4Kに戻す。解像感はリアル4Kに僅かに劣るが、色乗りが凄まじい。過剰に色乗りが出る設定にしてはあるのだろうが、高輝度・ハイコントラストであることも相まってこってりした色合いで迫ってくる。
とまぁ、4Kプロジェクターは凄いのだが、値段も凄い。4Kプロジェクターの新型はなんと「値上げ」となった。2Kに比べて消費電力も増える。筐体も大きく重く動作音も大きい。
2Kプロジェクターが4Kの4分の1の性能しかないのかと言えばそうでもない。私は150インチ級で2Kプロジェクターを使っているが、解像度で不満を感じたことはない。水平解像度480p→720p→1080p(2K)では情報量に明瞭に差がでるが、2K→4Kで画素4倍、水平解像度2倍の数値ほどに差がでるのかといえばそうでもない。2Kで既に十分な解像度を持っているからである。仮に300インチなどの巨大投影面積となれば4Kの威力がいかんなく発揮されるのかもしれないが、投影距離や壁面の縦寸法制限で、これ以上の画面サイズ拡大は不可能である。
そして、最大の問題は4Kの映像素材が提供されていない点だ。Youtubeには4K解像度の映像がアップロードされているが、特段見たいと思うものもない。私にとっての主力コンテンツはアニメである。地デジがそもそもフルHDに対応していない。アニメによっては720pで製作されているものすらある。であるから、プロジェクターだけ4Kにしてもその利点を最大限活かせない。
ハードSF作品として名画の誉高い「ブレードランナー」にデッカードと日本食老店主と以下のやりとりがある。
ちなみに、ブレードランナーにはAndroidのNexus6が出てくる。Goggleはブレードランナーから商標を引用している。
「なんにしましょう」
「四つくれ」("Give me four")
「二つで充分ですよ」
「いや四つだ。二と二で四つだ」("No four. Two,two,four.")
「二つで充分ですよ!」
ここで店主の説得にあきらめた表情になる。
「うどんもくれ」("And noodle")
「分かって下さいよ」
これを引き合いに出せば「2Kで十分ですよ。分かって下さいよ。」という事になる。
参考
プロジェクターには3管式と液晶式があります。ここでは両者の違いを解説しましょう。
http://kanaimaru.com/av/sankan.htm
 | 長岡鉄男のオリジナルスピーカー設計術 基礎編 SpecialEdition 1 |
| 長岡鉄男 | |
| 音楽之友社 |













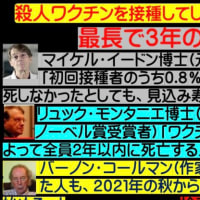
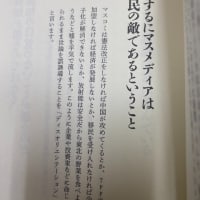

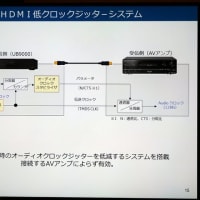
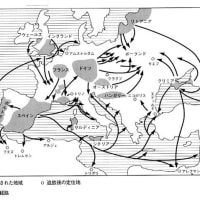

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます