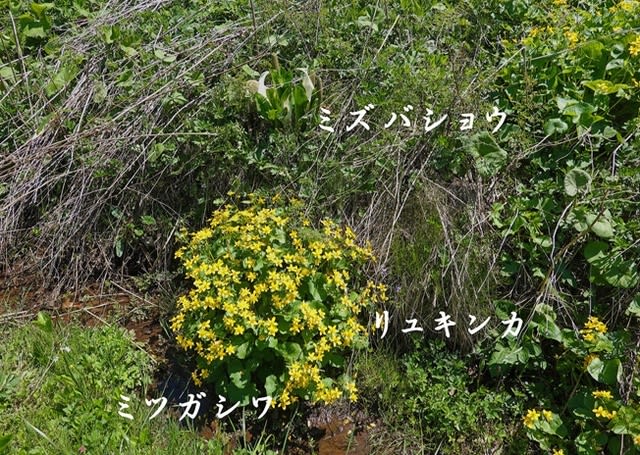葉が小さいという特徴からノミノフスマ(蚤の衾)とノミノツヅリ(蚤の綴り)という紛らわし和名
の付けられたナデシコ科の植物、名称だけからはしばしば混同され易のですが、生育する場所も外観も
異なるため区別するのは容易です。その違いを書いてみます。
ノミノフスマ
通常、湿った水田とか畑、荒れ地などに見られます。
茎はまばらに分枝する。 葉は対生、無柄、長楕円形で先端が尖る。まばらな集散花序を出し、白い
7〜9mmほどの小さな5弁花を開く。花弁は2深裂して10枚に見える。萼片は花弁よりやや短い。雄蕊
は5〜7本、花柱は短く、3裂。




ノミノツヅリ
乾いた場所、ことに街中の歩道の縁などでも見られます。
茎は根元から分枝する。 葉は対生、無柄、広卵形〜狭卵形で先が尖らない。白い4〜6mmの小さな
5弁花は裂けない。雄蕊10本。3本に分かれた長い花柱がある。萼片は花弁より長い。全体に短毛が密
生する(腺毛の生えたものをネバリノミノツヅリとされる)。



花、茎、葉、種を比較する画像
(左:ノミノツヅリ 右:ノミノフスマ)



種