監督 ワン・チュアンアン 出演 リン・フォン、リサ・ルー、シュー・ツァイゲン、モニカ・モー
前半にとてもおもしろいシーンがある。台湾から上海に帰って来た老いた元兵士。その男を歓迎する食卓で、その地区の党の委員が挨拶をする。「家族の再会」というところを「恋人の再会」と言ってしまう。間違えたのだ。「あ、間違えちゃった」という感じで笑ってしまう。出席している人たちも「あ、間違えて言っている」と気が付く。どうするんだろう、という感じでみつめる。委員は、笑いながら、「家族の再会」と言いなおして映画がつづいていく。
アドリブ? それとも脚本どおり? いや、どうも単純なミスだと思うのだけれど、それをそのまま映画に取り込んでしまう。これがなかなかいい。アドリブでも、脚本どおりでも、こんなにうまい具合にはいかない。出演者全員が「あ、間違えている」と気づくような顔はできない。これを、そのまま映画にするんだ、と判断(決意)する一瞬の力--これは、すごいなあ。
このシーンを見るだけのために、この映画があるといってもいい。これは、もし神様がいるとしたら、映画の神様がこの映画のためにくれたシーンである。
なぜなら、どんなときだってひとは間違える。そして間違いを修正して人生はつづいていく。--というのが、この映画のテーマであり、このシーンはテーマそのものを象徴することになるからだ。
もちろん歓迎の挨拶のように、あ、間違えちゃった、言いなおします--というだけではやりなおせないのが人生なのだが、笑ってやりなおすしかないのが人生でもある。そして、それはこの映画そのものでもある。この監督の「人生観(思想)」でもあるように思える。
台湾から帰って来た男は、これまで女と連絡をとらなかったのが間違いだと気づく。いわば、恋人を取り戻しに上海に帰って来たのだ。いま、上海で家族をつくっている女と男は離婚し、元兵士といっしょに女が台湾へ行くことにいったんは同意する。しかし、上海の男が病気に倒れたために、女は男を捨てて台湾へゆくことはできないと思う。いっしょに暮らしてきた時間の重さを感じ、それを大切にしようとする。
「間違い」に気がつき、その「間違い」だと気づいたことが「間違い」だと気づく。そんな具合に、人間のこころは動くのだけれど、人間のこころが動くとき、そこには「間違い」なんて、ない。あるのは、何を大切にしたいかと思うこころだけである。何かを大切にしたいと思うこころに「間違い」などありえない。
「家族」というべきところを「恋人」と言ってしまうのは、それがほんとうは「家族」ではなく「恋人」の再会でもあるからだ。委員は「家族」の再会とは思っていない。名目は「家族」だが、実際は「恋人」の再会であり、「恋人」の帰還なのだ。そして、そこには「恋人」は「恋人」のもとへ帰るべきだというほんとうの願いが込められている。そういう思いがあるから台本の「家族」を「恋人」と「誤読」し、ことばにしてしまうのだ。「家族」というせりふを「恋人」と読み間違えたとき、委員(委員を演じた役者)は自分自身のこころを読み間違えてはいないのである。
こころは読み間違えることができない、自分のこころは「誤読」できない。だから、人生は複雑になる。そして豊かになる。
この映画は、俳優たちが、自分自身のこころの「誤読」を表現する一瞬を待つかのように長回しで撮られている。どのシーンも長い。どのシーンも、先に書いた挨拶の間違いのシーンをのぞけば、間違いはないのだが、長回しのために不思議な余裕がある。上海の風景が自然にスクリーンのなかに入ってくる。他人が入ってくる。他人の暮らしが入ってくる。それがこの映画を、とても自然な感じにしている。
それは最後のシーンと比較すると明確になる。上海の女と男、そして姪は、古い家から高層マンションに引っ越している。豪華な食卓がある。けれど、そこには「他人」(家族)がいない。3人だけである。窓の外には上海が見えるが、それは暮らしではない。
このシーンの前の、元兵士が上海に帰る前に挨拶する「路上の食卓」。そこには他人がいる。家族を越える他人の暮らしがある。他人のなかに吸収され、受け止められることで静かに落ち着いていくこころというものがある。長回しの映像はそういうものをやさしく取り込んでいる。
最後のシーンも、長回しではなのだが、状況が違ってきたために、暮らしではなく「孤独」を取り込んでしまう。
「孤独」と「誤読」は音にすれば一字違いだが、その隔たりはとてつもなく大きい。「孤独」の夢は他人に共有されない。「誤読」の夢は他人のなかでひろがり、笑いとともに生きる。「誤読」の夢は、ひとに、一種の希望を呼び起こしてくれる。
*
あ、映画の感想とは言えないものを書いてしまったかなあ。
「食卓」について、少し書き加えておく。
中国(台湾)の映画は食卓が豊かである。いつでも、とてもおいしそうである。いっしょに食べて生きる、それが人生だとだれもが思っているのだ。それが豊かな色と味になる。自分の箸で料理を取るだけでなく、自分の箸で取ったものをだれかの食器に運んでやるという「お節介」もいいなあ。お節介をしながら、生きていく。その料理を食べたいと思うのは、その料理を箸で運んだものの「誤読」である。お節介は「誤読」から成り立っている。--でも、そのお節介のおかげで、こころというものを知ることができるのだ。
と、いうところから、この映画を語りはじめてみると、また違ったことが言えるかもしれない。
でも、まあ、省略。
(2011年03月27日、福岡・ソラリアシネマ2)
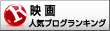
前半にとてもおもしろいシーンがある。台湾から上海に帰って来た老いた元兵士。その男を歓迎する食卓で、その地区の党の委員が挨拶をする。「家族の再会」というところを「恋人の再会」と言ってしまう。間違えたのだ。「あ、間違えちゃった」という感じで笑ってしまう。出席している人たちも「あ、間違えて言っている」と気が付く。どうするんだろう、という感じでみつめる。委員は、笑いながら、「家族の再会」と言いなおして映画がつづいていく。
アドリブ? それとも脚本どおり? いや、どうも単純なミスだと思うのだけれど、それをそのまま映画に取り込んでしまう。これがなかなかいい。アドリブでも、脚本どおりでも、こんなにうまい具合にはいかない。出演者全員が「あ、間違えている」と気づくような顔はできない。これを、そのまま映画にするんだ、と判断(決意)する一瞬の力--これは、すごいなあ。
このシーンを見るだけのために、この映画があるといってもいい。これは、もし神様がいるとしたら、映画の神様がこの映画のためにくれたシーンである。
なぜなら、どんなときだってひとは間違える。そして間違いを修正して人生はつづいていく。--というのが、この映画のテーマであり、このシーンはテーマそのものを象徴することになるからだ。
もちろん歓迎の挨拶のように、あ、間違えちゃった、言いなおします--というだけではやりなおせないのが人生なのだが、笑ってやりなおすしかないのが人生でもある。そして、それはこの映画そのものでもある。この監督の「人生観(思想)」でもあるように思える。
台湾から帰って来た男は、これまで女と連絡をとらなかったのが間違いだと気づく。いわば、恋人を取り戻しに上海に帰って来たのだ。いま、上海で家族をつくっている女と男は離婚し、元兵士といっしょに女が台湾へ行くことにいったんは同意する。しかし、上海の男が病気に倒れたために、女は男を捨てて台湾へゆくことはできないと思う。いっしょに暮らしてきた時間の重さを感じ、それを大切にしようとする。
「間違い」に気がつき、その「間違い」だと気づいたことが「間違い」だと気づく。そんな具合に、人間のこころは動くのだけれど、人間のこころが動くとき、そこには「間違い」なんて、ない。あるのは、何を大切にしたいかと思うこころだけである。何かを大切にしたいと思うこころに「間違い」などありえない。
「家族」というべきところを「恋人」と言ってしまうのは、それがほんとうは「家族」ではなく「恋人」の再会でもあるからだ。委員は「家族」の再会とは思っていない。名目は「家族」だが、実際は「恋人」の再会であり、「恋人」の帰還なのだ。そして、そこには「恋人」は「恋人」のもとへ帰るべきだというほんとうの願いが込められている。そういう思いがあるから台本の「家族」を「恋人」と「誤読」し、ことばにしてしまうのだ。「家族」というせりふを「恋人」と読み間違えたとき、委員(委員を演じた役者)は自分自身のこころを読み間違えてはいないのである。
こころは読み間違えることができない、自分のこころは「誤読」できない。だから、人生は複雑になる。そして豊かになる。
この映画は、俳優たちが、自分自身のこころの「誤読」を表現する一瞬を待つかのように長回しで撮られている。どのシーンも長い。どのシーンも、先に書いた挨拶の間違いのシーンをのぞけば、間違いはないのだが、長回しのために不思議な余裕がある。上海の風景が自然にスクリーンのなかに入ってくる。他人が入ってくる。他人の暮らしが入ってくる。それがこの映画を、とても自然な感じにしている。
それは最後のシーンと比較すると明確になる。上海の女と男、そして姪は、古い家から高層マンションに引っ越している。豪華な食卓がある。けれど、そこには「他人」(家族)がいない。3人だけである。窓の外には上海が見えるが、それは暮らしではない。
このシーンの前の、元兵士が上海に帰る前に挨拶する「路上の食卓」。そこには他人がいる。家族を越える他人の暮らしがある。他人のなかに吸収され、受け止められることで静かに落ち着いていくこころというものがある。長回しの映像はそういうものをやさしく取り込んでいる。
最後のシーンも、長回しではなのだが、状況が違ってきたために、暮らしではなく「孤独」を取り込んでしまう。
「孤独」と「誤読」は音にすれば一字違いだが、その隔たりはとてつもなく大きい。「孤独」の夢は他人に共有されない。「誤読」の夢は他人のなかでひろがり、笑いとともに生きる。「誤読」の夢は、ひとに、一種の希望を呼び起こしてくれる。
*
あ、映画の感想とは言えないものを書いてしまったかなあ。
「食卓」について、少し書き加えておく。
中国(台湾)の映画は食卓が豊かである。いつでも、とてもおいしそうである。いっしょに食べて生きる、それが人生だとだれもが思っているのだ。それが豊かな色と味になる。自分の箸で料理を取るだけでなく、自分の箸で取ったものをだれかの食器に運んでやるという「お節介」もいいなあ。お節介をしながら、生きていく。その料理を食べたいと思うのは、その料理を箸で運んだものの「誤読」である。お節介は「誤読」から成り立っている。--でも、そのお節介のおかげで、こころというものを知ることができるのだ。
と、いうところから、この映画を語りはじめてみると、また違ったことが言えるかもしれない。
でも、まあ、省略。
(2011年03月27日、福岡・ソラリアシネマ2)
 | トゥヤーの結婚 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| マクザム |

























