監督 ジョージ・ノルフィ 出演 マット・デイモン、エミリー・ブラント
フィリップ・K・ディックの小説は一時期興味をもって読んだことがあるが、映画むきとは言えない。「アメリカン民主主義」の「思想」を丸出しにしたSF小説というよりは、観念(理想)小説の趣がある。映画(あるいはテレビ番組)でいうなら「スタートレック」の世界というか……。
この映画では(原作は、私は読んだかどうか覚えていない)、主役が将来の「大統領」。彼ははめも外すが、スラム出身で、理想に燃えている青年である。その青年の前に「調整局」という変な組織があらわれ、「こうしないと(愛をあきらめないと)大統領になれない」と運命をあやつろうとする。それに対して「自由」を求める主人公は、愛を貫きながら自分の手で未来を切り開いていく。そのフロンティアスピリッツ。それにそった展開。
まあ、映画だからいいんだけれど。
--でも、つまらないねえ。ばかばかしいねえ。
フィリップ・K・ディックの小説は、もともと「頭」で読む小説。お馬鹿さんは読んでもわからないよ、アメリカ民主主義の精神を理解し、理想実現には「頭」を働かして、論理を正確に追っていく力が必要だよ、という読者を小馬鹿にしたことろがある。こういうことは「ことば」で書かれる小説では成立するが、映像ではうまくいかないねえ。
この映画で言うと、「調整局」の存在--これが、薄っぺらい。ぜんぜん、怖くない。組織の「わけのわからなさ」もまったく伝わってこない。小説では「調整局」という存在(そこに動いている人間)は「観念」のままでいいのだが、映像は観念ではないからねえ。調整する前に、ことばの「論理」が整いすぎている。映像が入り込む余地がない。「不思議」どころか、ほんのひとかけらの「謎」もない。「わかりすぎる」。その結果として、「わけのわからない」おもしろさが完全に欠落する。
「調整」をことばでなく、「肉体」で表現しないことには、不気味さは出てこないのである。映像の主体は、あくまで目に見える肉体。わけのわからない「論理」の強靱さと複雑さは、ふつうの「肉体」では「論理」の具体化(観念の具体化)にならない。
まあ、「論理」にならないから、「帽子」の小道具(ドラえもんの「どこでもドア」の役割の一部を帽子が担っている)と、ばかばかしい「本」のなかの「設計図(といっても、都市動くときの平面図、というか鳥瞰図)」を使って、超能力と運命を説明することになる。
小説では「帽子」も「設計図」も「文字」をはみだしているから、それはそれで「不思議」な効果を獲得できるが、「映像」にしてしまうと「映像」を超えたものにならない。「映像」にすっぽりとおさまってしまう。「不思議」ではなくなる。ばかばかしい「図」(絵解き)になってしまう。やだねえ。
ことばと映像では「不思議」をあらわす方法が違うのだ。読者・観客の想像力を刺激する方法が違うのである。文字で書かれたものをそのまま映像化しても、映像は不思議でもなんでもない。複雑な「設計図」もあほらしい鳥瞰図にすぎなくなる。「時間」を水平に動かして「運命」なんて言ったって、そんなもの、だれが「運命」と思う? 空間、時間を超えて、動かないとねえ。
さらに。
本物のキスをすれば、「波動」(だったっけ?)が広がり、全体の「運命」がかわる--って、なんだこれは、「中学生向けの恋愛講座」か。
私は3回ほど、舟を漕いでしまった。
恋愛なら恋愛を描くでいいのだけれど、「運命」に関係する男を将来の大統領(下院議員であり、上院議員の候補者)ではなく、ふつうの市民にして、「調整局」のエージェントももっと不気味な冷徹さを具現しなくては、「筋書き」に終わってしまう。映画は「筋書き」ではなく、筋書きを破って動いていく映像でつくるものだということを、この監督は忘れてしまっている。
(2011年05月31日、天神東宝3)
*
2011年05月のベスト3
1「八日目の蝉」
2「トスカーナの贋作」
3「ブラックスワン」
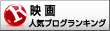
フィリップ・K・ディックの小説は一時期興味をもって読んだことがあるが、映画むきとは言えない。「アメリカン民主主義」の「思想」を丸出しにしたSF小説というよりは、観念(理想)小説の趣がある。映画(あるいはテレビ番組)でいうなら「スタートレック」の世界というか……。
この映画では(原作は、私は読んだかどうか覚えていない)、主役が将来の「大統領」。彼ははめも外すが、スラム出身で、理想に燃えている青年である。その青年の前に「調整局」という変な組織があらわれ、「こうしないと(愛をあきらめないと)大統領になれない」と運命をあやつろうとする。それに対して「自由」を求める主人公は、愛を貫きながら自分の手で未来を切り開いていく。そのフロンティアスピリッツ。それにそった展開。
まあ、映画だからいいんだけれど。
--でも、つまらないねえ。ばかばかしいねえ。
フィリップ・K・ディックの小説は、もともと「頭」で読む小説。お馬鹿さんは読んでもわからないよ、アメリカ民主主義の精神を理解し、理想実現には「頭」を働かして、論理を正確に追っていく力が必要だよ、という読者を小馬鹿にしたことろがある。こういうことは「ことば」で書かれる小説では成立するが、映像ではうまくいかないねえ。
この映画で言うと、「調整局」の存在--これが、薄っぺらい。ぜんぜん、怖くない。組織の「わけのわからなさ」もまったく伝わってこない。小説では「調整局」という存在(そこに動いている人間)は「観念」のままでいいのだが、映像は観念ではないからねえ。調整する前に、ことばの「論理」が整いすぎている。映像が入り込む余地がない。「不思議」どころか、ほんのひとかけらの「謎」もない。「わかりすぎる」。その結果として、「わけのわからない」おもしろさが完全に欠落する。
「調整」をことばでなく、「肉体」で表現しないことには、不気味さは出てこないのである。映像の主体は、あくまで目に見える肉体。わけのわからない「論理」の強靱さと複雑さは、ふつうの「肉体」では「論理」の具体化(観念の具体化)にならない。
まあ、「論理」にならないから、「帽子」の小道具(ドラえもんの「どこでもドア」の役割の一部を帽子が担っている)と、ばかばかしい「本」のなかの「設計図(といっても、都市動くときの平面図、というか鳥瞰図)」を使って、超能力と運命を説明することになる。
小説では「帽子」も「設計図」も「文字」をはみだしているから、それはそれで「不思議」な効果を獲得できるが、「映像」にしてしまうと「映像」を超えたものにならない。「映像」にすっぽりとおさまってしまう。「不思議」ではなくなる。ばかばかしい「図」(絵解き)になってしまう。やだねえ。
ことばと映像では「不思議」をあらわす方法が違うのだ。読者・観客の想像力を刺激する方法が違うのである。文字で書かれたものをそのまま映像化しても、映像は不思議でもなんでもない。複雑な「設計図」もあほらしい鳥瞰図にすぎなくなる。「時間」を水平に動かして「運命」なんて言ったって、そんなもの、だれが「運命」と思う? 空間、時間を超えて、動かないとねえ。
さらに。
本物のキスをすれば、「波動」(だったっけ?)が広がり、全体の「運命」がかわる--って、なんだこれは、「中学生向けの恋愛講座」か。
私は3回ほど、舟を漕いでしまった。
恋愛なら恋愛を描くでいいのだけれど、「運命」に関係する男を将来の大統領(下院議員であり、上院議員の候補者)ではなく、ふつうの市民にして、「調整局」のエージェントももっと不気味な冷徹さを具現しなくては、「筋書き」に終わってしまう。映画は「筋書き」ではなく、筋書きを破って動いていく映像でつくるものだということを、この監督は忘れてしまっている。
(2011年05月31日、天神東宝3)
*
2011年05月のベスト3
1「八日目の蝉」
2「トスカーナの贋作」
3「ブラックスワン」
 | アジャストメント―ディック短篇傑作選 (ハヤカワ文庫 SF テ 1-20) |
| フィリップ K.ディック | |
| 早川書房 |

























