監督 フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク 出演 アンジェリーナ・ジョリー、ジョニー・デップ
大どんでん返しのストーリーである。こういうどんでん返しは小説なら有効かもしれないが、映画では興醒めしてしまう。小説と映画の一番の違いは、そこに「肉体」があるかどうかである。小説では「肉体」は見えない。描写があるにはあるのだが、それは想像力を働かせないと見えて来ない肉体である。ところが映画では、そこに役者の肉体がある。どんな説明も抜きにして、肉体が何事かを語る。語ってしまう。そして、その肉体が語ったことがらをとおして観客はストーリーに接近していく。だから、よっぽど巧妙にストーリーを展開し、役者が肉体で語ってしまうことを防がなければならない。肉体はそこにあるが、その肉体は何も語らない--「役」ではなく、俳優の人生そのものを見せるという具合でないと、どんでん返しは「嘘」になる。
この映画で、そういう問題点を指摘すると……。
最初の方、ジョニー・デップが殺し屋に襲われる。このときのジョニー・デップは単純にツーリストの顔をしている。肉体は何がなんだかわからない状況に追い込まれてあたふたするツーリストを演じている。観客は、そんなふうにしてジョニー・デップを見る。
これは、この段階ではそれでいいのだが、大どんでん返しから振り返ると変だよ。
ジョニー・デップは殺し屋がどんなものかを知っている。どんなふうに逃げなければならないかを知っている。それがホテルのフロントに助けを求める? ホテルから屋根づたいに逃げる? いや、逃げてもいいのだけれど、そのときの表情はツーリストでいいわけ? 変だよねえ。そこでツーリストを演じる必要がどこにある? むしろ、ツーリストの仮面を脱ぎ捨てて必死で逃げる必要がある。必死で逃げてしまうのが「現実」というものだろう。でも、そんなときもジョニー・デップの肉体(顔やからだの動かし方)はツーリストでありつづける。こんなふうに、観客をだましてはいけない。
ジョニー・デップがイタリアの警察につかまり、そこでツーリストを演じるのはいい。そこにはジョニー・デップをみつめる相手がいるからである。ツーリストであると嘘をつき、警察に守ってもらわなければならない理由がある。
でも、ホテルから屋根づたいで逃げるときは、これとはまったく違う。殺し屋に対してツーリストを演じる必要はない。
敵をだます。あるいは味方であるはずのアンジェリーナ・ジョリーをだますというのはわかる。ストーリーとして必要だからである。けれど観客をだましてはいけない。その点をこの映画は踏み外している。「伏線」というものが、ない。「伏線」であるべき部分が観客をだますためだけにつかわれている。こういう映画は嫌いだなあ。
エドワート・ノートン、リチャード・ギアが主演の「真実の行方」という作品がある。この映画も大どんでん返しなのだが、最後の、ほんのちょっとだけ手前で、エドワート・ノートンが絶妙の演技を見せる。それまでエドワート・ノートンは吃っているのだが、一回だけ吃らない。「あ、いま、吃らなかった」と観客にわからせる。それが大どんでん返しにつながっていく。肉体できちんと大どんでん返しの伏線を(あるいは補助線を)描いている。
そういう映像が、「ツーリスト」にはない。いや、最後の方の手錠をピンで外してしまうところに伏線が--と言えるかもしれないけれど、でも、それはアンジェリーナ・ジョリーが教えた方法である。もちろん教えられたことを完璧にこなせるのはそういう素質があるからだ、と強引にいうことはできるが、これではおもしろくない。
あのホテルからの逃走劇のシーンでは、最初は別人の顔(肉体)で逃走し、アンジェリーナ・ジョリーに目撃されているとわかって、そこからもう一度ツーリストに戻る演技をしないといけない。これはジョニー・デップの問題かもしれないが、それ以上に演出、監督の責任だなあ。ホテルからの逃走劇に「ほんとうの顔」と「ツーリスト」をつかいわける演技を要求し、それを映像にするというのは無理。あそこで観客をだましてしまったことが、この映画の大失敗である。
とても「善き人のためのソナタ」の監督の作品とは思えない。
(03月11日、福岡天神東宝)
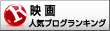
大どんでん返しのストーリーである。こういうどんでん返しは小説なら有効かもしれないが、映画では興醒めしてしまう。小説と映画の一番の違いは、そこに「肉体」があるかどうかである。小説では「肉体」は見えない。描写があるにはあるのだが、それは想像力を働かせないと見えて来ない肉体である。ところが映画では、そこに役者の肉体がある。どんな説明も抜きにして、肉体が何事かを語る。語ってしまう。そして、その肉体が語ったことがらをとおして観客はストーリーに接近していく。だから、よっぽど巧妙にストーリーを展開し、役者が肉体で語ってしまうことを防がなければならない。肉体はそこにあるが、その肉体は何も語らない--「役」ではなく、俳優の人生そのものを見せるという具合でないと、どんでん返しは「嘘」になる。
この映画で、そういう問題点を指摘すると……。
最初の方、ジョニー・デップが殺し屋に襲われる。このときのジョニー・デップは単純にツーリストの顔をしている。肉体は何がなんだかわからない状況に追い込まれてあたふたするツーリストを演じている。観客は、そんなふうにしてジョニー・デップを見る。
これは、この段階ではそれでいいのだが、大どんでん返しから振り返ると変だよ。
ジョニー・デップは殺し屋がどんなものかを知っている。どんなふうに逃げなければならないかを知っている。それがホテルのフロントに助けを求める? ホテルから屋根づたいに逃げる? いや、逃げてもいいのだけれど、そのときの表情はツーリストでいいわけ? 変だよねえ。そこでツーリストを演じる必要がどこにある? むしろ、ツーリストの仮面を脱ぎ捨てて必死で逃げる必要がある。必死で逃げてしまうのが「現実」というものだろう。でも、そんなときもジョニー・デップの肉体(顔やからだの動かし方)はツーリストでありつづける。こんなふうに、観客をだましてはいけない。
ジョニー・デップがイタリアの警察につかまり、そこでツーリストを演じるのはいい。そこにはジョニー・デップをみつめる相手がいるからである。ツーリストであると嘘をつき、警察に守ってもらわなければならない理由がある。
でも、ホテルから屋根づたいで逃げるときは、これとはまったく違う。殺し屋に対してツーリストを演じる必要はない。
敵をだます。あるいは味方であるはずのアンジェリーナ・ジョリーをだますというのはわかる。ストーリーとして必要だからである。けれど観客をだましてはいけない。その点をこの映画は踏み外している。「伏線」というものが、ない。「伏線」であるべき部分が観客をだますためだけにつかわれている。こういう映画は嫌いだなあ。
エドワート・ノートン、リチャード・ギアが主演の「真実の行方」という作品がある。この映画も大どんでん返しなのだが、最後の、ほんのちょっとだけ手前で、エドワート・ノートンが絶妙の演技を見せる。それまでエドワート・ノートンは吃っているのだが、一回だけ吃らない。「あ、いま、吃らなかった」と観客にわからせる。それが大どんでん返しにつながっていく。肉体できちんと大どんでん返しの伏線を(あるいは補助線を)描いている。
そういう映像が、「ツーリスト」にはない。いや、最後の方の手錠をピンで外してしまうところに伏線が--と言えるかもしれないけれど、でも、それはアンジェリーナ・ジョリーが教えた方法である。もちろん教えられたことを完璧にこなせるのはそういう素質があるからだ、と強引にいうことはできるが、これではおもしろくない。
あのホテルからの逃走劇のシーンでは、最初は別人の顔(肉体)で逃走し、アンジェリーナ・ジョリーに目撃されているとわかって、そこからもう一度ツーリストに戻る演技をしないといけない。これはジョニー・デップの問題かもしれないが、それ以上に演出、監督の責任だなあ。ホテルからの逃走劇に「ほんとうの顔」と「ツーリスト」をつかいわける演技を要求し、それを映像にするというのは無理。あそこで観客をだましてしまったことが、この映画の大失敗である。
とても「善き人のためのソナタ」の監督の作品とは思えない。
(03月11日、福岡天神東宝)
 | 善き人のためのソナタ [Blu-ray] |
| クリエーター情報なし | |
| ソニー・ピクチャーズエンタテインメント |

























