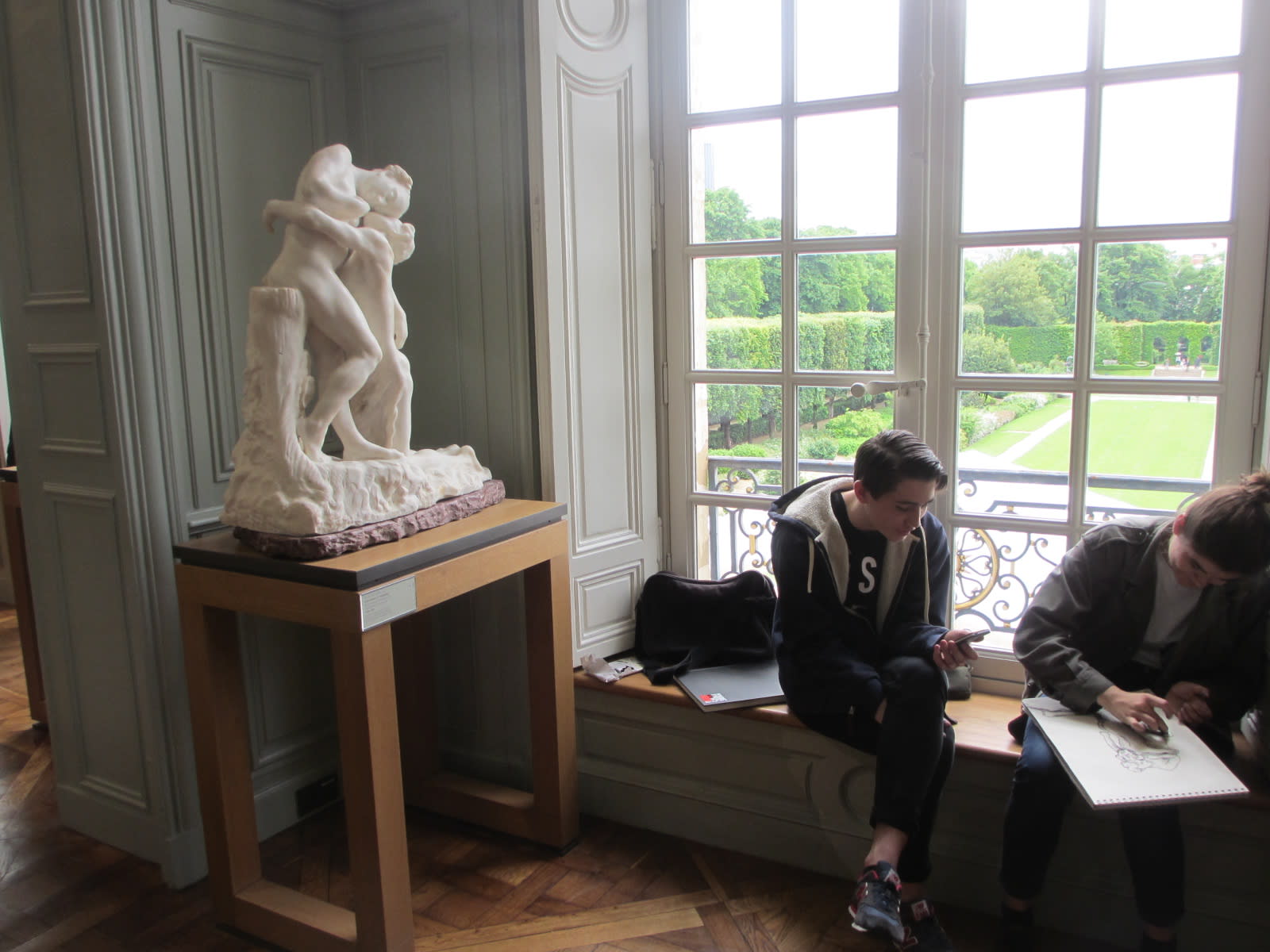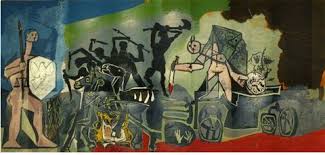中井久夫『中井久夫集1 働く患者』(みすず書房、2017年01月16日発行)
私が中井久夫を初めて読んだのは『カヴァフィス詩集』だった。そのあと、リッツォスの詩を知った。それ以後、エッセイも読むようになったが、『カヴァフィス』以前については何も知らなかった。今度の著作集には、私の知らなかった時代の中井久夫がいる。知らなかった時代の中井久夫なのだけれど、ふと、あっ、知っていると感じるものがある。
私にとって中井久夫は「他人の声」を生きることができる人である。「他人の声」を聞き取り、ただ再現するのではなく、その声を伝えるとき、中井自身がその声の持ち主になる。声の中に動いている「感情」を生きて、声を動かす。
「ことば(意味)」を動かすというのではなく「感情」を動かす。
そのとき、なんといえばいいのか、「感情」を支えるというか、「感情」が動きやすいように、「縁の下の力持ち」のような感じでよりそう。そのよりそい方が自然なので、「感情を生きている」という印象になるのかもしれない。
中井がサリヴァンを翻訳するようになった経緯を書いた文章を読むと、これは私だけの印象ではなく、他の人の印象でもあるかもしれない。翻訳が単に「意味」を伝えるだけではなく、「ことば」そのものを伝える。「ことば」の強さを伝える。「感情」のなかにある「強弱」、あるいは「リズム」というものを中井は呼吸し、一種の「和音」という形で表に出すことができるのかもしれない。「和音」によって音が安定するというと変かもしれないが、「強さ」が生まれる。
「統合失調症者における『焦燥』と『余裕』」という文章の中に「あせり」「ゆとり」さとり」ということばが出てくる。「あせり」は「焦燥」を言い換えたもの。「ゆとり」は「余裕」を言い換えたもの。では、「さとり」は? ここからは、中井のことばをていねいに追いかけるというよりも、私は、中井に誘われて自分で「誤読」をはじめる。
「焦燥」「余裕」ということばだけを読んでいたときは聞こえなかった「音」が「肉体」のなかから「あせり」「ゆとり」ということばになって動き始める。それが「さとり」を揺さぶる。そうか、「さとり」とは「あせり」と「ゆとり」という「区別」を超えるものなのか、と直感する。「さとり」というものを私自身は体験したことがないが、「予感」として「さとり」がわかった気がする。
中井は「統合失調症者」について書いているのだが、限定しなくてもいいと思う。私は、「あせり」も「ゆとり」も誰もが経験することと思って読み、「さとり」も誰もが経験できるものだと、はげまされたような気持ちになる。この「はげまされたような気持ち」というのは「誤読」だね。「誤読」とわかっているが、私は「誤読」のなかにとどまる。
「思春期患者とその治療者」「ある教育の帰結」という文章も刺戟的だった。
高度成長期の教育を「知を知る喜びを追求する教育ではなく、新しいやり方を迅速に身につけるものが勝ちという訓練であった」と批判し、同時に「それは、日本の失業者、とくに青年失業者が非常に少ないことに大きな貢献をしている」と指摘している。この指摘にはびっくりた。1978年、1979年に書かれた文章なのだが、そのまま「現在」を語っている。
青年の失業を、親が雇っているのである。江戸時代は、青年は家の金を持ちだし遊び、刃傷ざたを引き起こした。そうやって親に苦労をかけた。いまは家の金を盗み出しはしないが、同じように親の金を浪費している。子が働き、給料を稼ぐということの代わりに、子供が大学に行き、勉学という「労働」に対して親が金を払っている。そのために「失業者」が少ない。「もし、戦前のように大半が小学校卒で就職したとすれば、不況のときには相当の失業者が発生したであろう。青年の九割が高校へ、過半数が大学へ進むということは、失業保険を払うどころか、家族の負担で膨大な潜在失業者のプールを維持していることになる」と指摘している。「このプールはかなり効果的な弾力性がある。不況のために、今、就職すればあまりよい展望がもてそうになければ、その代わりに一段階上の学校に進学して、次のチャンスに賭けるという選択に傾く。しかもその間は父兄負担である。失業手当の支払いを政府はする必要がない」とも。
(中井が指摘したときから約40年たって、状況は少し変わってきている。「父兄負担」ではまかないきれず、学生は奨学金を借りる。卒業したあとは奨学金の返済に追われる。政府は「奨学金」を手当てする必要もない。これについては、批判が高まり、「完全給付型奨学金」というものをつくろうとしているようだが。)
こういう指摘は、患者治療の「本筋」ではないのだが、そこに私は中井の「耳」を感じる。中井は「複数の声」を広い領域から聞き取り、その「複数の声」で具体的な患者の姿をとらえようとしている。「複数の声」のなかに、患者といっしょに生きている「声」があると予感している。それを探そうとしている。(私は医者ではないので、治療がどういう姿であるべきかといいうことは考えられないので、どうしても脱線し、「誤読」するのかもしれないが……。)
これは「ある教育の帰結」のなかの、ひとつの「結論」として書かれた部分。この「結論の意味」に共感すると同時に、私は「資本」を「もとで」と読ませているところに、はっとする。「あせり」「ゆとり」「さとり」に通じるものを感じる。「頭」で整理したことばではなく、「身振り」に近いもので納得していることばというものがある。繰り返し聞くことでなんとなく「わかっている」感じのことば。その「なんとなく」を踏み外さないことば。
「身振りでわかっていることば」というのは、ちょっと説明がしにくいが、こういうことばは詩にとってはとても強いことばである。「ほんもの」である。頭でつくったものではない、という意味で「ほんもの」。
ここで「飛躍」してしまえば。
中井の詩の翻訳のことばに感じるのは、この「身振りのことば」である。頭で理解し、整理したことばではなく、そこにいる人、その詩を書いた詩人の「身振り」をそのまま言いなおしたようなことば。「身振り」が動くことば。
著作集1のタイトルになっている「働く患者」のなかに、患者は「治療という大仕事」をしている、ということばがあるが、この言い回しが「身振りのことば」そのものである。患者のいのちの内側から動いていることばだ。
文章のいたるところに、他人の声に耳を傾けることで豊かにした中井の「もとで」が感じられる。中井の「もとで」は「生きているひと」そのものの「もとで」、「いのちのもとで」。
これを整理することは難しい。たぶん、整理してしまうと違ったものになる。だから、思いついたまま、書いておく。私は勝手な読者なので、「誤読」を誤読のままにしておく。
私が中井久夫を初めて読んだのは『カヴァフィス詩集』だった。そのあと、リッツォスの詩を知った。それ以後、エッセイも読むようになったが、『カヴァフィス』以前については何も知らなかった。今度の著作集には、私の知らなかった時代の中井久夫がいる。知らなかった時代の中井久夫なのだけれど、ふと、あっ、知っていると感じるものがある。
私にとって中井久夫は「他人の声」を生きることができる人である。「他人の声」を聞き取り、ただ再現するのではなく、その声を伝えるとき、中井自身がその声の持ち主になる。声の中に動いている「感情」を生きて、声を動かす。
「ことば(意味)」を動かすというのではなく「感情」を動かす。
そのとき、なんといえばいいのか、「感情」を支えるというか、「感情」が動きやすいように、「縁の下の力持ち」のような感じでよりそう。そのよりそい方が自然なので、「感情を生きている」という印象になるのかもしれない。
中井がサリヴァンを翻訳するようになった経緯を書いた文章を読むと、これは私だけの印象ではなく、他の人の印象でもあるかもしれない。翻訳が単に「意味」を伝えるだけではなく、「ことば」そのものを伝える。「ことば」の強さを伝える。「感情」のなかにある「強弱」、あるいは「リズム」というものを中井は呼吸し、一種の「和音」という形で表に出すことができるのかもしれない。「和音」によって音が安定するというと変かもしれないが、「強さ」が生まれる。
「統合失調症者における『焦燥』と『余裕』」という文章の中に「あせり」「ゆとり」さとり」ということばが出てくる。「あせり」は「焦燥」を言い換えたもの。「ゆとり」は「余裕」を言い換えたもの。では、「さとり」は? ここからは、中井のことばをていねいに追いかけるというよりも、私は、中井に誘われて自分で「誤読」をはじめる。
「焦燥」「余裕」ということばだけを読んでいたときは聞こえなかった「音」が「肉体」のなかから「あせり」「ゆとり」ということばになって動き始める。それが「さとり」を揺さぶる。そうか、「さとり」とは「あせり」と「ゆとり」という「区別」を超えるものなのか、と直感する。「さとり」というものを私自身は体験したことがないが、「予感」として「さとり」がわかった気がする。
中井は「統合失調症者」について書いているのだが、限定しなくてもいいと思う。私は、「あせり」も「ゆとり」も誰もが経験することと思って読み、「さとり」も誰もが経験できるものだと、はげまされたような気持ちになる。この「はげまされたような気持ち」というのは「誤読」だね。「誤読」とわかっているが、私は「誤読」のなかにとどまる。
「思春期患者とその治療者」「ある教育の帰結」という文章も刺戟的だった。
高度成長期の教育を「知を知る喜びを追求する教育ではなく、新しいやり方を迅速に身につけるものが勝ちという訓練であった」と批判し、同時に「それは、日本の失業者、とくに青年失業者が非常に少ないことに大きな貢献をしている」と指摘している。この指摘にはびっくりた。1978年、1979年に書かれた文章なのだが、そのまま「現在」を語っている。
青年の失業を、親が雇っているのである。江戸時代は、青年は家の金を持ちだし遊び、刃傷ざたを引き起こした。そうやって親に苦労をかけた。いまは家の金を盗み出しはしないが、同じように親の金を浪費している。子が働き、給料を稼ぐということの代わりに、子供が大学に行き、勉学という「労働」に対して親が金を払っている。そのために「失業者」が少ない。「もし、戦前のように大半が小学校卒で就職したとすれば、不況のときには相当の失業者が発生したであろう。青年の九割が高校へ、過半数が大学へ進むということは、失業保険を払うどころか、家族の負担で膨大な潜在失業者のプールを維持していることになる」と指摘している。「このプールはかなり効果的な弾力性がある。不況のために、今、就職すればあまりよい展望がもてそうになければ、その代わりに一段階上の学校に進学して、次のチャンスに賭けるという選択に傾く。しかもその間は父兄負担である。失業手当の支払いを政府はする必要がない」とも。
(中井が指摘したときから約40年たって、状況は少し変わってきている。「父兄負担」ではまかないきれず、学生は奨学金を借りる。卒業したあとは奨学金の返済に追われる。政府は「奨学金」を手当てする必要もない。これについては、批判が高まり、「完全給付型奨学金」というものをつくろうとしているようだが。)
こういう指摘は、患者治療の「本筋」ではないのだが、そこに私は中井の「耳」を感じる。中井は「複数の声」を広い領域から聞き取り、その「複数の声」で具体的な患者の姿をとらえようとしている。「複数の声」のなかに、患者といっしょに生きている「声」があると予感している。それを探そうとしている。(私は医者ではないので、治療がどういう姿であるべきかといいうことは考えられないので、どうしても脱線し、「誤読」するのかもしれないが……。)
発達期は、現在の課題に対応しながら別の成長のための分をとっておかねばならない時期である。その分までも食い込むとは、それは成人になる資本(もとで)をつぶしていることになる。
これは「ある教育の帰結」のなかの、ひとつの「結論」として書かれた部分。この「結論の意味」に共感すると同時に、私は「資本」を「もとで」と読ませているところに、はっとする。「あせり」「ゆとり」「さとり」に通じるものを感じる。「頭」で整理したことばではなく、「身振り」に近いもので納得していることばというものがある。繰り返し聞くことでなんとなく「わかっている」感じのことば。その「なんとなく」を踏み外さないことば。
「身振りでわかっていることば」というのは、ちょっと説明がしにくいが、こういうことばは詩にとってはとても強いことばである。「ほんもの」である。頭でつくったものではない、という意味で「ほんもの」。
ここで「飛躍」してしまえば。
中井の詩の翻訳のことばに感じるのは、この「身振りのことば」である。頭で理解し、整理したことばではなく、そこにいる人、その詩を書いた詩人の「身振り」をそのまま言いなおしたようなことば。「身振り」が動くことば。
著作集1のタイトルになっている「働く患者」のなかに、患者は「治療という大仕事」をしている、ということばがあるが、この言い回しが「身振りのことば」そのものである。患者のいのちの内側から動いていることばだ。
文章のいたるところに、他人の声に耳を傾けることで豊かにした中井の「もとで」が感じられる。中井の「もとで」は「生きているひと」そのものの「もとで」、「いのちのもとで」。
これを整理することは難しい。たぶん、整理してしまうと違ったものになる。だから、思いついたまま、書いておく。私は勝手な読者なので、「誤読」を誤読のままにしておく。
 | 中井久夫集 1 働く患者――1964-1983(全11巻・第1回) |
| 中井 久夫 | |
| みすず書房 |