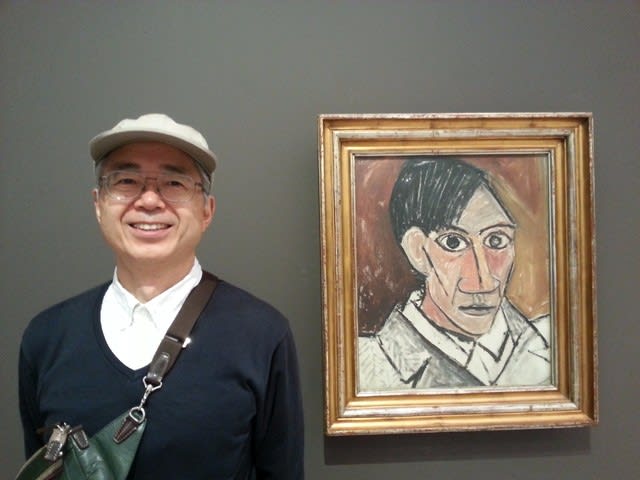沼田真佑「影裏」(「文藝春秋」2017年09月号)
沼田真佑「影裏」は第百五十七回芥川賞受賞作。書き出しは、最近の芥川賞の受賞作とは印象がまるっきり違う。文章が美しい。(引用ページは「文芸春秋」)
勢いよく夏草の茂る川沿いの小道。一歩踏み出すごとに尖った葉先がはね返してくる。かなり離れたところからでも、はっきりそれとわかるくらいに太く、明快な円網をむすんだ蜘蛛の巣が丈高い草花のあいだに燦めいている。( 398ページ)
美しいを通り越して華麗。自然の描写なのだが、どこか人工的な感じがする。ことば数が多い。自然に触発されてことばが動いたというよりも、ことばの力で自然をつくりだしていく、という感じ。
蜘蛛の巣の描写の「はっきり」を「わかる」という動詞で言いなおした後、さらに「太く」「明快な」と言い直している。それらの「修飾語」は、「はっきりしたものになる」「太くなる」「明快になる」という具合に「なる」という動きをともなって「わかる」を支える。「わかる」は、他のことばに支えられながら、「燦めいている」にかわっていく。「燦めいている」は蜘蛛の巣の描写なのだが、蜘蛛の巣を認識する主人公の感覚(認識力)そのものが「燦めいている」ように感じられる。「強さ」を含んでいる。これが、実に美しい。
「かなり離れた」が「細部」の「はっきり」を強調している。さらに、その前の「踏み出す」とか「尖った」とか「はね返す」ということばが「強さ」を前もって引き出しているので、まるで夏の野原に肉体がひきだされたような感じになる。
とても美しいが、うるさい感じもする。初期のカポーティのような文章である。
この書き出しは、こうつづいていく。
しばらく行くとその道がひらけた。行く手の藪の暗がりに、水楢の灰色がかった樹肌がみえる。( 398ページ)
私は、ここで少し違和感を覚えた。文体が書き出しとは違っている。「小道」が「広い道(道がひらかれた)」にかわり、変わった瞬間に「暗がり」という閉塞感のあるものが対比される。歩いている「小道」の描写が「開かれた」感じのするものなのだから、わざわざ「道」を「ひらか」なくてもいような気がするのである。
つまり、
しばらく行くと、藪の暗がりに、水楢の灰色がかった樹肌がみえる。
でも十分な気がする。「その道がひらけた。行く手の」が、どうも「説明」的すぎる。そして、「説明」の仕方が書き出しと大きく異なっている。「はっきり」「太く」「明快な」、「わかる」「燦めいている」というような、感覚をこじあけるような動きがない。「しばらく」ということばが、それまでのことばに比べて「間が抜けている」。文章の「勢い」「緊張感」がまるっきり違ってしまう。
さらに、こうつづく。
もっとも水楢といっても、この川筋の右岸一帯にひろがる雑木林から、土手道に対し斜めに倒れ込んでいる倒木である。それが悪いことにはなかなか立派な大木なのだ。( 398- 399ページ)
「もっとも」からつづく「説明」がまた輪をかけて間が抜けている。「倒れ込んでいる倒木である」は「いにしえの昔、武士のさむらいが、馬から落ちて落馬して」の類である。「悪いことには」と書かれても、どうして「悪いこと」なのかわからない。
「悪いことには」は、次の文章で、こう説明される。
ここから先は、この幹をまたいで乗り越えなければ目的の場所までたどり着けない。
「悪いこと」は水楢に属するものではない。主人公にとって「不都合」ということである。ここにも「またいで乗り越える」という「馬から落ちて落馬して」が出てくる。ことばに酔っているのかもしれない。
このあと、ようやく主人公が登場する。
近ごろではわたしは、それこそ暇さえあればここ生田川に釣りをしに出かけることに決めている。( 399ページ)
やはり描写になっていない。「説明」なので、非常にうるさい感じがする。引用は省略するが、「昨日」の説明がこのあとにつづき、非常にまだるっこしい。「昨日」は、そのあとストーリーになって動くというか、主人公の「履歴」を語っているのだが、どうもめんどくさい書き方である。
そういうものを挟んで、
午後五時の時報が流れる時分には、わたしはすでにこの川端の草むらに立ち、餌箱から大ぶりのブドウ虫の繭を選り出し、引き裂いていた。( 399ページ)
対岸の沢胡桃の喬木の梢にコバルトブルーの小鳥がいたり、林の下草からは山楝蛇が、ほんとうに奸知が詰まっていそうに小さくすべっこい頭をもたげて水際を低徊に這い出そうとする姿を目の当たりにした。一種の雰囲気を感じて振り仰いだら、川づたいの往還に、立ち枯れたように直立している電信柱のいただきに、黒々と蹲まる猛禽の視線とわたしの視線がかち合ったりした。( 400ページ)
釣りの描写がある。ここは美しいといえば美しいが、奇妙といえば奇妙である。梢のコバルトブルーの小鳥(上)、山楝蛇(下)と視線を動かした後、「自然」の中で敏感になる感覚が「気配」を察して振り返ると、電信柱(人工)に「猛禽」がいる(上)。視線の動きが忙しい。それはそれでいいけれど、「ブドウ虫」「山楝蛇」と餌や蛇が特定されているのに、小鳥は「コバルトブルー」、猛禽に至っては「猛禽」でしかない。名前がない。「馬から落ちて落馬して」とは逆に、ことばが不足している。こんなに視線(感覚)が鋭敏なら、とうぜん鳥の名前も知っていてよさそうな気がする。
このあと、主人公の友人が登場する。釣りには二人できていることがわかる。その主人公の描写が、すごい。えっ、と思い、私は三回読み直してしまった。
ゆうべの酒がまだ皮膚の下に残っているのか、磨きたての銃身のように首もとが油光りに輝いている。( 400ページ)
「銃身」という比喩がなぜここで突然出てくるのか。獣をつかう猟師ならわからないでもないが、釣りをしているふたりである。その身の回りに「銃」があるのか。そもそも主人公は「銃」を見たことがあるのか。
これは「描写」ではなく、「借り物の」説明である。
沼田のことばは、沼田の「肉体」から生まれてきているのではなく、読んだ「文学」から借りてきたものであると感じた。「油光り」「輝く」も「馬から落ちて落馬して」の類だ。「定型」というか「常套句」の「無意識」。これが、借り物の文章という印象を強くする。
もっとも「銃身」は、次のように言いなおされている。友人が倒れた水楢を「樹木医」のように調べる場面である。
医者というより、仕留めた獲物の鼓動を調べるハンターだった。( 401ページ)
ハンター(猟師)を引き出すための「伏線」として「銃身」がある、ということになるかもしれないが、これはどうみてもおかしいだろう。
釣りのことをていねいに描ける(釣りの世界に没頭している)主人公が「銃身」の比喩を出してくることは不自然すぎる。銃もつかえば釣りもするという、まあ、外国の文学ならありそうな比喩ではあるが。たとえばヘミングウェーとか。
変な比喩は、たとえば、こんなところにもある。
雨の日に遊園地に出かけるような、心もとない気持ちを抱えて、わたしがこの川原に到着したのは六時過ぎだった。( 410ページ)
わかるけれど、「雨の日に遊園地に出かける」ということを、ほんとうにしたことがあるのか。ひとりでしたのか、だれかとしたのか、そのだれかはだれなのか。そういうことが一緒に思い浮かんでこなければ、その比喩は嘘、借り物ということになるだろう。
さらにぎょっとしたのは、主人公が友人の父親を訪問する場面である。
「息子さんが、釜石で被災した可能性があるのはご存じでしょう」こんどは日浅氏ははっきり首を振った。
「もう三か月になろうとしていますよ」
うつむき加減で氏はコーヒーを啜っていた。( 429ページ)
日浅氏を「氏は」と省略する形で受けている。新聞か何かの「文体」のようだ。主人公は、「氏は」ということばをどういう気持ちでつかうのだろうか。これがわからない。友人の父親に対して、まるっきり感情というものがない。友人の消息を心配しているのに、父親に対してはまるで第三者。会話こそ心配口調であるけれど、「地の部分」には「心配」が滲んでいない。
これはいったい何なのだろう。
どういう気持ちになったら、こういう文章が書けるのだろう。
選考会では「文章のうまさ」が評価されたらしいが、うまければいいというものでもないだろう。それにほんとうにそんなにうまいのか。一見、うまそうに書いてあるだけのように思える。
「うまさ」よりも「ほんとう」かどうかが重要だろうと思う。釣りのシーンで「銃身」が出てきた段階で、私は「ほんとう」が書かれていないと思った。「氏は」という部分で、とても嫌な気持ちになった。