監督 ジョージ・ロイ・ヒル 出演 ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、キャサリン・ロス
好きなシーンがいくつもあるが、いちばん好きなのはやっぱり自転車に乗るシーン。ポール・ニューマンがキャサリン・ロスをハンドルに座らせて自転車をこぐ。バート・バカラックの曲が流れる。西部劇からはるか遠く離れて、「いま」が突然あふれてくる。それを真っ正面からとらえるのではなく、木立や小屋(?)の板壁越しに撮る。隙間から、二人の楽しい様子が見え隠れする。それが光のようにまぶしく、美しい。
映画は違うけれど、やはりキャサリン・ロスが出演した「卒業」でも、キリサリン・ロスとダスティン・ホフマンが大学を歩くとき、回廊の柱越しに二人が撮られている。柱の影が二人を邪魔する。その邪魔なものかげの向こう側に、二人がとぎれとぎれにあらわれる。
この夾雑物を自然に取り入れながら、画面に奥行きと自然な感じを広げるという手法は、アメリカン・ニューシネマによって完全に「市民権」を得るようになったものだけれど、そのなかでも、「明日に向かって撃て!」の自転車のシーンがいい。
ストーリーと無関係--というと言い過ぎだけれど、ストーリーを突き破って、ただ、そこに映像の輝きがある。音楽の美しさがある。まねしたくなるよねえ。「西部劇」であることを忘れて、「いま」としてまねしたくなる。だれかを自転車に乗せて、光あふれる自然のなかを走ってみたくなる。恋をしてみたくなる。いや、恋、というより、青春かなあ。
白い綿の塊みたいなものがふわふわ飛んでくるなかを、二人が歩くシーンもいいなあ。このシーンなんかも、自然の美しさと、その自然のなかで触れ合うこころ、青春の一瞬の思い出を撮りたくて撮っているだけのシーンだねえ。「あのとき、綿のようなふわふわした花が飛んできて、きみは話をしながら、その花を手でつかまえていた」と思い出す。なんの話をしたかは忘れても、そのふわふわと飛ぶ白い花をつかまえるきみの手、その目の動きを覚えている……なんて、青春としかいいようがない。
ボリビアでポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが追いかけられるとき、というか、二人をボリビアの警察(?)が追いかけるときの、しゃれた音楽もいいなあ。西部劇とは無縁の音楽だね。ここにも、「現実」というより「夢」が輝いている。
そういういくつもの「青春の輝き」があるから、キャサリン・ロスが「ホームに帰る」というときのさびしい目、そしてクライマックスの銃撃戦が胸に迫ってくる。あ、「青春」がおわってしまう……。
そして。
また、思う。この映画のなかでポール・ニューマンは何度も「俺たちはもう若くない」という。この「若くない」という自覚も、ひとつの「青春」なんだなあ。アメリカン・ニューシネマが、「もう若くない」という「青春」を映画に持ち込んだのだ。--でも、それは何もかもが「青春」の時代だったなあ。「もう若くない」も「青春」の感慨だった。いま、青春のおわりを自覚する青春はあるんだろうか、とふと思った。この映画がつくられた時代、世界は「青春」だった、と--いま、思う。
(午前十時の映画祭、22本目)
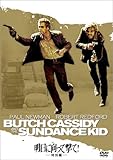 | 明日に向って撃て! (特別編) [DVD]20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパンこのアイテムの詳細を見る |





























