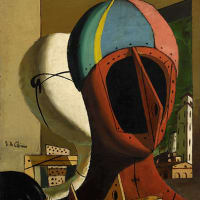※金子武蔵(カネコタケゾウ)『ヘーゲルの精神現象学』ちくま学芸文庫(1996)(Cf. 初刊1973)
Ⅱ本論(三)「理性」1「観察」(その3)(166-168頁)
(35)「観察」とは、「『記述』が『標識の指示』を通じて『法則』を得る」ことだ!
★ヘーゲルにおいては「自然の観察」((C)(AA)「理性」:Ⅴ「理性の確信と真理」A「観察的理性」)といっても、「有機体」の観察が偏重されている。しかし「無機物」の観察を全然、考えていないわけではない。(166頁)
★さて一般に「観察的理性」における「観察」とは、「『記述』が『標識の指示』を通じて『法則』を得る」ことだ。(166頁)
《参考》ヘーゲル『精神現象学』(C)(AA)「理性」A「観察的理性」あるいは1「観察」(金子武蔵)にかんして全体の見透しを確認する。「観察的理性」における「観察」とは、全般的に言えば「記述」に出発して「標識」を見いだすことを通じて「法則」を定立することだ。発見せらるべき「法則」には「自然」の法則、「精神」の法則、「自然と精神の関係」の法則の3つがある。(160-161頁)
(35)-2 「観察的理性」における「観察」①「記述」:「個別的なもの」には必ず「普遍的なもの」が絡まっている!
★「記述」は、「理性」が「対象意識」の態度をとるにあたり最初に行うもので、「感覚」の段階にあたる。(166-167頁)
☆「感覚」は「個別的なもの」をつかんだつもりでいるが、「純粋な個別的なもの」はない。「個別的なもの」には必ず「普遍的なもの」が絡まっている。(167頁)
☆「観察的理性」における「観察」①「記述」においても、事情は同様だ。(167頁)
《参考》(A)「意識」(「対象意識」)の段階におけるⅠ「感覚」・Ⅱ「知覚」・Ⅲ「悟性」は、「個別性」・「特殊性」・「普遍性」という論理の基本形式にあてはまる!(91頁)
☆Ⅰ「感覚」は「個別的なもの」をつかむ。「感覚」の段階は、「このもの」の「私念」にあたる。「感覚」は論理的には「個別性」の段階だ。(91頁)
☆Ⅱ「知覚」は論理的には「特殊性」の段階だ。すなわち「感覚」は「個別的なもの」をつかんでいると考えても、それは自分で「個別的なもの」をつかんだと考えているだけであって、じつは単なる「個別的なもの」をつかんでいるのではなく、「普遍的なもの」における「個別的なもの」をつかんでいる。「普遍」が「個別」になり、「個別」が「普遍」になるというように、それらが矛盾的に結合している段階、これが「個別性」と「普遍性」の中間としての「特殊性」の段階だ。その「特殊性」の段階に当たるものがⅡ「知覚」の段階だ。(91-92頁)
☆Ⅲ「悟性」の段階:「個別性」と「普遍性」との矛盾がいわゆる止揚された契機として綜合されるようになったとき、そのときに「真の意味の普遍」、「無制約的な普遍」が現れてくる。その「無制約的普遍」が「悟性」の段階における「内なるもの」だ。(92頁)
☆以上、(A)「意識」(「対象意識」)におけるⅠ「感覚」・Ⅱ「知覚」・Ⅲ「悟性」の3つの段階は、「個別性」・「特殊性」・「普遍性」という論理の3つの形式をふんでゆく。(92頁)
(35)-3 「観察的理性」における「観察」②「標識の指示」:「あるものを他のものから区別する」にあたり「目じるし」となる「本質的なもの」を指示すること!
★「感覚」は「個別的なもの」をつかんだつもりでいるが、「純粋な個別的なもの」はない。「個別的なもの」には必ず「普遍的なもの」が絡まっている。「観察的理性」における「観察」①「記述」においても、事情は同様だ。(167頁)(前述)
★そこで、「観察的理性」における「観察」は、②あるものを他のものから区別するにあたり「目じるし」となる「標識の指示」を求めるという段階に移る。これは「理性」が「対象意識」の態度をとるにあたっての「知覚」の段階に相当する。(167頁)
☆「標識の指示」とは、「非本質的なもの」に対する「本質的なもの」、つまり「あるものを他のものから区別する」にあたり「目じるし」となるものを、「指示」することだ。(167頁)
(35)-4 「観察的理性」における「観察」③「法則」:「連続と非連続の弁証法」から脱け出すために「観察的理性」は「対立を統合したもの」、すなわち「法則」をつかもうとする!
★さて「本質的なもの」とは、「それぞれのもの」を「それぞれのもの」として、「他のもの」から「分離」する規定だ。ここ(「観察的理性」における「観察」)にも、(A)「意識」(「対象意識」)の段階におけるⅡ「知覚」の場合の「連続と非連続の弁証法」が起きてくる。(167頁)
☆「あるものの特色」(「本質」)とは、「そのもの」を「他のもの」から区別し「分離」するゆえんのものだ。(167頁)
☆しかしこの「分離」(※「そのもの」と「他のもの」との「分離」)も同時に「結合」(※「そのもの」と「他のもの」との「結合」)だ。例えば、「赤」(「本質」)といっても、もし「すべてのものが赤であれば、赤というものもなくなってしまう」ので、「赤でないもの」との関係においてこそ、「赤」(「本質」)は存在しうる。(167頁)
☆かくて「自」と「他」との「非連続」のほかに、「連続」も考慮することが必要だ。かくて「観察的理性」((C)(AA)「理性」:Ⅴ「理性の確信と真理」A「観察的理性」)の「観察」は「連続と非連続」、「自と他」というような「対立」したものの「弁証法」に巻き込まれてしまう。(167頁)
★「観察的理性」は、これ(「連続と非連続」、「自と他」というような「対立」したものの「弁証法」)から脱け出ようとして「対立を統合したもの」、すなわち「法則」をつかもうとする。(167頁)
☆ここに「理性」は、(A)「意識」(「対象意識」)の段階におけるⅢ「悟性」に相応する段階に到達した。けだし「法則」は「悟性」によって定立されるものだからだ。(167頁)
(35)-4-2 「法則」は「観察的理性」の「対象的」把握によって「対象」化され、「概念」の諸「契機」は、生命を失い固定され、したがってそれら「固定された契機」の「数量的関係」のみが問題になる!
★「法則」は「対立するものの統合」として本来的には「概念」だが、しかし「概念」自身ではなく、「観察的理性」の「対象的」把握によって「対象」化されたものだ。(167-168頁)
☆「対象」化されるから「概念」の諸「契機」は、生命を失い固定される。(168頁)
☆そこで「法則」においては、「固定された契機」の「綜合」、したがってそれら「固定された契機」の「数量的関係」のみが問題になる。(168頁)
《参考》「自己としての内なるもの」(「主体的なるものとしての内なるもの」「実体はじつは主体である」という場合の「主体」)、すなわちこの「自己」・「主体」は、ヘーゲルでは「概念」とも言われる。(111頁)
☆この「主体」としての「概念」に、「対象」の側において対応するものが「法則」だ!(111頁)
☆ヘーゲルは「法則」とは「互いに対立した二つの契機をつねにふくむ」と考える。(Ex. 「引力と斥力」、「陰電気と陽電気」、「空間と時間」など。)即ち「法則」の内容は「弁証法的に対立したもの」とヘーゲルは考える。(111頁)
☆さて「弁証法」とは「対立したもの」が「区別され分離されている」と同時に、「相互に転換し統一をかたちづくる」ことだ。「弁証法」的に考えると「対立」は「静的」なものでなく「動的」なものだ。(111頁)
☆ところが「法則」では、そういう「動的」な点がはっきりしていない。そもそも「法則」は「主体」としての「概念」(「動的」な「内なるもの」)を、「存在的なもの」・「対象的なもの」・「静的なもの」として定立することによって成り立つものだからだ。「法則」の立場は「対象的存在的」だ。(111頁)
☆かくて「法則」では「互いに外的のもの・没交渉のもの」が関係づけられる。この関係づけは「量」の見地からからのみなすことができる。(111頁)
★「観察」とは、「記述」が「標識の指示」(本質的なもの)を通じて「法則」を得ることだが、①「記述」の段階では、たとえば、陽電気はガラス電気、陰電気は樹脂電気というようにイメージを描いて「表象」されるが、②「標識の指示」(本質的なもの)をへて、③「法則」が定立されるようになると、かかる「表象」から純化されて、「概念」的に思考せらるべき陰電気と陽電気となり、これらの相対立した「契機」の間に「法則」が立てられる。(168頁)
☆また「自由落下の法則」(落下距離=時間の2乗×重力加速度×1/2)では、「時間」と「空間」という相対立した「契機」の間に「法則」的関係が定立せられる。(168頁)
★さてこのさい、「法則」がじつは「概念」であるところからすれば、「陽電気と陰電気」、「空間と時間」など「対立した契機」は相互に他に転換して帰一し、そうして「統一」がまた「対立」に分裂するという「無限性」の生ける精神的運動が行われるべきはずだ。(168頁)
☆だが「観察的理性」なるものは、「理性」が「対象意識」の形式をとったものであるために、それぞれの「項」がそれぞれ「独立のもの」として固定せられてしまい、したがって「内面的な質的な規定」がではなく、ただ「量的な規定」だけが問題になり、かくて「数量的関係」を提示することが「法則」定立の課題となる。(168頁)
☆ヘーゲルは、「近代科学」における「法則」が、諸契機の間の「数量的関係」を規定することをもって課題とするという事実を、以上のように解釈している。(168頁)
《参考1》へーゲルは「無限性」について2通りのもの区別する。すなわち①「無限性であるにとどまる」場合と、②「無限性であることを自覚している」場合だ。即ち①「客観的な即自的な無限性」(普通に「生命」とか「生きもの」とかいわれるもの)と②「対自的自覚的な無限性」(Cf. 「相互承認」)だ。(129-130頁)
《参考2》「生命」の世界はたしかに「無限性」を実現しているが、しかし「ただ無限性である」ことにとどまって、「無限性であることを自覚する」までに至っていない。そこに「生命」の立場の限界がある。(132頁)
《参考2-2》かくて「無限性」は、「対象的」には実現されず、「主体的」にのみ実現される。(132頁)
《参考3》ヘーゲルは問題を「主体」(Cf. 「対象」)の方向に転じて、「『主体』において『無限性』はどうして実現するか」を考える。ヘーゲルは「一つの『主体』と他の『主体』との関係においてのみ、いいかえると一つの『自己意識』と他の『自己意識』との関係においてのみ、『無限性』は真に成りたちうる」ことを証明しようとする。(133頁)
Ⅱ本論(三)「理性」1「観察」(その3)(166-168頁)
(35)「観察」とは、「『記述』が『標識の指示』を通じて『法則』を得る」ことだ!
★ヘーゲルにおいては「自然の観察」((C)(AA)「理性」:Ⅴ「理性の確信と真理」A「観察的理性」)といっても、「有機体」の観察が偏重されている。しかし「無機物」の観察を全然、考えていないわけではない。(166頁)
★さて一般に「観察的理性」における「観察」とは、「『記述』が『標識の指示』を通じて『法則』を得る」ことだ。(166頁)
《参考》ヘーゲル『精神現象学』(C)(AA)「理性」A「観察的理性」あるいは1「観察」(金子武蔵)にかんして全体の見透しを確認する。「観察的理性」における「観察」とは、全般的に言えば「記述」に出発して「標識」を見いだすことを通じて「法則」を定立することだ。発見せらるべき「法則」には「自然」の法則、「精神」の法則、「自然と精神の関係」の法則の3つがある。(160-161頁)
(35)-2 「観察的理性」における「観察」①「記述」:「個別的なもの」には必ず「普遍的なもの」が絡まっている!
★「記述」は、「理性」が「対象意識」の態度をとるにあたり最初に行うもので、「感覚」の段階にあたる。(166-167頁)
☆「感覚」は「個別的なもの」をつかんだつもりでいるが、「純粋な個別的なもの」はない。「個別的なもの」には必ず「普遍的なもの」が絡まっている。(167頁)
☆「観察的理性」における「観察」①「記述」においても、事情は同様だ。(167頁)
《参考》(A)「意識」(「対象意識」)の段階におけるⅠ「感覚」・Ⅱ「知覚」・Ⅲ「悟性」は、「個別性」・「特殊性」・「普遍性」という論理の基本形式にあてはまる!(91頁)
☆Ⅰ「感覚」は「個別的なもの」をつかむ。「感覚」の段階は、「このもの」の「私念」にあたる。「感覚」は論理的には「個別性」の段階だ。(91頁)
☆Ⅱ「知覚」は論理的には「特殊性」の段階だ。すなわち「感覚」は「個別的なもの」をつかんでいると考えても、それは自分で「個別的なもの」をつかんだと考えているだけであって、じつは単なる「個別的なもの」をつかんでいるのではなく、「普遍的なもの」における「個別的なもの」をつかんでいる。「普遍」が「個別」になり、「個別」が「普遍」になるというように、それらが矛盾的に結合している段階、これが「個別性」と「普遍性」の中間としての「特殊性」の段階だ。その「特殊性」の段階に当たるものがⅡ「知覚」の段階だ。(91-92頁)
☆Ⅲ「悟性」の段階:「個別性」と「普遍性」との矛盾がいわゆる止揚された契機として綜合されるようになったとき、そのときに「真の意味の普遍」、「無制約的な普遍」が現れてくる。その「無制約的普遍」が「悟性」の段階における「内なるもの」だ。(92頁)
☆以上、(A)「意識」(「対象意識」)におけるⅠ「感覚」・Ⅱ「知覚」・Ⅲ「悟性」の3つの段階は、「個別性」・「特殊性」・「普遍性」という論理の3つの形式をふんでゆく。(92頁)
(35)-3 「観察的理性」における「観察」②「標識の指示」:「あるものを他のものから区別する」にあたり「目じるし」となる「本質的なもの」を指示すること!
★「感覚」は「個別的なもの」をつかんだつもりでいるが、「純粋な個別的なもの」はない。「個別的なもの」には必ず「普遍的なもの」が絡まっている。「観察的理性」における「観察」①「記述」においても、事情は同様だ。(167頁)(前述)
★そこで、「観察的理性」における「観察」は、②あるものを他のものから区別するにあたり「目じるし」となる「標識の指示」を求めるという段階に移る。これは「理性」が「対象意識」の態度をとるにあたっての「知覚」の段階に相当する。(167頁)
☆「標識の指示」とは、「非本質的なもの」に対する「本質的なもの」、つまり「あるものを他のものから区別する」にあたり「目じるし」となるものを、「指示」することだ。(167頁)
(35)-4 「観察的理性」における「観察」③「法則」:「連続と非連続の弁証法」から脱け出すために「観察的理性」は「対立を統合したもの」、すなわち「法則」をつかもうとする!
★さて「本質的なもの」とは、「それぞれのもの」を「それぞれのもの」として、「他のもの」から「分離」する規定だ。ここ(「観察的理性」における「観察」)にも、(A)「意識」(「対象意識」)の段階におけるⅡ「知覚」の場合の「連続と非連続の弁証法」が起きてくる。(167頁)
☆「あるものの特色」(「本質」)とは、「そのもの」を「他のもの」から区別し「分離」するゆえんのものだ。(167頁)
☆しかしこの「分離」(※「そのもの」と「他のもの」との「分離」)も同時に「結合」(※「そのもの」と「他のもの」との「結合」)だ。例えば、「赤」(「本質」)といっても、もし「すべてのものが赤であれば、赤というものもなくなってしまう」ので、「赤でないもの」との関係においてこそ、「赤」(「本質」)は存在しうる。(167頁)
☆かくて「自」と「他」との「非連続」のほかに、「連続」も考慮することが必要だ。かくて「観察的理性」((C)(AA)「理性」:Ⅴ「理性の確信と真理」A「観察的理性」)の「観察」は「連続と非連続」、「自と他」というような「対立」したものの「弁証法」に巻き込まれてしまう。(167頁)
★「観察的理性」は、これ(「連続と非連続」、「自と他」というような「対立」したものの「弁証法」)から脱け出ようとして「対立を統合したもの」、すなわち「法則」をつかもうとする。(167頁)
☆ここに「理性」は、(A)「意識」(「対象意識」)の段階におけるⅢ「悟性」に相応する段階に到達した。けだし「法則」は「悟性」によって定立されるものだからだ。(167頁)
(35)-4-2 「法則」は「観察的理性」の「対象的」把握によって「対象」化され、「概念」の諸「契機」は、生命を失い固定され、したがってそれら「固定された契機」の「数量的関係」のみが問題になる!
★「法則」は「対立するものの統合」として本来的には「概念」だが、しかし「概念」自身ではなく、「観察的理性」の「対象的」把握によって「対象」化されたものだ。(167-168頁)
☆「対象」化されるから「概念」の諸「契機」は、生命を失い固定される。(168頁)
☆そこで「法則」においては、「固定された契機」の「綜合」、したがってそれら「固定された契機」の「数量的関係」のみが問題になる。(168頁)
《参考》「自己としての内なるもの」(「主体的なるものとしての内なるもの」「実体はじつは主体である」という場合の「主体」)、すなわちこの「自己」・「主体」は、ヘーゲルでは「概念」とも言われる。(111頁)
☆この「主体」としての「概念」に、「対象」の側において対応するものが「法則」だ!(111頁)
☆ヘーゲルは「法則」とは「互いに対立した二つの契機をつねにふくむ」と考える。(Ex. 「引力と斥力」、「陰電気と陽電気」、「空間と時間」など。)即ち「法則」の内容は「弁証法的に対立したもの」とヘーゲルは考える。(111頁)
☆さて「弁証法」とは「対立したもの」が「区別され分離されている」と同時に、「相互に転換し統一をかたちづくる」ことだ。「弁証法」的に考えると「対立」は「静的」なものでなく「動的」なものだ。(111頁)
☆ところが「法則」では、そういう「動的」な点がはっきりしていない。そもそも「法則」は「主体」としての「概念」(「動的」な「内なるもの」)を、「存在的なもの」・「対象的なもの」・「静的なもの」として定立することによって成り立つものだからだ。「法則」の立場は「対象的存在的」だ。(111頁)
☆かくて「法則」では「互いに外的のもの・没交渉のもの」が関係づけられる。この関係づけは「量」の見地からからのみなすことができる。(111頁)
★「観察」とは、「記述」が「標識の指示」(本質的なもの)を通じて「法則」を得ることだが、①「記述」の段階では、たとえば、陽電気はガラス電気、陰電気は樹脂電気というようにイメージを描いて「表象」されるが、②「標識の指示」(本質的なもの)をへて、③「法則」が定立されるようになると、かかる「表象」から純化されて、「概念」的に思考せらるべき陰電気と陽電気となり、これらの相対立した「契機」の間に「法則」が立てられる。(168頁)
☆また「自由落下の法則」(落下距離=時間の2乗×重力加速度×1/2)では、「時間」と「空間」という相対立した「契機」の間に「法則」的関係が定立せられる。(168頁)
★さてこのさい、「法則」がじつは「概念」であるところからすれば、「陽電気と陰電気」、「空間と時間」など「対立した契機」は相互に他に転換して帰一し、そうして「統一」がまた「対立」に分裂するという「無限性」の生ける精神的運動が行われるべきはずだ。(168頁)
☆だが「観察的理性」なるものは、「理性」が「対象意識」の形式をとったものであるために、それぞれの「項」がそれぞれ「独立のもの」として固定せられてしまい、したがって「内面的な質的な規定」がではなく、ただ「量的な規定」だけが問題になり、かくて「数量的関係」を提示することが「法則」定立の課題となる。(168頁)
☆ヘーゲルは、「近代科学」における「法則」が、諸契機の間の「数量的関係」を規定することをもって課題とするという事実を、以上のように解釈している。(168頁)
《参考1》へーゲルは「無限性」について2通りのもの区別する。すなわち①「無限性であるにとどまる」場合と、②「無限性であることを自覚している」場合だ。即ち①「客観的な即自的な無限性」(普通に「生命」とか「生きもの」とかいわれるもの)と②「対自的自覚的な無限性」(Cf. 「相互承認」)だ。(129-130頁)
《参考2》「生命」の世界はたしかに「無限性」を実現しているが、しかし「ただ無限性である」ことにとどまって、「無限性であることを自覚する」までに至っていない。そこに「生命」の立場の限界がある。(132頁)
《参考2-2》かくて「無限性」は、「対象的」には実現されず、「主体的」にのみ実現される。(132頁)
《参考3》ヘーゲルは問題を「主体」(Cf. 「対象」)の方向に転じて、「『主体』において『無限性』はどうして実現するか」を考える。ヘーゲルは「一つの『主体』と他の『主体』との関係においてのみ、いいかえると一つの『自己意識』と他の『自己意識』との関係においてのみ、『無限性』は真に成りたちうる」ことを証明しようとする。(133頁)