
幕末の東北を語るにおいて、外せない人物がいます。
盛岡、南部藩家老、楢山佐渡(ならやまさど)。
佐渡を語るにおいてまず、語るべきは、江戸時代最大の農民一揆といわれる、「三閉伊一揆」でしょう。
********************
南部藩13代藩主、南部利済は、領内が度重なる飢饉等で窮乏しているにも関わらず散財を繰り返し、領民に重税を課し続けます。折しも天保の大飢饉で領民達は飢餓に苦しめられ、それでも遊蕩三昧の藩主。特に重税を課せられていたのは、海産物の盛んだった九戸郡、上閉伊・下閉伊両郡の、いわゆる三閉伊と言われる、北三陸沿岸地域ででした。
この三閉伊の領民たちが、税の減免と藩主・利済の隠居を要求して、弘化4年(1847)に一揆を起こします。
藩はこの要求を一旦は受け入れ、利済は隠居し、家督を長男の利義に譲ります。
しかし、利済はその後も藩政の実権を握り、院政を敷きます。これに不満をもつ藩主・利義と対立。利済は利義をわずか1年で藩主の座から引きずりおろし、三男の利剛を新たに藩主に据えます。
こうして利済は再び藩政を完全にその手に握り、またしても悪政を繰り返したのです。
嘉永6年(1853)、三閉伊にて再び大規模な一揆が発生します。1万6千人、一説には3万5千人と言われる領民たちが、南部藩領を越えて、隣の仙台藩領に越境し、仙台藩に直訴を行ったのです。
直訴の内容は、三閉伊を南部藩領から外し、幕府直轄地か、あるいは仙台藩領に組み入れて欲しい。この願いを、仙台藩を通じて幕府に上申して欲しいという、前代未聞の内容でした。
南部藩は、領民から完全に見切りを付けられてしまったわけですね。なんともはや、情けない限りではあります。
この、農民運動ともいうべき一揆により、利済の悪政は幕府の知る所となり、時の幕府老中、阿部正弘によって南部藩は激しく叱責され、利済は江戸の南部藩邸にて蟄居謹慎を命じられるに至ります。
********************
これが、江戸時代最大の農民一揆「三閉伊一揆」の概要です。
さて、肝心の楢山佐渡はなにをしていたのか?
それは次回、改めて。
つづく、でありやす。












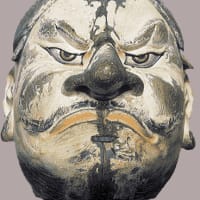







こちらはほとんど揺れませんでした。関東限定のようです。