
今回は、私の生まれ故郷の対馬(つしま)についての話をしようと思う。
もしも対馬がどこにあるのか知らないならば、地図上の九州本土の博多あたりと朝鮮半島の釜山あたりとに交互に視線をくれてやればいい。その中間地点くらいのところにふた粒のへそのゴマのような島が玄界灘に浮かんでいるのがいやでも視野に入るだろう。それが対馬である。
対馬では、河童のことをなぜか「ガッパ」という。同じく対馬生まれの母の実家に、その「ガッパ」にまつわるけっこう生々しいエピソードがあるので紹介したい。
いまから六十年ほど前のことである。母には三人の兄がいた。そのなかの次兄のイタルが、あるとき四十二度の高熱を発した。イタルが十代なかばのころのことだ。父親のマサルじいさまが病院に連れて行って、お医者さまにいろいろと細かく診てもらったのだが、どうにも原因が分からないという。
とりあえず、解熱剤をもらって決められたとおりしばらくの間服用し続けてみたのだけれど、熱がちっとも下がらなかった。マサルじいさまは、仕方なくもう一度病院にイタルを連れて行ったのだが、やはり原因がわからなかった。そうして、別の種類の解熱剤を渡すときに、立派な髯の板垣退助によく似たお医者さまは眉を八の字に寄せながらマサルじいさまにこう告げた。「このまま熱が下がらんようじゃったら、脳に障害が残ることを覚悟してくだされぃ。」
残念なことに、別の種類の解熱剤も効き目がなかった。イタルは一週間続いた高熱でゆで蛸のようになってしまっている。マサルじいさまは、このままイタルがうんうん唸りながら低能児みたいなものになってしまうのを座視しているよりほかにないのかと思って、目の前が真っ暗になる思いを味わったという。イタルは、近所で評判の秀才であったのだ。いわゆる神童である。他の二人の兄たちも、長女だった母も、下の年端のいかないマチヨ、ユタカも心配そうに替わり番こに襖を開けてイタルが寝ている薄暗い寝室をのぞきこむのだった。にわかにアビル家に暗雲が立ち込めはじめたのである。
そのころ母親のおデンちゃん(私の母方の祖母に当たるのだが、みんなが彼女をそう呼んでいたので、それを踏襲する)は、たまたま金毘羅サマをご本尊とする新興宗教団体に入信していた。かねてから信仰心の篤かった人で、折に触れては八百万の神に両の手を合わせるのが習い性になっていた。普段は冷静に物事を処するマサルじいさまのきりきり舞いの様子を見るに見かね、そうしてもちろんお腹を痛めたわが子の窮状をなんとかして救いたいと思って、おデンちゃんは教団に駆け込んだ。そうして、そこの女の拝み屋さんに情況を説明して、神サマにお伺いを立ててもらった。
拝み屋さんが数珠の玉をしわくちゃの、老人特有のシミのある右手の親指の腹でひとつずつたぐりよせながら口のなかでぶつぶつわけの分からぬ呪文を唱えるうちに、その脇に控えていた依り代の、薄化粧をした別嬪さんで一重瞼の十代後半くらいの娘の形相がやおら変わり、目が狐のようにつりあがってきた。そうして、小刻みに体を震わしながら、おデンちゃんを高音のひしゃげたような変な声で唐突にののしった。
「おい、こら。こんちくしょうめ。お前んとこの悪ガキめが、オレの頭の皿に石をぶっつけやがった。オレが気持ちよく泳いどったら、あんちきしょうめ、橋の上から面白がって石を投げたんだ。おらぁ、痛くて悔しくて、悪ガキをうんとこらしめてやってるんだい。へん。お前の親父さんも、オレに失礼なことをしたんだぞ。州藻(すも)の坂んとこで、オレがアイサツしたのを無視して自転車で通りすぎようとしたんで、相撲をとって自転車ごとひっくりかえしてやったんだ。へんだ。」
金毘羅サマのご託宣によれば、ガッパへのイタルの心ない悪戯とマサルじいさまの悪気のない失礼がどうやらイタルの高熱の原因であるという。父親の過失の分だけ、息子はうんと苦しんでいるらしい。
家にすっとんで帰ったおデンちゃんは、まずは、うんうん唸っているイタルに尋ねた。「イタル、お前は、一週間前にガッパの皿に石をぶつけたのかい。」記憶の糸をそろりそろりとたぐり寄せるうちに、思い当たるところがあったらしく、イタルはうるんだ目を少しだけ開けてとぎれとぎれに、そういえば川で泥鰌すくいをした帰り道、川上から、周りを枯れた雑草のようなもので囲まれた丸くて平べったい灰色の変なものが流れてきたのを目にしたので、橋の上からそれに何の気なしに石を投げたらたまたま当った、といった。
今度は、庭で薪割りに精を出しているマサルじいさまのところへ駆けて行き、尋ねた。「お前さまは、一週間くらい前に、隣村の州藻のあたりで自転車ごと転びなさりましたでしょうか。」じいさまは、額の汗をぬぐいながら、州藻から帰ってくるとき下り坂のところで自転車ごと宙返りをするようにして確かに転んだといった。
それを聞くやいなや、おデンちゃんは、教団に折り返しすっとんで行き、拝み屋さんにどうすればイタルの熱が下がるのかお伺いを立てた。彼女から、「離れの便所の近くの柿の木の下に、夜明け前まだ村のみんなが寝静まっているときに、白い皿に稲荷寿司を三個載せたのをお供えしておけ。それを三日間続ければ息子の熱は下がる。ただし、それは誰にも見られてはならぬぞ。」と言われたので、おデンちゃんがその通りのことをしてみたところ、三日目の明け方にイタルはウソのように熱を下げたのだった。正気を取り戻したイタルの第一声は、「母ちゃん、腹減った。」であったという。
母の実家は、対馬のほぼ中央部に位置する雉(け)知(ち)にあったのだが、その周りの州藻や上里などという集落の特定の坂とか池とかに住み着いているガッパには、三太とか笠太郎とか三郎とかいった名前がつけられていて、彼らはちょくちょく人間様に悪戯をしかけたという。上里のだれそれになにか障りが生じたら、村人たちは、あれは三太の仕業やげな、とうわさしあったのである。ちなみに、対馬方言の「げな」は、伝聞の「そうだ」とほとんど同じ意味である。対馬には、「げなげな話は、嘘やげな」ということわざがある。なかなかのユーモアのセンスではなかろうか。
河童の悪戯については、柳田国男の『遠野物語』のなかのいくつかのエピソードが人口に膾炙しているのではあるが、どうやら対馬にも「ガッパ」話は豊富にあるようだ。もちろん全国いたるところにあるのだろう。昔の日本人は、とても素敵な精神空間に生きていたのだとつくづく思う。時間の流れが、いまとはくらべものにならないほどにゆるやかでやわらかいものであったようだ。幼少のころにかすかに触れたそういう時の流れを、私は、数年前に行ったタイのメコン川沿いのゲストハウスで数日間過ごしたときに、本当に久しぶりに思い出した。
母の実家の裏庭の柿の木のことで、ひとつ思い出した話があるので、付け加えておこう。それは、「ガッパ」騒動よりずっと昔のことである。
おデンちゃんには妹が二人いた。そのうち、末の妹の名をミツエという。彼女は、小学校を卒業してから働き詰めで、そうこうするうちに病を得た。それからは、おデンちゃんの嫁ぎ先、つまり母の実家の庭先に作られた粗末な小屋で養生を続けていた。おデンちゃんは、姑の厳しい監視の目を盗んでは、細やかに妹の面倒を見た。自分の食事を削ってでも、妹に食事を与えて、その養生に努めたという。しかし、そのかいもなく、ミツエは十八歳のときに亡くなった。幸薄い生涯であった。おデンちゃんは、妹の早すぎた死をとても切ながった。
ミツエの死から一週間くらい経ったころだった。マサルじいさまが、おデンちゃんにそっと告げた。実は、お前の妹が亡くなったときからずっと、真夜中、裏庭の柿の木の下に、生きていたときの姿のままの悲しそうな風情でうつむきかげんに立っているのだ、毎晩のことだから錯覚でもなんでもない、と。さらに、このことは子供たちに絶対に教えるな、またお前も決して彼女の姿を見てはならぬ、さもないと子供たちやお前によくないことが起こる、なぜかそのことが自分には分かる、という意味のことを言ったのである。マサルじいさまは世間で評判になるくらいに実直な性格の男であったから、大切に思っている妻や子供たちにまつわることで世迷言を垂れ流したとは到底考えられない。責任ある家長としての独特の勘が働いたのだろうと私は考える。それを聞いたおデンちゃんは、暇さえあれば仏壇に座り込み合掌して妹の成仏を祈ったという。
その後の顛末は、残念ながら聞き及んでいない。
ミツエは、この世によっぽど強い思いを残して亡くなったのだろう。私はこの話をいまにいたるまでそのままに受けとめ、ひそやかに信じているのである。それが、いささかなりとも回向になればと思う。










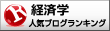

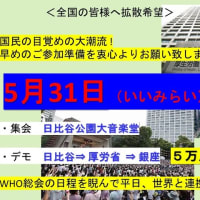














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます