数年前に読売新聞の書評欄で見かけた「合成生物学の衝撃」(須田桃子著 2018年4月 文藝春秋発行)という本のことが気になっていたが、入手することなく時間が過ぎて行って、はやいものでもう4年近くになる。
スクラップしてあったこの書評(評者 塚谷裕一・東大教授)を読み直してみると、次のようであり、最初にこの書評を読んだ時に受けた衝撃が蘇る。
「合成生物学ということばをご存じの方は、まだ日本ではごくわずかだろう。生物学者であっても馴染みのある人は未だ多くない。
しかし日常生活とは縁の遠い学問の話、と悠長に構えている暇は、実はない。
すでにこの世界では、ヒトを、そのDNA配列から、それも一から『合成』し、組み立てようというプロジェクトが始まっているのだ。その当初のもくろみ通り、十年程度で実現するかどうかは、まだ分からない。
しかし微生物レベルであれば、すでに人類は、そのDNA配列の設計から始めて一から合成することに成功している。・・・」

「合成生物学の衝撃」についての書評が掲載された読売新聞(2018.5.20付)
この本のことを思い出したのは、「エントロピー」に関連する本をいくつか読んでいて、ポール・ナース博士の著書「生命とは何か」(竹内 薫訳 2021年ダイヤモンド社発行)に出会った時である。後半の章「世界を変える」の中に「合成生物学」のインパクトについての次の記述がある。
「今後10年で、遺伝子工学的手法を利用する必要性がさらに出てくると私は思う。・・・
遺伝子組み換えと合成生物学により、生命の輝きを再編成し、別の目的に向かわせることができる。・・・再設計された動植物や微生物を作り出して、そこからまったく新しいタイプの薬剤、燃料、生地、建築材料を生産しているわれわれの姿が目に浮かぶ。・・・」
ここで博士は、ポジティブな捉え方を述べているのであるが、実際のところはどうだろうか。前述の書評との差も気になり、早速「合成生物学の衝撃」を注文したのであった。
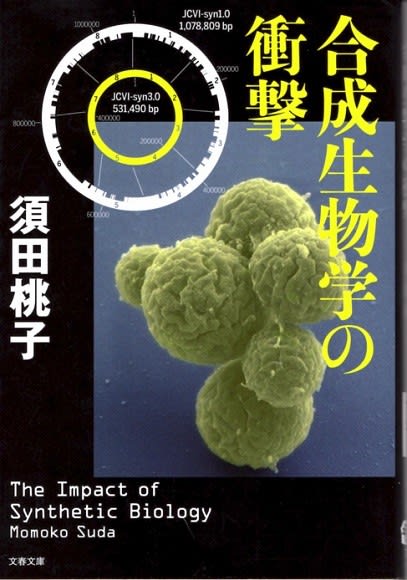
「合成生物学の衝撃」(須田桃子著 2021年6月発行 文春文庫)のカバー表紙
そうこうしているうちに注文してあった須田さんの本が届いた。2021年6月に文庫化された本の方を選択したが、これが幸いした。
この文庫版には「文庫版あとがき」が追加されているので、先ずそこから見ておくが、2018年4月発行の単行本とこの文庫版との間の3年間に「ゲノム編集ベビー」の誕生と、「コロナワクチン」の開発というこの本の内容に関連した二つの大きな出来事が起き、そのことが採りあげられているのである。いずれも中国が関係している内容である。
その一つは、2018年11月下旬、中国の研究者、南方科技大学(広東省深圳市)の賀建奎・副教授(当時)が、CRISPR(米国で開発された究極の遺伝子編集技術とされるもの)を使って遺伝子改変したヒト受精卵から双子を誕生させたという出来事である。
技術が未成熟で国際的な議論が進まない中での暴挙に、世界中から非難の声が上がり、中国でも遺伝子操作した子供を出産させることを禁止する指針があることから、賀氏は大学を解雇され、2019年12月に懲役3年の実刑、罰金300万人民元(4,700万円相当)の判決を受けた。
二つ目は、今も尚世界中を混乱に陥れているパンデミック(世界的大流行)を引き起こした新型コロナウィルス感染症(COVID-19)のワクチンの開発である。
日本でも、最も新しいオミクロン株が第6波として現在も猛威を振るっていて、3回目のワクチン接種、いわゆるブースター接種が始っている。
軽井沢でも「新型コロナワクチン3回目接種券」の送付がはじまり、1月31日から予約受付が開始された。昨年実施された中央公民館などでの集団接種時に使用されたワクチンは米ファイザー社製であったが、今回は日本でライセンス製造された、武田/モデルナ社製が先行接種される予定である。ファイザー社製のワクチンの集団接種については、少し遅れて2月22日に予約が開始され、3月16日から接種が始まる。
さてこのワクチン、いくつかの治療薬と共に、COVID-19によるパンデミックのゲームチェンジャーとなっているが、通常、新規の感染症のワクチン開発には10年かかるとされる中で、1年未満というごく短期間のうちに実用化にたどりついた。
2020年1月11日に中国の研究チームがウィルスのゲノム情報(塩基配列)を公表すると、その2日後にワクチンの設計を終え、3月16日には実際に被検者に投与する第1相臨床試験を開始するという驚異的な開発速度で一躍、世界の注目を浴びた企業がバイオベンチャーのモデルナ社であった。
モデルナ社は今回のm-RNAワクチンを米国立衛生研究所(NIH)と共同開発しているとされるが、米国防高等研究計画局(DARPA)から出資を受けた企業であり、著書「合成生物学の衝撃」でも取り上げられていた。
この二つの出来事はいわば、合成生物学に関連した光と影という事になるが、やはり気になるのは影の部分である。では、この著書に戻って、どのような衝撃的な内容が紹介されていたのかを見てみようと思う。
その前に先ず、「合成生物学」とは何かについてウィキペディアの記述を見ると、次のようである。
「合成生物学(ごうせいせいぶつがく、英語: synthetic biology)は、生物学と工学の学際的な分野である。構成的生物学や構成生物学とも呼ばれる。・・・
合成生物学は、幅広い研究領域を統合して生命を全体的に理解しようとする学問であったが、科学と工学の融合が進むにつれ、新しい生命機能あるいは生命システムをデザインして組み立てる分野も含むようになっていった。生物を設計する、作成する、操作することで生命への理解を深めるアプローチや、有用物質を生産するキメラの作製も主要なテーマとなっている。」
このように、合成生物学は事前に私が考えていたよりも広い範囲をカバーする学問として定義されていることが判る。今回の著書「合成生物学の衝撃」では、この中の「新しい生命機能あるいは生命システムをデザイン」する学問にフォーカスしていることになる。
実際、この本の中で、須田氏のインタビューに答えて、クレイグ・ベンター博士(1946.10.14ー)はDNAを一から合成することを含むミニマル・セルプロジェクトの一連の研究を総称して、かなり広い意味を持つ「合成生物学」ではなく、その一部である「合成ゲノミクス」という言葉を使っているとして、彼の「我々の研究を『合成生物学』と呼ぶのは、東京に住んでいるのを『日本に住んでいる』というようなものだ。」という言葉を紹介している。
こう話した「クレイグ・ベンター博士」と、博士たちの作った「ミニマル・セル」がこの本の主人公ともいえる。
彼が主催する非営利の研究所「J・クレイグ・ベンター研究所」がミニマル・セル研究の本拠地とされるが、サンディエゴ市北部の地区ラホヤにあり、2006年に、それまであった5つの組織を統合してできたとされる。
ここで、ベンター博士と共に、ハミルトン・スミス、クライド・ハッチンソン、ジョン・グラスの三人がミニマル・セルプロジェクトを主導しており、研究所は250人以上の研究者やスタッフを擁している。
さて、ミニマル・セルとは何か。それは、生命の維持に欠かせない最小のゲノムを持つ人工遺伝子を持つ細胞のことで、遺伝子数は473個、塩基対で約53万とされる。
ここで用いられた遺伝子は、酵母を利用して合成され、およそ100万塩基対のゲノムを持つマイコプラズマ・マイコイデスという細菌の遺伝子を入れ替える形で移植された。その研究過程で、不要な遺伝子をそぎ落とす作業をして、この数字にたどり着いたのである。着想を得てから20年目に成功したとされるもので、この研究成果は2016年3月、米サイエンス誌で発表された。[ Hutchison, C. A. III et al. Science351, aad6253 (2016). ]
遺伝子を入れ替えた細胞は生きていて、増殖をすることが確かめられた。その様子は次の「J・クレイグ・ベンター研究所」のウェブサイトの動画で見ることができる。
各遺伝子の持つ機能や役割を追求すること、そして細胞の生命維持に必要な最小限の遺伝子を見いだし、それを人工的に合成し、既存の天然の細胞に移植し、その細胞が生き続けることを確認した偉業であるが、考えてみると、人工と言えるのは遺伝子であり、細胞そのものを作ったわけではない。
いわば、少しばかり居心地の悪い貝殻に引っ越したヤドカリのようなものである。ところが、これから先が違っている。移植された遺伝子は、自らの設計図に基づいて新たな細胞を作りはじめる。
DNAの指令に基づき、すべてのタンパク質、細胞質から細胞膜までが入れ替わり、分裂を繰り返すうちに、元の細胞の特徴はすっかり失われ、理論的には30回の分裂を繰り返した細菌には、元の細胞に由来する分子はたった一つしか含まれていないのだと、同研究所のハッチンソン博士は説明しているという。
最小の細菌を構成する原子数はおよそ10億個とされている。30回の分裂を起こすと1個の細胞は2の30乗個、すなわち10億個に増えるので、こうした説明がなされるのだろう。最初の細胞に含まれていた原子が分裂を繰り返すごとに1/2ずつ次の細胞に受け継がれていくとしての計算である。
この技術の先に何が待ち受けているのか。細胞の生命維持に必要な最小限の遺伝子が突き止められたとしているが、重要なことはコンピュータ上で設計したDNAが生命の基本的な働きである細胞分裂を起こし、自己を複製したことである。そしてもう一つは、人工合成したDNAを、まるごと細胞に移す技術が確立されたことである。
さて、このベンター博士たちの挑戦とは別に「ヒトゲノム合成計画」のことが本では紹介されている。
2017年5月に「ゲノム合成計画」のキックオフがニューヨークで開かれたが、これはその前にあった「ヒトゲノム合成計画」の名前を変えたものであった。
「ヒトゲノム合成計画」はその1年前の2016年6月に米国などの研究者25名が米科学誌「サイエンス」に構想を発表していた。発起人の一人、フューチャリスト(未来学者)のアンドリュー・ハッセルに須田氏はインタビューを試みている。
この計画の概要は、ヒトゲノムを含む医療や農業分野で役立つさまざまな生物のゲノムの合成を目指す過程で、DNAを合成したり、できたDNAの機能をテストしたりする費用を現在の1000分の1にするというものであった。
この発表は、メディアが取り上げ、米国内では大きな反響を巻き起こしたが、報道の多くは批判的なトーンだったという。
この構想を作り上げた会議自体が秘密会議であった事、そして内容では、やはり人工的なヒトゲノムを作ること自体がはらむ倫理的、宗教的な問題がその批判の的であった。
多くの議論を経て、「ヒトゲノム合成計画」のリーダーたちは、計画のタイトルから「ヒト」を外し、「ゲノム合成計画」としたのであったが、合成ゲノムを持つヒト細胞の作製は、重要なコアの活動として残し、倫理的な課題について議論を重ねていくとされた。
2017年5月に開催されたキックオフ会合には、日本を含む10か国から約250人が参加している。以前とは異なり、事前に登録して参加費を払いさえすれば誰でも参加できる”オープンな”会議であったという。
会議ではすでに選ばれていたものを含め、最初の5年間で取り組むパイロット・プロジェクトとして14件の研究課題が出そろい、日本からは唯一東京工業大学の相澤康則准教授が提案した課題が含まれている。
本の著者須田氏はここで次のように述べている。
「この計画を取材中、私はある人物の”不在”がずっと気にかかっていた。かつてのヒトゲノム解読計画で公的研究チームと競い、実質的な勝利を収めたクレイグ・ベンターその人である。その後の合成生物学へと向かう研究の潮流でも常に第一人者として走り続け、合成ゲノムで働く細胞を世界に先駆けて作製した。彼こそ、地球上で最もヒトゲノムの合成に近いところにいるのではないだろうか。・・・」
そのベンター博士に須田氏はインタビューをするが、その際、彼は次のように語ったという。
「ヒトゲノムの合成は現実的なプロジェクトではない。なぜなら、それについて話している人々は、私達の研究所がやったような、小さな細胞を作る能力すら持ち合わせていないからだ。もし小さな細胞を作ることができないとしたら、どうやってその数百万倍も複雑な細胞を作ろうというのだろう? 10年以内に成し遂げるなど、絶対に不可能だと確信している」
この部分を読むと、複雑な思いにとらわれる。20年間の苦労を重ね、ようやくミニマル・セルにたどり着いたことを考えると、ベンター博士の云う通りかもしれない。しかし、技術は日々進歩しており、計画は遅れることになるかもしれないが、そして研究チームとベンター博士のどちらが先行するかは判らないが、いずれこのプロジェクトが目指す技術が出来上がることだろう。
著者の須田氏はそうした未来を想像して、取材をしていた。人類が得た究極のテクノロジーの一つ、原子の核に迫る技術は核兵器を生み出した。今進んでいる細胞の核に迫る技術を進めていくと、人工生命の次には人工人間を生み出す技術なっていくことになる。
核兵器の製造と使用を人類が止めることができなかったように、人工人間の製造に人類が手をつけることもまた止めることができないのではという懸念が著者の須田氏にはあるし、そしてもちろん多くの人にもある。
こうしたことを踏まえて、この本の第四章では旧ソ連のシベリアの生物兵器研究所で、約50人を擁する研究部門の部門長だった微生物学者、セルゲイ・ポポフ氏とのインタビュー内容を紹介している。氏はソ連崩壊後に米国に渡り、現在はバージニア州にあるジョージ・メイソン大学・システム生物学スクールの教授を務める。
ポポフ氏だけではなく、1989年以降、西側諸国に亡命した複数の科学者らが、手記などを発表して告発をしているという。それによると、1973年にはある大型プロジェクトが始まったとされる。
二つあるというこのプロジェクトの目的は、従来の生物兵器を近代化することと、遺伝子操作を行って抗生物質やワクチンにも耐えうる病原体を作り出すことであった。
こうした研究には多数のDNA断片を合成する手法を学ぶことが必要であり、ポポフ氏はそのために英国に留学し、ケンブリッジ大学に半年滞在し、自動合成装置を使ってどのようにオリゴヌクレオチド(ごく短いDNA断片)を合成するかを学んでいる。帰国後、彼は1981年、シベリアにあった研究所で約50人を擁する研究部門の部門長になる。研究計画の目的は、新たな症状、誤診断を促す症状、治療や検知が難しいといった高い病原性をもつ人工ウイルス作製である。
米国の諜報機関は、ソ連が生物兵器研究に携わっていないと信じていたが、ソ連は米国が生物兵器を製造していると信じていたという、ある種の相互不信が背景にあった。
研究は成果をあげ、ラットやモルモットを使った動物実に成功し、後は霊長類であるサルで効果を試す最終実験をするばかりになっていたが、1992年5月のソ連崩壊ですべての研究が中断された。
ポポフ氏は、その後英国に渡り、次いで米国に移り、ここで2000年になって自身の経験を周囲の専門家に語り、米国の複数の記者から取材を受けている。旧ソ連の科学者たちの中には、米国以外の国に亡命した者もいる。ポポフ氏によると、旧ソ連の研究で培われた知識が、それらの国々に拡散したと確信しているという。
1999年に首相に就任したウラジミール・プーチン現大統領は、旧ソ連で行われた研究はすべて防衛目的であり、生物兵器禁止条約に違反する内容ではなかったとの公式見解を出している。
科学者のあくなき探究心は多くの光を我々人類に与えてくれているが、そのもたらす影の部分について制御する力を科学者と政治家が持ち合わせているかどうか、問われるのはこれからだが、どのような未来が我々を待ち受けているのか。見たいようであり、恐ろしくもある。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます