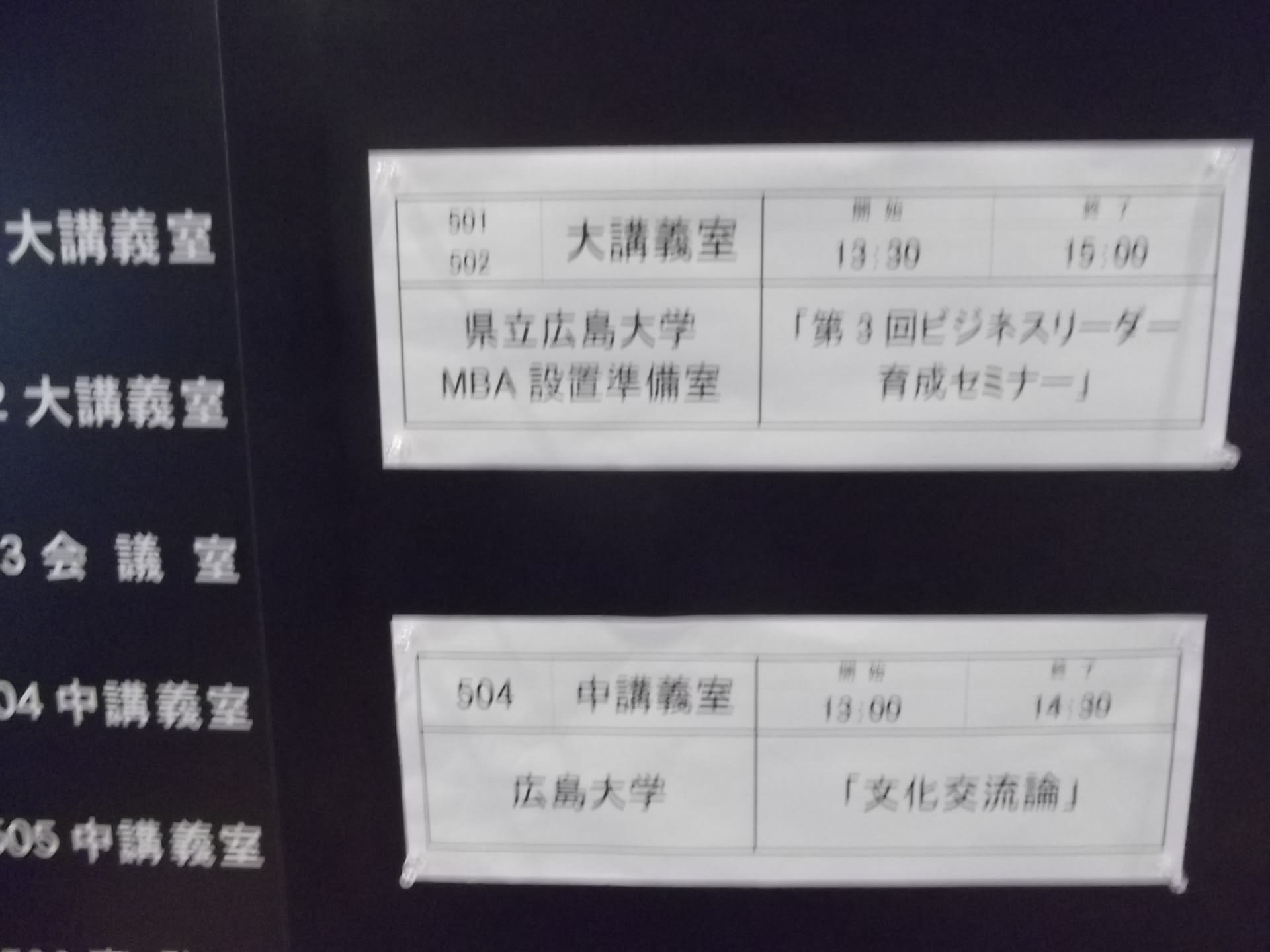| チャレンジする地方鉄道―乗って見て聞いた「地域の足」はこう守る (交通新聞社新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 交通新聞社 |
関東への一極集中が続く中で、地方は人口が減り、学校も統廃合が続いて、ローカル線の経営環境はどんどん苦しくなってきている。黙っていても人が乗ってくれる都市部の鉄道とは違い、生き残りのために、ローカル線では様々な取り組みが行われているのをご存じだろうか。「チャレンジする地方鉄道―乗って見て聞いた「地域の足」はこう守る」(堀内重人:交通新聞社)は、全国14のローカル線を取り上げ、その生き残り戦略を紹介したものだ。
ローカル線といえども、その一義的意義は、地域の生活路線だというところにある。たとえ、列車ダイヤが1日に数本しか無いようなローカル線でも、それがなくては困る人がいるのだ。しかし、地方では、とても地元からの運賃収入では、路線を維持していけないという現実がある。だから、ローカル線の経営主体は、収入を増やすための様々な活動を行わなくてはならないのだ。例えば、イベントを仕掛けて観光客を誘致したり、そのローカル線ならではの物販を行ったりするといったようなことはまだ序の口。枕木やつり革のオーナー制度を取り入れたり、駅名などのネーミングライツ権の販売をといった色々なアイディアで収入を増やそうと努力をしているのである。
またローカル線は、旧国鉄から切り離された第三セクター形態のものも多い。第三セクターでは、地元自治体の役人が経営者についている例が多いが、お役人では柔軟な発想ができないとして、民間から社長を公募したところもあるという。お役人は柔軟な発想ができないというのは、定説のようになっているが、これが正しいとすれば、通常の行政事務を行っていくうえでも、困ったことだ。もちろん、鉄道経営に限らず、できる人を連れてくるというのは当然のことだし、そうしなければならない。
鉄道会社の負担を減らすためにインフラ部分は地方自治体が持ち、鉄道会社は、列車の運行に専念するという上下分離方式を取り入れているところもある。関係自治体の負担は増えるが、地域の足を守るためにはこれもひとつの手段だと思う。
私が大学を卒業して就職してからでも、中国地方では多くのローカル線が廃線になった。一度失われた鉄道は、よほどのことがなければ再建されない。しかし本書を読めば、その一方で、様々な知恵を絞って生き残っているローカル線も沢山あることも分かる。そんな頑張っているローカル線にエールを送りたくなってくる一冊だ。
☆☆☆☆
※本記事は、書評専門の拙ブログ、「風竜胆の書評」に掲載したものです。