
 姪っ子メグ あーあ、宗像教授シリーズの連載が終わっちゃったわねぇ。残念。
姪っ子メグ あーあ、宗像教授シリーズの連載が終わっちゃったわねぇ。残念。 キミオン叔父 うん、大英博物館に行っちゃうんだよな。でも現実にも、日本の漫画ではじめて星野之宣の原画が大英博物館に翻訳展示されたんだからたいしたものだ。
キミオン叔父 うん、大英博物館に行っちゃうんだよな。でも現実にも、日本の漫画ではじめて星野之宣の原画が大英博物館に翻訳展示されたんだからたいしたものだ。 別冊の「神南火」シリーズもあったけど、あたし好敵手の歴史家忌部神奈さんが好きだったなぁ。すぐ煙草をプカプカしちゃうんだけどさ、ちょっと寂しい過去もあって。これも悲しい過去を持つ宗像伝奇(むなかたただくす)と結ばれるのかなぁと思ってるんだけど。
別冊の「神南火」シリーズもあったけど、あたし好敵手の歴史家忌部神奈さんが好きだったなぁ。すぐ煙草をプカプカしちゃうんだけどさ、ちょっと寂しい過去もあって。これも悲しい過去を持つ宗像伝奇(むなかたただくす)と結ばれるのかなぁと思ってるんだけど。 オジさんは、宗像神社の巫女でもある姪っ子の三姉妹がお気に入り。でも、星野さんのテーマでもあるけど、宗像教授の一番追い求めていたのが、鉄と古代史だよな。
オジさんは、宗像神社の巫女でもある姪っ子の三姉妹がお気に入り。でも、星野さんのテーマでもあるけど、宗像教授の一番追い求めていたのが、鉄と古代史だよな。 「鉄」って面白いよね。最初に人間が出会ったのは隕石に含まれる「隕鉄」よね。紀元前3000年位のシュメール文明で早くも鉄器がつくられている。で、有名なのはオリエントのヒッタイト文明でしょ。鉄でオリエントを統一するみたいなもんじゃない。紀元前2000年ぐらいかな。
「鉄」って面白いよね。最初に人間が出会ったのは隕石に含まれる「隕鉄」よね。紀元前3000年位のシュメール文明で早くも鉄器がつくられている。で、有名なのはオリエントのヒッタイト文明でしょ。鉄でオリエントを統一するみたいなもんじゃない。紀元前2000年ぐらいかな。 そう、オスマントルコにつながる。石器→青銅器→鉄器となるわけだけど、中国に伝わったのが紀元前7世紀、で紀元前4世紀ぐらいには普及して、戦で使われ、支配の道具となる。日本にもそのころ伝わったのかな、弥生の中期から後期あたり。日本では砂鉄がよくとれたから、出雲地方なんかを中心に「たたら製鉄」が盛んになる。もののけ姫の世界だよね。
そう、オスマントルコにつながる。石器→青銅器→鉄器となるわけだけど、中国に伝わったのが紀元前7世紀、で紀元前4世紀ぐらいには普及して、戦で使われ、支配の道具となる。日本にもそのころ伝わったのかな、弥生の中期から後期あたり。日本では砂鉄がよくとれたから、出雲地方なんかを中心に「たたら製鉄」が盛んになる。もののけ姫の世界だよね。 ベストセラーにもなったジャレド・ダイヤモンド博士の『銃・病原菌・鉄』にもあったけど、古代インカ帝国なんかはコロンブスなんかがくる14,15世紀まで石器だったんだものね。金属加工技術はあったけど、ほとんど宝飾品だったから。
ベストセラーにもなったジャレド・ダイヤモンド博士の『銃・病原菌・鉄』にもあったけど、古代インカ帝国なんかはコロンブスなんかがくる14,15世紀まで石器だったんだものね。金属加工技術はあったけど、ほとんど宝飾品だったから。 あのねぇ、ヘシオドスだったかが、人間の歴史を五つに分けているの。金の時代、銀の時代、銅の時代、英雄の時代、そして最後が鉄の時代。そしてその「鉄の時代」になって人間は堕落して、戦争に終始するようになったんだって。
あのねぇ、ヘシオドスだったかが、人間の歴史を五つに分けているの。金の時代、銀の時代、銅の時代、英雄の時代、そして最後が鉄の時代。そしてその「鉄の時代」になって人間は堕落して、戦争に終始するようになったんだって。





 ちょっと制作風景がビデオ映像になってたけど、すごいねぇ。ひたすら鉄をカーン、カーンと叩いている。
ちょっと制作風景がビデオ映像になってたけど、すごいねぇ。ひたすら鉄をカーン、カーンと叩いている。 鉄の正方体にしてもさ、2tも3tもあるんだからさ、面を移動させるのだけでもさ、いろんな幅の枕木みたいなのをさしこんで、ちょっとづつ浮かせて、フォークリフトで持ち上げて、ゴロッと向きを変える。その作業だけでも気が滅入るけどさ(笑)。そこから5kgとか8kgのハンマーで延々とカーン、カーンと。何万回も叩き続けるんだよな。そのハンマーを持って見たけど、重くてよろけてしまったよ。
鉄の正方体にしてもさ、2tも3tもあるんだからさ、面を移動させるのだけでもさ、いろんな幅の枕木みたいなのをさしこんで、ちょっとづつ浮かせて、フォークリフトで持ち上げて、ゴロッと向きを変える。その作業だけでも気が滅入るけどさ(笑)。そこから5kgとか8kgのハンマーで延々とカーン、カーンと。何万回も叩き続けるんだよな。そのハンマーを持って見たけど、重くてよろけてしまったよ。 これさぁ、この会場にどうやって運び込んだのよ。
これさぁ、この会場にどうやって運び込んだのよ。 そう、その作業を想像しただけで、腰が痛くなってきたよ。鉄は貴重な物質だったからな。「鉄は国家なり」と言われるけど、日本でも朝鮮半島から製鉄技術が伝播されたんだろうけど、貴族社会ではそれをうまく使って荘園を管理し、幅広く大衆化されるとそれを武器にすることで武家社会が興ってくる。で、織田信長の鉄砲軍団のような戦闘で統一をとげるようになる、幕末では西洋の鉄の産業技術を目のあたりにして、開国となるわけだ。それから以降も、やはり鉄の果たす意味は大きいし、環境問題なんかも製鉄に起因することも大きいね。
そう、その作業を想像しただけで、腰が痛くなってきたよ。鉄は貴重な物質だったからな。「鉄は国家なり」と言われるけど、日本でも朝鮮半島から製鉄技術が伝播されたんだろうけど、貴族社会ではそれをうまく使って荘園を管理し、幅広く大衆化されるとそれを武器にすることで武家社会が興ってくる。で、織田信長の鉄砲軍団のような戦闘で統一をとげるようになる、幕末では西洋の鉄の産業技術を目のあたりにして、開国となるわけだ。それから以降も、やはり鉄の果たす意味は大きいし、環境問題なんかも製鉄に起因することも大きいね。 この多和さんは、その鉄の塊を、延々と叩き続けながら、文明そのものの歴史を追体験しているようなところもあるのかしら。
この多和さんは、その鉄の塊を、延々と叩き続けながら、文明そのものの歴史を追体験しているようなところもあるのかしら。 1970年代から1980年代に公園などを開放して、アーチストが結構巨大な屋外芸術にチャレンジしていたんだよな。オジサンも田舎に戻ると、夏場の一定期間、アーチストたちが巨大なオブジェに何組も取り掛かっていて、飽きずに見ていたことを思い出すね。
1970年代から1980年代に公園などを開放して、アーチストが結構巨大な屋外芸術にチャレンジしていたんだよな。オジサンも田舎に戻ると、夏場の一定期間、アーチストたちが巨大なオブジェに何組も取り掛かっていて、飽きずに見ていたことを思い出すね。それにしても、作品の移動がねぇ。イタタタタ、また腰が痛くなってきたよ。











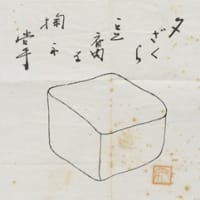


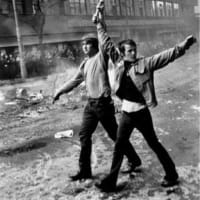



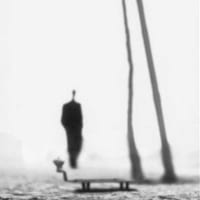

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます