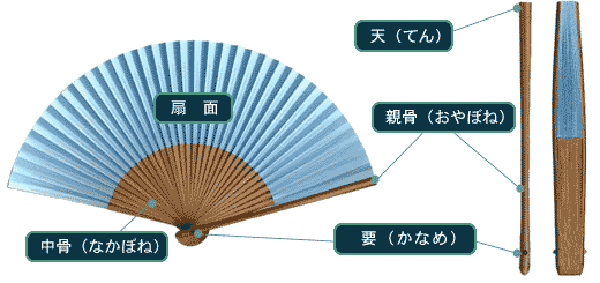
「団扇(うちわ)」と同じく中国から伝わったものだと思っていたが、なんと、扇子は日本人が発明したものだった。
古墳時代に中国から伝わった「翳(さしは)」が原型で、貴人や女性の顔を隠したり、虫やハエを追い払ったり、災いを払う役目もあったという小型の「翳」を「打ち翳(は)」と呼び、その後「うちわ」に変化した。団扇が日本に伝わってから約100年後、平安時代に折りたためて携帯しやすい扇子が発明された。
「扇」の語源は、本来「扉」と記され「とびら」と読んだ。
「扇」の漢字は、「戸」が「羽」のように動き扇いで風を起こすことに由来する。団扇の「団」は「まるい」を意味する。

平安時代初期に、木材(竹など)を板状にしたものを使って、その木の板に短歌などを書いてメモ帳代わりにしていた。これが「扇子の起源」とされ、檜扇(ひおうぎ)と呼ばれていた。仰ぎ物として使っていたわけではなかった。
平安時代中頃に現在の扇子の原型とされる片側に紙を貼った蝙蝠扇(かはほりあふぎ)が登場し、和歌を書いて贈答したり、花を載せて贈ったと源氏物語などに数多く記載されている。また、扇面写経も平安時代に多く作られた。
そして、時代が進むにつれて儀式等の装飾品として使われた。初めは一部の貴族や神職者といった高貴な人達でしか使うことができなかったが、やがて芸能や茶道などに用いられるようになってから一般庶民にも普及していった。
中国大陸には北宋の時代に伝わったとされ、日本僧の喜因が檜扇と蝙蝠扇を宋の朝廷に献上したとされる記録(988年)がある。
16世紀に入るとポルトガルとの交易によって、ヨーロッパへと伝わり、ヨーロッパでは貴族の女性の持ち物として使用されるようになった。
現在では、扇子は様々な種類が存在する。扇子が末広がりと言われるのは、扇子を開いた時に先端である末のほうが広がることから、繁栄を意味し縁起が良いとされた。そのことから、扇子は現在でも結婚や長寿のお祝いなど、様々なお祝い事に記念品として贈答される。海外でも日本の伝統文化として高く評価され、お土産にも喜ばれる。
中国で使われた団扇(うちわ)の携帯用団扇から、「扇の子」 扇子 と名づけられたのだろう・・・。
なかなか、センスがよい。

古墳時代に中国から伝わった「翳(さしは)」が原型で、貴人や女性の顔を隠したり、虫やハエを追い払ったり、災いを払う役目もあったという小型の「翳」を「打ち翳(は)」と呼び、その後「うちわ」に変化した。団扇が日本に伝わってから約100年後、平安時代に折りたためて携帯しやすい扇子が発明された。
「扇」の語源は、本来「扉」と記され「とびら」と読んだ。
「扇」の漢字は、「戸」が「羽」のように動き扇いで風を起こすことに由来する。団扇の「団」は「まるい」を意味する。

平安時代初期に、木材(竹など)を板状にしたものを使って、その木の板に短歌などを書いてメモ帳代わりにしていた。これが「扇子の起源」とされ、檜扇(ひおうぎ)と呼ばれていた。仰ぎ物として使っていたわけではなかった。
平安時代中頃に現在の扇子の原型とされる片側に紙を貼った蝙蝠扇(かはほりあふぎ)が登場し、和歌を書いて贈答したり、花を載せて贈ったと源氏物語などに数多く記載されている。また、扇面写経も平安時代に多く作られた。
そして、時代が進むにつれて儀式等の装飾品として使われた。初めは一部の貴族や神職者といった高貴な人達でしか使うことができなかったが、やがて芸能や茶道などに用いられるようになってから一般庶民にも普及していった。
中国大陸には北宋の時代に伝わったとされ、日本僧の喜因が檜扇と蝙蝠扇を宋の朝廷に献上したとされる記録(988年)がある。
16世紀に入るとポルトガルとの交易によって、ヨーロッパへと伝わり、ヨーロッパでは貴族の女性の持ち物として使用されるようになった。
現在では、扇子は様々な種類が存在する。扇子が末広がりと言われるのは、扇子を開いた時に先端である末のほうが広がることから、繁栄を意味し縁起が良いとされた。そのことから、扇子は現在でも結婚や長寿のお祝いなど、様々なお祝い事に記念品として贈答される。海外でも日本の伝統文化として高く評価され、お土産にも喜ばれる。
中国で使われた団扇(うちわ)の携帯用団扇から、「扇の子」 扇子 と名づけられたのだろう・・・。
なかなか、センスがよい。


















扇子は なるほど団扇よりセンスが良い
・・と言うと「ウチワもめ」になるかも
この話題は、数か月前につづっていましたが、ようやく日の出をみました。
「子」は漢語で、名詞の末尾に付く「名詞接尾辞」です。よって、「扇」ということです。
禅語に「庭前栢樹子」がありますが、これも「柏の木」の名詞の接尾辞として「子」が付いており、「柏の樹の子」という意味ではありません。
上のご解説をよくは理解できませんが、わざわざのお越しをありがとうございました。
日本人は平安の昔からに物を改良して使いやすくする能力に長けていたのですね。(センスがいいですね)
>ヘらを大きくしたようなもので里芋をゴロゴロまわして洗ってました。
皮をうまく取り除きますから、面白く見てました。
道具を使えばきれいに洗えるのでしょうが、手で洗うと結構大変です。
私はゴム手袋をして洗っています。
団扇が中国で、団扇の団は「まるい」を意味し、団扇を参考にして日本で発明たのが扇子でしたか。
勉強になります。
「雨模様」は、空が雨の模様になっている状態ですから、「雨が降りそうな様子」のように思ってました。
冬の季節は、太平洋側は
短歌などを書く檜扇(ひおうぎ)を戯れに扇いでみたら風を送れて気持ち良いからと、「扇子」と名づけたという印象です。
陽当たり良好で見晴らしもよく、風情ありそうです。
相模湖畔を歩くと、案外とおもしろそうです。
しかし、国道20号を歩くのは交通量が多く恐いですょ。