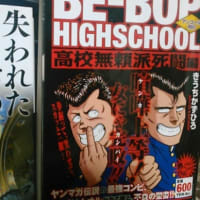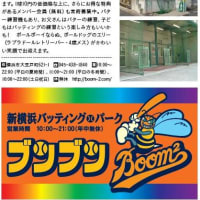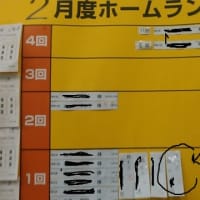「不思議の国のアリス」は、いま世界でもっとも読まれている童話のうちのひとつです。
疑問の余地のない傑作というのは文学史のうえでも案外少ないものなのですが、この作品はその稀な例外にあたります。
ジョン・レノンも、バート・ヤンシュも、先代エリザベス女王も、あと、僕の小学校時代の憧れの女の子も、みーんな、この童話が大好きでした。
作家の北杜夫氏もかつてエッセイのなかで、この童話の非凡な独創性について言及されていたことがありました。自分はこの作者が天才だとは思わないが、作品自体は、これは天才の業である、誰にも真似のできない、これほど独創的な話は、今後誰にも書けないだろう---みたいな内容だったと記憶してます。
僕自身もまったくその意見に賛成ですね。
こんな、唖然とするほどおかしな話はないですよ。
自分の流した涙の海で溺れたり、兎の竪穴を延々と落下していくとちゅうの穴の棚からオレンジ・マーマレードの瓶をとりだしたり、急激に巨大化したおりに、遠去っていく自分の足にむけて手紙を書こうとしたり、気狂い帽子屋とヤマネと3月兎とで終りのないキテレツお茶会をいきなりおっぱじめたり……。
奇想天外でもって、ちょっぴり不気味わるいけど、胸底がきゅっとなるような無垢なキュートさもしっかり宿してる---こんなアリスの白日夢のようなまほろば世界に惹かれない子供なんて、果たしてこの世にいるんでせうか?
僕にいわせれば、アリス・ワールド、イコール、童心そのもの。
ですから、この話を解さないひととは友達になりたくないなあ、なんてつい思っちゃいますね。
知っての通り、この話の作者であるルイス・キャロルは、本名をチャールズ・ラドウッジ・ドジソンといって、1832年、英国のチェシャー州ダーズベリ産まれの---ここで早くもチェシャー猫を連想してにこっとされたあなた、あなたは凄い、アリスの有段者認定です!---有名な大学教授さんなのでありました。
ええ、彼、本職は、数学者であり論理学者であったわけでして。
本職以外でもなかなかに多趣味なひとでして、当時まだ幼年期だった写真術に凝り、知りあいの少女のポートレイトなどいっぱい撮影してます。彼女たちのヌード写真なんてのもけっこう残ってる---いまだったらスキャンダルですよね、こういうの---どうも、ちょっとばかりロリコン趣味のある方だったようですね。
実際、「不思議の国のアリス」の母胎は、キャロルが彼のいちばんのお気に入りの少女---アリス・リデル---のために語った、即興のお伽話がもとだったんですから。
お気に入りの少女をなんとか喜ばせたくて、彼女を物語のヒロインにしたウケ狙いの話を紡いでいったら、それを聴いたアリスがもうむちゃくちゃに喜んじゃって、その話をぜひ本にしてくれ、とせがんだ。それが、結果的に「地下の国のアリス」という自家製の本となり、のちの「不思議の国のアリス」のクロッキーともなったわけなんです。
こういうの聴くと、いい話だなあ、と僕なんかは自然に頬がゆるんじゃいますね。
いい話、かくあるべし。
誰か特定の個人を喜ばすための、素朴な奉仕の気持ちが、あらゆる傑作のたまごなんですよ。
ひとりのひとを喜ばせたい気持ちが、結果的にほかの、多数のひとの気持ちに徐々に伝播していく---これが、傑作のあるべき正しい姿でせう。
最初から「マス」を相手にして発信される名作は、それは名作なんかじゃなくて、名作という体裁だけ借りた企業プロジェクトじゃないの、と皮肉突きを咽喉元に一発入れたくなりますね。
というようなわけで「不思議の国のアリス」という作品は、世評の通り、誰が読んでもおっそろしく面白い作品として仕上がって、日夜不特定多数の読者から愛されてるわけなんですが、よくよく読みこんでいってみると、この作品内の大部分を占めている「不思議の国」というのが、すこぶる異様な相貌をしてるんですよ。
なにが? どのへんが異様なの?
うーん、うまくいえないんですけど、この不条理世界、たくらんで編まれた形跡がまったくないんです。
ライマン・フランク・ボームの「オズの魔法使い」あたりだと、なにか作者の「読者をびっくりさせてやろう!」みたいな、健康な空想上の茶目っ気を感じられる部分がずいぶん多いんですよ---いうなれば、意図的な悪戯魂みたいな。
要するに、ボームの生みだしたオズの国というのは、あくまで作者ボームの空想の管理下にあるわけなんですよ。
したがって、作者ボームの管理人としてのたくらみ手腕も、しっかり窺える。「オズの魔法使い」なんかでは、読んでてそのあたりの機微が明瞭に分かります。ああ、さすが、ミスター・ボームは自分の幻想世界をしっかり管理してるなあって。
しかるに、アリスの場合はぜんぜんちがう、アリス世界の場合においては、完全に主客の逆転が実現しちゃってる。
というか、物語の背景であるべきキテレツ世界のリアルティーが、あんまりありすぎる。
つまり、物語内の空想世界が、作者であるキャロルの筆力を完全に凌駕しちゃってる感じなんです。さながら氾濫寸前の濁流とでもいった様相ですか。
で、作者であるキャロルは、それに食われまいと必死に奮戦してはいるけど、そんなけなげな堤防工事がいつまでもつのか、はなはだ心もとない感じです。
ええ、僕は、アリスのいる不思議の国は、度を超したナンセンス・エネルギーをたえず噴出してる、と感じます。
本来なら、こんな不毛な土壌に、物語の花は咲かないはずです。
このささやかな童話が、物語として成立していられるのは、一重に、物語のモデルであり、主人公でもあったアリス・リデルという一少女のおかげでせう。
彼女のおかげで、この物語は物語として成立していられるのです。
僕は、この物語の作者であるキャロルは、心に非常に深い闇を抱えた人間であったと見ますね。あなただってその気になれば、アリスの物語のあちこちの隙間から、なにか「無明」の闇のけむりがもくもくとあがっているのが見分けられると思う。この不思議の国全体がキャロル内面のデッサンだとするなら、このひと、恐らくこの世でなんにも信じてないですよ…。
かろうじて少女であるアリスと、彼女の健康な肉体だけを信じてるような顔はしてますが、それは、通常にいうところの「信じる」という単語とはだいぶレベルの異なる感じです。
信じるというより、内面いっぱいに広がった、キャロル内部の暗いカオス的情熱が、エントロピーの増大で崩壊しきってしまうまえに、アリスという少女の肉体にすがりつき、ぶら下がって、落ちまいと必死にもがいている、といったほうがむしろ実情に近いでせうか。
ちょろっとまとめてみませうか---。
えーと、作者であるキャロルはね、僕にいわせれば、明らかに影の国の住人であり、徹底して非存在のひとなんですよ。
アリスはその真逆---れっきとして存在してる、触ることのできる、あくまで健康な一少女です。
で、そのルイス・キャロル教授が、ある日の午後、影の国から光の国のアリスにむかって手紙を書いたわけ。
年齢、ずいぶん離れてますけど、まあ、これは求愛の手紙として解釈すべきなんでせうね。
無意味の国の影法師が、分不相応な光の国の少女に恋しちゃったんですよ---切ないなあ…。
恋をしたら、まず相手の気を惹きたくなりますよね? 自分のなしうるあらゆる手練手管を使って、綺麗な花束をいっぱい相手に捧げなくっちゃ、です! この花束が、アリス内に登場するあらゆるナンセンスであり、また、不条理であったというのが僕の持論です。
影が実在に接近しようとしたら、影なりの手練手管を使うしかない---それが、ナンセンスであり、あるゆる不条理であったというわけです。皮肉といえばまあ皮肉なんでせうけど、キャロル的には、もうそれしかなかったんですよ。
アリス世界のなかに満ち満ちている、あらゆるナンセンス・ギャグのヴァラエティーは、あれは、キャロルなりの精一杯の「遊戯」であり「社交」であり、さらにいうなら彼流の「エンゲージ・リング」でもあったんですよ。
ええ、「不思議の国のアリス」という作品は、根本にそのような構造を隠しもっている童話なんじゃないか、なんてイーダちゃんは思います。

上にUPしたのが、ルイス・キャロル氏の生前のフォトです。
ねっ、キャロルさん、ナイーヴすぎる、いくらか過敏症チックな人相されてるでせう?
これが、あの歴史的なキテレツ物語を生みだした顔なんですよね。
ちょっと見だけでも詩人肌の顔ですよねえ、これは?
ただ、詩人顔というだけじゃ収まりきれないものもけっこうある、思索するひと独自の石みたいな頑固さ、そんな独自の兆候がこめかみのあたりに兆してますね。それに、頭蓋のでかいこと! この顔はやっぱり詩人じゃなくて、数学者の顔なんでせうね。
うーむ、アリスを語ろうと思ったら、やはりそちら側からのアプローチも試みなければ片手落ちになる気がします。
というわけで数学者としてのルイス・キャロルについていきませう。
ただ、学生時代まったく数学がダメだったイーダちゃんにとって、数学についての発言権はほとんどありません。
こんな文系かつ体育会系男に数学を語らせちゃイカンと思いもします。けれど、そんなむかしむかしの中学少年だったイーダちゃんの目に、ある日、たまたまとまった数学者についての見解があったんです。
出典は---なんと、探偵小説!---それ、アメリカの古典探偵小説作家ヴァン・ダインの著作なのでありました。
創元推理文庫からでてた「僧正殺人事件」っていうの---これ、犯人が数学者なのでありまして、インテリ探偵のファイロ・ヴァンスっていうのが、数学者の精神的生活というものにウンチクを傾けるくだりがあるんです。
その部分をちょっとだけ書きぬいてみませうか。
----空間と物質---これが数学者の思索の領域だ。ウイレム・デ・ジッターの空間の形についての考えは球状、あるいは球面形である。アインシュタインの空間は円筒形で、その周線あるいは、『境界線の状態』といってもよいが、そこでは物質は零に近づく……さて。このような概念を片方において計算したとき、自然とか、われわれの住む世界とか、人間の存在とかいったものはどうなるというのか。エディントンは、自然の法則などというものは存在しない---ということは、自然は充分に合理性をもった法則では律し得ないという結論を出している。そしてバートランド・ラッセルは現代物理学が必然的にたどり着く結論を要約して、物質は単に出来事の集団であり、物質自体はなにも存在する必要は持たないと解釈すべきだと述べている……その理論を押しすすめていくと、どういうことになるかね。世界が非原因的で、無存在だとすれば、単なる人間の生命などは、何ものかね……人間社会の個人などというものはその中におくと、無限小なものにすぎない、このように巨大な、ふつうの標準ではとうてい計り切れないような概念と取り組んでいる人間が、やがて、地上のいっさいの相対的価値の観念をなくして、人間に対して、限りない軽蔑心を持つようになっても、べつにふしぎはあるまいじゃないか……そういった人間の態度は不可避的に皮肉になる。心中では、いっさいの人間的価値を笑いものにし、自分の周囲に見えるものすべてのけち臭さをあざ笑うことになる。たぶん、その態度のなかには嗜虐的な要素もふくまれていよう。冷笑癖というものは嗜虐性のひとつの形式だものね……。
(ヴァン・ダイン「僧正殺人事件」創元推理文庫より)
イーダちゃんは初めてこのくだりの部分を読んだとき、あれ、この感覚どっかで感じた覚えがあるぞ、と思ったんですね。
最初は分からなかった。
でも、考えているうちに思いだしてきた…。そう、それって当時から愛読していた「不思議の国のアリス」のなかで感じた、体感温度の奇妙なひんやり感と酷似してたんですよ。
特に、アリスの流した涙の海で濡れまくったアリスと動物たちが、自分たちの身体を乾かすために開催した、あのふしぎなコーカス・レース!
僕が、「僧正」のこのくだりを読んで最終的に辿りついたのは---ええ---実は、アリスの物語のなかの、このコーカス・レースのイメージだったんですよ…。
(次ページに続く)