
はじめに
土器の器形と模様が在地の光景とが合致するのを楽しく感じる。
1、「槻沢遺跡」栃木県那須塩原市(大木式土器)縄文中期
「東北地方の土器群は、周辺地域の土器群形や模様が混じり合う現象が発達するという特徴があります。
・・・形や模様が混じり合うことを交流の影響と考えたとしたら・・・地域間交流が発達したのではないかという仮説が生まれることになる。」と解説があります。
2、土器から見えること
・土器にめずらしい部位があるのは、解決につながることが多い。思いもしない答えと分かると楽しくなる。
この土器も、何かあるとは思っていた。口縁が飛び出しているのは、「崖とか岩場」とかであることは察しがついていた。また、そこに「突起部分」があるのは、よくある「滝」だと思いたくなる。
調べていると「スッカン沢」と言う変わった名前の景勝地が見つかる。画像を見ると、土器の模様らしい光景があったのだ。おもしろい!
土器の口縁に穴があいているが、実在の画像にも、それらしい洞窟状の穴があるのだった。

円筒形で底部が垂直に切れているのは、まだ地下の地界に続くという示唆を感じる。また、長い流れが続くとも受け取れる。課題にする。
胴部の線は「流れ」としても異論はないと思う。
3、思うこと
・「周辺地域の土器群形や模様が混じり合う現象が発達するという特徴があります。」とは思えない。
・祭祀用の土器にちがいあるまい。滝は今でも信仰の対象になっている。縄文ヒトも現代ヒトも同じ意識といえる。土器の模様の表現など、すごい技量だと驚く。
「おらの世界を土器に表す」 縄文ヒトはすごい技量の持ち主だと思う。感心する!
縄文楽 浄山



















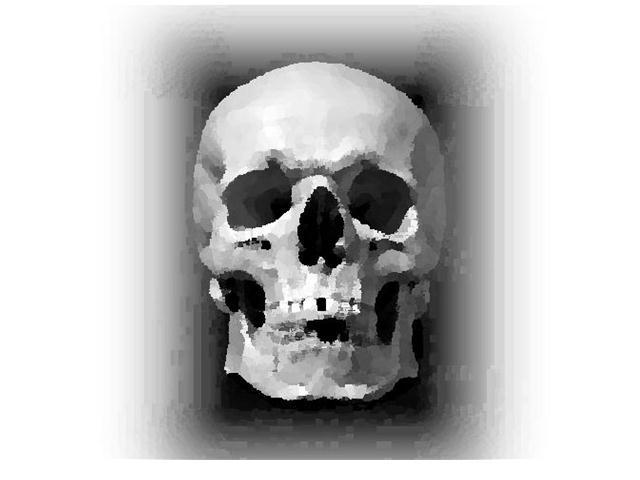





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます