
◇隆起線文尖底深鉢形土器
◇時代:縄文時代草創期 ◇所有者:青森県立郷土館 ◇サイズ:22×22×30 ◇遺跡所在地:上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢 遺跡)   ◎この土器から見えるもの
◎この土器から見えるもの
◇細隆起としたものを「隆起」にしました。前回が細隆起(草原)・・でしたので少し紋様が大きくなって「森林」としました。
◇土器の形態から深い森林地帯が生活の場と思います。
◇人工物は表に出ないようにしています。自然に対する心使いかとも感じます。
◇下地に「格子」が見えますが、この土器も格子縞の織物を下地にしているように思えます。
◇繊維入り土器である。初期の土器に多いという。
どのようにしてこのような土器を作成したのでしょか?疑問が残ります。
◇「隆起線」は森林・草原と環境の違いで線の太さが異なるという仮説を立てる。
「土器形体は地形」「紋様は生活環境」としています。
縄文楽 浄山
|



















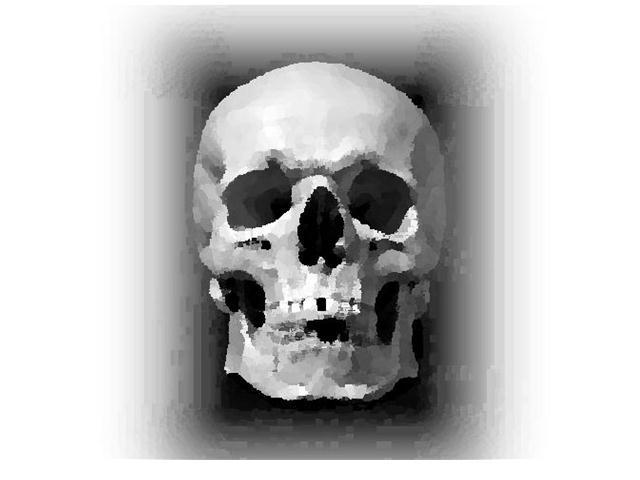





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます