ピント合わせに関しては、ハッキリ言ってSharpCap3.2_Proの
方が優れています。直観的だし、画像キャプチャーという観点
でのライブビュー性能が非常に使いやすいです。
N.I.N.A画像は、基本的にFitsで入ってくるため、CMOSなのに
MaxImDLで撮像したCCD画像の様です。
これはImagingパネルですが、Sequence撮像とは別に画像の取り込み
が出来ます。右上のImagingパネルで設定します。
Focus調整をやるにはSubSampling Frameを指定すると便利です。
Enable SubSamplingボタンをONにしてキャプチャーします。
Exposure Timeですが、いったん単発ショットで読み込まないと
設定時間が反映されないようです。
いきなりLive Viewでやってもキャプチャー時間が変化しません。
ここでGain450などとやれば、30.5cmF4の鏡筒ではHαフィルター
でも微小星像が見えます。なので、私の場合はバーティノフマスク
を使っていません。Bahtinov Analyzer機能があるので、併用しても
良いかもしれません。
単発ショットで撮った画像にPlateSolveを掛けることも出来ますが、
そのためにはN.I.N.AがASCOM_Telescope制御を握っていなければ
なりません。
N.I.N.AとCielで一晩に数対象程度を撮像する方法を書きます。
例として、M100をLRGB撮影する方法を書きます。
PlateSlveまでは不要なので、CielとASCOM_E-ZEUS2を接続します。
・CielとE-ZEUS2をASCOM driver for E-ZEUS Ver,2.20aで接続。
・観測地データをCielとASCOM_E-ZEUS2で揃える。
・CielとN.I.N.Aで同時にASCOM_Telescope接続は出来ない。
どちらか一方の排他的接続となるが、Cielでクリックした天体データ
をN.I.N.Aへ”一方通行に送る”ことができる。
これにより、Ciel上で撮影対象をクリックしておき、N.I.N.A側で
そのデータをワンクリックでインポート出来る。
N.I.N.A側でASCOM_Telescope制御を掴んでいて、かつ、座標データだけ
Cielにリアルタイム転送できれば一番良いのですが、今のところ
できない?または私が設定できていない?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授下さいm(__)m
・N.I.N.Aには32bit版と64bit版があります。
私の場合、古いOrion NautirusFilterWheelのASCOM driverが32bitで、
64bitのN.I.N.Aでは動きませんでした
よって、32bit版をインストールしてあります。
・N.I.N.AのEquipmentパネルからCamera , FilterWheel , Guiderを
接続します。ASCOM_Telescope制御はCielが握っているので使いません。
Focuserは非ASCOMの電動だし、Rotatorは付いていません。
雪の結晶アイコンをクリックすると冷却が始まります。
炎アイコンはウォーミングする際の速度を調整できます。
ASCOM_FilterWheelを接続
PHD2を接続(予めイニシャライズまで完了させておく。)
なお、現状で対応しているガイドソフトはPHD2のみである。
CielでM100を自動導入し、構図の微調整も行う。
N.I.N.AのFramingパネルでM100の情報をCielからインポートする。
Coordinatesアイコンをクリックすると入って来る。
この時、Image source = NASA Sky Surveyなどを選択してあり、
かつ、ネット接続があればこのような画像がDLされてくる。
尚、この画像はPC内に保存され、再利用できる。
ネット接続が無い場合はSkyAtlas(Offline Framing)を選んでおくと
このようになる。
Framingパネルから"Add as Sequence Target"をクリックすると、
SequenceパネルにM100の情報が転送される。
M100をLRGB撮像するSequenceを組んだところ。
LIGHTフレーム、各180秒露光、L=20枚 、RGB=各5枚、2X2binning、
Gain=250の設定である。
撮像される画像が何処に、どのような形式でセーブされるかを
設定できる。
Optios -> Imaging -> FileSettings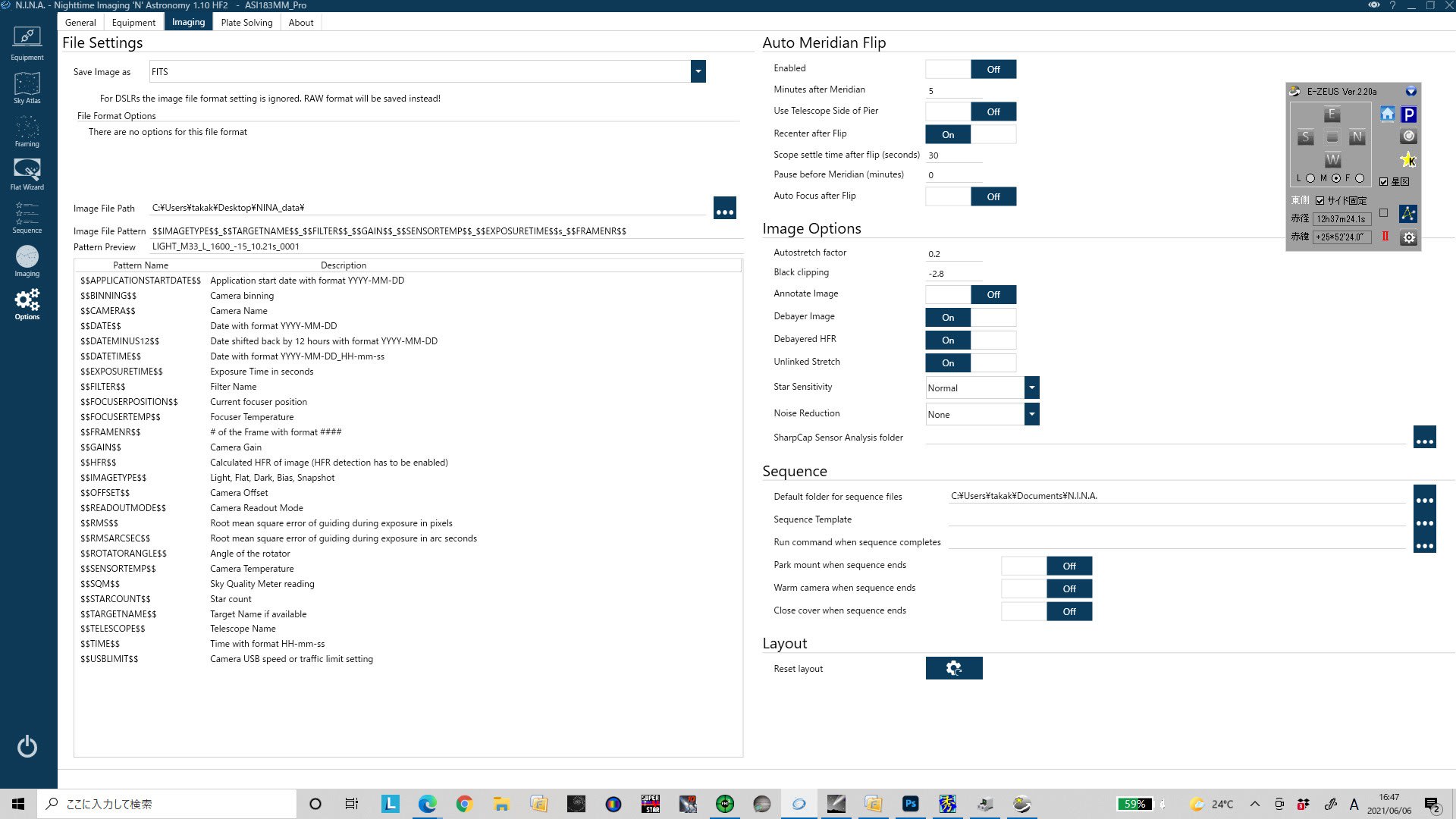
これで、Sequenceパネル右下の矢印をクリックすると連続撮像が開始
される。その際、PHD2 Guidingをスタートさせるかを設定できるが、
予めガイドさせておく方が確実である。
Sequenceは1時間45分42秒後に完了予定と表示されている。
5月29日~30日に掛けて、初めてN.I.N.AとCartes du Cielと言う
環境で撮影をやってみましたが、かなり使える印象でした。
今までにイロイロな環境で撮影をやって来ましたが、しばらくは
この組み合わせでやってみたいと思います。
いままで使ってきたソフトは、
MaxImDL_Pro , SharpCap3.2_Pro , PHD2
ステラ10 , SuperStarV
であり、ASCOM制御での撮像は殆どやっていませんでした。
まあ、それで過不足ある訳でもありませんが、個人的な興味から
N.I.N.AとCielに統合してみようかな・・・っと。
MaxImDL_Proは全部入りの統合ソフトであり、流石に高性能ですが
ライセンスが切れてしまいました。まだ一応一通りできるのですが、
問い合わせたらリニューアル代金が2万円程掛かるとのこと。
SuperStarVはE-ZEUS2と接続して自動導入に使ってきましたが、
どうにも進展が無いし、ASCOM対応もやってくれそうにないので
当面はオハコかな。軽くて良いのですけど・・・
ステラ10(あ~、まだ11にしていない)。
毎度お世話になっており、PGC天体のフレーミングなどでは助かります。
SuperStarVで導入しても、詳細はステラ10で確認したり計画したり
していました。以前よりASCOM経由でE-ZEUS2と接続できることも
分かっておりました(星羊爺さんに感謝!)。
同様にステラショット1でも動きましたが2はまだ試していません。
そもそも買っていませんし。
K-1に対応していないのと、当初はデジカメだけで冷却CMOS未対応で
魅力に欠けていたのが原因です。私にとっては費用対効果もあります。
と言うことで、今後は、
SharpCap3.2_Pro:PlateSolveによる極軸合わせ&電視系、
ピント合わせやカラーキャプチャーなど。
PHD2:定番ガイドソフトとしてN.I.N.Aとも連携使用。
Cartes du Ciel:ステラ10+SuperStarVの代わりになりそう。
N.I.N.A:一般撮像や多数天体の自動観測、自動撮影に使ってみる。
という方針を立ててみました。
気が付けば、殆どが無償ソフトウェアになってしまいました。
----------------------
っと言うことで、まずはCartes du Cielをカスタマイズ。
まだネット情報などを集めていないので我流です。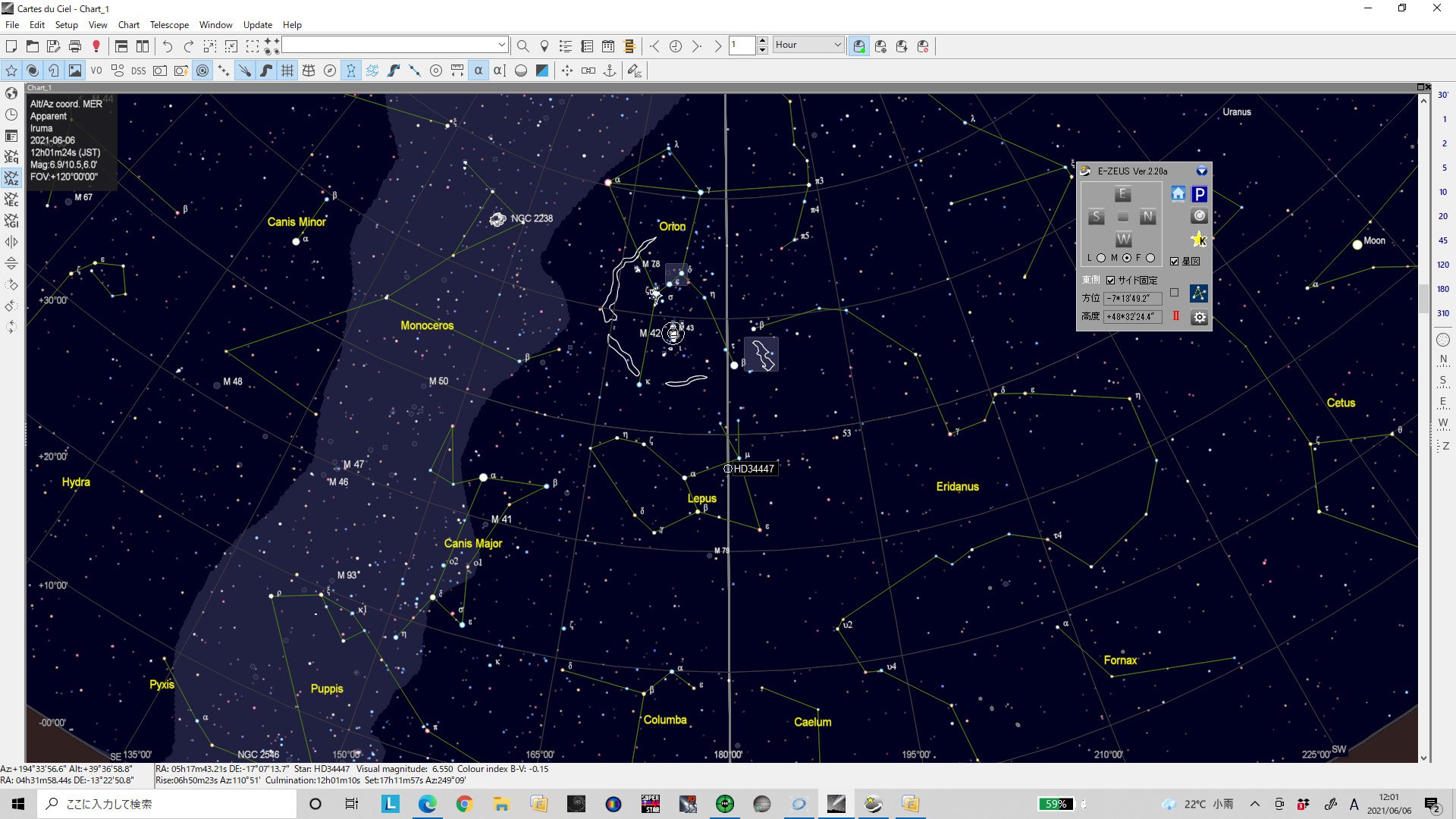
・ASCOM driver for E-ZEUS2で自動導入可能。
・追加カタログを入れるとDSO狙いにも使える。
下記は追加で入れたカタログ。
DSO-catalogs
SkyChart-data-Pictures-4.0-3421
Stars-catalogs
UCAC4-catalog-V2-Equator
UCAC4-catalog-V2-North
*GAIAデータは大きすぎるので入れませんでした。
これで16等星までの恒星、PGC天体などのDSOまで出せるようになりました。
主な天体やNGC天体は画像も出ます。


ここまで出せればステラ10の代わりに使えるし、SuperStarVの軽さも
備えた”現場で使えるソフト”になりますね。
写野のコーディネートもできます。
これは1220mmの焦点距離にASI183MMを組み合わせた場合。
DSS画像もDLできます。
一晩に3~5対象程度の撮像であれば、N.I.N.AでPlateSolveまで
やる意味はありません。また天球上のアチコチに指向させる場合、
完全に目を離せないというのもあります。
星図上でカーソルが動いて行くのも分かりやすいので、
このような使い方ではCiel + ASCOM_Telescope制御が良いかな。
その場合、N.I.N.Aは撮像ソフトに徹する使い方となります。
・300FNは30.5cmF4の短焦点ニュートン式反射鏡筒です。
・短焦点ニュートン式反射鏡筒では、無駄な光路遮蔽を減らす
ため、斜鏡をオフセット配置しなければなりません。
・オフセット配置された斜鏡である以上、レーザとコリメータ
で光軸が一致するように調整しなければなりません。
完全に光軸が合っている状態。
ドローチューブの偏りは、カメラの撮影位置によるもの。
中央のぼやけた黒点は5mmオフセットポイント。
やや右側のぼやけた黒点は斜鏡のセンターマーク。
中央に主鏡のセンターマーク◎が見える。
コリメーションアイピースで見たところ。
ハッキリした十字がスパイダー。
ぼけた十字がコリメーションアイピース内の十字。
向かって右手が主鏡側。
上記状態でのレーザ位置。
これは主鏡のセンターマークへ当たっているところ。
これは、主鏡から戻って来たレーザ光。
光軸調整ツール。
レーザコリメータはVブロックで回転させ、芯ずれ無き事を確認済。
斜鏡のオフセット位置決め用型紙。
完璧です!
さぞかしスバラシイ星像と、フラットな像面を見せてくれることでしょう!
-----------------------
っと、
まあ、分かったようなことを当然のごとく、偉そうに書きましたけど、
ココまでの道のりは長かったあ~~(*_*)
えっ!? アンタはニュートン反射の光軸合わせにも苦労
していたんかい!!
って聞こえて来そうですけどね、そりゃあ斜鏡のオフセットも
無い、しっかりと作り込まれたF8鏡筒ならば簡単なのですよ。
昨今の短焦点ニュートン反射鏡筒は、ほぼ全数が何らかの
斜鏡オフセットを施されています。
1.斜鏡ごと接眼部と反対側へオフセット。
2.斜鏡だけを45度のままスライドさせてオフセット。
3.1.と2.の組合せ。
300FNは2.の方法で斜鏡を”スライドオフセット”してあります。
F2.8などの超明るい鏡筒では3.を採用するでしょう。
300FNの光路図はこんな感じ。
主鏡から852mm付近で90度に折り曲げ、鏡筒面から201mm付近に
焦点面が配置されています。
この場合、主光束をカバーするには短径97.58[mm]の大きな斜鏡を
12[mm]スライドオフセット配置しなければなりません。
実際の短径は88[mm](メッキ面87[mm])、長径124[mm](メッキ面122[mm])
となっています。
仕様上はオフセットされていることになっていますが、
写真に撮ってみると・・・うーん、あまりオフセットされていない?
裸眼で見ると錯覚もあり、大きく左側にオフセットされているように
感じます。購入当初より気付いてはいましたが、金尺で斜鏡ホルダー
などを図っていました。おおよそのオフセットを4.5[mm]と決め、
√2X4.5=6.36[mm]として斜鏡に黒点を打って光軸調整を実施して
来ました。
以前より、光軸調整はコリメーションアイピースで実施しており、
その場合には概ね良好な結果を得ていました。
フルサイズのK-1で撮っても、周辺の星像乱れはあるものの納得
出来る範囲に収まっていました。
ところが、
ここ数年は撮影現場でレーザを使って再調整を実施しており、
これによって以前よりも星像が悪化していることに気付きました。
実際、コリメーションアイピースで光軸を合わせた後、
レーザで確認すると結構なズレがあったのです。
まあこれは、
接眼部が鏡筒中心を正確に向いていないのだろう・・・
とか、
主鏡セルが鏡筒に対して正確に組付けられていないのだろう・・
などと思っておりました。
しかし、
最近の粉DSO撮像をやればやる程、
ラッキーなイメージングをやればやる程、
微小な星像の乱れが看過出来なくなって来ました。
そもそも、何故レーザとコリメータで位置がズレるのかを確かめる
必要がありました。
アホか!って思われても構いませんよ。
恥を承知で備忘録として貼っておきますよ。
2021/06/18 追記
上記画像中に、
”斜鏡のオフセット貼りが何mmであれ、コリメーションアイピースで
センタリングすれば、真の斜鏡位置となる。”
とありますが、これは間違いでした。
コリメーションアイピースだけで、オフセット量不明の鏡筒を
光軸調整することはできません。
・斜鏡を取り外して定盤にねじ止めし、正確に”メッキ面”の
オフセット量を測定した。(3回)
|
+->オフセットは6.36[mm]ではなく、4.95[mm]だった。
・接眼部取付位置に対するオフセット量が5.5[mm]少なかった。
そのため、斜鏡と斜鏡に映った主鏡の位置がズレることが判明。
|
+->ズレていて正しいと言う、教科書には無い現実。
・接眼部から見た斜鏡の左側の無メッキ部(砂ずりコバ)+
斜鏡ホルダーの厚さ分が鏡面同様に円形に観測されており、
ここも含めて斜鏡の外観であると見誤っていた。
|
+->コレが一番のクセ者だった。
と言う事で、一から定量的にやり直してみました。
1.コリメーションアイピースで斜鏡の4.95[mm]オフセット点が
ドローチューブセンターに来るように調整。
この時、スパイダー十字とコリメーションアイピース内十字
が一致するようにすると、ドローチューブセンターに対する
斜鏡の光軸方向の配置、回転も決まる。
2.主鏡センターマークがコリメーションアイピースの中心に
来るように調整する。
3.再度斜鏡側を調整する。
4.再度主鏡側を調整する。
-------------
ここまでで、十分に光軸が合っています。
なーんだ、当たり前田のクラッカーかよ!!って思うでしょ?
だけどさあ~、斜鏡のコバまで含めて斜鏡外観と見誤ったり、
そもそも、オフセットが約5.5[mm]も違っていたら迷いますよ。
いくら調整しても斜鏡オフセットの黒点に乗って来ないし、
乗せてしまうとレーザとの位置ズレが激しいし・・・
それでも、レーザで調整するよりはコリメーションアイピース
だけでやっていた時代の方が良好だった訳です。
レーザで現場再調整をやってしまうと、接眼部平面に対して
光軸がやや曲がってしまっていた訳ですね。
これは、
斜鏡のオフセット位置がどうであれ、
ドローチューブ中心線と主鏡の光軸線の交わりポイントが
1点しか存在しない事に由来します。
コリメーションアイピースだと、それでもかなり良好に光軸が
合っていました。オフセット位置さえ間違えずに黒点を打って
いれば、それだけで十分に実用になるでしょう。
一方、
レーザだけで調整を始めた場合、
一番大切なドローチューブ中心線に対する斜鏡の光軸上配置が
いくらでもOKになってしまいます。
例えば2[mm]主鏡側に寄り過ぎていても、また、2[mm]筒先側に
寄り過ぎていても、斜鏡を調整すれば、いくらでも主鏡の
センターポイント◎へレーザを落とせます。
|
+->この段階で、既に光軸は曲がっています。
曲がった光軸に対して主鏡をいじって接眼部へレーザが戻って
来ても、それでは撮像面が盛大に傾いて片ボケになる道理です。
----------------------
<レーザとコリメータで位置がズレる原因>
・斜鏡のオフセット位置が不正確であった。
・斜鏡の外観を見誤っていた。
以上2点を正したことにより、冒頭画像の様にスッキリと理屈通り
の光軸調整が出来るようになりました。
これで、次回からは現場でもビビらずにレーザで微修正が出来ます。
主鏡の微修正をレーザでやると楽ですからなねえ~(^^♪
----------------------
これだけ固めて尚、全方向振り回しで30[μm]動く・・・
美しい星像を求めて・・・
2021/06/14 追記
1.オフセット斜鏡では正しく打点し、そこへ合わせ込む必要がある。
これは、コリメーション・アイピースでもレーザでも同様である。
2.市販品が正しく作り込まれていることは稀である。
3.最大限合わせ込んで尚、APSC以上ではスケアリング機構が必須である。
4.ニュートン式反射鏡筒では、主光束を100%カバーする大きな斜鏡で
ない限り、画面右側の光量が落ちる。接眼部の配置精度もあり、
光量中心や光量の偏りに神経質になり過ぎない。
現状、300FNの真の斜鏡オフセット量は4.95[mm]であり、
コリメーション・アイピースとレーザで光軸が一致している。
逆に言えば、斜鏡のオフセットが何ミリであれ、コリメーション・
アイピースとレーザで光軸が一致すれば、それが正しい斜鏡配置である。
接眼部や鏡筒精度は仕方なく受け入れ、不足であればスケアリング機構を
設けるしかない。
プライムフォーカスや屈折式望遠鏡は良いねえ~・・・
仮眠中にN.I.N.AのAutoSequenceで撮影したM57です。
等倍トリミングあり、処理強め、StarSharp無し。
L=30X60s , RGB=each 10X60s , 60min Total
------------------------------------------
撮影日時:2021/05/30
撮影場所:入笠山天体観測所 標高1810m
天候:快晴、微風、夜露僅少
気温:***
星空指数:50(大きなお月様あり)
シーイング:2/5
撮像鏡筒:300FN, 30.5cm , F4 , fl=1220mm
カメラ :ZWO-ASI183MM_Pro (Sony IMX183CLK-J Back Side Illuminated CMOS 1inch)
FilterWheel:Orion Nautilus 1.25"X7 (LRGB撮像)
コマコレクター:SkyWatcher_CCF4
Gain:250
binning:2X2
冷却温度:-10℃
露光:1カット60sを基本とした
Dark:20枚
Flat:***
ファイルフォーマット:Fits
赤道儀:SkyMaxエルボ改_E-ZEUSⅡ仕様
ガイド:50mmF4ガイドスコープ + QHY5L-ⅡM+PHD2_Ver,2.6.9_dev4(MultiStarGuide)
極軸合わせ:SharpCap3.2_ProのPolar Align機能
電子ビューファインダーのSSAG+25mmF1.4を流用。
ASCOM Platform 6.5_SP1
撮像ソフト:N.I.N.A(32bit)
プラネソフト:Cartes du Ciel+ステラ10
現像ソフト:SI7
微調整:PhotoShopCC_2021
撮像用PC:Lenovo_C340_Win10_64bit , USB_3.1C
ガイド&FilterWheel用PCもC340 , USB_3.0_Gen1
------------------------------------------















