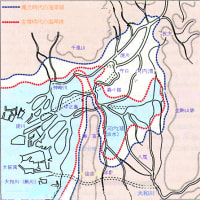4
ぼくは家へ帰っても、そのことはだまっていた。しかし、それはすぐに、お母さんにばれた。夕方、しげるのお母さんが、家へやってきたからだ。
玄関先での話を、ぼくは居間から耳をすましていた。おばさんは入ってくるなり、
「おたくは大丈夫だった?」
と、きいてきた。
「大丈夫って、なんのこと?」
「あら、きいてないの。きょう学校の帰りに、うちの子、かまれたのよ。」
「かまれたって、犬に?」
「それが犬じゃないのよ。人間によ!養護学校の子に、かまれたのよ。」
「えっ、ほんと?うちの子、なんにもそんなこと、はなさなかったわよ。でも、けがなんかしてないみたいだけど。」
「そう。そりゃよかったわね。うちのしげるなんか、あやうく、ふくらはぎの肉をくいちぎられるところだったのよ。」
「そんなにひどくかまれたの?」
「そうよ。思っただけでも、ぞっとするわよ。足がこんなにはれて、歩けやしないの。熱まで出て、うなされてるわよ。肉をくいちぎられてたら、あなた、歩けなくなってたかもしれないのよ。まったく、気ちがいざたよ。」
おばさんは、興奮をおさえきれないようすだった。
「まったく、気がしれないわ。肩がふれたからって、急にかみついてくるなんて。」
「肩がふれただけで?」
「そうよ、そうなのよ!」
「こんなところじゃなんだから、あがってよ。」
ふたりは部屋へあがってきた。居間にはいってきたおばさんは、ぼくを見つけると、
「あら、あんた、なんともなかったの。」
と、冷ややかにいった。それは、うちのしげるを、ひとりおいて逃げたんだってね、と非難しているように聞こえた。
「なんにもいわないから、わからないのよ。」
「いえないような、後ろめたいことがあるんでしょう。」
おばさんの言葉が、いやに耳にまとわりつく。
「しげるくん、かまえてけがしたっていうじゃない。いったい、何があったの。話なさいよ。」
「なにもないよ。あいつが、しげるの足をかんだだけだよ。」
「あら、かんだだけなんて、ちょっと冷たいんじゃない。」
おばさんは、どこまでもからんでくる。
「…………」
「あんたたちが、その子をいじめたんでしょう?」
「それがちがうのよ。しげるがいうにはね、肩がふれたので、生意気だってその子をおしたら、足がわるいでしょ、すぐころんじゃったらしいのよ。そしたら怒って、がぶりよ。そうなんでしょう?」
しげるの話は、ずいぶんとこちらの悪いところが省略されていた。けれども、ぼくにとっても、そのほうが都合が良かったから、「うん」と、こたえた。
「そりゃねぇ、最初におしたしげるのほうが悪いわよ。だけど、かみつくことないじゃない。それも、肉がちぎれそうになるまでよ。病院へつれていってくださったお年よりがいっていたわよ。まるで狂犬だって。すごい力よ。体はわるいくせに、力はあるのねぇ。手加減できないのよ。バカだから。しげるはショックで、熱までだしてるわよ。もう、腹が立つやら、くやしいやら。そいつが目の前にいたら、思いっきりかみついてやりたいくらいだわよ。」
おばさんは、はなせばはなすほど、気が高ぶるようすだった。
「そいでね、お年寄りがよってかかって、やっとのことで、しげるをたすけだしたんだけど、その子ったら、あやまれといってもあやまるどころが、くってかかったそうよ。まったくひどいじゃない。そんなやつが、このあたりをうろついているんじゃ、安心して子どもを外へだせやしないわよ。そうでしょ。」
「そうよねぇ。ほんとに、こわいわ。」
ぼくは、しげるがどういう具合に話をしたのか、だいたい察しがついた。
買い食いをしたことも、あいつの足を引っかけて、たおすカケをしたことも、公園の中まで追いかけて、三人で襲ったことも、一切隠されていた。それらは、ぼくとしても、隠しおいてもらいたいことだったけれど……。
ここはしげるの話に、あわせておくべきだと思った。
それからしばらくのあいだ、おばさんはぐちぐちと、同じ話をくりかえして、引きあげていった。帰りぎわ、ぼくに、
「先生には、二、三日、休むっていっといてちょうだい。」
それから、わざわざ付け加えてこういった。
「あんた、ほんとにけがなくてよかったねぇ。」
ぼくは家へ帰っても、そのことはだまっていた。しかし、それはすぐに、お母さんにばれた。夕方、しげるのお母さんが、家へやってきたからだ。
玄関先での話を、ぼくは居間から耳をすましていた。おばさんは入ってくるなり、
「おたくは大丈夫だった?」
と、きいてきた。
「大丈夫って、なんのこと?」
「あら、きいてないの。きょう学校の帰りに、うちの子、かまれたのよ。」
「かまれたって、犬に?」
「それが犬じゃないのよ。人間によ!養護学校の子に、かまれたのよ。」
「えっ、ほんと?うちの子、なんにもそんなこと、はなさなかったわよ。でも、けがなんかしてないみたいだけど。」
「そう。そりゃよかったわね。うちのしげるなんか、あやうく、ふくらはぎの肉をくいちぎられるところだったのよ。」
「そんなにひどくかまれたの?」
「そうよ。思っただけでも、ぞっとするわよ。足がこんなにはれて、歩けやしないの。熱まで出て、うなされてるわよ。肉をくいちぎられてたら、あなた、歩けなくなってたかもしれないのよ。まったく、気ちがいざたよ。」
おばさんは、興奮をおさえきれないようすだった。
「まったく、気がしれないわ。肩がふれたからって、急にかみついてくるなんて。」
「肩がふれただけで?」
「そうよ、そうなのよ!」
「こんなところじゃなんだから、あがってよ。」
ふたりは部屋へあがってきた。居間にはいってきたおばさんは、ぼくを見つけると、
「あら、あんた、なんともなかったの。」
と、冷ややかにいった。それは、うちのしげるを、ひとりおいて逃げたんだってね、と非難しているように聞こえた。
「なんにもいわないから、わからないのよ。」
「いえないような、後ろめたいことがあるんでしょう。」
おばさんの言葉が、いやに耳にまとわりつく。
「しげるくん、かまえてけがしたっていうじゃない。いったい、何があったの。話なさいよ。」
「なにもないよ。あいつが、しげるの足をかんだだけだよ。」
「あら、かんだだけなんて、ちょっと冷たいんじゃない。」
おばさんは、どこまでもからんでくる。
「…………」
「あんたたちが、その子をいじめたんでしょう?」
「それがちがうのよ。しげるがいうにはね、肩がふれたので、生意気だってその子をおしたら、足がわるいでしょ、すぐころんじゃったらしいのよ。そしたら怒って、がぶりよ。そうなんでしょう?」
しげるの話は、ずいぶんとこちらの悪いところが省略されていた。けれども、ぼくにとっても、そのほうが都合が良かったから、「うん」と、こたえた。
「そりゃねぇ、最初におしたしげるのほうが悪いわよ。だけど、かみつくことないじゃない。それも、肉がちぎれそうになるまでよ。病院へつれていってくださったお年よりがいっていたわよ。まるで狂犬だって。すごい力よ。体はわるいくせに、力はあるのねぇ。手加減できないのよ。バカだから。しげるはショックで、熱までだしてるわよ。もう、腹が立つやら、くやしいやら。そいつが目の前にいたら、思いっきりかみついてやりたいくらいだわよ。」
おばさんは、はなせばはなすほど、気が高ぶるようすだった。
「そいでね、お年寄りがよってかかって、やっとのことで、しげるをたすけだしたんだけど、その子ったら、あやまれといってもあやまるどころが、くってかかったそうよ。まったくひどいじゃない。そんなやつが、このあたりをうろついているんじゃ、安心して子どもを外へだせやしないわよ。そうでしょ。」
「そうよねぇ。ほんとに、こわいわ。」
ぼくは、しげるがどういう具合に話をしたのか、だいたい察しがついた。
買い食いをしたことも、あいつの足を引っかけて、たおすカケをしたことも、公園の中まで追いかけて、三人で襲ったことも、一切隠されていた。それらは、ぼくとしても、隠しおいてもらいたいことだったけれど……。
ここはしげるの話に、あわせておくべきだと思った。
それからしばらくのあいだ、おばさんはぐちぐちと、同じ話をくりかえして、引きあげていった。帰りぎわ、ぼくに、
「先生には、二、三日、休むっていっといてちょうだい。」
それから、わざわざ付け加えてこういった。
「あんた、ほんとにけがなくてよかったねぇ。」