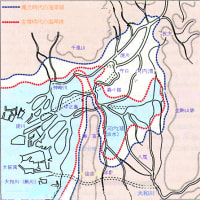3
翌日は肩透かしをくった。待っても待っても、あいつは来なかった。自分の番だと緊張していた一郎は、なかばほっとした気分だったに違いない。あいつはきっと、道をかえたに違いなかった。
その日から、ぼくたちは、獲物を追う猟犬の気分になった。
どこの学校の子か、家がどこなのかもわからなかった。けれども、あの道を通って帰るとしたら、およそのことは見当がつく。ぼくらは、毎日、道をかえて、しつこく探しまわった。
ぼくはぼくで、なんとしても、あのときのしかえしをしなくちゃと思っていた。しかし、三日間探しまわったけれども、あいつに出会わなかった。
四日目は、掃除当番で遅くなった。学校を出るとき、ぼくはふと思った。あいつは道をかえたのではなく、時間をずらしたのではないかと。
「そうだよ。きっと、そうだ。いってみようよ。」
一郎がいきおいこんでいった。
「よし、今からいってみようぜ。」
と、しげるもうなずいた。
ぼくの推理は、はたして当たっていた。ぼくらが、公園の植え込みから、二十分くらい見張っていると、あいつの姿が、道の向こうに見えたのだ。
「きた。」
息をひそめて、あいつが近づくのを待った。二、三十メートルに近づいたのを見計らって、ぼくらは道へとびだしていった。あいつは、すぐに気がついたらしく、立ちどまってこちらを見ていた。ぼくらは一郎を先頭にして、ゆっくり歩いていった。あいつにも、ぼくらにも、これからなにが始まろうとしているか、わかっていた。突然、あいつはくるりと背を向けた。そして、急いで、道をひきかえし始めたのだ。
「おい、逃げるぞ!」
しげるがどなった。ぼくらは後を追った。
あいつがいくらがんばっても、足の速さで、ぼくらにかなうはずがなかった。公園の入り口近くで、ぼくらは追いついた。
すると、あいつは助けを求めて、公園の中へ逃げ込もうとした。
公園の広場では、老人たちがゲートボールを楽しんでいた。あいつはそっちへ向かって、口をパクパク動かした。しかし、声にはならず、のどの奥のほうで、アぉーと、かすかな音がもれただけだった。ぼくらは、とりかこんでこづいた。しげるがあいつの足をけった。
「バカ!」
一郎も足をけとばした。
「このやろう!」
しげるが、頭を平手でたたいた。ぼくも負けずにたたいた。あいつは、それでも泣かなかった。抵抗もせず、唇をかんでいた。
ぼくらは大胆になり、荒っぽくなった。しげるが、ドンと肩をつくと、あいつは無様にひっくり返った。ぼくらは頭を殴りつけ、背中をけり続けた。
しげるが、あいつの手の甲を、右の足で踏みにじったときだった。突然、くるったように、目の前のしげるの足に、むしゃぶりついてきた。そして、むき出しのしげるのふくらはぎに、がぶりとくらいついたのだ。
しげるは、一瞬、何が起きたのかわからなかったのか、ぽかんとつっ立って、あいつを見下ろしていた。それから、血相をかえて、
「いたい!はなせ、はなせっ!」
と、叫びながら、あいつの頭をぽかぽか殴りつけた。
けれども、あいつの口はひらかなかった。しげるは火がついたように泣き叫んだ。
「いたいよう、いたいよう!」
ぼくと一郎は、あわててあいつの体をひきはなそうと、後ろから引っ張ったが、むだだった。
しげるの激しい泣き声に、なにごとかと、老人たちがあつまってきた。
「いたいよう、いたいよう。」
しげるは泣き叫んでいる。その足に、顔中、汗とほこりにまみれた男の子が、しがみついていた。そして、その子が、しげるの足にかみついているのを見た老人たちは、おどろいて口々にさけんだ。
「これ、はなしなさい!」
「はなせといったら、はなさんか!こらっ、はなせ!」
そして、ぼくと一郎がやったように、あいつの体を引き離しにかかった。あいつはしぶとくくらいつき、しげるは泣きわめきつづけていた。
「強情な子だ。」
「はやくしないと、肉が食いちぎられてしまうぞ。」
そのとき、老人のひとりが、棒きれをひろってきた。あいつの歯と歯の間に、その棒きれが無理やり突っ込まれた。そうして、やっとのことで、しげるの右足は開放されたのだった。
そのとたん、あいつは、地面を手でたたきながら、くるったように泣き出した。
しげるはしげるで、かまれた足をかかえて、ごーごーと泣いていた。ふくらはぎは紫色にはれあがり、歯のあとがくっきりとついていた。
「こりゃひどい傷だ。すぐ病院へつれていかなきゃ。」
「いったいどうしたんだ。え、おまえたち。」
ぼくらは、しどろもどろになりながらいった。
「こいつが急にかみついたんだよ。」
すると、あいつはさっと顔をあげた。そして、ぼくらを指差すと、なにやらわめいた。なにをいっているのか、わからなかった。が、そのことで、老人たちはその子が障害児だということに、やっと気がついたようだった。
「おまえたち、なにをしたんだ?」
老人の言葉がきつくなって、風向きがかわった。一郎が突然泣きだし、逃げだした。ぼくはすっかりあわてて、
「知らないよ。なんにも知らないよ!」
と、さけぶと、半分泣きたい気持ちで、一郎のあとを追ってかけだした。
翌日は肩透かしをくった。待っても待っても、あいつは来なかった。自分の番だと緊張していた一郎は、なかばほっとした気分だったに違いない。あいつはきっと、道をかえたに違いなかった。
その日から、ぼくたちは、獲物を追う猟犬の気分になった。
どこの学校の子か、家がどこなのかもわからなかった。けれども、あの道を通って帰るとしたら、およそのことは見当がつく。ぼくらは、毎日、道をかえて、しつこく探しまわった。
ぼくはぼくで、なんとしても、あのときのしかえしをしなくちゃと思っていた。しかし、三日間探しまわったけれども、あいつに出会わなかった。
四日目は、掃除当番で遅くなった。学校を出るとき、ぼくはふと思った。あいつは道をかえたのではなく、時間をずらしたのではないかと。
「そうだよ。きっと、そうだ。いってみようよ。」
一郎がいきおいこんでいった。
「よし、今からいってみようぜ。」
と、しげるもうなずいた。
ぼくの推理は、はたして当たっていた。ぼくらが、公園の植え込みから、二十分くらい見張っていると、あいつの姿が、道の向こうに見えたのだ。
「きた。」
息をひそめて、あいつが近づくのを待った。二、三十メートルに近づいたのを見計らって、ぼくらは道へとびだしていった。あいつは、すぐに気がついたらしく、立ちどまってこちらを見ていた。ぼくらは一郎を先頭にして、ゆっくり歩いていった。あいつにも、ぼくらにも、これからなにが始まろうとしているか、わかっていた。突然、あいつはくるりと背を向けた。そして、急いで、道をひきかえし始めたのだ。
「おい、逃げるぞ!」
しげるがどなった。ぼくらは後を追った。
あいつがいくらがんばっても、足の速さで、ぼくらにかなうはずがなかった。公園の入り口近くで、ぼくらは追いついた。
すると、あいつは助けを求めて、公園の中へ逃げ込もうとした。
公園の広場では、老人たちがゲートボールを楽しんでいた。あいつはそっちへ向かって、口をパクパク動かした。しかし、声にはならず、のどの奥のほうで、アぉーと、かすかな音がもれただけだった。ぼくらは、とりかこんでこづいた。しげるがあいつの足をけった。
「バカ!」
一郎も足をけとばした。
「このやろう!」
しげるが、頭を平手でたたいた。ぼくも負けずにたたいた。あいつは、それでも泣かなかった。抵抗もせず、唇をかんでいた。
ぼくらは大胆になり、荒っぽくなった。しげるが、ドンと肩をつくと、あいつは無様にひっくり返った。ぼくらは頭を殴りつけ、背中をけり続けた。
しげるが、あいつの手の甲を、右の足で踏みにじったときだった。突然、くるったように、目の前のしげるの足に、むしゃぶりついてきた。そして、むき出しのしげるのふくらはぎに、がぶりとくらいついたのだ。
しげるは、一瞬、何が起きたのかわからなかったのか、ぽかんとつっ立って、あいつを見下ろしていた。それから、血相をかえて、
「いたい!はなせ、はなせっ!」
と、叫びながら、あいつの頭をぽかぽか殴りつけた。
けれども、あいつの口はひらかなかった。しげるは火がついたように泣き叫んだ。
「いたいよう、いたいよう!」
ぼくと一郎は、あわててあいつの体をひきはなそうと、後ろから引っ張ったが、むだだった。
しげるの激しい泣き声に、なにごとかと、老人たちがあつまってきた。
「いたいよう、いたいよう。」
しげるは泣き叫んでいる。その足に、顔中、汗とほこりにまみれた男の子が、しがみついていた。そして、その子が、しげるの足にかみついているのを見た老人たちは、おどろいて口々にさけんだ。
「これ、はなしなさい!」
「はなせといったら、はなさんか!こらっ、はなせ!」
そして、ぼくと一郎がやったように、あいつの体を引き離しにかかった。あいつはしぶとくくらいつき、しげるは泣きわめきつづけていた。
「強情な子だ。」
「はやくしないと、肉が食いちぎられてしまうぞ。」
そのとき、老人のひとりが、棒きれをひろってきた。あいつの歯と歯の間に、その棒きれが無理やり突っ込まれた。そうして、やっとのことで、しげるの右足は開放されたのだった。
そのとたん、あいつは、地面を手でたたきながら、くるったように泣き出した。
しげるはしげるで、かまれた足をかかえて、ごーごーと泣いていた。ふくらはぎは紫色にはれあがり、歯のあとがくっきりとついていた。
「こりゃひどい傷だ。すぐ病院へつれていかなきゃ。」
「いったいどうしたんだ。え、おまえたち。」
ぼくらは、しどろもどろになりながらいった。
「こいつが急にかみついたんだよ。」
すると、あいつはさっと顔をあげた。そして、ぼくらを指差すと、なにやらわめいた。なにをいっているのか、わからなかった。が、そのことで、老人たちはその子が障害児だということに、やっと気がついたようだった。
「おまえたち、なにをしたんだ?」
老人の言葉がきつくなって、風向きがかわった。一郎が突然泣きだし、逃げだした。ぼくはすっかりあわてて、
「知らないよ。なんにも知らないよ!」
と、さけぶと、半分泣きたい気持ちで、一郎のあとを追ってかけだした。