都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「フランダースの光」(Vol.1・ウーステイヌ) Bunkamura ザ・ミュージアム
Bunkamura ザ・ミュージアム(渋谷区道玄坂2-24-1)
「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」
9/4-10/24
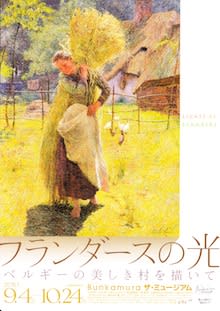
Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」へ行ってきました。
ちらしなどを見る限りでは、印象派風のそれこそ美しい作品ばかりが並んでいるのかと思ってしまいますが、実際には言わば一風変わった画家も多く登場するなかなか個性的な展覧会でした。そして全体の印象に触れる前に、その例として挙げておきたい画家が一人存在します。名はギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ(1881-1947)でした。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「悪しき種をまく人」1908年 油彩・板 個人蔵
そもそもこの展覧会は、フランダース地方ゲントの南方のラーテムと呼ばれる村に集まった画家たちを紹介するものですが、その中でもウーステイヌは象徴主義的な面が最も強いと言えるかもしれません。
この宗教的主題を借りた「悪しき種をまく人」(1908)の奇妙な画風には度肝を抜かれました。金色に光る荒野にはまさに種をまく人が大きく立ちはだかり、それを黒いカラスのような鳥が啄んでいます。作品のモデルは実在の農民とのことですが、顔の皺の質感までを執拗に追求した写実表現などにも大いに見入るものがありました。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「ミルク粥を食べる人」1911年 油彩・キャンバス 個人蔵
その顔の表現としてもさらに触れておきたいのが「ミルク粥を食べる人」(1911)です。テーブル上に置かれたミルクやパンの細密描写には彼が関心を寄せていたというルネサンス絵画を思わせるものがありますが、そこに殆ど唐突に出現する大きな顔面もまた奇異ではしないでしょうか。まさか「ベルギーの美しい村」を紹介する展覧会でこのような作品を見られるとは思いもよりませんでした。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「永遠に反射する光」1911年 油彩・キャンバス ヴァン・ビューレン庭園美術館
これら金色に光る絵画とは一転、月明かりを穏やかに捉えた「永遠に反射する光」(1911)もまた忘れられない一枚です。そのくすんだ色味をはじめ、独特な遠近感覚は、どこか日本画を連想させるものがないでしょうか。朧げな明かりは神秘的ですらありました。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「実り」1910年 油彩・キャンバス ヴァン・ビューレン庭園美術館
最後に果実に囲まれた大地で女性が寝そべる「実り」(1910)を挙げておきます。緑色のグラデーションも巧みな果実ではなく、むしろ豊満な肉体の女性こそこのタイトルの由来なのかもしれません。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「シント・マルテンス・ラーテムでの自画像」1900年 油彩・キャンバス 個人蔵
全体の感想は別エントリでまとめたいと思いますが、「フランダースの光」展はともかくも一筋縄ではいかない展覧会でした。お見逃しなきようご注意下さい。

図録表紙もウーステイヌの作品でした。Vol.2へ続きます。10月24日まで開催されています。
*関連エントリ
「フランダースの光」(Vol.2・全体の印象) Bunkamura ザ・ミュージアム
「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」
9/4-10/24
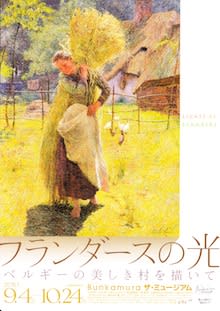
Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて」へ行ってきました。
ちらしなどを見る限りでは、印象派風のそれこそ美しい作品ばかりが並んでいるのかと思ってしまいますが、実際には言わば一風変わった画家も多く登場するなかなか個性的な展覧会でした。そして全体の印象に触れる前に、その例として挙げておきたい画家が一人存在します。名はギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ(1881-1947)でした。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「悪しき種をまく人」1908年 油彩・板 個人蔵
そもそもこの展覧会は、フランダース地方ゲントの南方のラーテムと呼ばれる村に集まった画家たちを紹介するものですが、その中でもウーステイヌは象徴主義的な面が最も強いと言えるかもしれません。
この宗教的主題を借りた「悪しき種をまく人」(1908)の奇妙な画風には度肝を抜かれました。金色に光る荒野にはまさに種をまく人が大きく立ちはだかり、それを黒いカラスのような鳥が啄んでいます。作品のモデルは実在の農民とのことですが、顔の皺の質感までを執拗に追求した写実表現などにも大いに見入るものがありました。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「ミルク粥を食べる人」1911年 油彩・キャンバス 個人蔵
その顔の表現としてもさらに触れておきたいのが「ミルク粥を食べる人」(1911)です。テーブル上に置かれたミルクやパンの細密描写には彼が関心を寄せていたというルネサンス絵画を思わせるものがありますが、そこに殆ど唐突に出現する大きな顔面もまた奇異ではしないでしょうか。まさか「ベルギーの美しい村」を紹介する展覧会でこのような作品を見られるとは思いもよりませんでした。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「永遠に反射する光」1911年 油彩・キャンバス ヴァン・ビューレン庭園美術館
これら金色に光る絵画とは一転、月明かりを穏やかに捉えた「永遠に反射する光」(1911)もまた忘れられない一枚です。そのくすんだ色味をはじめ、独特な遠近感覚は、どこか日本画を連想させるものがないでしょうか。朧げな明かりは神秘的ですらありました。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「実り」1910年 油彩・キャンバス ヴァン・ビューレン庭園美術館
最後に果実に囲まれた大地で女性が寝そべる「実り」(1910)を挙げておきます。緑色のグラデーションも巧みな果実ではなく、むしろ豊満な肉体の女性こそこのタイトルの由来なのかもしれません。

ギュスターヴ・ヴァン・ド・ウーステイヌ「シント・マルテンス・ラーテムでの自画像」1900年 油彩・キャンバス 個人蔵
全体の感想は別エントリでまとめたいと思いますが、「フランダースの光」展はともかくも一筋縄ではいかない展覧会でした。お見逃しなきようご注意下さい。

図録表紙もウーステイヌの作品でした。Vol.2へ続きます。10月24日まで開催されています。
*関連エントリ
「フランダースの光」(Vol.2・全体の印象) Bunkamura ザ・ミュージアム
コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )
| « 町田市立国際... | 束芋 「ててて... » |










ウースティヌが一番印象に残りました。
いろんな画家が住んでいたのですね。それぞれ
個性が強く、
圧倒されてしまいました。
ウースティヌ一人をまず取り上げてくださって
とてもよかったです。