都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」 東京都美術館
東京都美術館
「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」
2019/2/9~4/7
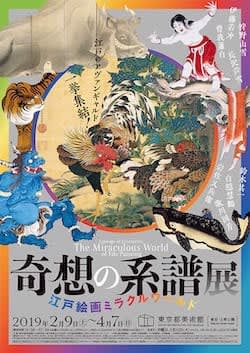
東京都美術館で開催中の「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」を見てきました。
1970年、美術史家の辻惟雄が著した「奇想の系譜」は、当時、傍流であった江戸の6名の絵師を「奇想」の概念に位置付け、美術史の研究に新たな視点をもたらしました。
「奇想の系譜」の絵師の作品が一堂にやって来ました。その絵師とは、岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳で、さらに今回の展覧会に際して、白隠慧鶴と鈴木其一が加えられました。
トップバッターは、2016年の展覧会で空前のブームを引き起こした伊藤若冲でした。象と鯨が対峙した「象と鯨図屏風」や、鶏が得意げにポーズを構える「鶏図押絵貼屏風」が並ぶ中、目を引いたのが「旭日鳳凰図」で、岸辺の岩の上で羽を広げる鳳凰を極彩色で表していました。ちょうど動植綵絵の2年前に制作された作品で、サイズが一回り大きく、ハート形の尾の模様や妖艶な表情の顔、さらには粘り気を帯びたような波など、まさに若冲ならではの描写を見せていました。
このほか、雨の中、屈曲する竹を水墨で描いた「雨中の竹図」や、糸瓜の蔦の先にカマキリが乗った「糸瓜群虫図」も興味深い作品でした。ともかく先の回顧展にて全貌が明かされた若冲でしたが、新出の「鶏図押絵貼屏風」や、所蔵館以外では初公開となった「宇宙の竹図」など、見慣れない作品もあり、また改めて絵師の魅力に接することが出来ました。

曽我蕭白「雪山童子図」 明和元年(1764)頃 三重・継松寺
続くのが曽我蕭白で、チラシ表紙でも目立つ「雪山童子図」が、一際、異彩を放っていました。同作は、釈迦が前世で雪山童子として修行した際、鬼に姿を変えた帝釈天から熱意を試される場面を表したもので、鬼の青と童子の腰布の赤が、鮮烈なコントラストを描いていました。蕭白の35歳の頃の作品と言われています。
「唐獅子図」も異様な迫力を見せていて、高さは2メートル超の大画面に、口を開く阿形と、口を閉じた吽形の唐獅子が相対していました。ともかく乱れるような筆遣いが特徴的で、獰猛な獅子も、何かに怯えているような姿に見えなくもありません。「ふざける」(解説より)ような落款も、どこか滑稽でした。

長沢芦雪「群猿図襖」 寛政7年(1795) 兵庫・大乗寺
「京のエンターテイナー」として、一昨年の愛知での回顧展も話題を集めた、長沢芦雪にも優品が揃っていました。兵庫の大乗寺に伝わり、東日本初公開となった「群猿図襖」は、海辺の岩場の猿を表したもので、その生態を写実的に捉えつつも、擬人化したような人懐っこい姿を見せていました。
「白象黒牛図屏風」も機知に富んだ作品で、右に白い象、そして左に黒い牛を、ともに画面からはみ出さんとばかりに描き、さらにそれぞれ小さな烏と仔犬を加えていました。何よりも、安心しきった様子で笑みを浮かべる仔犬がすこぶる可愛らしく、もはや絵の主人公と呼んでも差し支えないかもしれません。ここに芦雪は、黒と白、そして大と小を対比して表現しました。
奇想で最も絵が上手い絵師とは、岩佐又兵衛かもしれません。とりわけ凄まじいのが「山中常盤物語絵巻」で、源義経伝説を元に、母の常盤御前の仇討ちを12巻に描いていました。(会期中、第4巻と5巻を公開。)うち、第4巻は、山中の宿で常盤御前が襲われる場面を示していて、まさに刀を胸に突きつけられ、血を垂らしては仰向けで横たわる御前の姿を、極めて臨場感のある形で表していました。
また「堀江物語絵巻」にも、凄惨な殺害場面が登場していて、鮮血が吹き飛び、身体が裂ける姿を、何らためらうことなく、克明に示していました。ともかく血みどろを含め、着衣の紋様までをも執拗までに細かく描いていて、そこには確かに絵師の「執念のドラマ」(解説より)が現れていました。

狩野山雪「梅花遊禽図襖」 寛永8年(1631) 京都・天球院
狩野山雪では「梅花遊禽図襖」が目立っていました。金地を背に、一本の老いた梅が幹を左へのばしていて、花を咲かせつつ、紅葉した蔦が絡んでいました。梅の花と紅葉という、春と秋の異なった季節を1つの画面に落とし込んだ作品で、うねっては屈曲する幹は、まるで悶えているかのようでした。
目をぎょろりと開いては、上を見やる達磨を描いたのが、白隠慧鶴の「達磨図」で、80歳を超えた最晩年の作品と言われています。一見、即興的な筆触ながらも、髭や瞼、さらには着衣など、硬軟のある線を自在に使い分けていて、量感のある達磨を巧みに表していました。なお今回、新たに奇想に位置付けられた白隠は、近年、若冲や蕭白、芦雪などの18世紀の京都の絵師に影響を与え、一連の個性的な表現の起爆剤になったと指摘されているそうです。

鈴木其一「百鳥百獣図」(部分) 天保14年(1843) 米国・キャサリン&トーマス・エドソンコレクション
同じく新たに奇想の絵師となった鈴木其一では、アメリカより初めて里帰りした「百鳥百獣図」に魅せられました。四季の草花が広がる野山の中、鳥やたくさんの動物を事細かに描いた作品で、どこか若冲の画風を思わせてなりません。右に百鳥、左に百獣を配した双幅の作品で、特に百獣図では、前景の白い象が目立っていました。一般的な琳派のイメージとは一線を画していて、其一像に新たな視点を呼び込む作品と言えるかもしれません。
ラストは奇想で唯一の浮世絵師である歌川国芳でした。ここでは人気の「相馬の古内裏」などの浮世絵とともに、「一ツ家」や「火消千組の図」といった絵馬も目立っていて、大画面の肉筆にも充実した作品を生み出した、国芳の高い画力に改めて感じ入るものがありました。
展示替えの情報です。会期中、一部の作品が入れ替わります。
「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」出品リスト(PDF)
前期:2月9日(土)~3月10日(日)
後期:3月12日(火)~4月7日(日)
若冲は18点のうち7点、蕭白は12点中10点、芦雪は16点中4点、又兵衛は約20点のうち1点を除き全て入れ替えなど、絵師により差がありますが、大幅に作品が替わります。事実上、前期と後期をあわせて1つの展覧会と言って差し支えありません。(場面替えもあり。)

最後に会場の状況です。会期3日目、2月11日の祝日に出かけて来ました。美術館に到着したのは14時頃でした。
チケットブースに僅かな待機列こそあったものの、入場への待ち時間はありませんでした。また場内は、最初の若冲と、ラストの国芳の展示室こそやや混み合っていたものの、ほかは思いの外にスムーズで、どの作品も最前列で鑑賞出来ました。何かと混みがちな絵巻の展示も、少し並ぶと、難なく見ることが出来ました。
現在のところ、実際に入場が規制されたのは、シルバーデーのみで、土日に関しても制限は行われていません。
とはいえ、おそらくは今年、最も注目を集める江戸絵画展であることは間違いありません。会期終盤へ向かって混雑することも予想されます。混雑情報については専用のアカウント(@kisoukonzatsu)がリアルタイムでこまめに発信しています。まずは早めに観覧されることをおすすめします。
あまりにも小さな芦雪の「方寸五百羅漢図」や、実に細密な其一の「百鳥百獣図」など、肉眼では細部が判別しにくい作品も少なくありません。よって単眼鏡が有用でした。
今でこそすっかり人気を得た奇想の絵師でしたが、こうして作品を並び立て見られる機会は殆どありませんでした。あえて比べることで、奇想の括りよりも、各絵師の個性なりが際立って見えるかもしれません。

4月7日まで開催されています。
「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」(@kisou2019) 東京都美術館(@tobikan_jp)
会期:2019年2月9日(土)~4月7日(日)
時間:9:30~17:30
*毎週金曜日、及び11月1日(木)、3日(土・祝)は20時まで。
*入館は閉館の30分前まで。
休館:月曜日、2月12日(火)。但し2月11日(月・祝)、4月1日(月)は開館。
料金:一般1600(1400)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、65歳以上1000(800)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。
*( )は20名以上の団体料金。
*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。
*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)
住所:台東区上野公園8-36
交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。
「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」
2019/2/9~4/7
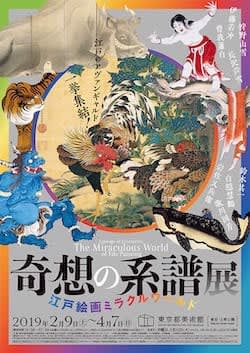
東京都美術館で開催中の「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」を見てきました。
1970年、美術史家の辻惟雄が著した「奇想の系譜」は、当時、傍流であった江戸の6名の絵師を「奇想」の概念に位置付け、美術史の研究に新たな視点をもたらしました。
「奇想の系譜」の絵師の作品が一堂にやって来ました。その絵師とは、岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳で、さらに今回の展覧会に際して、白隠慧鶴と鈴木其一が加えられました。
トップバッターは、2016年の展覧会で空前のブームを引き起こした伊藤若冲でした。象と鯨が対峙した「象と鯨図屏風」や、鶏が得意げにポーズを構える「鶏図押絵貼屏風」が並ぶ中、目を引いたのが「旭日鳳凰図」で、岸辺の岩の上で羽を広げる鳳凰を極彩色で表していました。ちょうど動植綵絵の2年前に制作された作品で、サイズが一回り大きく、ハート形の尾の模様や妖艶な表情の顔、さらには粘り気を帯びたような波など、まさに若冲ならではの描写を見せていました。
このほか、雨の中、屈曲する竹を水墨で描いた「雨中の竹図」や、糸瓜の蔦の先にカマキリが乗った「糸瓜群虫図」も興味深い作品でした。ともかく先の回顧展にて全貌が明かされた若冲でしたが、新出の「鶏図押絵貼屏風」や、所蔵館以外では初公開となった「宇宙の竹図」など、見慣れない作品もあり、また改めて絵師の魅力に接することが出来ました。

曽我蕭白「雪山童子図」 明和元年(1764)頃 三重・継松寺
続くのが曽我蕭白で、チラシ表紙でも目立つ「雪山童子図」が、一際、異彩を放っていました。同作は、釈迦が前世で雪山童子として修行した際、鬼に姿を変えた帝釈天から熱意を試される場面を表したもので、鬼の青と童子の腰布の赤が、鮮烈なコントラストを描いていました。蕭白の35歳の頃の作品と言われています。
「唐獅子図」も異様な迫力を見せていて、高さは2メートル超の大画面に、口を開く阿形と、口を閉じた吽形の唐獅子が相対していました。ともかく乱れるような筆遣いが特徴的で、獰猛な獅子も、何かに怯えているような姿に見えなくもありません。「ふざける」(解説より)ような落款も、どこか滑稽でした。

長沢芦雪「群猿図襖」 寛政7年(1795) 兵庫・大乗寺
「京のエンターテイナー」として、一昨年の愛知での回顧展も話題を集めた、長沢芦雪にも優品が揃っていました。兵庫の大乗寺に伝わり、東日本初公開となった「群猿図襖」は、海辺の岩場の猿を表したもので、その生態を写実的に捉えつつも、擬人化したような人懐っこい姿を見せていました。
「白象黒牛図屏風」も機知に富んだ作品で、右に白い象、そして左に黒い牛を、ともに画面からはみ出さんとばかりに描き、さらにそれぞれ小さな烏と仔犬を加えていました。何よりも、安心しきった様子で笑みを浮かべる仔犬がすこぶる可愛らしく、もはや絵の主人公と呼んでも差し支えないかもしれません。ここに芦雪は、黒と白、そして大と小を対比して表現しました。
【又兵衛作品 山中常盤物語絵巻 第四巻】源義経伝説のうち、母・常盤御前の仇討を題材とした全12巻の極彩色絵巻📜山中の宿で常盤御前が賊に襲われ、殺されてしまう悲劇の場面😨本展特別顧問 #辻惟雄 先生が、修士論文のテーマに選んだ作品です📝#奇想の系譜展 #東京都美術館 #又兵衛 #前期展示 pic.twitter.com/xO5rTqrCo1
— 【公式】奇想の系譜展@東京都美術館 (@kisou2019) 2019年2月17日
奇想で最も絵が上手い絵師とは、岩佐又兵衛かもしれません。とりわけ凄まじいのが「山中常盤物語絵巻」で、源義経伝説を元に、母の常盤御前の仇討ちを12巻に描いていました。(会期中、第4巻と5巻を公開。)うち、第4巻は、山中の宿で常盤御前が襲われる場面を示していて、まさに刀を胸に突きつけられ、血を垂らしては仰向けで横たわる御前の姿を、極めて臨場感のある形で表していました。
また「堀江物語絵巻」にも、凄惨な殺害場面が登場していて、鮮血が吹き飛び、身体が裂ける姿を、何らためらうことなく、克明に示していました。ともかく血みどろを含め、着衣の紋様までをも執拗までに細かく描いていて、そこには確かに絵師の「執念のドラマ」(解説より)が現れていました。

狩野山雪「梅花遊禽図襖」 寛永8年(1631) 京都・天球院
狩野山雪では「梅花遊禽図襖」が目立っていました。金地を背に、一本の老いた梅が幹を左へのばしていて、花を咲かせつつ、紅葉した蔦が絡んでいました。梅の花と紅葉という、春と秋の異なった季節を1つの画面に落とし込んだ作品で、うねっては屈曲する幹は、まるで悶えているかのようでした。
目をぎょろりと開いては、上を見やる達磨を描いたのが、白隠慧鶴の「達磨図」で、80歳を超えた最晩年の作品と言われています。一見、即興的な筆触ながらも、髭や瞼、さらには着衣など、硬軟のある線を自在に使い分けていて、量感のある達磨を巧みに表していました。なお今回、新たに奇想に位置付けられた白隠は、近年、若冲や蕭白、芦雪などの18世紀の京都の絵師に影響を与え、一連の個性的な表現の起爆剤になったと指摘されているそうです。

鈴木其一「百鳥百獣図」(部分) 天保14年(1843) 米国・キャサリン&トーマス・エドソンコレクション
同じく新たに奇想の絵師となった鈴木其一では、アメリカより初めて里帰りした「百鳥百獣図」に魅せられました。四季の草花が広がる野山の中、鳥やたくさんの動物を事細かに描いた作品で、どこか若冲の画風を思わせてなりません。右に百鳥、左に百獣を配した双幅の作品で、特に百獣図では、前景の白い象が目立っていました。一般的な琳派のイメージとは一線を画していて、其一像に新たな視点を呼び込む作品と言えるかもしれません。
ラストは奇想で唯一の浮世絵師である歌川国芳でした。ここでは人気の「相馬の古内裏」などの浮世絵とともに、「一ツ家」や「火消千組の図」といった絵馬も目立っていて、大画面の肉筆にも充実した作品を生み出した、国芳の高い画力に改めて感じ入るものがありました。
展示替えの情報です。会期中、一部の作品が入れ替わります。
「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」出品リスト(PDF)
前期:2月9日(土)~3月10日(日)
後期:3月12日(火)~4月7日(日)
若冲は18点のうち7点、蕭白は12点中10点、芦雪は16点中4点、又兵衛は約20点のうち1点を除き全て入れ替えなど、絵師により差がありますが、大幅に作品が替わります。事実上、前期と後期をあわせて1つの展覧会と言って差し支えありません。(場面替えもあり。)

最後に会場の状況です。会期3日目、2月11日の祝日に出かけて来ました。美術館に到着したのは14時頃でした。
チケットブースに僅かな待機列こそあったものの、入場への待ち時間はありませんでした。また場内は、最初の若冲と、ラストの国芳の展示室こそやや混み合っていたものの、ほかは思いの外にスムーズで、どの作品も最前列で鑑賞出来ました。何かと混みがちな絵巻の展示も、少し並ぶと、難なく見ることが出来ました。
現在のところ、実際に入場が規制されたのは、シルバーデーのみで、土日に関しても制限は行われていません。
【#奇想の系譜展 混雑状況】開催中の奇想の系譜展では、公式ツイッター@kisou2019の他に、@kisoukonzatsuにて混雑状況をお知らせしています。ご来館の際はぜひ参考にしてください。#東京都美術館 pic.twitter.com/4mGApcJXME
— 東京都美術館 (@tobikan_jp) 2019年2月19日
とはいえ、おそらくは今年、最も注目を集める江戸絵画展であることは間違いありません。会期終盤へ向かって混雑することも予想されます。混雑情報については専用のアカウント(@kisoukonzatsu)がリアルタイムでこまめに発信しています。まずは早めに観覧されることをおすすめします。
あまりにも小さな芦雪の「方寸五百羅漢図」や、実に細密な其一の「百鳥百獣図」など、肉眼では細部が判別しにくい作品も少なくありません。よって単眼鏡が有用でした。
今でこそすっかり人気を得た奇想の絵師でしたが、こうして作品を並び立て見られる機会は殆どありませんでした。あえて比べることで、奇想の括りよりも、各絵師の個性なりが際立って見えるかもしれません。

4月7日まで開催されています。
「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」(@kisou2019) 東京都美術館(@tobikan_jp)
会期:2019年2月9日(土)~4月7日(日)
時間:9:30~17:30
*毎週金曜日、及び11月1日(木)、3日(土・祝)は20時まで。
*入館は閉館の30分前まで。
休館:月曜日、2月12日(火)。但し2月11日(月・祝)、4月1日(月)は開館。
料金:一般1600(1400)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、65歳以上1000(800)円、高校生800(600)円。中学生以下無料。
*( )は20名以上の団体料金。
*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。
*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)
住所:台東区上野公園8-36
交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。
コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )









