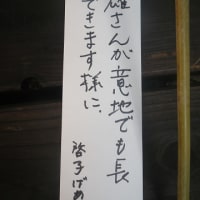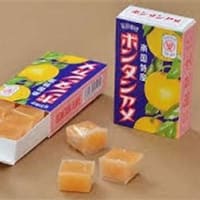さぬき市地方は、高気圧に覆われて昼過ぎまでは晴れていたが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がってきた。気温は18度から26度、湿度は90%から68%、風は2mから3mの北北東の風が少し。明日の16日は、引き続き気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいらしい。

奥方のけいこばぁが「じ(地)をひいて(耕して)よ~」というので、このミニ耕耘機で畑を耕すことになった。朝の間は肌寒いくらいだったが、8時過ぎになると気温もぐんぐんと上昇してきた。

ま、このくらいの畑だから20分もあれば耕して終わる。それでもうっすらと汗が流れた。今日はシャワーなしの着替えだけで済んだ。今度は何を植えるツモリなんだか。

昨日のこの本の中に、「靜御前」が出て来る。四国霊場87番札所の「長尾寺」の境内に「靜御前剃髪塚」というものがあるし、本堂には位牌も残されている。このお寺で、靜御前とお母さんの「イソ」が剃髪し得度したということになっている。靜は「宥心尼」となり、お母さんは「磯野禅尼」になった。

ここで、義経の思い出を断ち切るために宝物である「鼓(つづみ)」を流したとされる「鼓淵」である。ここに川があったのだろう。今は細い水路があるばかり。

これが、お母さんの「磯野禅尼」の碑である。この碑の後ろに小さな石碑がある。

ご近所の方がお水とお花を供え続けているらしい。そこから少し西に進むと木田郡三木町に入る。川沿いに南に進んでしばらく行くと、山の手に大きな池が見えて来る。さらに進むと「鍛冶池」という池がある。

その池の西側の土手にこのような建物が見えて来る。ここが「靜薬師」という庵跡で、ここに「宥心尼」が住んで、義経とその子供の供養のために念仏三昧をしていたという。

その後、侍女の琴路(ことじ)もやってきて世話をしたらしいが、靜は病のために24才の若さで亡くなったという。侍女の琴路も七日後に、この池に入って亡くなったという。

右から静御前のお墓、真ん中が殺された靜の子供のお墓、その左が侍女琴路のお墓ということになっている。自然石の石碑は寄進者の名前が刻まれている。

これが靜薬師のお堂の中の様子。

そこから少し西に進んだ下高岡にある願勝寺は、800年前に源平合戦後に出家した佐々木三郎盛綱が、静御前の菩提を弔うために開基したと伝えられている。佐々木盛綱は源平の戦いなどで活躍し、源頼朝に仕えた武将である。境内に「静の松」があったらしいが、近年になって枯死したという。

ここの梵鐘に、静御前の姿が浮き彫りにされている。

これが静御前のお墓だという。

今日の掲示板はこれ。「大いなる恵みの中に生かされし 我とは知らず 今の今まで」というもの。ある先生のお話で、「ある朝、朝霧の流れる田園の中の道で、東の地平線に赤い太陽の美しさを見掛けたとき、ふっと、これは二千五百年前、ブッダが悟りをひらかれた時、また、八百年前、親鸞聖人が比叡山で修行をされていた時に、仰ぎ見られた太陽と同じ太陽だなと思ったことがあった。そうだ、私はこの太陽に、そして、このかぐわしい空気やこの川を流れる水や、草木の中で 「生かされて」 いたのだと、全身で感じて足を止めたことがあった」という。「そう思ったとき、われ知らず「なもあみだぶつ、なもあみだぶつ」 というお念仏が出ていた。今の今まで私はごくあたりまえのように「わたしが生きている」と考えてきたけれど、しかしそれは間違いで、ほんとうは私は「生かされて」いたと気づいたのだ」という。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。