▼幼少の子どもをお持ちのお母さんやお父さん、あるいは元子どもであったお母さんやお父さん、NHKの「お話出て来い」の番組をご存知だろうか。今もこの番組に耳を傾けているお母さんやお父さんはいらっしゃるだろうか。
▼今は朝の午前10時、NHK第二放送において、月曜から金曜までの毎日この「お話出て来い」の番組は流されている。対象は、年少・年中・年長の主に幼稚園の子どもたち。もしかすると、この番組を子どもたちに聞かせている幼稚園があるかもしれない。私が知らないだけで、結構多いのかも知れない。現状を知りたい気もする。
▼“どんどこどん、・・どんどこどんどこどんごこどん、・・でーてこい、でーてこい、でてこい・・お話でてこい、どんどこどんどこどんどこどん・・でてきた、でてきた、でてきたよ、ほーらでてきた・・ ”
太鼓の音に乗って、こんな言葉で番組は始まる。語りの佐野浅夫さんは今も現役である。氏の語りはもう4000回を超えるらしい。
▼NHKの“お話出て来い”のサイトの謳い文句には次のようにある。
「幼児の想像力を育てるのに、ラジオはもってこいのメディアです。ラジオに神経を集中させて聞くことは、子どもたちにとっては難しいところがあると思います。一方でその集中力は「人の話を聞く」力にもつながります。イメージをふくらませる音楽と効果音、そして一流の語りが子どもたちを物語の世界へ誘います。」
正にこの言葉の通りだと私も思う。
▼不思議なことに、私は自分もこの佐野浅夫氏の番組を聴いて育ったような気持ちがしている。本当だろうか。思い込みと記憶とがどこかでごっちゃになっているのかもしれない。この私もこの番組を聴いて育った一人である──そんな気が本当にするのだ。一体、この番組はいつから始まったのだろう?
まだ、自分で書物を読むには早すぎた時期、周りに子どもの私にじっくり本を読んで聞かせてくれるような環境がなかった時、私はこの番組のテーマソングが始まると、ウキウキとして「今日はどんなお話が聞けるか」と楽しみにしていたものだ、というように自分のことを感じているのだ。私は今でも小さな子どもになって佐野浅夫さんや香椎くに子さんの語りにじっと耳を傾けている自分を見出す。
▼今はアニメなどの映像、しかも動画が主流の時代であるけれども、当時はまだラジオが主流の時代であった。そして、ラジオそのものは地域社会の伝達の大事な手段となっていて、もちろん子どもにチャンネル権などはなかったが、どういうわけかこの番組がよくラジオから流れていて、私はそれを聴いていた──そんな気がしている。
あまり書物に恵まれなかった私は、この番組を通して、その言葉や音響から自由に想像の翼を羽ばたかせ、空想し考えることを学んだのだと今でも思っている。
▼実際はどうなのだろうか。この番組は一体いつから始まったのだろうか。
▼今、私がなぜこんな番組を話題にするかというと、今も時々私はそれを聴いているからである。確かに、自分の子どもたちがまだ小さかった頃、「泣いた赤鬼」とか「島引き鬼」の語りの入ったLPレコード(佐野浅夫氏の吹き込みによる)などを買い求めて、当時からそれなりの評価はしていた。が、今はもっと別の角度から、この番組を評価している自分がいる。
▼少し前、斉藤孝氏の「声に出して読みたい日本語」シリーズがブームになり、日本語を音声で理解することの大切さを再認識することにもなったが、それは飽くまでも大人の視点から見た、大人が理解できる立場から評価したものであった。だが、実際はそれでは遅すぎるのである。子どもの頃から、幼児の頃から、日本語に声を、語りを取り戻さなければならない。私らの場合には大人が聞いていた落語や浪曲の語りや口上などをそれなりに聴いて育っては来たけれど、今の子どもたちには学ばせるものがまるでない。それをこの「お話出て来い」は補ってくれるのではないか──と考えている。
▼そうすれば、日本語にも英語等に劣らない豊かな語りや話術があるのだということを発見することにもなるのではなかろうか。実際、私たちは日常、人と話をしたり、テレビで番組を観たりしても、それをどれだけ言葉として定着させているだろうか。
「国語力の低下」などと巷では言われているが、今まで子どもたちにそういう話のメモの取り方や話のまとめ方、表現の仕方、弁舌のあり方などについてなんら方法論的な取り組みはしていない。「国語力の低下」などというのはその結果に過ぎない。今、アメリカの大統領の予備選を見ていて、候補者に限らず彼らの弁舌のさわやかさに圧倒されるような思いがしている。小さい頃からそういう教育を受けているかいないかの影響はとてつもなく大きい。
▼そういうことを含めて、子どもの表現力の向上、語りの復権のためにも、幼児だけでなく小学生や中学生くらいまでの子どもたちに是非この「お話出て来い」に耳を傾けることをお勧めしたい。
http://ping.blogmura.com/xmlrpc/wq1wgvuchbaj
▼今は朝の午前10時、NHK第二放送において、月曜から金曜までの毎日この「お話出て来い」の番組は流されている。対象は、年少・年中・年長の主に幼稚園の子どもたち。もしかすると、この番組を子どもたちに聞かせている幼稚園があるかもしれない。私が知らないだけで、結構多いのかも知れない。現状を知りたい気もする。
▼“どんどこどん、・・どんどこどんどこどんごこどん、・・でーてこい、でーてこい、でてこい・・お話でてこい、どんどこどんどこどんどこどん・・でてきた、でてきた、でてきたよ、ほーらでてきた・・ ”
太鼓の音に乗って、こんな言葉で番組は始まる。語りの佐野浅夫さんは今も現役である。氏の語りはもう4000回を超えるらしい。
▼NHKの“お話出て来い”のサイトの謳い文句には次のようにある。
「幼児の想像力を育てるのに、ラジオはもってこいのメディアです。ラジオに神経を集中させて聞くことは、子どもたちにとっては難しいところがあると思います。一方でその集中力は「人の話を聞く」力にもつながります。イメージをふくらませる音楽と効果音、そして一流の語りが子どもたちを物語の世界へ誘います。」
正にこの言葉の通りだと私も思う。
▼不思議なことに、私は自分もこの佐野浅夫氏の番組を聴いて育ったような気持ちがしている。本当だろうか。思い込みと記憶とがどこかでごっちゃになっているのかもしれない。この私もこの番組を聴いて育った一人である──そんな気が本当にするのだ。一体、この番組はいつから始まったのだろう?
まだ、自分で書物を読むには早すぎた時期、周りに子どもの私にじっくり本を読んで聞かせてくれるような環境がなかった時、私はこの番組のテーマソングが始まると、ウキウキとして「今日はどんなお話が聞けるか」と楽しみにしていたものだ、というように自分のことを感じているのだ。私は今でも小さな子どもになって佐野浅夫さんや香椎くに子さんの語りにじっと耳を傾けている自分を見出す。
▼今はアニメなどの映像、しかも動画が主流の時代であるけれども、当時はまだラジオが主流の時代であった。そして、ラジオそのものは地域社会の伝達の大事な手段となっていて、もちろん子どもにチャンネル権などはなかったが、どういうわけかこの番組がよくラジオから流れていて、私はそれを聴いていた──そんな気がしている。
あまり書物に恵まれなかった私は、この番組を通して、その言葉や音響から自由に想像の翼を羽ばたかせ、空想し考えることを学んだのだと今でも思っている。
▼実際はどうなのだろうか。この番組は一体いつから始まったのだろうか。
▼今、私がなぜこんな番組を話題にするかというと、今も時々私はそれを聴いているからである。確かに、自分の子どもたちがまだ小さかった頃、「泣いた赤鬼」とか「島引き鬼」の語りの入ったLPレコード(佐野浅夫氏の吹き込みによる)などを買い求めて、当時からそれなりの評価はしていた。が、今はもっと別の角度から、この番組を評価している自分がいる。
▼少し前、斉藤孝氏の「声に出して読みたい日本語」シリーズがブームになり、日本語を音声で理解することの大切さを再認識することにもなったが、それは飽くまでも大人の視点から見た、大人が理解できる立場から評価したものであった。だが、実際はそれでは遅すぎるのである。子どもの頃から、幼児の頃から、日本語に声を、語りを取り戻さなければならない。私らの場合には大人が聞いていた落語や浪曲の語りや口上などをそれなりに聴いて育っては来たけれど、今の子どもたちには学ばせるものがまるでない。それをこの「お話出て来い」は補ってくれるのではないか──と考えている。
▼そうすれば、日本語にも英語等に劣らない豊かな語りや話術があるのだということを発見することにもなるのではなかろうか。実際、私たちは日常、人と話をしたり、テレビで番組を観たりしても、それをどれだけ言葉として定着させているだろうか。
「国語力の低下」などと巷では言われているが、今まで子どもたちにそういう話のメモの取り方や話のまとめ方、表現の仕方、弁舌のあり方などについてなんら方法論的な取り組みはしていない。「国語力の低下」などというのはその結果に過ぎない。今、アメリカの大統領の予備選を見ていて、候補者に限らず彼らの弁舌のさわやかさに圧倒されるような思いがしている。小さい頃からそういう教育を受けているかいないかの影響はとてつもなく大きい。
▼そういうことを含めて、子どもの表現力の向上、語りの復権のためにも、幼児だけでなく小学生や中学生くらいまでの子どもたちに是非この「お話出て来い」に耳を傾けることをお勧めしたい。
http://ping.blogmura.com/xmlrpc/wq1wgvuchbaj










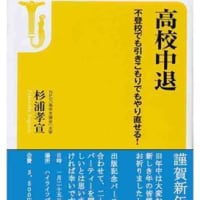
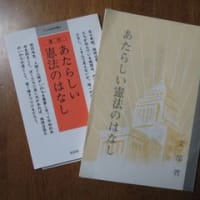


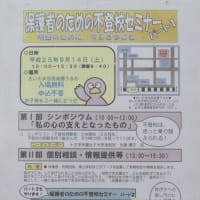
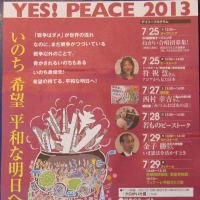



やはり小さかった頃、聞いていらっしゃいましたか。
そういう方とお話できるなんて幸せです。
当時は多分、男の語り手だけだったように思います。
「語りの復権」「話し言葉の見直し」を、と言ったら大げさかもしれませんが、「文字」や「映像」が全盛の現代にあっても、いや、だからこそ「語ること」「聞くこと」の大事さを感じます。
もしかすると、日本人の相対的な「劣化」現象は「聞く」ことを等閑にしたことからきているのではないかとも思っています。