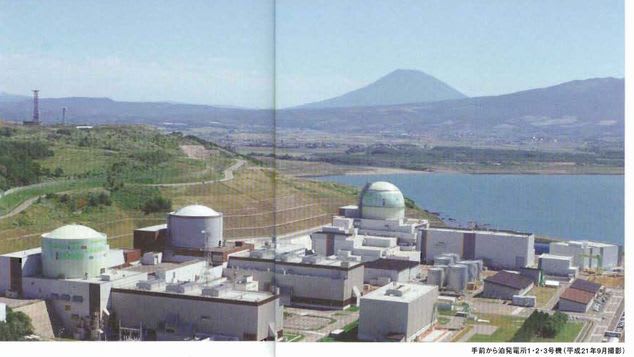2月20日の北海度新聞の朝刊に「羊蹄山避難小屋建替え」が掲載されていました。

昨年9月に定例議会の一般質問で「急を要す『羊蹄山避難小屋』の建替え!」を問うておりました。
山小屋の管理人さんのブログや町内の登山愛好家の方々から話を聞き、自分でも山登りを始めていたので、とても気になる問題でした。
質問の内容は、「羊蹄山の避難小屋は、築37年たっており、老朽化が著しく、危険な状態であります。現在、環境省では支笏洞爺国立公園管理計画を作成しており、羊蹄山の避難小屋も含め、関係行政機関と検討を図っていくと書かれておりますが、いつになるかわかりません。年間1万人を超える登山者を迎え、1、000人ほどが宿泊しています。登山者の安全・安心を確保するためにも、避難小屋の修理、あるいは補強、建替えを積極的に国に要請すべきと思いますが、町長のご見解をお聞かせ願います。」という内容でした。
町長の答弁は、「後志総合開発期成会としましても、これまで北海道や環境省へ避難小屋の再整備に関する要望活動を行ってきたところであります。また、7月には羊蹄山避難小屋整備検討委員会を開き地元としての考え方を後志支庁が中心となって最終取りまとめを行って、何としても環境省の来年度予算に向けた本要望を提出すべく、準備を進めているところであります。避難小屋の現状を考えて、北海道を通じた要望とは別に、地元関係町村として羊蹄山管理保全連絡協議会による環境省への陳情書の提出、また、環境省による建替えには最短でも約3年間を要することが想定されることから、北海道に対しての緊急補強工事の要請、陳情もあわせて検討したいと考えております。」
町長としては前向きの答弁でしたが、地域の実情をもっと発信しないと動きが鈍いままのような状態でした。
10月1日に村田道議会議員を先頭に支庁や役場の担当者や倶知安観光協会の鈴木会長さんはじめスタッフ2名の方と共に避難小屋の視察に羊蹄山登山を行いました。
私は、建築士ということもありレーザー水平器などの機材を持って登り、建物の垂直・水平を行ってきました。
壁は最大100mmほど歪みがあり、床も100mmほどの傾斜があり、歩行禁止の部分もあり、いつ壊れても不思議ではない状況でした。


その後、村田道議会議員の活動や地元の整備検討委員会と道や国との協議が続けられてきていました。
情報も入ってきていましたが、問題点は避難小屋を新設するとしても現在の半分以下のものになる。トイレは、持ち帰り可能な携帯方式が検討されていました。国の考えと地元の要望とに隔たりがありました。
国としては、羊蹄山が独立峰なので日帰り登山の小屋というスタンスで、トイレも汲み取りなどのライニングコストの掛からない、登山者自らが携帯トイレで対処する初期投資の掛からない計画を考えているようです。
地元では、独立峰といっても片道5時間は掛かる山なので宿泊を視野に入れており、現状でも多いときは小屋が満杯で窮屈な状況なのに半分では話にならないということと、トイレ設備も設置しないと携帯トイレをその辺に捨てられては堪ったものではないので、きちんと管理ができる設備にしてほしいといった要望を持っています。
新聞報道では、「小屋の規模や維持管理費の負担は、今後協議をする」となっているので、問題解決はまだのようで、現状の応急処置と新設の計画といった当初の方針を発表したようです。
是非、現状に相応し、登山者の安全・安心に繋がる「人に優しい」避難小屋にしてもらいたいものです。
2010,02.20 北海道新聞の朝刊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
羊蹄山避難小屋建て替え 環境省、新年度に基本計画
建て替えが決まった羊蹄山9合目の避難小屋
環境省は、老朽化して倒壊の恐れがある羊蹄山(1898メートル)の避難小屋を建て替える方針を決めた。新年度に現地調査を行い、基本計画を策定する。一方、現在の小屋を所有・管理する道は、建て替えまでの間の応急措置として、6月ごろに補強工事を行う。
羊蹄山は支笏洞爺国立公園の一部。2005年に国が国立公園の管理を道から国直轄に移したため、道や倶知安町など後志管内5町村が環境省に建て替えを要望していた。
環境省は植生への影響や小屋の建設位置などを調査、基本計画をまとめ、11年度以降に実施設計を行って工事に取り掛かる。小屋の規模や完成後の維持管理費の負担については今後、同省と道や町村が協議する。
一方、道は新しい小屋が完成するまでの登山者の安全を確保するため、現在の小屋の応急補修に乗り出す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・