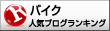今年春先の「井戸端会議」で蘇ったcaffe 月の虹の井戸。。。
その時の課題のフィルターを交換しようと最近、入手したステンレスメッシュで予め自作してあった部品を持ち込み交換作業。
こうやって観ると未だ網目が荒いけど破れてるフィルターよりは断然マシ・・・。

砂こし器の蓋を外してゴムパッキンの上に乗っけて撮ってますが、このゴムパッキンの下へ潜らせて装着しなくてはいけません。
既存の破れを補修したフィルターを取り外し、何とか形(三角形の角度)を修正しながら無事に装着も出来、今回も
「水神さま」の怒りも買わず作業は終了。
しかし、先日の「炎天下で測量」とは違い、冷たい井戸水を触りながらの作業は気持ち良い♪
この時期なると、「そろそろ敷いてあるのかなぁ~」と期待を寄せ、いつものFKI市の浜町の「泰平」へ。
又もやの11時半の開店前にも関わらず、招き入れてくれる季節を感じさせてくれるお気に入りの空間。

季節に合わせ障子も「よし戸(素戸)」に入れ替えてある。

ただ残念なのは小上がり席がテーブル椅子席に変わったこと。今の時代、客のニーズに応えるとこうなってしまうけど
テーブル椅子の下になってしまった「油団」がなんとも勿体ない・・・。

そして、いつもの「日替わり定食」は「ホッケの揚げ出汁」をメインとした外れなしの御膳。

一番客の土花吉が店を出る頃には、平日にも関わらず席がほぼ埋まるという人気店「旬味 泰平」。
DVDのボカシ作業と言っても、ボカシを取り除くのではなくて。。。
以前、この場でも書いた「最も美しく撮る」の映画「今夜、ロマンス劇場で」の中古DVDを買いましてん。
そうしたところが、ジャケットに貼ってあったのであろうシールを剥がした跡が剥げてまして。手前の花園部分。
まぁ~、レンタル落ちのDVDなので、そんなことよりディスク自体に問題が無ければそれで良いのですが・・・。

でも、気になるぅ~ってことで早速、色鉛筆やらクレヨンを取り出してボカシに掛かる。
少し青味を入れ過ぎたけどまぁ~、ジャケットのフィルム越しだし、パッと見ぃで分からないであろうレベルで妥協。

さぁ~ボカシも終わったところで、もう一度見直そ~おっと ♪
昨年、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定された「今庄宿」。
そして、以前から何度か訪れたいた「coffee&bread 木ノ芽」があったところが「甘味処 てまり」に変わってました。
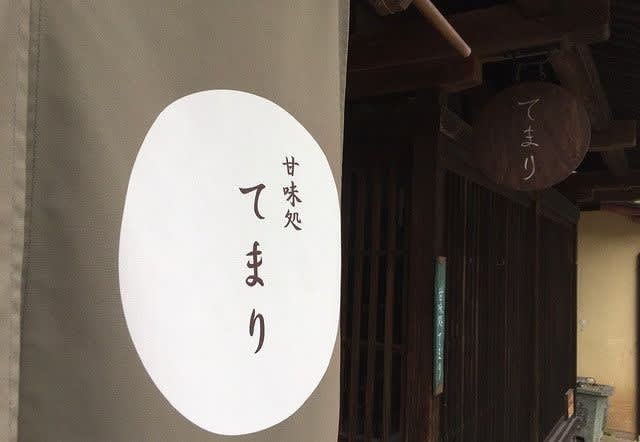
建物の外観、内装はそのまま。。。

黒蜜きなこ白玉団子:¥500-

帰りに以前、「再会の今庄宿」で修復中をみせてもらった建物が「大黒屋」という「暮らしや?」
要は普通の八百屋みたいな日用品屋みたいな用途に使われてた。(少しもったいない・・・)

まぁ~今回は予想通り、修理に相当な手間暇が掛かってしまったオールドカリモクロビーチェア3シーター。
取り敢えず、、caffe 月の虹にバラバラの状態で持ち込み組み立てることに。設置してみる場所はKチェア2シーター+1の所。

置き換えてみるも。。。ん・・・デカいっ。

座ってみると、どうしてもロビーチェアという性質上、座面に角度ついていてお尻が奥深くへ沈んでしまう。
これについては手持ちのロビーチェア1シーターでも同じことが言えるけど、3シーターにもなると両脇に余裕がある分尚更、感じてしまう。

色々と検討した結果、これでは珈琲も飲み難いかもの結論に至り設置を断念。
再度、分解の上一時保管することに。しかし、こうやって観るとカリモクの数、半端ない・・・(笑)

滋賀県米原市から彦根市に入った直ぐにある「近江鉄道・鳥居本駅」の駐車場に車を停め、徒歩で国道8号を渡り旧中山道へ入る。
この「鳥居本駅」を訪れたのは6年ぶり。。。以前の「木造駅舎/近江鉄道:鳥居本駅」

先日もNHK・BS「こころ旅」でも火野正平氏がチャリオで走っていた所。江戸から63番目の宿場町で
「江戸へ百十八里(約463km)、京へ十八里(約70km)」の場所。
先ずは目に入るのは登録有形文化財のヴォーリズ建築。
(ぱっと見はヴォーリズとは気付かない。近年、改修されているため奇麗過ぎて尚更)

この場所は本陣があった場所で、戦前にこの建物へと建て替えられている。
旧中山道を北へ歩き始めると先ずは奇麗に保存されている「合羽屋」だった平入りの建物。(こちらも市の指定文化財)

暫く歩くと、この辺りでは珍しい妻入りの建物。旧集会場だったせいか他の建物とは異なる様式。

そして、90度右折れの正面に建つのが例の「赤玉神教丸本舗」の薬局(現役)。

番組でも登場してますが、その大きさには驚かされる。(国指定重要文化財)

残念ながらお休みだったため、店内を観ることは出来ず。
しかし大きい・・・この入母屋がここまで入り組んだ屋根などは今まで観たことがない。

手前側は明治天皇も休憩された「御小休所」となる。
そして直ぐ近場には崩落した茅葺の建物。(ここまで来ると見苦しい)

先へ進むと未だに点在する当時の平入浅瓦の建物。やがてこの先は「北国街道」へと繋がる。

少しづつ進めている「オールドカリモクロビーチェア3シーター」の修理。
座面や背もたれは今回、大層な貼り換え等はせずにつづくろいで収めて行き、その傷みも趣とすることに。
次にシート部分の修理なのですが結構、キルティングの糸がほつれたり完全に抜けている箇所が多々。

ここなんかは完全に抜けてます。

それに上糸が何と、ナイロン糸。あまりナイロン糸で縫ったことが無いのでねぃ・・・。
そして結構、邪魔臭いのがこのジッパー(ファスナー)。

所どころ、エレメント(務歯)が経年劣化なのか抜け落ちている状態。
先日の「TALON壊れた・・・」の折の「蝶棒」部分なら未だしも、エレメントが欠けたりしたら交換というのが常識。
未だまだ掛かりそうですねぃ・・・。
先週、「昭和の日」に合わすかのように当時物の「カリモクロビーチェアー3シーター」が土花亭に届く。
地元のとある公共機関で半世紀ほど使われていた物でこの度、廃棄処分となったため譲り受けることに。

この椅子自体、土花吉も仕事でそこへ訪れた折には座っていたので馴染みもあるし今回、廃棄されずに
救出できたことが個人的には嬉しくもある。
早速、この大人が横になれるような物が場所を占領されると困るので、分解作業へ取り掛かる。
その構造については以前、「オールドカリモクロビーチェアのカリモク60との違い」でも経験しているので承知済。

まぁ~、傷んでいることは分かっていたものの、健全なのは少し破れのある両側の肘掛部分のみで、
包みボタンが数個ない3人分のシートをはじめ、座面から背もたれから、そのほとんどが相当な手間暇を掛け
修理しなければいけないことが判明。
分解過程で破断したスプリングワッシャと共に出て来た10円玉ひとつでは足りない・・・。(笑)

狭い地元FKI県とはいえ、未だまだ足を踏み入れたことがない地区も沢山あるようで。。。
地元国立大教育学部を出て公立中学校の美術教員として活躍しておられた「清水正男氏」の個展
「shimizu Gallery in Bushu」を観にFKI市の山奥の「武周(ブシュウ)町」へ。

ご自宅の古民家の2階をギャラリーに改装。そのほとんどが大判という油絵が展示してある。

一通り目の保養が済んだところで、ご近所でたまたま人形展を開催されていたので、そちらへも。

「ちりめん」を使った人形たち。
このお宅は代々、雅楽の「笙」の演奏家らしく、古い雅楽の写真や天皇陛下からの賞状や勲章が飾られていた。
残念ながら現在は途切れてしまったらしく、座敷に並ぶ4代前までの肖像が寂しそうにも見えた。
ところで、ここ「武周町」は「花もも」で有名なところ。

未だ、時期的には少し早かったのが残念なのと、何といっても「3本の枝垂れ桜」で有名な「西雲寺」も
未だ桜には染まっていなかった。

この辺りは山間豪雪地。通常、枝垂れ桜は雪害を受けやすく、樹齢百数十年といわれるここの枝垂れ桜が
ここまで生き延びたことも稀。
開花は遅く、農作業の目安とされているため5月に入ってからですかねぃ。。。

例にもれず、空き家が多いのかNPO等が利用する古民家がチラホラ。。。
昨年からの課題、「触らぬ神に」でも書いた、caffe 月の虹の外部散水用井戸の「砂こし器」。
もう、、消雪のシーズンも終わり最悪、何かトラブって対応に時間が掛かってもいいか?とか、やっぱ
下手に触らない方がいいか?とか・・・。
そんな「井戸端会議」の末、やはり分解清掃作業をすることに。(会議といっても妻と二人ですが)

早速昨年、交換したフランジ用のステンレスボルトを外し、ソロリと蓋を開けにかかる。
鋳鉄製の蓋と硬質塩化ビニール製の窓を外すと自噴が始まる。「おぉ~、水神様ぁ~。お手柔らかにぃ~」

見ての通り、内部は鉄錆と砂とマンガン?でコテコテ状態。下部のドレンボルトを外しても、そこからは一滴たりとも水が出ない状態。
ドライバーを突っ込んだり、手を突っ込んだりして内部の異物を取り出すとやがて、ドレンからも流れ出るように。
ステンレス製のフィルターも取り外し、内部の清掃も出来たところで硬質塩化ビニール製の窓の清掃と寸法取り。

(あわよくば、いずれ自作出来そうなので)
因みにステンレス製の「茶こし」みたいなフィルターは破れがあったので少しつづくろって再利用。
こちらも自作出来そうなので適当に寸法を記録しておく。

清掃が終わったところで、元へ戻す。(案の定、硬質塩化ビニール製の窓は清掃したとは言え内部は見えない)

さぁ~、ここからが問題で「古い砂こし器は無闇に手を出すとポンプが井戸を汲み上げないことがある」ってな、
専門業者がよく使う「素人は触るな」的都市伝説。
確かに「水神様」のご機嫌を損ねた日にゃ~痛い目にも合うかもですが、そこは土花吉。
「モノに触る時は愛情を込めて丁寧に触る」主義。
そんな、恐る恐る蛇口を捻ると出るわ出るはの水量っていうか赤錆混じりの水。
暫く、流しっ放しでやがて透明な水になり、水量は今までとは雲泥の違いで復活した井戸水。
「水神様、ありがとうございました」