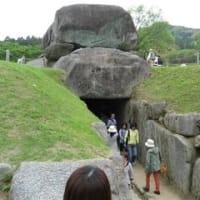流転の果て(下)を読み進めています。
90年代初頭の株価下落時代は
株価の下落は政府の責任だと言わんばかりに
政府は株価の推移に神経をとがらせていました。
いつ頃から、政府はあまり株価に関心を示さなくなったのでしょうか?
いや、株価には関心があっても自らの内閣の信任のバロメーターと
感じなくなったのはいつ頃からなのでしょう?
小泉内閣が登場して、
自由競争を旗印に掲げてからでしょうか?
90年代のPKO(peace keeping operations (国連)平和維持活動)
にちなんで、政府が株価維持に乗り出すことを
PKO(price keeping operation 価格維持操作。)と呼んでいました。
いまや、その言葉が死語になるほど
株価に対する政策の是非を問う声は一つも聞こえてきません。
株式市場への政府の介入は言語道断だとは思いますが、
経済政策の無策が、株価低迷を招いていると考えられません?
↓いつも読んでいただいてありがとうございます。
あなたのポチっとがとても励みになっています。


人気ブログランキングへ
90年代初頭の株価下落時代は
株価の下落は政府の責任だと言わんばかりに
政府は株価の推移に神経をとがらせていました。
いつ頃から、政府はあまり株価に関心を示さなくなったのでしょうか?
いや、株価には関心があっても自らの内閣の信任のバロメーターと
感じなくなったのはいつ頃からなのでしょう?
小泉内閣が登場して、
自由競争を旗印に掲げてからでしょうか?
90年代のPKO(peace keeping operations (国連)平和維持活動)
にちなんで、政府が株価維持に乗り出すことを
PKO(price keeping operation 価格維持操作。)と呼んでいました。
いまや、その言葉が死語になるほど
株価に対する政策の是非を問う声は一つも聞こえてきません。
株式市場への政府の介入は言語道断だとは思いますが、
経済政策の無策が、株価低迷を招いていると考えられません?
↓いつも読んでいただいてありがとうございます。
あなたのポチっとがとても励みになっています。
人気ブログランキングへ