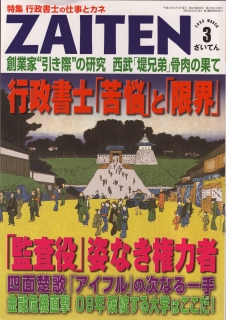今の仕事がとても忙しくなって、
ブログを継続的に書き続けるどころか
独立開業もおぼつかなくなってきています。
まぁ、ブログが書けない言い訳を
「仕事が忙しい」せいにしているだけかもしれませんが・・・笑
ところで、3/16プレジデント誌で特集されていた
「いる社員、捨てられる社員」の中の記事で
『黄金資格、紙切れ資格』という内容のものがあり、
若干興味を聞かれました。

不況下になると、やはり独立や転職を視野に入れて
難関資格に挑戦するケースが多くなるそうです。
しかし、現実には不況下で独立・転職はあまりにも
リスクが大きく、資格を持っているだけで、
そこにスキルが伴わなければ、
開業後収入を維持していくのは
難しいようです。
ただ、八方ふさがりなわけではありません。
進んでいく方向性はあります!
記事でポイントとなっていたのは
『資格』として体系化される前のスキルの部分が、
その人のキャリアと一体化して評価される
という点です。
僕の場合でいえば、
行政書士として開業を目指していますが、
現実のキャリアは中小企業の中間管理職として
事業部内のマネジメントのスキルを磨いているという状態です。
現在の仕事のキャリアアップの延長線上に資格を位置づけるという
のが最も有効な方向性といえるのであれば、
通常は行政書士ではなく中小企業診断士のほうが
よかったのかなぁとも思いますが。
もっとも、僕の場合は法律の知識が若干残っていたので、
行政書士の資格を取りやすかったという事情はありました。
さらに誤解を恐れずに言えば、
行政書士は「官公庁への書類申請の代行」というイメージが強いですが、
仕事の幅自体はもっと広いとおもわれます。
主たる業務に付随して企業へのコンサルティング業務を行う余地は
充分考えられ、そこに差別化の道が残されているように思います。
とすれば、キャリアプランの戦略としては
今現在のキャリアのマネジメントスキルをさらに磨き
企業内で起こるさまざまな問題点の解決手法を身に付けた上で
行政書士としての独立開業に道を探るというのが
もっとも適切かなぁと思うのですが・・・。
どうでしょう?
↓いつも読んでいただいてありがとうございます。
↓あなたのポチが大変励みになっています。

ブログを継続的に書き続けるどころか
独立開業もおぼつかなくなってきています。
まぁ、ブログが書けない言い訳を
「仕事が忙しい」せいにしているだけかもしれませんが・・・笑
ところで、3/16プレジデント誌で特集されていた
「いる社員、捨てられる社員」の中の記事で
『黄金資格、紙切れ資格』という内容のものがあり、
若干興味を聞かれました。

不況下になると、やはり独立や転職を視野に入れて
難関資格に挑戦するケースが多くなるそうです。
しかし、現実には不況下で独立・転職はあまりにも
リスクが大きく、資格を持っているだけで、
そこにスキルが伴わなければ、
開業後収入を維持していくのは
難しいようです。
ただ、八方ふさがりなわけではありません。
進んでいく方向性はあります!
記事でポイントとなっていたのは
『資格』として体系化される前のスキルの部分が、
その人のキャリアと一体化して評価される
という点です。
僕の場合でいえば、
行政書士として開業を目指していますが、
現実のキャリアは中小企業の中間管理職として
事業部内のマネジメントのスキルを磨いているという状態です。
現在の仕事のキャリアアップの延長線上に資格を位置づけるという
のが最も有効な方向性といえるのであれば、
通常は行政書士ではなく中小企業診断士のほうが
よかったのかなぁとも思いますが。
もっとも、僕の場合は法律の知識が若干残っていたので、
行政書士の資格を取りやすかったという事情はありました。
さらに誤解を恐れずに言えば、
行政書士は「官公庁への書類申請の代行」というイメージが強いですが、
仕事の幅自体はもっと広いとおもわれます。
主たる業務に付随して企業へのコンサルティング業務を行う余地は
充分考えられ、そこに差別化の道が残されているように思います。
とすれば、キャリアプランの戦略としては
今現在のキャリアのマネジメントスキルをさらに磨き
企業内で起こるさまざまな問題点の解決手法を身に付けた上で
行政書士としての独立開業に道を探るというのが
もっとも適切かなぁと思うのですが・・・。
どうでしょう?
↓いつも読んでいただいてありがとうございます。
↓あなたのポチが大変励みになっています。